最頻生涯年数:高齢化時代の寿命指標
-
National Institute of Population and Social Security Research
国立社会保障・人口問題研究所 特別講演会
下記の要領で国立社会保障・人口問題研究所の特別講演会を開催しました。
日時 : 2016年4月25日(月)10:30 ~ 12:00
場所 : 日比谷国際ビル(内幸町)6階 国立社会保障・人口問題研究所 第4・第5会議室(地図)
講演者: 堀内四郎(ニューヨーク市立大学総合大学院人口学課程主任、同大学公衆衛生学大学院疫学・応用統計学部教授)
題目 :「最頻生涯年数:高齢化時代の寿命指標」
講演概要
多くの経済先進諸国において、とくに1970年頃以降、高齢死亡率の顕著な低下が見られた。最頻生涯年数(以下M)は生涯時間の代表値のひとつだが、このような老年生存伸長の時代において、とりわけ有用と考えられる。死亡年齢の指標としては平均値(0歳平均余命、以下e0)が広く用いられており、中間値も時々使われ、また老年における生存に焦点を当てる場合は、前期高齢における平均余命(たとえばe65)も使用される。Mは、これらの指標とはかなり異なる数学的・統計学的・人口学的特性を持ち、違った趨勢や人口間差異のパターンを示すこともある。Mは高齢の死亡率によってのみ決定されるので、老年生存の指標として有用である。現在の先進諸国ではe0よりも約5年ほど長く(日本女性では平成26年に87歳と92歳)、一生の典型的な長さについて、e0とはかなり異なった印象を一般の人達に与える。またe65など高齢平均余命の増加は実際の寿命伸長よりも小さくなる傾向があるが、Mの増加にはこのような問題はない。さらに、成年死亡の年齢パターンについての主要な数式モデルでは、最頻値が平均値や中間値よりも明確な数学的役割を果たしている。Mの有用性を考慮し、e0と併用していくことが有効であろう。
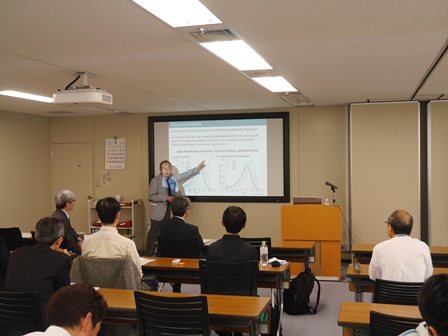
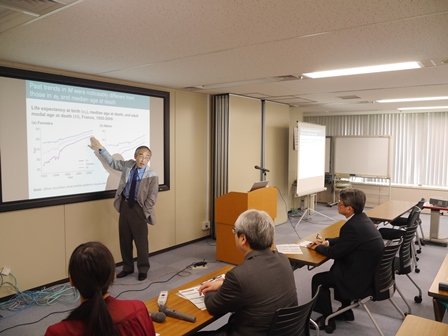

* ご講演・討論は日本語で行われました。
