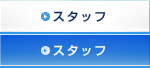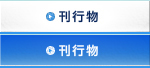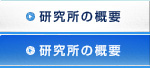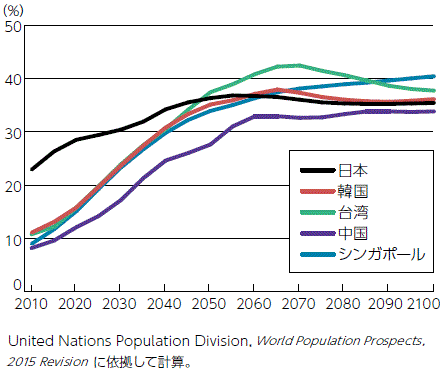| 1. 2025擭丄偦偺屻傪尒悩偊偨抧堟偺堛椕丒夘岇採嫙懱惂偺昡壙懱宯偺峔抸傪栚巜偟偰 堛椕媦傃夘岇偺憤崌揑側妋曐偵帒偡傞婎嬥偺岠壥揑側妶梡偺偨傔偺帩懕揑側昡壙偲寁夋傊偺斀塮偺偁傝曽偵娭偡傞尋媶乮暯惉27乣28擭搙乯 乵岤惗楯摥壢妛尋媶旓曗彆嬥乶 |
|
2025擭偵乽抍夠偺悽戙乿偑慡偰75嵨埲忋偲側傞挻崅楊幮夛傪寎偊傑偡丅崙柉堦恖堦恖偑丄堛椕傗夘岇偑昁梫側忬懺偲側偭偰傕丄偱偒傞尷傝廧傒姷傟偨抧堟偱埨怱偟偰惗妶傪宲懕偟丄偦偺抧堟偱恖惗偺嵟婜傪寎偊傞偙偲偑偱偒傞娐嫬傪惍旛偟偰偄偔偙偲偑廳梫壽戣偱偡丅偦偺傛偆側拞偱丄棙梡幰偺帇揰偵棫偭偰愗傟栚偺側偄堛椕媦傃夘岇偺採嫙懱惂傪峔抸偟丄崙柉堦恖堦恖偺帺棫偲懜尩傪巟偊傞働傾傪彨棃偵傢偨偭偰帩懕揑偵幚尰偟偰偄偔偙偲偑昁梫偲偝傟偰偄傑偡丅
杮尋媶偱偼丄忋婰偺岤惗楯摥徣偺巤嶔偵偮偄偰尋媶柺偐傜峷專偡傋偔丄乽抧堟偵偍偗傞堛椕媦傃夘岇偺憤崌揑側妋曐偺懀恑偵娭偡傞朄棩乿戞6忦偵婎偯偔婎嬥乮抧堟堛椕夘岇憤崌妋曐婎嬥乯偵偮偄偰丄乮1乯婎嬥偺岠壥揑丒岠棪揑側妶梡偵昁梫側帩懕揑側昡壙曽朄偲丄偦偺偨傔偺巜昗摍傪峔抸偡傞偙偲丄乮2乯婎嬥偱幚巤偡傞帠嬈偺搒摴晎導偵傛傞慖戰偵塭嬁傪梌偊傞梫場傪柧傜偐偵偡傞偙偲丄乮3乯搒摴晎導偵偍偗傞幚巤僒僀僋儖偺幚嵺傪柧傜偐偵偡傞偙偲丄傪峴偄傑偟偨丅 仠堛椕偲夘岇偺憤崌揑側妋曐偵岦偗偨昡壙偺榞慻傒乮奣擮恾乯
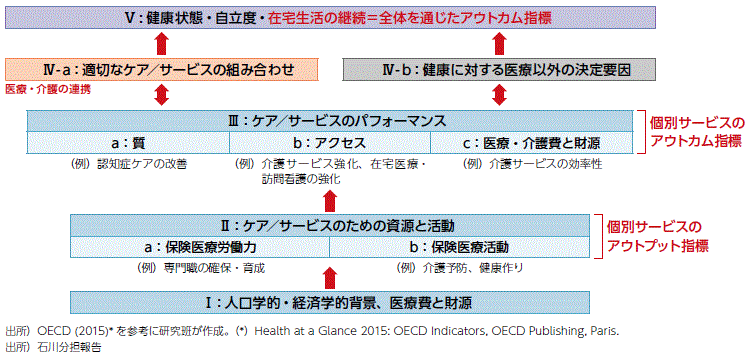 仠峔惉偝傟偨婎嬥帠嬈偺昡壙巜昗椺乮帠嬈嬫暘1乯
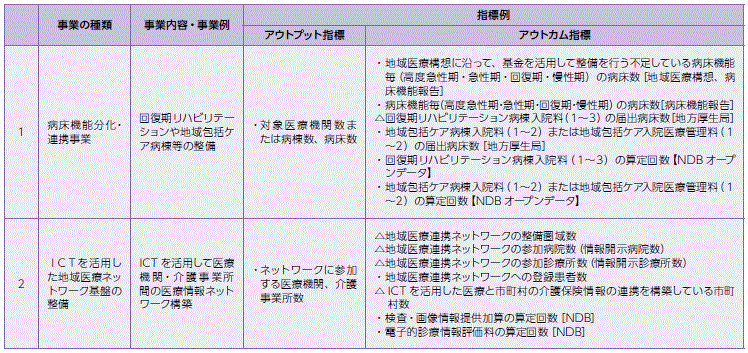 |
| 2. 乽妶摦乿乽嶲壛乿儗儀儖傪岦忋偝偣傞儕僴價儕僥乕僔儑儞偺偁傝曽傪偝偖傞 梫夘岇崅楊幰偺惗妶婡擻岦忋偵帒偡傞岠壥揑側惗妶婜儕僴價儕僥乕僔儑儞乛儕僴價儕僥乕僔儑儞儅僱僕儊儞僩偺偁傝曽偵娭偡傞憤崌揑尋媶乮暯惉27乣29擭搙乯 [岤惗楯摥壢妛尋媶旓曗彆嬥] |
|
抍夠偺悽戙偑75嵨埲忋偲側傞2025擭偵岦偗偰丄廳搙側梫夘岇忬懺偲側偭偰傕廧傒姷傟偨抧堟偱帺暘傜偟偄曢傜偟傪懕偗傞偙偲偑偱偒傞傛偆丄堛椕丒夘岇丒梊杊丒廧傑偄丒惗妶巟墖偑堦懱揑偵採嫙偝傟傞乽抧堟曪妵働傾僔僗僥儉乿偺峔抸偑恑傔傜傟偰偄傑偡丅
惗妶婡擻偺掅壓偟偨崅楊幰偑廧傒姷傟偨抧堟偱惗妶傪懕偗偰偄偔偨傔偵偼丄乽怱恎婡擻乿乽妶摦乿乽嶲壛乿偺偦傟偧傟偺梫慺偵僶儔儞僗傛偔摥偒偐偗傞偙偲偑廳梫偲偝傟偰偄傑偡偑丄尰嵼採嫙偝傟偰偄傞儕僴價儕僥乕僔儑儞偺懡偔偼乽怱恎婡擻乿偺夞暅偵曃偭偰偄傞偺偑幚懺偱偡丅 杮尋媶偱偼丄崅楊幰偺乽妶摦乿乽嶲壛乿儗儀儖偺岦忋偵帒偡傞儕僴價儕僥乕僔儑儞偺曽朄傪柧傜偐偵偟丄偙傟傜偺曽朄傪岠壥揑偵婡擻偝偣傞偨傔偺儅僱僕儊儞僩偺庤朄傪奐敪偡傞偙偲傪栚揑偲偟偰偍傝傑偡丅 仠恾1丂崅楊幰儕僴價儕僥乕僔儑儞偺僀儊乕僕
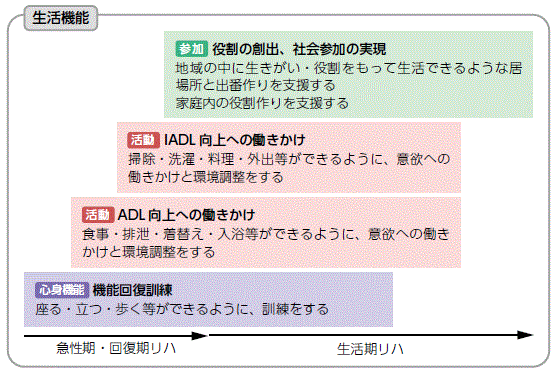
仠恾2丂儕僴價儕僥乕僔儑儞棙梡幰偺忬懺偺曄壔
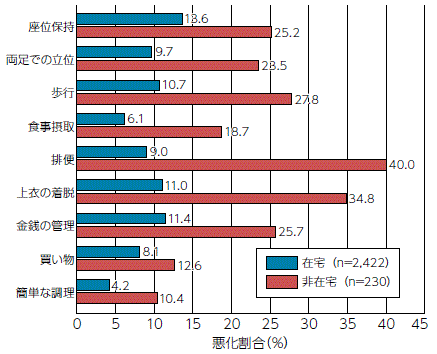
仠恾3丂儕僴價儕僥乕僔儑儞偺幚巤忬嫷
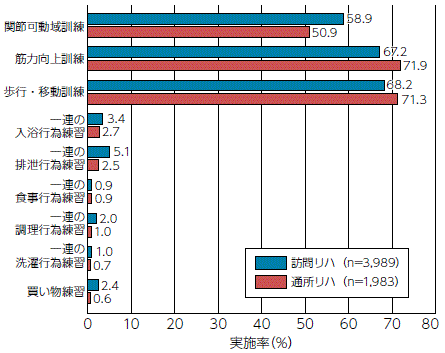
|
| 3. 恖岥傗悽懷偺愭抂揑摦岦暘愅偵婎偯偒師悽戙偺彨棃悇寁僔僗僥儉傗偦偺惌嶔揑墳梡傪扵媮 恖岥尭彮婜偵懳墳偟偨恖岥丒悽懷偺摦岦暘愅偲師悽戙彨棃悇寁僔僗僥儉偵娭偡傞憤崌揑尋媶乮暯惉26乣28擭搙乯 乵岤惗楯摥壢妛尋媶旓曗彆嬥乶 |
||||
|
恖岥丒悽懷偺彨棃悇寁偼奺庬巤嶔棫埬偵妶梡偝傟偰偄傑偡偑丄傢偑崙偑恖岥尭彮婜傪寎偊傞偵偁偨傝丄抧堟傗悽懷偺曄壔偑彮巕壔丒挿庻壔摍偺慡崙揑挭棳偵塭嬁傪梌偊丄憡忔偟側偑傜揥奐偡傞傛偆偵側偭偰偄傞偙偲偐傜丄嵟怴偺尋媶摦岦傪斀塮偟偨恖岥丒悽懷偺摦岦暘愅偺怺壔傗丄抧堟丒悽懷偺彨棃偵娭偡傞忣曬採嫙偵傛傝廳揰傪抲偒偙傟偵慡崙揑側彮巕壔丒挿庻壔偺孹岦傪惍崌偝偣傞偲偄偆怴偨側娤揰傪摫擖偟偨彨棃悇寁儌僨儖偺奐敪丄傑偨恖岥丒悽懷偺彨棃悇寁傪梡偄偨惌嶔揑僔儈儏儗乕僔儑儞偑媮傔傜傟偰偍傝丄恖岥尭彮婜偵懳墳偟偨怴偨側恖岥妛揑彨棃悇寁偵娭偟偰憤崌揑側尋媶傪峴偆偙偲傪栚揑偲偟偰尋媶傪峴偄傑偟偨丅
嬶懱揑偵偼丄嘆嵟愭抂媄弍傪墳梡偟偨恖岥尭彮婜偵偍偗傞憤崌揑側恖岥丒悽懷偺摦岦暘愅丄嘇抧堟丒悽懷偵娭偡傞悇寁偵廳揰傪抲偄偨師悽戙彨棃悇寁儌僨儖偵娭偡傞婎慴揑尋媶丄嘊彨棃悇寁傪妶梡偟偨惌嶔揑僔儈儏儗乕僔儑儞偵娭偡傞尋媶偺嶰椞堟偵暘偗偰尋媶傪悇恑偟傑偟偨丅 仠僾乕儖儌僨儖偵傛傞恖岥堏摦偺彨棃悇寁朄乮奣擮恾乯
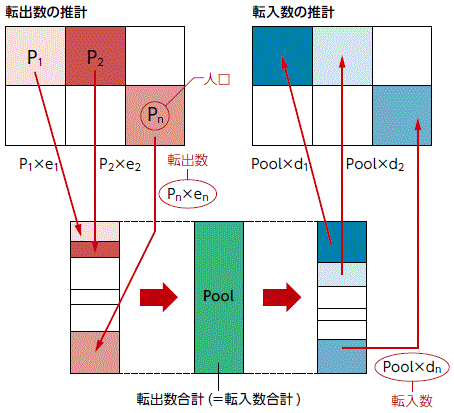 師悽戙彨棃悇寁僔僗僥儉偵娭偡傞尋媶偱偼丄僾乕儖儌僨儖偵傛傞搒摴晎導暿彨棃恖岥悇寁傪峴偄傑偟偨丅偙偺尋媶偵傛傞偲丄恖岥堏摦偵娭偟偰柕弬偑側偔埨掕偟偨悇寁寢壥偑嶼弌偝傟傞偙偲丄扨堦抧堟儌僨儖偱弮堏摦棪傪弅彫偝偣偨応崌偵嬤偄寢壥偑摼傜傟傞壜擻惈偑偁傞偙偲丄奺壖掕偑懠抧堟傕娷傔偨悇寁寢壥偵媦傏偡塭嬁傕掕検揑偵昡壙偡傞偙偲偑壜擻偱偁傞偙偲側偳偑柧傜偐偲側傝傑偟偨丅
仠奜崙恖庴擖傟偺岤惗擭嬥強摼戙懼棪傊偺塭嬁乮僷僞乕儞侾乯
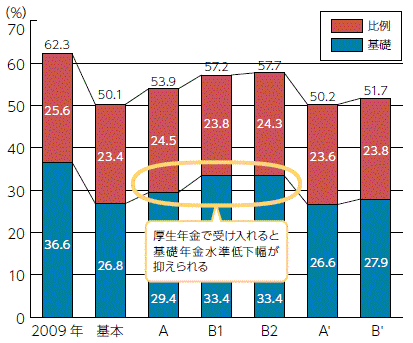 惌嶔僔儈儏儗乕僔儑儞傊偺墳梡偲偟偰丄奜崙恖恖岥庴擖傟偑岞揑擭嬥偵梌偊傞嵿惌塭嬁僔儈儏儗乕僔儑儞傪幚峴偟傑偟偨丅嵍恾偼丄奜崙恖楯摥幰傪庴偗擖傟偨応崌偺岤惗擭嬥傊偺塭嬁傪強摼戙懼棪偱帵偟偨傕偺偱丄僷僞乕儞侾偲偼抝惈掅捓嬥楯摥幰傪庴偗擖傟傞働乕僗偱偡丅墶幉偼庴擖働乕僗傪帵偟丄奜崙恖庴擖奼戝傪峴傢側偄婎杮働乕僗偵懳偟丄岤惗擭嬥偱庴偗擖傟傞偺偑A丄B1丄B2丄崙柉擭嬥偑A'丄B' 偱偡丅A偼奜崙恖楯摥幰偺傒庴偗擖傟傞偺偵懳偟丄B 偼攝嬼幰傗壠懓偺懷摨丒屇傃婑偣傪峴偆傕偺偱丄偝傜偵丄B1 偲B2 偼戞俀悽戙埲崀偺楯摥幰偺捓嬥儗儀儖偱丄B1 偼掅捓嬥丄B2 偼崅捓嬥偺働乕僗偱偡丅
庴偗擖傟偨奜崙恖傪岤惗擭嬥傊揔梡偡傞応崌丄婎慴擭嬥偺悈弨掅壓暆偺奼戝偑梷偊傜傟傞偙偲偑傢偐傝傑偡丅偙偺傛偆偵丄奜崙恖庴擖傟偺媍榑偵偍偄偰偼丄挿婜偺恖岥摦岦傊偺塭嬁偵壛偊丄婎慴擭嬥悈弨掅壓栤戣偵懳墳偡傞岠壥偑偁傞偙偲偵傕拲栚偑昁梫偱偡丅
|