本セミナーは終了いたしました。
多数のご参加ありがとうございました。
※当日の資料は「プログラム」からPDF形式で見ることができます。
※第14回厚生政策セミナー報告書内容を、PDFファイルでこちらに掲載しました。![]() (3.3MB)
(3.3MB)
- 会期: 2009年12月22日(火)
- 会場: 国連大学 国際会議場
- 主催: 国立社会保障・人口問題研究所
- 後援: 読売新聞社
- 言語: 英語及び日本語(同時通訳あり)
- 定員: 300名
- 参加費:入場無料(事前申し込み・先着順)
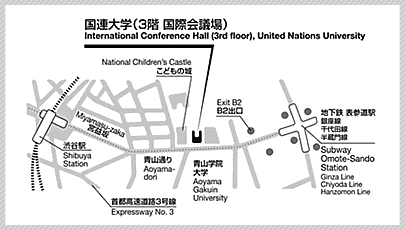
会場: 国連大学 国際会議場
JR渋谷駅より徒歩8分東京メトロ表参道駅2番出口より徒歩5分
20世紀後半は人類の寿命に革命的な変化が起こった時代であった。すなわち、従来の「多くの人は中高年で人生を全うし、老年期を迎える人は稀であった」時代から、「多くの人にとって老年期を過ごすのはごく普通のこと」である時代へと変化を遂げたのである。まさに「長寿革命」といってもよい。世界の平均寿命の変化をみると、1950-55年には男性45.2年、女性48.0年であったのが、2005-10年には男性65.4年、女性69.8年へと約20年伸長したと推定されている(国連世界人口推計2008年版)。日本の場合、この変化はさらに劇的であり、日本人の平均寿命は1950-52年の男性59.57年、女性62.97年から、2008年の男性79.29年、女性86.05年へと著しく伸びている。すなわち日本は平均寿命において、第二次世界大戦後間もない頃は先進諸国の中でほとんど最下位にあったのが、1980年代前半には世界の最長寿国へと変貌を遂げたのである。
この著しい寿命伸長の傾向は21世紀に入っても続いており、現在でも世界の先頭を走っている日本人の平均寿命は、さらに伸び、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計(2006年公表、死亡中位仮定)によれば2055年には男性83.67年、女性90.34年に達すると推計されている。まさに日本人は、人類の寿命伸長のフロンティアを切り開いているともいえる。
しかしこのような日本人の長寿化のパターン、原因、将来見通しに関して、これまで必ずしも広範かつ系統的な科学的議論がなされ、その成果が科学的知識として国民の間で共有されてきたわけではない。過去の寿命伸長の原因を振り返り、今後のさらなる長寿化の見通しを立てるに当たっては、人口統計学的な分析を基礎とした上で、医学生物学的あるいは社会経済学的視点(環境、遺伝、健康、栄養、労働、ライフスタイル、保健医療システム、社会システム、教育など)を含めた多方面の研究アプローチの共同化が必要である。
現在なお日本人の寿命伸長の勢いは止まるところを知らない。人々の「老い」に対する意識そのものが変わりつつあり、抗加齢医学といった「老化」そのものを制御する技術も開発されつつある。しかも将来のSF(空想科学小説)的ともいえる医療技術の飛躍的な発展(遺伝子治療、新型万能細胞の利用、人工臓器など)により、さほど遠くない将来、従来の常識を越えるようなさらなる寿命伸長が起こる可能性も否定できない。本セミナーでは、寿命の人口学研究における世界最先端の研究者を招き、国際的視点から日本の寿命革命を再検討する。すなわち長寿化のメカニズムに迫るとともに、日本社会に課せられた課題を明らかにする。このことは人口学を基礎とする寿命をめぐる幅広い学際的研究の発展を促すことになるだろう。
このような驚異的な寿命伸長が日本社会にはかりしれないほど大きな影響を及ぼすことは間違いない。人口の超高齢化とライフスパンの延伸は、家族、仕事、生き甲斐、地域社会、社会保障などあらゆる局面で人々の意識や行動に大きな変化をもたらし、社会や経済のしくみに根本的な見直しを迫るであろう。健康長寿産業の発展などによる大規模な雇用拡大や経済成長にも期待が寄せられている。
長寿化で世界をリードする日本の姿を世界の人々が注視している。わたしたちに課せられた課題は大きい。


