1999年 社会保障・人口問題基本調査
第4回世帯動態調査
結果の概要 [要旨]
2001年10月
国立社会保障・人口問題研究所
過去数十年の間、わが国ではきわめて重大な人口学的変化が進行している。死亡率の低下、平均寿命の伸長、出生率の低下、高齢化、晩婚化・未婚化、離婚率の上昇といった変化は、世帯の規模と構成、形成過程と解体過程に大きな影響を与えている。増加する高齢者人口の家族関係と世帯構成の変化、ひとり親と子から成る世帯の増加、未婚のまま親と同居を続ける若・中年層の増加などは、学術的にも行政的にも重大な関心事である。
国立社会保障・人口問題研究所では、こうした世帯変動の現状を把握し、また将来の動向を予測するための基礎データを得ることを目的として、5年ごとに「世帯動態調査」を行っており、平成11(1999)年7月1日に第4回目となる調査を実施した。調査項目は前回(1994(平成6)年に実施)とほぼ同様で、現在の世帯規模・世帯構成に加え、過去5年間の世帯主経験、親元からの離家、配偶関係の変化等の世帯形成・解体行動について尋ねている。
本調査は、平成11(1999)年国民生活基礎調査区1,048地区(平成7(1995)年国勢調査地区から層化無作為抽出)からさらに無作為に抽出した300調査区のすべての世帯を対象としている。調査票の配布・回収は調査員が行い、調査票への記入は原則として世帯主に依頼した。
対象世帯数は16,267世帯であり、うち13,385世帯から調査票が回収され、最終的に12,434世帯を有効票として集計・分析の対象とした。回収率は82.3%、有効回収率は76.4%となる。
◇ 世帯の現状 ◇
前回と比較すると、平均世帯規模は3.1人から2.9人へと減少、単独世帯の割合は18.9%から19.8%、核家族の割合は60.8%から62.5%へとそれぞれ上昇し、この5年間に小家族化・核家族化が進んだ。
◇ 親族との居住関係 ◇
[子との居住関係][親との居住関係]
65歳以上の高齢者で子をもつ人の割合は92.6(前回は94.1。以下同じ)%、18歳以上の子と同居している人の割合は52.1(58.3)%でいずれも前回に比べ低下している。年齢別にみると、男子70-74歳、女子65-69歳で最も同居率が低く、高齢になるほど上昇するが、前回に比べほぼ全年齢層で同居率は低下している。
65歳以上の高齢者の息子との同居率は38.0(41.2)%、娘との同居率は13.2(10.6)%で、前回に比べると娘との同居率は増加している。
65歳以上の高齢者の息子との同居率は38.0(41.2)%、娘との同居率は13.2(10.6)%で、前回に比べると娘との同居率は増加している。子と同居している高齢者のなかでの娘との同居の割合は25.4(18.8)%である。
子との同居を「継続同居」と「再同居」に分けると、65歳以上では継続同居より再同居の方が多い。
[その他の親族との関係]
18歳以上人口のうち、自分の親が少なくとも1人生存している人は68.1(64.1)%である。
65歳以上でも8人に1人程度(13.3%)は、親(配偶者の親を含む)が生存している。
18歳以上の人で、自分の親と同居している人の割合は男子32.8%、女子22.0%である。年齢別にみると、20-24歳では男女とも80%弱であるが、30-34歳では男子39.0(41.2)%に対し、女子は22.9(21.5)%と結婚を契機として急減し、30歳を境にして男女で差がみられる。
同居率は加齢とともに減少するが、65歳以上でも男子4.3(3.3)%、女子1.1(0.8)%が親と同居しており、高齢者が老親と同居する割合は前回に比べやや上昇した。
配偶者の親と同居する者は、男子4.8(4.0)%、女子16.3(18.0)%であり、妻が夫の親と同居する割合は前回よりわずかに低下している。
きょうだい数は、1960-64年出生コーホート以降では漸減傾向にあり、平均きょうだい数は1960-64年生まれで2.52人、1975-79年生まれでは2.38人となっている。
きょうだい数の減少とともに、男子のうち長男の割合は1960-64年出生コーホート以降では70%前後に達する。また、女子のうち男きょうだいを含まない姉妹のみの女子は1945-49年生まれの25.3%から1975-79年生まれの44.9%まで増加している。
◇ 世帯の継続と発生 ◇
[現世帯主の世帯主歴][世帯員の転入・転出]
現世帯のうち5年前から存在していた「継続世帯」は90.5%、残る9.5%は新たに発生した世帯である。継続世帯は、世帯主が5年前と同一である世帯85.4%と世帯主が交代した世帯5.1%に分けられる。
18歳以上人口のうち世帯主であるものは、男子で75.8%、女子で14.0%を占める。新たに世帯主になる人の割合は、男女とも10代後半から20代で高い。他方、女子高齢層では、とくに交代により世帯主になる人が目立つ。
過去5年間に世帯主が交代した世帯(590世帯、全世帯の5.1%)では、親から世帯主を継承した世帯が42.5%、配偶者から世帯主を引き継いだ世帯が42.0%を占める。
交代時の前世帯主の状態は、同居43.1%、死亡56.9%で、男子の場合、同居(65.6%)が多く、女子では死亡(80.6%)が多い。
[世帯規模の変化]
継続世帯のうち過去5年間に世帯員の転入があった世帯は16.1%、転出があった世帯は26.7%となっており、全体としては世帯規模が縮小傾向にあることを示唆する。
[家族類型の変化]
継続世帯のうち過去5年間に世帯員が増加した世帯は13.7%、減少した世帯は22.0%であり、平均世帯規模は3.08人から2.97人へ減少した。
継続世帯について5年前との変化をみると、単独世帯、夫婦世帯が増加し、親と子の世帯、その他の一般世帯が減少した。
◇ 世帯の形成と拡大 ◇
[親世帯からの離家][結婚]
女子25-29歳では、親元に残る割合がこの5年間に46.2%から51.3%へ約5ポイント上昇している。
最初の離家年齢は、男子では1945-49年生まれ(20.2歳)、女子では1950-54年生まれ(20.8歳)を底として、それ以降の出生コーホートでは上昇している。
高学歴化によって、最近では、進学離家、就職離家が拮抗しているが、進学離家の割合は1960年出生コーホート以降は頭打ちになっている。
[ライフコースから見た世帯形成]
ここの5年間に、女子では20代後半から30代前半の未婚割合が4〜5ポイント上昇しており、晩婚化が顕著である。
30代以降では男女とも多数が離家、結婚、出生を経験するが、離家せずに結婚、出生する世帯形成パターンは男子に多く、30代後半では15.9%を占める。
今回の調査から仮想コーホートの世帯形成行動を予測すると、将来の35-39歳女子が親元にとどまる割合は現在より高くなる可能性がある。
◇ 世帯の解体と縮小 ◇
[配偶者との死別・離別][子の離家とエンプティ・ネスト]
5年前の配偶関係が有配偶であった者のうち、65歳以上では男子3.4%、女子16.7%が死別へと変化した。夫婦のみの世帯で一方が死亡した場合、9割以上は単独世帯に移行している。
5年前に有配偶であった者のうち、40歳未満では男子4.0%、女子5.0%が離別へと変化した。男子では夫婦のみの世帯や夫婦と子の世帯から単独世帯への移行が多く(16.9%、12.4%)、女子では夫婦と子の世帯から女親と子の世帯への移行が全体の37.5%を占める。
[高齢者の健康状態と同居相手]
継続世帯では、5年間に夫婦と子の世帯から夫婦のみの世帯へ移行した世帯は9.8%であった。このエンプティ・ネストへ移行する割合は60代世帯主で20%を超える。
子をもつ人のうち、すべての子と別れて暮らしているエンプティ・ネスト期の人は24.5%である。この5年間にこの状態に移行した人は7.5%であり、年齢別には男女とも50代後半がもっとも多い(男子15.1%、女子14.3%)。
要介護の高齢者の属する世帯は、単独世帯、夫婦のみ世帯は少なく、その他の世帯が多い。
子と同居している高齢者について、介護の要・不要別に、同居子に離家経験のある者の割合をみると、男女とも要介護高齢者のほうが高く、男子で11.3ポイント、女子で5.7ポイントの差がある。
|
本報告の資料『第4回世帯動態調査 結果の概要』(全文)をPDF形式で提供しています。 このファイル(NSHC99.pdf)を閲覧・入手したい方は、右のアイコンをクリックしてください。 なお、本調査の内容を刊行物・報告書等にご利用になった場合は、参考のため その掲載紙などを一部本研究所世帯動態調査担当宛てお送りいただければ幸いです。 |
NSHC99.pdf(233KB) (2001.10.05改訂版) |
|
------- PDF(Portable Document Format)形式のファイルを見るためには、AcrobatReader(アクロバットリーダー)というソフト(無料)が必要です。 アクロバットリーダーを入手したい方は,右のアイコンをクリックして下さい。 (アクロバットリーダーのダウンロードサイトへジャンプします) | 
|
本調査の報告書で公表している巻末表データが、エクセルファイルでダウンロードできます。
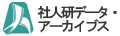 (2003年3月24日掲載開始)
(2003年3月24日掲載開始)