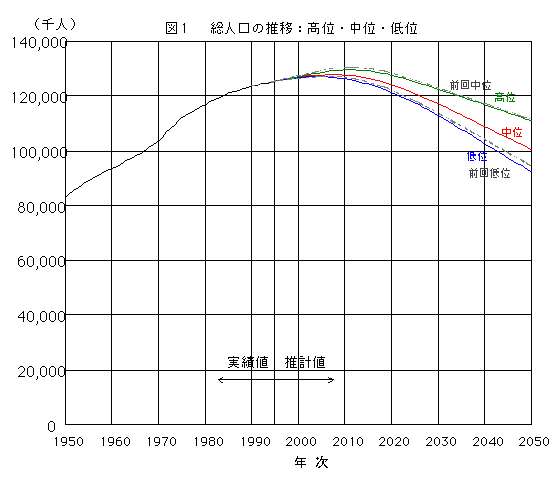
Ⅰ.推計結果の概要
1.総人口の推移
わが国の総人口は平成7(1995)年10月1日現在で1億2,557万人である。今回の中位推計によると、総人口は今後増加を続け、平成12(2000)年の1億2,689万人を経て、平成19(2007)年に1億2,778万人でピークに達した後減少に転じ、推計期間の最終年次の平成62(2050)年には1億50万人に達するものと予想される。
高位推計によれば、総人口は平成23(2011)年に1億2,956万人でピークに達し、以後減少して平成62(2050)年には1億1,096万人に達する(表1、図1)。低位推計では平成16(2004)年に1億2,705万人でピークに達し、以後減少して平成62(2050)年には9,231万人に達する。
| 83,200 | 4.9 | ||||||||
| 89,276 | 5.3 | ||||||||
| 93,419 | 5.7 | ||||||||
| 98,275 | 6.3 | ||||||||
| 103,720 | 7.1 | ||||||||
| 111,940 | 7.9 | ||||||||
| 117,060 | 9.1 | ||||||||
| 121,049 | 10.3 | ||||||||
| 123,611 | 12.1 | ||||||||
| 124,043 | 12.6 | ||||||||
| 124,452 | 13.1 | ||||||||
| 124,764 | 13.5 | ||||||||
| 125,034 | 14.1 | ||||||||
| 125,570 | 125,570 | 125,570 | 125,570 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | ||
| 125,869 | 125,869 | 125,869 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | ||||
| 126,156 | 126,143 | 126,178 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | ||||
| 126,420 | 126,378 | 126,492 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | ||||
| 126,665 | 126,577 | 126,813 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | ||||
| 126,892 | 126,742 | 127,140 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | ||||
| 127,100 | 126,873 | 127,469 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | ||||
| 127,286 | 126,969 | 127,796 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | ||||
| 127,447 | 127,029 | 128,113 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | ||||
| 127,581 | 127,050 | 128,413 | 19.1 | 19.2 | 19.0 | ||||
| 127,684 | 127,031 | 128,690 | 19.6 | 19.7 | 19.4 | ||||
| 127,752 | 126,970 | 128,938 | 20.2 | 20.3 | 20.0 | ||||
| 127,782 | 126,865 | 129,150 | 20.7 | 20.9 | 20.5 | ||||
| 127,772 | 126,716 | 129,322 | 21.2 | 21.4 | 21.0 | ||||
| 127,719 | 126,521 | 129,450 | 21.8 | 22.0 | 21.5 | ||||
| 127,623 | 126,281 | 129,531 | 22.0 | 22.3 | 21.7 | ||||
| 127,481 | 125,994 | 129,563 | 22.2 | 22.5 | 21.9 | ||||
| 127,292 | 125,660 | 129,544 | 23.0 | 23.3 | 22.6 | ||||
| 127,056 | 125,280 | 129,473 | 23.8 | 24.1 | 23.3 | ||||
| 126,773 | 124,855 | 129,349 | 24.6 | 25.0 | 24.1 | ||||
| 126,444 | 124,384 | 129,175 | 25.2 | 25.6 | 24.7 | ||||
| 126,068 | 123,869 | 128,952 | 25.7 | 26.2 | 25.1 | ||||
| 125,648 | 123,311 | 128,680 | 26.1 | 26.6 | 25.5 | ||||
| 125,184 | 122,712 | 128,364 | 26.4 | 27.0 | 25.8 | ||||
| 124,679 | 122,071 | 128,005 | 26.6 | 27.2 | 26.0 | ||||
| 124,133 | 121,391 | 127,608 | 26.9 | 27.5 | 26.1 | ||||
| 123,551 | 120,675 | 127,176 | 27.0 | 27.6 | 26.2 | ||||
| 122,934 | 119,923 | 126,715 | 27.1 | 27.8 | 26.3 | ||||
| 122,287 | 119,139 | 126,229 | 27.2 | 27.9 | 26.3 | ||||
| 121,612 | 118,325 | 125,723 | 27.3 | 28.1 | 26.4 | ||||
| 120,913 | 117,484 | 125,201 | 27.4 | 28.2 | 26.5 | ||||
| 120,193 | 116,618 | 124,667 | 27.5 | 28.3 | 26.5 | ||||
| 119,454 | 115,728 | 124,126 | 27.5 | 28.4 | 26.5 | ||||
| 118,699 | 114,817 | 123,578 | 27.6 | 28.6 | 26.5 | ||||
| 117,930 | 113,887 | 123,027 | 27.8 | 28.7 | 26.6 | ||||
| 117,149 | 112,938 | 122,473 | 28.0 | 29.0 | 26.8 | ||||
| 116,357 | 111,974 | 121,918 | 27.9 | 29.0 | 26.6 | ||||
| 115,557 | 110,994 | 121,362 | 28.2 | 29.3 | 26.8 | ||||
| 114,748 | 110,002 | 120,805 | 28.4 | 29.6 | 27.0 | ||||
| 113,934 | 108,998 | 120,248 | 28.7 | 30.0 | 27.2 | ||||
| 113,114 | 107,985 | 119,689 | 29.0 | 30.4 | 27.4 | ||||
| 112,290 | 106,962 | 119,129 | 29.3 | 30.8 | 27.7 | ||||
| 111,462 | 105,934 | 118,568 | 29.7 | 31.3 | 27.9 | ||||
| 110,632 | 104,900 | 118,004 | 30.2 | 31.8 | 28.3 | ||||
| 109,800 | 103,862 | 117,438 | 30.6 | 32.3 | 28.6 | ||||
| 108,964 | 102,820 | 116,868 | 31.0 | 32.8 | 28.9 | ||||
| 108,125 | 101,773 | 116,293 | 31.3 | 33.2 | 29.1 | ||||
| 107,285 | 100,725 | 115,713 | 31.5 | 33.5 | 29.2 | ||||
| 106,443 | 99,676 | 115,131 | 31.7 | 33.8 | 29.3 | ||||
| 105,601 | 98,627 | 114,546 | 31.8 | 34.1 | 29.4 | ||||
| 104,758 | 97,579 | 113,959 | 32.0 | 34.3 | 29.4 | ||||
| 103,915 | 96,532 | 113,369 | 32.1 | 34.5 | 29.4 | ||||
| 103,065 | 95,479 | 112,772 | 32.1 | 34.7 | 29.4 | ||||
| 102,211 | 94,423 | 112,170 | 32.2 | 34.9 | 29.3 | ||||
| 101,354 | 93,366 | 111,566 | 32.3 | 35.0 | 29.3 | ||||
| 100,496 | 92,309 | 110,962 | 32.3 | 35.2 | 29.2 | ||||
| 96,188 | 87,021 | 107,956 | 31.9 | 35.3 | 28.4 | ||||
| 91,848 | 81,698 | 105,007 | 31.0 | 34.9 | 27.1 | ||||
| 87,636 | 76,476 | 102,257 | 30.3 | 34.5 | 26.2 | ||||
| 83,773 | 71,594 | 99,850 | 30.0 | 34.3 | 26.0 | ||||
| 80,368 | 67,207 | 97,824 | 29.9 | 34.1 | 26.2 | ||||
| 77,375 | 63,316 | 96,104 | 30.0 | 34.0 | 26.4 | ||||
| 74,640 | 59,798 | 94,533 | 29.8 | 33.8 | 26.3 | ||||
| 72,068 | 56,569 | 93,015 | 29.5 | 33.4 | 25.9 | ||||
| 69,635 | 53,596 | 91,523 | 29.1 | 32.9 | 25.7 | ||||
| 67,366 | 50,884 | 90,085 | 28.8 | 32.4 | 25.6 | ||||
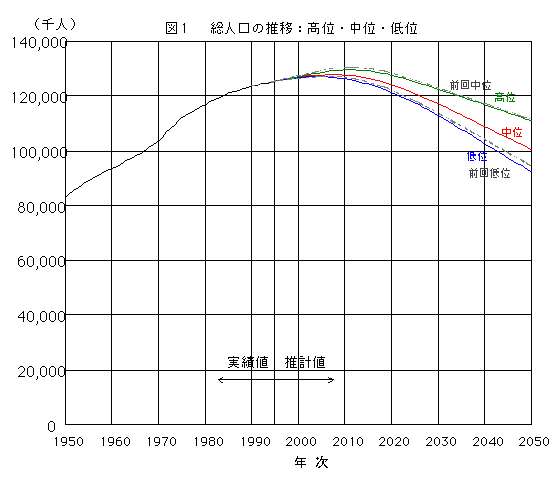
2.年齢別人口の推移
(1)年齢3区分別人口の推移
平成7(1995)年10月1日現在の年齢3区分別人口をみると、年少人口(0~14歳人口と定義)は2,003万人、生産年齢人口(15~64歳人口と定義)は8,726万人、老年人口(65歳以上人口と定義)は1,828万人である。
今回の中位推計によると、年少人口は近年の出生数の減少を反映して平成16(2004)年の1,823万人まで減少を続ける。その後は、出生数の反騰の影響で増加を示し、平成22(2010)年に1,831万人でピークに達する。その後は再び減少して、平成62(2050)年には1,314万人となる。
生産年齢人口は平成7(1995)年以後減少し続け、平成37(2025)年の7,198万人を経て、平成62(2050)年には5,490万人に達する。
老年人口は、今後多少の変動を伴いながら増加を続け、平成37(2025)年の3,312万人を経て、平成62(2050)年には3,245万人となる。
(2)年齢3区分別人口割合の推移
今回の中位推計によると、年少人口の割合は、平成7(1995)年の16.0%から減少を続け、平成15(2003)年には14.3%に達する(図4)。その後も減少を続け、平成32(2020)年に13.7%、平成42(2030)年には12.7%となる。以後は出生数の変動を反映してやや上昇し、平成62(2050)年には13.1%となる。
生産年齢人口の割合は、平成7(1995)年の69.5%から平成33(2021)年の59.4%まで減少を続ける。その後やや増加して、平成40(2028)年の値は59.6%となる。その後再び減少傾向に入り、平成62(2050)には54.6%となる。
老年人口の割合は、平成7(1995)年の14.6%から増加し続け、平成27(2015)年の25.2%まで急増し、その後は緩やかな増加に転じ、平成42(2030)年に28.0%に達する。その後再び増加傾向が強まり、平成61(2049)年にピークに達し、平成62(2050)年には32.3%になる。
(3)従属人口指数の推移
今回の中位推計によると、従属人口指数(年少人口と老年人口の和を生産年齢人口で除した値)は平成7年(1995)年の43.9%から上昇を続け、平成16(2004)年には50%を超え、平成33(2021)年に68.3%に達する。その後はやや低下して平成39(2027)年には67.8%となり、再び増加傾向に入り、平成62(2050)年には83.0%に達する。
年少人口指数(年少人口を生産年齢人口で除した値)は平成7(1995)年で23.0%から21%~24%の間で緩やかに増減を繰り返し、平成62(2050)年は23.9%となる。
老年人口指数(老年人口を生産年齢人口で除した値)は平成7(1995)年の20.9%から一貫して上昇を続け、平成37(2025)年の46.0%を経て、平成62(2050)年には59.1%となる。
3.人口動態率の推移
今回の中位推計によると、普通死亡率(人口千人当たりの死亡数)は平成8(1996)年の7.2‰(パーミル)から一貫して上昇を続け、平成32(2020)年には12.7‰、平成62(2050)年には16.7‰に達する。平均寿命が伸び続けると仮定しているにもかかわらず普通死亡率が上昇を続けるのは、日本の人口が今後急速に高齢化し死亡率の高い老年人口の割合が増えていくためである。
普通出生率(人口千人当たりの出生数)は平成8(1996)年の9.7‰から平成17(2005)年の9.8‰までわずかに回復するが、以後低下を続け平成34(2022)年には8.1‰に達する。その後やや上昇して平成53(2041)年に8.5‰となり、再び低下傾向となり、平成62(2050)年に8.1‰となる。
普通出生率と普通死亡率の差である自然増加率は、平成8(1996)年の2.4‰から一貫して減少し続け、平成20(2008)年からはマイナスに転じ、平成62(2050)年には-8.5‰となる。
4.出生数、死亡数の推移
今回の中位推計によると、年間の出生数は平成8(1996)年の122万から出産年齢人口の増加を反映し、平成16(2004)年の125万まで増加する。その後は減少過程に入り、平成37(2025)年の97万を経て、平成62(2050)年の81万まで減少する。
一方、死亡数は平成8(1996)年の91万から一貫して増加を続け、平成37(2025)年の166万を経て、平成48(2036)年にはピークの176万に達する。その後、やや減少して平成62(2050)年には166万となる。
Ⅱ.推計方法の概要
1.推計期間
推計期間は平成8(1996)年~平成62(2050)年の55年間とした。
2.推計の方法
推計の方法としては、前回同様コーホート要因法を採用した。この方法は、国際人口移動を考慮しつつ、すでに生存する人口については将来生命表を用いて年々加齢していく人口を求めると同時に、新たに生まれる人口については、将来の出生率を用いて将来の出生数を計算してその生存数を求める方法である。コーホート要因法によって将来人口を推計するためには、(1)
基準人口、(2)
将来の生残率、(3)
将来の出生率、(4)
将来の出生性比、(5)
将来の国際人口移動率の5つのデータが必要である。
3.基準人口
推計の出発点となる基準人口は、総務庁統計局『平成7年国勢調査』による平成7(1995)年10月1日現在男女年齢各歳別人口(総人口)を用いた。ただし、年齢「不詳」の人口を各歳別に按分して含めた。
4.生残率の仮定(将来生命表)
すでに生存するある年の人口から翌年の人口を推計するには男女年齢各歳別の生残率が必要であり、それを得るためには将来生命表を作成する必要がある。
将来生命表の作成方法には、年齢別死亡率に基づく方法、死因別死亡率に基づく方法などがあるが、本推計では、年齢区分別死因別死亡率法を採用した。今回用いた方法は、年齢区分を死亡率の水準ならびに変動の差異等を考慮し0~14歳、15~39歳、40~64歳、65歳以上に4区分し、それら年齢区分毎に前回用いた死因別死亡率法を適用した。具体的には、年齢区分毎に死因別年齢標準化死亡率の将来値を推定し、これを年齢別死亡率に変換して将来生命表を作成する方法である。
求められた将来生命表に基づく男女別平均寿命は表2、図5に示されている。これによると、平成7年(1995)年に男子76.36年、女子82.84年であった平均寿命は今後一貫して増加し、平成12(2000)年には男子77.40年、女子84.12年、平成37(2025)年には男子78.80年、女子85.83年、平成62(2050)年には、男子79.43年、女子86.47年に達する。
| (年) | |||||||||||||
5.出生率の仮定
将来の出生数を推計するには、将来における女子の年齢各歳別出生率が必要である。将来の出生率を推計する方法としては期間出生率法とコーホート出生率法があるが、本推計では後者の方法を採用した。コーホート出生率法は、毎年の女子出生コーホート毎に出生過程を観察し、出生過程が完結していないコーホートについて完結出生力の水準と出生タイミングを予測しようとするものである。将来の各年の年齢別出生率ならびに合計特殊出生率は、推計されたコーホート出生率データを年次別データに変換することによって得られる。出生率の将来については不確定要素が大きいため以下の三つの仮定(中位、高位、低位)を設け、それぞれについて出生率を推計した。
(1)中位の仮定について
① コーホート別にみた晩婚化は昭和20(1945)年出生コーホートの24.2歳から昭和55(1980)年出生コーホートの27.4歳まで進み、以後は変わらない。
② 生涯未婚率は昭和16~19(1941~45)年出生コーホートの4.6%から昭和55(1980)年出生コーホートの13.8%まで進み、以後は変わらない。
③ 夫婦の完結出生児数は、晩婚・晩産の影響で昭和18~22(1943~47)年出生コーホートの2.18人から昭和55(1980)年出生コーホートの1.96人まで低下し、以後は変わらない。
④ 全女子の完結出生児数別の分布は以下のように変化し、以後一定となる。
出生児数 |
||||||
(1940-44) | ||||||
(1980) |
この場合、合計特殊出生率は平成7(1995)年の1.42から平成12(2000)年の1.38まで低下した後は上昇に転じ、平成42(2030)年には1.61の水準に達して、以後一定となる。
(2)高位の仮定について
① コーホート別にみた晩婚化は昭和20(1945)年出生コーホートの24.2歳から昭和55(1980)年出生コーホートの25.7歳まで進み、以後は変わらない。
② 生涯未婚率は昭和16~19(1941~45)年出生コーホートの4.6%から昭和55(1980) 年出生コーホートの8.3%まで進み、以後は変わらない。
③ 夫婦の完結出生児数は、晩婚・晩産の影響で昭和18~22(1943~47)年出生コーホートの2.18人から昭和55(1980)年出生コーホートの2.12人まで低下し、以後は変わらない。
④ 全女子の完結出生児数別の分布は以下のように変化し、以後一定となる。
出生児数 |
||||||
(1980) |
この場合、合計特殊出生率は平成7(1995)年の1.42から直ちに上昇に転じ、平成42(2030)年には1.85の水準に到達して、以後一定となる(表3、図6)。
| 8 | ||||||||||
| 9 | 39 | |||||||||
| 10 | 40 | |||||||||
| 11 | 41 | |||||||||
| 12 | 42 | |||||||||
| 13 | 43 | |||||||||
| 14 | 44 | |||||||||
| 15 | 45 | |||||||||
| 16 | 46 | |||||||||
| 17 | 47 | |||||||||
| 18 | 48 | |||||||||
| 19 | 49 | |||||||||
| 20 | 50 | |||||||||
| 21 | 51 | |||||||||
| 22 | 52 | |||||||||
| 23 | 53 | |||||||||
| 24 | 54 | |||||||||
| 25 | 55 | |||||||||
| 26 | 56 | |||||||||
| 27 | 57 | |||||||||
| 28 | 58 | |||||||||
| 29 | 59 | |||||||||
| 30 | 60 | |||||||||
| 31 | 61 | |||||||||
| 32 | 62 | |||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
(3)低位の仮定について
① コーホート別にみた晩婚化は昭和20(1945)年出生コーホートの24.2歳から昭和55(1980)年出生コーホートの28.9歳まで進み、以後は変わらない。
② 生涯未婚率は昭和16~19(1941~45)年出生コーホートの4.6%から昭和55(1980)年出生コーホートの17.9%まで進み、以後は変わらない。
③ 夫婦の完結出生力は、晩婚・晩産の影響で昭和18~22(1943~47)年出生コーホートの2.18人から昭和55(1980)年出生コーホートの1.76人まで低下し、以後は変わらない。
④ 全女子の完結出生児数別の分布は以下のように変化し、以後一定となる。
出生児数 |
||||||
(1980) |
この場合、合計特殊出生率は平成7(1995)年の1.42から平成17(2005)年の1.28まで低下し、その後回復するものの、平成42(2030)年に1.38に達し、以後この水準にとどまる。
6.出生性比の仮定
将来の出生数を男児と女児に分けるための出生性比については、最近の5年間の実績に基づき女子100に対して男子105.6とし、平成8(1996)年以降一定とした。
7.国際人口移動率の仮定
将来の国際人口移動については、最近5年間の男女年齢各歳別入国超過率の平均値を求め、これを平成8(1996)年以降一定と仮定した。
 |
「日本の将来推計人口(平成9年1月推計)」 国立社会保障・人口問題研究所 編 入手については政府刊行物サービスセンターへお問い合わせ下さい。 |