日本の将来推計人口における推計方法は、これまでと同様にコーホート要因法を基礎としている。コーホート要因法とは、年齢別人口の加齢にともなって生ずる年々の変化をその要因(死亡、出生、および人口移動)ごとに計算して将来の人口を求める方法である。すでに生存する人口については、加齢とともに生ずる死亡と国際人口移動を差し引いて将来の人口を求める。また、新たに生まれる人口については、再生産年齢人口に生ずる出生数とその生存数、ならびに人口移動数を順次算出して求め、翌年の人口に組み入れる。
このコーホート要因法によって将来人口を推計するためには、男女年齢別に分類された(1) 基準人口、ならびに同様に分類された(2) 将来の出生率(および出生性比)、(3) 将来の生残率、(4) 将来の国際人口移動率(数)に関する仮定が必要である。本推計では、これらの仮定の設定については、これまでと同様に各要因に関する統計指標の実績値に基づいて、人口統計学的な投影を実施することにより行った。ただし、将来の出生、死亡等の推移は不確実であることから、本推計では複数の仮定を設定し、これらに基づく複数の推計を行うことによって将来の人口推移について一定幅の見通しを与えるものとしている。
推計方法の要約はこちら
1.基準人口
推計の出発点となる基準人口は、総務省統計局『平成22年国勢調査による基準人口』による平成22(2010)年10月1日現在男女年齢各歳別人口(総人口)を用いた。これは、総務省統計局が国勢調査による人口を基準としてその後の人口の推計を行うため、平成22年国勢調査人口(人口等基本集計結果)に含まれる国籍及び年齢不詳人口をあん分して、平成22年国勢調査による基準人口(平成22年10月1日現在)として算出したものである。
2.出生率、および出生性比の仮定
本推計において将来の出生数を推計するためには、当該年次における女性の年齢別出生率が必要である。これを推計する方法として、本推計ではコーホート出生率法を用いた。これは女性の出生コーホート(同一年に生まれた集団)ごとにそのライフコース上の出生過程を観察し、出生過程が完結していないコーホートについては、完結に至るまでの年齢ごとの出生率を推定する方法である。将来各年次の年齢別出生率ならびに合計特殊出生率は、コーホート別の率を年次別の率に組み換えることにより得る。なお、出生率動向の測定の精密化を図る観点から、日本人女性に発生する出生に限定した出生率を対象として実績動向の把握を行い、これに基づいて総人口の出生動向を推計した。したがって、以下に記述する結婚、出生に関する指標の仮定値は、すべて日本人女性における事象に関するものである(外国人女性の出生率の扱いについては後述)。
コーホートの年齢別出生率は出生順位別に生涯の出生確率、出生年齢等を指標としたモデルによって統計的推定ないし仮定設定が行われた。すなわち、出生過程途上のコーホートでは、過程途上の実績値により生涯の出生過程の統計的推定を行うが、実績値が少ないか、あるいはまったく存在しない若いコーホートについては、参照コーホートに対して別途推計された指標をもとに各コーホートの出生過程完了時の指標を算出した。なお、参照コーホートは平成7(1995)年生まれとし、その初婚行動、夫婦の出生行動、ならびに離死別・再婚行動に関する各指標を実績統計に基づいて投影により求め、それらの結果として算定されるコーホート合計特殊出生率、ならびに出生順位別出生分布を定めた。
なお、出生率の将来推移は不確実であることから、出生仮定についてはこれまでと同様に以下の三つの仮定(中位、高位、低位)を設け、それぞれについて将来人口推計を行うこととした。これにより現状から見た出生変動にともなう将来人口の想定し得る変動幅を与えるものとしている。
(1)出生中位の仮定について
① コーホート別にみた女性の平均初婚年齢は、昭和35(1960)年出生コーホートの25.7歳から平成7(1995)年出生コーホートの28.2歳まで進み、平成22(2010)年出生コーホートまでほぼ同水準で推移し以後は変わらない。
② 生涯未婚率は昭和35(1960)年出生コーホートの9.4%から平成7(1995)年出生コーホートの20.1%まで上昇し、平成22(2010)年出生コーホートまでほぼ同水準で推移し以後は変わらない。
③ 夫婦の完結出生児数は、晩婚・晩産の影響および夫婦の出生行動の変化によって変動する。夫婦の出生行動の変化を示す係数(結婚出生力変動係数)は、妻が昭和10(1935)~29(1954)年出生コーホートを基準(1.0)として以後低下し、平成7(1995)年出生コーホートの0.920に至り、平成22(2010)年出生コーホートまでほぼ同水準で推移し以後は変わらない。この係数と①②に示される初婚行動の変化によって、夫婦の完結出生児数は昭和33~37(1958~62)年出生コーホートの2.07人から平成7(1995)年出生コーホートの1.74人まで低下し、以後同水準で推移する。
④ 出生率に対する離婚や死別、再婚の効果は、それらを経験した女性の完結出生児数とそれら配偶関係構造変化の動向により求めた。その結果、出生過程を完結した初婚どうし夫婦の出生水準を基準(1.0)として、離死別・再婚の効果は、昭和35(1960)年出生コーホートの実績値0.962から平成7(1995)年出生コーホートの0.938まで進み、以後は変わらない。
以上、①~④の結果から、日本人女性のコーホート合計特殊出生率は、昭和35(1960)年出生コーホートの実績値1.808から平成7(1995)年出生コーホートの1.301まで低下し、平成22(2010)年出生コーホートまでほぼ同水準で推移し、以後は変わらない。
以上により得られたコーホート年齢別出生率を年次別の出生率に組み替え、さらに実績から求めた外国人女性出生率とのモーメント間の関係を一定と仮定して外国人女性の年齢別出生率を求めた。これらにより人口動態統計と同定義の出生率(外国籍女性が生んだ日本国籍出生児も含めた出生率-下式参照)を推計の際に算出することが可能となる。
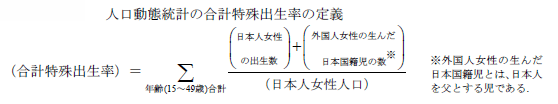
なお、平成23(2011)年3月に発生した東日本大震災の影響により、平成23(2011)年12月以降の出生数に短期的変動が見込まれるため、平成23(2011)年および平成24(2012)年については、阪神淡路大震災が発生した平成7(1995)年における出生数の変動実績ならびに最近における妊娠届出数等を参考にして別途推計し、これを仮定値として用いた。
以上の結果、人口動態統計と同定義による合計特殊出生率は、実績値が1.39であった平成22(2010)年から平成26(2014)年まで、平成24(2012)年の1.37を除き、概ね1.39で推移する。その後平成36(2024)年の1.33に至るまで緩やかに低下し、以後やや上昇して平成42(2030)年の1.34を経て、平成72(2060)年には1.35へと推移する(表4-1、図4-1)。
(2)出生高位の仮定について
① コーホート別にみた女性の平均初婚年齢は平成7(1995)年出生コーホートの27.9歳まで進み、平成22(2010)年出生コーホートまでほぼ同水準で推移し以後は変わらない。
② 生涯未婚率は平成7(1995)年出生コーホートの14.7%を経て、平成22(2010)年出生コーホートで14.3%に至り以後は変わらない。
③ 夫婦の出生行動の変化を示す結婚出生力変動係数は、妻が昭和10(1935)~29(1954)年出生コーホートを基準(1.0)として以後一旦低下するが、平成7(1995)年出生コーホートまでに再び1.0に回復する。この係数と上記の初婚行動の変化によって、夫婦の完結出生児数は平成7(1995)年出生コーホートの1.91人を経て、平成22(2010)年出生コーホートで1.92人に至り、以後は変わらない。
④ 出生率に対する離死別、再婚の効果は、昭和35(1960)年出生コーホートの実績値0.962から平成7(1995)年出生コーホートの0.937まで進み以後は変わらない。
以上、①~④の結果から、日本人女性のコーホート合計特殊出生率は、昭和35(1960)年出生コーホートの実績値1.808から平成7(1995)年出生コーホートの1.531を経て、平成22(2010)年出生コーホートの1.541に至り以後は変わらない。
東日本大震災の影響につき、出生中位仮定と同様の処置を行った後、以上に対応する人口動態統計と同定義の合計特殊出生率は、平成22(2010)年の実績値1.39から平成23(2011)年に1.44となった後、平成32(2020)年に1.61を経て、平成72(2060)年には1.60へと推移する(表4-1、図4-1)。
(3)出生低位の仮定について
① コーホート別にみた女性の平均初婚年齢は平成7(1995)年出生コーホートの28.5歳を経て、平成22(2010)年出生コーホートで28.6歳に至り以後は変わらない。
② 生涯未婚率は平成7(1995)年出生コーホートの26.2%まで進み、平成22(2010)年出生コーホートで26.6%に至り以後は変わらない。
③ 夫婦の出生行動の変化を示す結婚出生力変動係数は、妻が昭和10(1935)~29(1954)年出生コーホートを基準(1.0)として以後低下し、平成7(1995)年出生コーホートの0.842を経て、平成22(2010)年出生コーホートで0.845に至り以後は変わらない。この係数と上記の初婚行動の変化によって、夫婦の完結出生児数は平成7(1995)年出生コーホートの1.57人まで低下し、平成22(2010)年出生コーホートまで同水準で推移し以後は変わらない。
④ 出生率に対する離死別、再婚の効果は、昭和35(1960)年出生コーホートの実績値0.962から平成7(1995)年出生コーホートの0.938まで進み以後は変わらない。
以上、①~④の結果から、日本人女性のコーホート合計特殊出生率は、昭和35(1960)年出生コーホートの実績値1.808から平成7(1995)年出生コーホートの1.087を経て、平成22(2010)年出生コーホートの1.079に至り以後は変わらない。
東日本大震災の影響につき、出生中位仮定と同様の処置を行った後、以上に対応する人口動態統計と同定義の合計特殊出生率は、平成22(2010)年の実績値1.39から平成23(2011)年に1.31となった後、平成35(2023)年に1.08台まで低下し、その後わずかに上昇を示して平成72(2060)年には1.12へと推移する(表4-1、図4-1)。
将来の出生数を男児と女児に分けるための出生性比(女児数100に対する男児数の比)については、2006~2010年の5年間の実績値である105.5を、平成23(2011)年以降一定として用いた。
3.生残率の仮定(将来生命表)
ある年の人口から翌年の人口を推計するには男女年齢各歳別の生残率が必要である。将来の生残率を得るためには将来生命表を作成する必要がある。本推計ではこれを作成する方法として現在国際的に標準的な方法とされるリー・カーター・モデルを採用しつつ、これに対して世界の最高水準の平均寿命を示すわが国の死亡動向の特徴に適合させるため、新たな機構を加えて用いた。リー・カーター・モデルは、年齢別死亡率を、標準となる年齢パターン、死亡の一般的水準(死亡指数)、死亡指数の動きに対する年齢別死亡率変化率および誤差項に分解することで、死亡の一般的水準の変化に応じて年齢ごとに異なる死亡率の変化を記述するモデルである。本推計では、若年層ではリー・カーター・モデルを用いつつ、高齢層では、死亡率改善を死亡率曲線の高齢側へのシフトとして表現するモデル(線形差分モデル)を組みあわせることにより、死亡率改善のめざましいわが国の死亡状況に適合させた。なお、線形差分モデルとは、高齢死亡率曲線の横方向へのシフトの差分を年齢の線形関数によって記述するモデルである。
死亡指数の将来推計にあたっては、最近40年間で徐々に緩やかになっている死亡水準の変化を反映させるために、昭和45(1970)年以降のデータを用い、男女の死亡率の整合性を図る観点から両者同時に関数当てはめを行った。また、線形差分モデルに用いる高齢部の死亡率曲線のシフト量については過去15年間の死亡指数に対する変化率を用いて将来推計し、勾配については直近の平均値(過去5年分)を将来に向けて固定した。
また、近年の死亡水準の改善が従来の理論の想定を超えた動向を示しつつあることから、前回推計同様、今後の死亡率推移ならびに到達水準については不確実性が高いものと判断し、複数の仮定を与えることによって一定の幅による推計を行うものとした。すなわち、標準となる死亡率推移の死亡指数パラメータの分散をブートストラップ法等により求め、これを用いて死亡指数が確率99%で存在する区間を推定して、死亡指数がその上限を推移する高死亡率推計である「死亡高位」仮定、下限を推移する低死亡率推計である「死亡低位」仮定を付加した。
以上の手続きにより求められたパラメータと変数から最終的に平成72(2060)年までの死亡率を男女別各歳別に算出し、将来生命表を推計した。なお、平成23(2011)年については東日本大震災が発生したことから、人口動態統計の死亡数、及び警察庁、岩手・宮城・福島県警察による被害状況データを用い、震災の影響を織り込んだ生命表を別途算定して仮定した。
(1) 死亡中位の仮定について
標準的な将来生命表に基づくと、平成22(2010)年に男性79.64年、女性86.39年であった平均寿命は、平成32(2020)年に男性80.93年、女性87.65年、平成42(2030)年に男性81.95年、女性88.68年となり、平成72(2060)年には男性84.19年、女性90.93年となる(表4-2、図4-2)。
(2) 死亡高位の仮定について
死亡高位の仮定では、中位仮定に比べて死亡率が高めに、したがって平均寿命は低めに推移する。その結果、この仮定においては、平均寿命は平成42(2030)年に男性81.25年、女性87.97年となり、平成72(2060)年には男性83.22年、女性89.96年となる(表4-2、図4-2)。
(3) 死亡低位の仮定について
死亡低位の仮定では、中位仮定に比べて死亡率が低めに、したがって平均寿命は高めに推移する。その結果、この仮定においては、平均寿命は平成42(2030)年に男性82.65年、女性89.39年となり、平成72(2060)年には男性85.14年、女性91.90年となる(表4-2、図4-2)。
4.国際人口移動率(数)の仮定
国際人口移動の動向は、国際化の進展や社会経済情勢の変化、また出入国管理制度や関連規制等によって大きな影響を受ける。また、内外における社会経済事象や災害の発生は国際人口移動に大きな変動をもたらすことがある。近年では同時多発テロ(2001年)、新型肺炎の発生(2002~3年)、リーマンショック(2008年)などがこれにあたる。さらには、平成23(2011)年3月に発生した東日本大震災はわが国における外国人の出入国に大きな変動をもたらした。
国際人口移動数・率の実績値の動向をみると、日本人と外国人では異なった推移傾向を示している。また人口学的にみると日本人の移動は人口の年齢構造による影響を受けるが、外国人の場合にはわが国の人口規模あるいは年齢構造との関係は限定的である。そのため、本推計においては国際人口移動の仮定は日本人と外国人とに分け、日本人については入国超過率、外国人については入国超過数を基礎として仮定値の設定を行った。
日本人の国際人口移動の実績をみると、概ね出国超過の傾向がみられる。また、男女別入国超過率(純移動率)の年齢パターンも比較的安定していることから、平成16(2004)~21(2009)年における日本人の男女年齢別入国超過率の平均値を求め(ただし、年齢ごとに最大値、最小値を除く4か年の値を用いる)、これらから偶然変動を除くための平滑化を行い、平成23(2011)年以降における日本人の入国超過率とした(表4-3、図4-3)。
外国人の国際人口移動の実績をみると、不規則な上下動を繰り返しつつも、概ね入国超過数の増加傾向が続いてきた。ただし、直近の年次においてはリーマンショックや東日本大震災に起因する大規模な出国超過が生じるなど、外国人の出入国傾向は短期間に大きな変動を示している。そこで、昭和45(1970)年以降の外国人入国超過数のうち社会経済事象・災害等の影響により一時的に大きく変動したとみなされる年のデータを除いたうえで、入国超過数の長期趨勢を投影することにより平成42(2030)年までの仮定値とした。ただし、東日本大震災の影響による出国超過の影響については、平成24(2012)年までの仮定値に反映させた。なお、各年の男女別入国超過数は、昭和45(1970)年以降における入国超過数の男女性比の平均値を用いて算出し、それらの年齢別割合については、実績値の得られる昭和61(1986)~平成22(2010)年の平均値を平滑化して用いた(表4-4・表4-5、図4-4・図4-5)。ただし、長期的には外国人の国際人口移動の規模をわが国の人口規模と連動させる必要があるため、各推計において平成42(2030)年の男女年齢別入国超過率(ただし日本人・外国人を合わせた総人口を分母とする)を求め、以降これを一定とした。
目次へ
