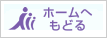(2) 研究計画
平成20年度までの研究成果について,社会政策学会第118回(21年5月)にて報告する。その後は,平成20年度に本研究プロジェクトで行った「2008年社会生活調査」の分析を中心に行い,3月のワークショップで報告する。(3) 研究実施状況
まず,「2008年社会生活調査」を用いて,貧困と社会的排除の実態測定と要因分析がなされた。次に,東京大学と大阪商業大学が2000年以降実施している「日本版総合社会調査」(以下,JGSS調査)の個票データを使い,二つの異なる貧困定義を用いて貧困層を特定し,その属性や世帯類型,就業形態との関係を分析した。社会保険の減免制度,自己負担のあり方と給付に関する研究においては,社会保険制度の中での低所得者対策(保険料の減免制度,自己負担の軽減など)の現状を把握し,その,あり方を検討する。最終年度の平成21年度は,これまでの研究成果を踏まえて,新たな低所得者に対する諸制度を現行の社会保険制度の中で提案する。提案された新しい制度は,①ワーキング・プア対策としての給付つき税額控除,②低所得者に対する医療費補助制度,である。
最後に,低所得者支援制度のあり方に関する研究(公的扶助など)においては,国際機関(おもに経済協力開発機構(OECD))を中心とする国際比較データおよび先行研究のサーベイを行い,日本の最低賃金と生活保護の水準のあり方を検討した。
(4) 研究組織の構成
- 研究代表者
- 阿部 彩(国際関係部第2室長)
- 研究分担者
- 西村幸満(社会保障応用分析研究部第2室長),菊地英明(武蔵大学社会学部准教授),
- 山田篤裕(慶應義塾大学経済学部准教授)
- 研究協力者
- 上枝朱美(東京国際大学経済学部准教授),田宮遊子(神戸学院大学経済学部准教授)
- 西山 裕(北海道大学公共政策大学院教授)
(5) 研究成果の公表
・刊行物厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)『低所得者の実態と社会保障のあり方に関する研究』平成21年度報告書(2010年3月)
阿部 彩「誰が路上に残ったか-自立支援センターからの再路上者とセンター回避者の分析-」『季刊社会保障研究』第45巻第2巻,pp.134-144.(2009年9月)
Abe,Aya"Deprivation and Earlier Disadvantages in Japan."Journal of Social Science Japan(webjournal)
Abe,Aya & Saunders, Peter "Poverty and Deprivation in Young and Old:A Comparative Study of Australia and Japan."Poverty and Public Policy,Vol.2,Iss.1web.
阿部 彩「女性と年金:高齢女性の最低生活保障」『年金と経済』第28巻第3号,pp.29-38.(2009年10月)
阿部 彩「「子ども手当」は社会手当か,公的扶助か」『生活経済政策』第156号,pp.20-24.(2010年1月)
・学会発表等
山田篤裕「国際的パースペクティヴから観た最低賃金・公的扶助の目標性」社会政策学会第119回大会・共通論題『最低賃金制度と生活保護制度-仕事への報酬と生活保障との整合性-』,金城学院大学(2009年10月31日)
社会政策学会第118回(2009年春季)大会テーマ別分科会「-最低生活保障のあり方:データから見えてくるもの-」,日本大学(2009年5月24日)
12 所得・資産・消費と社会保険料・税の関係に着目した社会保障の給付と負担の在り方に関する研究(平成19 ~ 21 年度)
(1) 研究目的
持続可能な社会保障制度を構築するためには,社会経済の変化に応じて絶えず社会保障の給付と負担の在 り方を検討していく必要がある。2008年開始の後期高齢者医療制度の財源は1/2が公費負担であり,基礎年 金も2009年度にその国庫負担割合を2分の1にするため法改正行われた。このように,社会保障財政にお ける税負担の割合が高まる傾向にある今日,社会保険料と税に着目して社会保障の給付と負担の在り方を検 討することは,緊急の課題である。とくに,所得・資産格差の拡大に関心が高まっている今日,給付と負担 の在り方については,社会保障給付と税制それぞれの再分配効果に関する検証に基づく検討が必要である。 また,所得は現役時代に増加し引退期に減少し,資産は所得格差に応じて引退期にも変化するなどライフサ イクルの段階ごとに負担賦課の対象は変化するので,給付と負担の在り方を検討するためには,引退過程の 実態把握も必要である。したがって,本研究では,格差是正とライフサイクルにおけるニーズの変化に対応できる持続可能な社会 保障制度の構築に資するために,所得・消費・資産と社会保険料・税の関係に着目した社会保障の給付と負 担の在り方に関する研究を,所得・消費・資産に関する実証分析と制度分析とを合わせ総合的に行う。
(2) 研究計画
初年度,「国民生活基礎調査」調査票再集計の許諾を得てこれに基づく実証分析と国際比較研究を行う。 2年目は,このような実証分析,国際比較研究,制度分析に加え,ライフサイクルのニーズ変化を把握する ため健康・引退に関するパネル・データ作成を行う。3年目に研究成果全体のとりまとめと普及を行う。本研究では,研究目的で示した問題意識のもとに,所得・資産・消費の実態把握のために「国民生活基礎 調査」等の使用申請に基づく再集計を行い,所得等の分布の変化と人々のライフサイクルに着目した実証分 析を行う。なお,公的統計では必ずしも十分に補足できないが所得・資産・消費に影響を及ぼす事項,例えば引退過程と健康状況等との関係については,アンケート調査を3年計画の各年で実施しパネル・データを構築し,分析を行う。
また,格差是正に配慮しながら負担賦課の対象として所得・資産・消費のいずれを選択するかは,社会保 障制度の各制度における給付と負担の歴史的経緯,現状及び課題に照らして分析する必要があるため,制度 分析・社会保障法学を応用した政策研究を行う。
さらに,わが国の所得・消費・資産の実態を客観的に評価するため,OECDの所得格差比較研究プロジェ クト及び税財源による社会保障制度を持つカナダ等の国々との研究協力を行うとともに,成長著しく所得変 動の大きい東アジア諸国との比較研究を行う。
(3) 研究実施状況
平成21年度は,所得・資産格差の実態と社会保障の給付と負担に関する研究の動向とを把握するために, 「国民生活基礎調査」個票の目的外使用申請に基づく再集計を行うとともに,外部の学界有識者からのヒア リング調査を行った。「国民生活基礎調査」の再集計結果に基づく分析として,人的資産と関連する生涯所 得ベースにおける再分配効果の推計,年金制度を組み入れた世帯構成・所得分布に関するマイクロシミュレー ション,税制を組み入れた再分配効果のマイクロシミュレーション,OECD相対的貧困基準と生活保護基準 の重なりの検討,等のテーマについてそれぞれ研究分担者が分析を行った。ライフサイクルに応じた社会保障の給付と負担の効果を明らかにしてその在り方を考察するために,加齢 とともに変化する健康と引退過程に着目して,前年度と同様,健康と引退に関するアンケート調査を実施し てパネル・データを作成し,これに基づく実証分析を行った。また,疑似パネル・データという手法もある ので「国民生活基礎調査」再集計を活用する場合どのように疑似パネル・データを作ることが可能かその方 法を検討した。
制度分析については,各研究分担者・研究協力者の研究に基づき,社会保障財源への公費投入の動向と公 的年金制度体系に関する考察,介護保険制度の特徴と制度改正の評価,要介護高齢者の収入階級別の家計の 状態に関する分析,地方自治改革の影響を踏まえた公立病院の経済分析,医療保険財政を改善する医薬品産 業政策の在り方(医薬品開発の研究開発促進税制等とジェネリック医薬品の使用促進等),生活保護法における能力活用要件に関する考察などをテーマとして分析を行った。
国際比較研究については,「国民生活基礎調査」個票の再集計を引用活用して,OECDの所得格差比較研 究に協力した。2008年の景気後退の影響を踏まえた比較研究として,近年の定量的研究を参照しながらア メリカの低所得者支援策の評価に関する分析を行った。また成長著しく所得変動の大きい東アジア諸国との 比較研究として,中国の所得格差の要因分解と年金給付の再分配効果の推計,及び賃金格差に関する実証分 析を行った。
(4) 研究組織の構成
- 研究代表者
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部長)
- 研究分担者
- 東 修司(企画部長),米山正敏(同部第1室長),
- 野口晴子(社会保障基礎理論研究部第2室長),山本克也(同部第4室長),
- 酒井 正(同部研究員),小島克久(社会保障応用分析研究部第3室長),
- 尾澤 恵(同部主任研究官),稲垣誠一(年金シニアプラン総合研究機構審議役),
- 岩本康志(東京大学大学院経済学研究科教授),
- 小塩隆士(一橋大学経済研究所教授),
- 田近栄治(一橋大学副学長),西山 裕(北海道大学公共政策大学院教授),
- 濱秋純哉(内閣府経済社会総合研究所研究官),
- チャールズ・ユウジ・ホリオカ(大阪大学社会経済研究所教授),
- 八塩裕之(京都産業大学経済学部准教授),山田篤裕(慶應義塾大学経済学部准教授)
- 野口晴子(社会保障基礎理論研究部第2室長),山本克也(同部第4室長),
- 研究協力者
- 京極髙宣(所長),白瀨由美香(社会保障応用分析研究部研究員),
- 黒田有志弥(同部研究員),長江 亮(早稲田大学高等研究所助教),
- 雍 イ(横浜市立大学大学院院生)
- 黒田有志弥(同部研究員),長江 亮(早稲田大学高等研究所助教),
(5) 研究成果の公表
・刊行物厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)『所得・資産・消費と社会保険料・税の関係に着目した社会保障の給付と負担の在り方に関する研究』平成21年度総合・総括・分担研究報告書(2010年3月)
岩本康志・濱秋純哉「社会保険料の帰着分析」国立社会保障・人口問題研究所編『社会保障財源の効果分析』東京大学出版会( 2009年4月)
小塩隆士「社会保障と税制による再分配効果」『社会保障財源の効果分析』東京大学出版会(2009年4月)
東 修司「税制との関係に着目した公的年金給付と財源等に関する制度的考察」国立社会保障・人口問題研究所編『社会保障財源の制度分析』東京大学出版会(2009年4月)
山本克也「地方分権化の医療保障への影響-公立病院改革ガイドラインと公立病院-」『社会保障財源の効果分析』東京大学出版会(2009年4月)
米山正敏・金子能宏「社会保険料と税に関する賦課徴収の理論と実態」,国立社会保障・人口問題研究所編『社会保障財源の制度分析』東京大学出版会(2009年4月)
金子能宏・雍 イ「中国における公的年金制度の再分配効果と持続可能性との関係-保険数理的な将来推計による分析-」『比較経済研究』第47巻第1号(2010年1月)
・学会発表
金子能宏・雍 イ「中国における所得格差の動向と年金制度の役割」平成21年度比較経済制度学会,立命館大学(2009年10月24日)
濱秋純哉 "Does Health Status Matter to People's Retirement Decision in Japan?:An Evaluation of"Justification Hypothesis" and Measurement Errors in Subjective Health",2009 Far East and South Asia Meeting of the Econometric Society,東京大学(2009年8月4日)
濱秋純哉・野口晴子 "Does Health Status Matter to People's Retirement Decision in Japan?: An Evaluation of "Justification Hypothesis"and Measurement Errors in Subjective Health",7th World Congresson Health Economics,International Health Economics Association,北京大会(2009年7月13日)
小島克久「要介護高齢者の費用負担の動向に関する考察」日本人口学会第61回大会,関西大学(2009年6月14日)
13 医療・介護制度における適切な提供体制の構築と費用適正化に関する実証的研究 (平成19 ~ 21 年度)
(1) 研究目的
本研究の目的はこれまでの医療・介護制度改革について実証的検証を行い,分析結果に基づいて制度改革に関する提言を行うことである。(2) 研究計画
年度当初より,厚生労働省大臣官房統計情報部の調査データの個票,および国民健康保険・介護保険データをマッチングしたデータを利用して分析を進めた。また,英国等に対する現地調査を実施したほか,国内においてもヒアリング調査等を実施した。(3) 研究実施状況
-
① 平均在院日数,転帰,医療費の地域差等について,急性期・慢性期の機能分化による在院日数の短縮には一定程度の効果が確認されたが,介護保険導入の効果は極めて限定的であると考えられた。また,平均在院日数の短縮化は医療費の節約に必ずしも結びついていなかったが,それは技術普及の偏差によ
ると推定された。
② 医療連携の効果について,医療連携を単に報酬で評価することだけでは適切な連携システムの構築のためには十分ではないと考えられた。地域で利用可能な医療・介護資源は異なるため,全国均一のシステムは構築しにくいと考えられた。
③ 患者受診行動の分析について,複数の市町村から提供受けたレセプトデータについて分析を実施した。自宅から遠距離の医療機関に受診している患者ほど医療費が高くなる構造は共通に観察された。医療と介護のレセプトデータを個人単位で接合し,高齢者の入院・入所行動についても分析を行った。患者の 疾病をコントロールした上でも,介護ニーズの高い患者ほど入院期間が長かった。
④ プライマリー・ケア(PC)の制度化可能性について,英国等に現地調査を行って検討した。その調査結果から,「PCとは人々の不安に対処することが本質的に重要であり,不安に対処する方法は信頼できる人が責任を持つことである」と考えられた。
⑤ 自宅死亡割合の分析について,2005年時点の二次医療圏の地域区分を過去に遡って適用し,「人口動態調査」のデータにより経年比較したところ,自宅死亡の割合が高かった地域ほど自宅死亡割合が大きく低下していた。65歳以上に限定して分析したところ,年齢が高いほど自宅死亡割合が高かった。悪性新生物,脳血管疾患,心疾患に限定しても自宅死亡割合の経年的低下が観察された。
(4) 研究組織の構成
- 研究代表者
- 泉田信行(社会保障応用分析研究部第1室長)
- 研究分担者
- 東 修司(企画部長),川越雅弘(社会保障応用分析研究部第4室長),
- 野口晴子(社会保障基礎理論研究部第2室長),菊池 潤(企画部研究員),
- 島崎謙治(政策研究大学院大学政策研究科教授),郡司篤晃(聖学院大学大学院教授),
- 橋本英樹(東京大学大学院医学系研究科教授),田城孝雄(順天堂大学医学部准教授),
- 宮澤 仁(お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科准教授),
- 西田在賢(静岡県立大学地域経営研究センター教授)
- 野口晴子(社会保障基礎理論研究部第2室長),菊池 潤(企画部研究員),
- 研究協力者
- 熊谷成将(近畿大学経済学部准教授),川村 顕(財団法人医療科学研究所研究員),
- 岸由依子(東京大学大学院医学系研究科院生),
- 徳永 睦(東京大学大学院医学系研究科院生)
- 岸由依子(東京大学大学院医学系研究科院生),
(4) 研究成果の公表
・刊行物厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)「医療・介護制度における適切な提供体制の構築と費用適正化に関する実証的研究」平成21年度報告書(2010年3月)
宮澤 仁「東京大都市圏における有料老人ホームの立地と施設特性」E-JournalGEO,vol.4,no.2,pp.69-85(2010年2月)
川越雅弘・小森昌彦・備酒伸彦「病床区分別にみた病床運営および退院先のリハビリテーション連携状況の差異」理学療法兵庫,vol.15,pp.35-42(2009年12月)
住友和弘・泉田信行・野口晴子他「地域住民の受診動向,医療連携の現状分析-中頓別町国民健康保険病院と旭川医科大学病院を事例として-」旭川医科大学フォーラム,vol.10,pp.64-75(2010年2月)
泉田信行「医療サービス供給体制」宮島洋・西村周三・京極髙宣編『社会保障と経済第3巻』,pp.65-87,東京大学出版会(2010年3月)
・学会発表等
川越雅弘・小森昌彦・備酒伸彦「病床区分別にみた病床運営および退院先とのリハビリテーション連携状況の差異」第68回日本公衆衛生学会総会,奈良(2009年10月22日)
14 家族・労働政策等の少子化対策が結婚・出生行動に及ぼす効果に関する総合的研究 (平成20 ~ 22 年度)
(1) 研究目的
政府の少子化への対応は,1994年12月に策定された「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について(エンゼルプラン)」に始まり,その後「新エンゼルプラン」を経て,2005年から「少子化対策大綱」に基づく「子ども・子育て応援プラン」が実施に移された。また,地方自治体や一部の企業では,次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画が実施されている。こうした中で,これまでの政策がどのような形で効果を上げているか,さらに最終的には少子化の進行の抑制や出生率の回復に効果を及ぼしうるのかどうか, 実証的に明らかにすることが求められている。よって,施策の効果とその評価に関する手法の開発や研究が重要である。こうした背景をふまえ,本研究事業は,わが国において社会経済的要因が結婚・出生行動に及ぼす影響を明らかにすること,および政府や自治体が少子化対策として実施している家族・労働政策等がそれらの行動へ及ぼす影響・効果を検証することを通じて,今後の少子化関連施策の展開に資する研究知見を得ることを目的として行った。
(2) 研究計画
この研究では,第一に,出生率の変動に影響を及ぼす社会経済的な諸要因を人口学的,経済学的,社会学 的な観点から分析を行った。第二に,家族政策や労働政策に関連する政策変数と結婚や出生率との関係を表 す計量経済学モデルを開発し,シミュレーション分析によって両者の関係を実証的に検証する作業を行った。 第三に,地域において子育てに関わる父母の育児参加の問題について,ワーク・ライフ・バランスの観点か ら質問紙調査を実施し,政策のあり方について分析を行い,自治体に研究成果を還元した。さらに,第四に, 地方自治体の未婚化・少子化の実態と次世代育成支援対策推進法に基づく地方自治体の行動計画の実施状況 について,ヒアリング調査を行い,その結果から地域における取り組み状況と特性について分析した。(3) 研究実施状況
本研究事業では,研究代表者ならびに各研究分担者によって3つの研究班を構成し,研究協力者の参加のもと研究を実施した。各班の成果は,研究代表者がとりまとめて総括報告書とした。第一の研究班では,「出生率の変動に影響を及ぼす社会経済的な諸要因の人口学的,経済学的,社会学的要因分析」および「家族政策や労働政策に関連する政策変数と結婚・出生率の関係を計量経済学的に把握するモデルの開発」という2つの課題を掲げて研究を進めた。研究方法としては,前者の課題は,各種の人口・社会経済統計データや,就業構造基本調査(総務省)等の調査個票データを利用し,結婚・出生行動に関する社会経済的な規定要因について実証分析を行った。後者の課題については,計量経済学的なマクロ・シミュレーション・モデルによる少子化対策の影響評価研究を行った。研究会は,2009年9月~ 2010年1月に計5回実施した。
第二・第三の研究班は,地域における少子化の分析を担当した。まず第二の研究班は,地域における若い親世代のワーク・ライフ・バランスに及ぼす要因の検討を目的として質問紙調査を行った。調査は,岡山県内2市と神奈川県内1市で実施し,調査対象はそれら地域に在住する末子が就学前の世帯とした。地方自治体と連携した調査のため,各市の保育所・幼稚園を管轄する課を通じて対象該当者に調査協力を求めることができた。
第三の研究班では,地方自治体の未婚化・少子化の実態や,自治体における少子化対策の政策過程について統計分析を行うとともに,結婚対策や,次世代法に基づく前期行動計画の実施状況と問題点,および2010年度から始まる後期行動計画の策定に向けた準備等についての自治体ヒアリング調査を行い,地域における実際の取組み内容を把握・分析した。ヒアリングを行った自治体は,長崎県,大分県,岩手県,および岩手県八幡平市・遠野市・金ヶ崎町,東京都江戸川区,渋谷区,荒川区,中野区,北区,葛飾区,足立区,品川 区,千代田区,新宿区,練馬区である。
(4) 研究組織の構成
- 研究代表者
- 髙橋重郷(副所長)
- 研究分担者
- 佐々井司(人口動向研究部第1室長),守泉理恵(同部主任研究官),
- 中嶋和夫(岡山県立大学保健福祉学部教授)
- 研究協力者
- 別府志海(情報調査分析部主任研究官),鎌田健司(客員研究員),
- 安藏伸治(明治大学政治経済学部教授),大淵 寛(中央大学名誉教授),
- 大石亜希子(千葉大学法経学部准教授),君島菜菜(大正大学非常勤講師),
- 桐野匡史(岡山県立大学保健福祉学部助手),工藤 豪(埼玉学園大学非常勤講師),
- 金 潔(岡山県立大学保健福祉学部准教授),
- 増田幹人(内閣府経済財政分析担当政策企画専門職),
- 永瀬伸子(お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科教授),
- 尹 靖水(梅花女子大学現代人間学部教授),関根さや花(明治大学大学院院生)
- 安藏伸治(明治大学政治経済学部教授),大淵 寛(中央大学名誉教授),
(5) 研究成果の公表
本年度の研究成果は,平成21年度総括・分担研究報告書としてまとめた。また,報告書以外にプロジェ クト参加研究者が発表した成果は以下の通りである。・論文
Ji-Sun Park,Rie Kondo,Jung-Suk Kim,Tsukasa Sasai,Shigesato Takahashi,Chun-Man Park,and Kazuo Nakajima(2009)"Examination of Generating Mechanism Concerning Father's Participation in Child-rearing", Korean Journal of Health Education and Promotion, Vol.26,No.5,pp.57-70( 2009年12月)
鎌田健司「地方自治体における少子化対策の政策過程-「次世代育成支援対策に関する自治体調査」を用いた政策出力タイミングの計量分析-」明治大学『政経論叢』第78巻3・4号,pp.213-242( 2010年1月)
・学会発表
日本人口学会第61回(関西大学,2009年6月12日~ 14日)における研究報告
守泉理恵「日本における第3子出生行動の分析」日本家族社会学会第19回大会,奈良女子大学(2009年9月13日)
守泉理恵「女性の就業と子育て支援」人口学研究会第521回定例会,中央大学理工学部校舎(後楽園キャンパス)6号館(2010年1月9日)
大石亜希子「育児休業給付の引き上げと女性の継続就業」2009年度(財)統計研究会労働市場研究委員会「社会保障と労働市場政策:格差社会のセーフティネットの構造」報告,東京・国際フォーラム(2009年11月15日)
15 人口動態変動および構造変化の見通しとその推計手法に関する総合的研究(平成20 ~ 22 年度)
(1) 研究目的
わが国はすでに恒常的な人口減少過程に入り,同時に少子高齢化も急ピッチで進行している。今後に見込 まれる人口動態ならびに人口構造の未曾有の変動は,わが国の社会経済の基盤を根底から揺るがすものであり,その見通しに定量的な指針を与える将来推計人口の重要性は増大している。しかし一方では前例のない 少子化(出生率低下),長寿化(平均寿命の伸長),国際化(国際人口移動の増大)は,人口動態の見通しを 不透明としており,これらの新たな事態に対する知見の集積や推計技術の開発が急がれている。本研究では, こうした状況を踏まえ,将来人口推計手法の先端的技術と周辺諸科学の知見・技術を総合することにより, 人口動態・構造変動の詳細なメカニズムの解明,モデル化,推計の精密化を図ることを目指す。これまで難 しいとされてきた人口動態~社会経済との連関を考慮した人口推計技術についてのアプローチを含め,実績 統計データの体系化と新たな技術の総合化を目指している。(2) 研究計画
本研究においては,第一に人口変動の元となる国民生活やライフコース・家族の変容・健康や寿命に関す るデータを体系化し,いち早く正確に捉えるための分析システムの開発を行なう。すなわち,既存の人口統 計ソースである国勢調査データ,人口動態統計データ,全国標本調査データの体系的な再集計・分析システ ムの構築を行い,モニタリング体制の確立に取り組んでいる。第二にそれらのシステムと既存の将来推計人 口技術を確率推計手法,多相生命表手法をはじめとする構造化人口動態モデルなどの先端的技術と融合させ, これらの新しい技術の実用化への発展を図るものとする。さらに第三として,社会経済変動との連動など広 い視野を持った研究の基礎として,エージェント技術などに代表される革新的な技術を用いたモデル,なら びにシステムの開発に着手した。これらは,今後予想される人口動態と社会経済との相互関係の複雑化に対 応するものであり,各国の指導的研究者と連携して研究を展開している。(3) 研究実施状況
平成21度の事業ではまず基礎的な作業として,目的外申請によって取得した人口動態統計データの整備 を行ったほか,国連の人口推計データなど内外の人口統計データの整備を合わせて行った。また人口動態の 数理的解析研究として,①変動環境下における人口再生産力の分析,人口動態の実態分析として②出生分 析,③死亡・寿命分析,④国際人口移動分析,人口動態と社会経済変動との関係に関する研究として,⑤出 生意欲を介した出生率と社会経済要因との関係の5領域に関する研究を行った。分野ごとの主な成果は以下 のとおりである。①動態率変動下での純再生産率や内的増加率,繁殖価などの基本的概念の拡張に向けて, 周期的環境変動下における純再生産率の定義および繁殖価概念の拡張を数理的に検討した結果,人口過程の 弱エルゴード性に依拠することで,マルサス的成長解の存在が系の長期的挙動を決定することが示され,純 再生産率,繁殖価の適切な定義が可能であることがわかった。②わが国における2005年以降の合計出生率 の反転上昇の原因とメカニズムを解明するため,まず全国レベルでの年次変動をテンポ効果とそれ以外のピ リオド効果に分離したところ,後者の割合が高いことが示唆された。また,都道府県別に空間自己回帰項を 含む重み付き空間誤差モデルを用いて検証したところ,キャッチアップによる合計出生率の緩やかな上昇が 期待できる側面もあることがわかった。③まず基礎事項として,将来生命表の作成方法として広く使用され ているリー・カーター・モデルの利点と問題点を整理し,課題を検討した後,わが国の推計でこれを修正す る形で採用された「年齢シフトモデル」を年齢変換という概念で一般化しその数理的性質を明らかにすると ともに,わが国の動態に有効な具体的な年齢変換を特定した。④国際人口移動の仮定設定方法について変遷 を整理して課題を明らかにするとともに,新たな指標化によってこれを克服する手法の提言を行っている。 また,様々な検討の結果,仮定設定にシナリオ的要素を導入することを検討する余地があることが示される。 ⑤出生意欲の指標を媒介して社会経済要因を取り入れた推計方法について検討を行った結果,年齢別追加予 定子ども数は社会経済要因によってかなりの程度説明でき,また若い世代ほどその影響が大きく,将来の完 結出生児数を変動させるということが分かった。以上のように各分野とも理論・手法の検討・開発と実証的 な分析の成果が得られ,わが国の人口動態・人口構造変動のメカニズムや社会経済との連関に関する理解に 資するものとなった。(4) 研究組織の構成
- 研究代表者
- 金子隆一(人口動向研究部長)
- 研究分担者
- 佐々井司(人口動向研究部第1室長),岩澤美帆(同部第3室長),
- 石井 太(国際関係部第3室長),守泉理恵(人口動向研究部主任研究官),
- 稲葉 寿(東京大学大学院准教授)
- 石井 太(国際関係部第3室長),守泉理恵(人口動向研究部主任研究官),
- 研究協力者
- 石川 晃(情報調査分析部第2室長),別府志海(同部主任研究官),
- 三田房美(企画部主任研究官),国友直人(東京大学経済学部教授),
- 堀内四郎(ニューヨーク市立大学ハンター校教授),
- 大崎敬子(国連アジア太平洋経済社会委員会),
- エヴァ・フラシャック(ワルシャワ経済大学教授),
- スリパッド・タルジャパルカ(スタンフォード大学教授)
- 三田房美(企画部主任研究官),国友直人(東京大学経済学部教授),
(5) 研究成果の公表
本年度の研究成果は,平成21年度総括研究報告書としてまとめた。また,報告書以外にプロジェクトメ ンバーが公表した研究成果は以下の通りである。・論文
Ryuichi Kaneko, Akira Ishikawa, Futoshi Ishii, Tsukasa Sasai, Miho Iwasawa, Fusami Mita, andRie Moriizumi. 2009."Commentary to Population Projections for Japan-A Supplement to Report of the 2006 Revision-" The Japanese Journal of Population, National Institute of Population and Social Security ResearchVol.7No.1pp.1-46.
金子隆一「将来人口推計における出生仮定設定の枠組みについて」『人口問題研究』第65巻第2号,国立社会保障・人口問題研究所,pp.1-27(2009.9)
H.Inaba(2010),The net reproduction rate and the type reproduction number in multiregional demography, to appear in Vienna Yearbook of Population Research 2009,pp.197-215(2010.3.11)
・学会発表
Ryuichi Kaneko.2009. "Life-course Transformation of Fertility Process in Japan ; Where did the Reduction occur to Which Cohort by What Causes?" Paper presented at the annual meeting of Population Association of America, April 29 to-May 1,2009,Detroit, MI.
Futoshi Ishii,"Future Change of Old-Age Dependency Ratio in Japan-Relating to the Public Pension-" Population Association of America, 2009 Annual Meeting, Detroit(2009.5.1)
Iwasawa,Miho, Kenji Kamata, Kimiko Tanaka and Ryuichi Kaneko. 2009."Regional patterns and correlates in recent family formation in Japan : Spatial Analysis of Upturn in Prefecture-level Fertility after 2005" Paper presented at the annual meeting of Population Association of America, April 29 to May 1,2009,Detroit,MI.
Iwasawa,Miho, Ryuichi Kaneko, Kenji Kamata, Kimiko Tanaka and James Raymo. 2009."Recent family formation patterns in Japan : Evidence from geographical patterns andr egional correlates" Paper presented at the XXVI IUSSP International Population Conference, September 27 to October 2,2009, Marrakech, Morocco.
Ryuichi Kaneko. 2009."Fertility Prospects in Japan : Trends, Recent Rise, and Life Course Developments," paper presented at United Nations Expert Group Meeting on Recent and Future Trends in Fertility, Population Division, United Nations Department of Social and Economic Affairs, New York 2-4 December 2009(2009.12).
Iwasawa, Miho. 2009. "The end of lowest-low fertility in Japan? : explanations for regional fertility reversalafter 2005. "Demographic Seminar, Center for Demography and Ecology, University of Wisconsin-Madison, November 3, 2009, Madison. WI,US.
金子隆一・三田房美,「高齢期における死亡年齢パターンの地域変異と時系列変化の分析」日本人口学会第61回年次大会,関西大学(2009.6.14)
石川晃「行政記録に基づく人口統計の現状と課題」日本人口学会第61回年次大会,関西大学(2009.6.14)
16 東アジアの家族人口学的変動と家族政策に関する国際比較研究 (平成21~ 23年度)
(1) 研究目的
東アジアではかねてから出生促進策を採ってきたシンガポールや日本に加え,2000年代に入って急激な 出生力低下を経験した韓国・台湾も出生促進策に急旋回した。これらは出生促進策を中心としながらも,子 どもの福祉向上,若者の経済的自立,多様化するニーズへの対応等を含む包括的な家族政策パッケージになっ ている。一方で東アジアの極端な出生力低下の要因に対しては,北西欧や英語圏先進国と異なる家族パター ンの重要性が指摘されている。この点で,結婚制度の衰退や不安定化,成人移行の遅れ,世帯規模の縮小と 世帯構造の多様化,国際結婚の増加といった家族人口学的変動の中に出生力低下を位置づけることが,きわ めて重要な意味を持つことになる。本研究は,日本を含む東アジアの低出生力国における家族人口学的変動 と家族政策の展開を比較分析し,それらを通じて得られた知見からわが国の今後の家族変動と家族政策に対 する示唆点を得ようとするものである。(2) 研究計画・実施状況
本研究では,東アジアの低出生力国の家族人口学的変動と家族政策の展開を,文献・理論研究および専門 家インタビュー,マクロおよびマイクロデータの分析,将来予測の各段階を踏んで分析を進める。そのよう な分析を通じて,東アジアにおける家族人口学的変動の特徴を明らかにし,それがどのような家族政策を発 現させ,そうした政策が過去にどの程度の効果を及ぼし,また将来及ぼし得るかを明らかにする。 第一年目の文献・理論研究では,東アジアの低出生力国における出生力低下を含む家族人口学的変動と, その社会経済的要因に関する既存研究を収集し,日本や欧米先進国から得られた知見と比較・検討した。ま た各国における出生促進策を中心とする家族政策パッケージの展開について調査し,その特徴を明らかにし た。アカデミックな文献調査と専門家インタビューを中心に情報を収集するが,それに限定せず,家族変動 や家族政策に関する議論や言説を新聞・雑誌等からも幅広く収集し分析を行った。(3) 研究会等の開催状況
第1回会議兼講演会(8月26日,関西学院大学)今年度研究計画,機関誌原稿執筆について
講演:山地久美子(関西学院大学)「東アジアの家族主義政策の変遷-父系血統から多文化家族まで」
第2回会議(2月19日,国立社会保障・人口問題研究所)
報告書の構成,来年度研究計画について
(4) 研究組織の構成
- 研究代表者
- 鈴木 透(企画部第4室長)
- 研究分担者
- 菅 桂太(人口構造研究部研究員),伊藤正一(関西学院大学経済学部教授),
- 小島 宏(早稲田大学社会科学総合学術院教授)
(5) 研究成果の公表
本年度の研究成果は,平成21年度総括研究報告書として取りまとめた。各研究者が発表した成果は以下の通りである。・論文
鈴木 透「序論:ポスト近代化と東アジアの極低出生力」『人口問題研究』第65巻第4号,pp.1-7,2009年12月
鈴木 透「韓国の極低出生力とセロマジプラン」『人口問題研究』第65巻第4号,pp.8-28,2009年12月
Toru Suzuki, "Trends in Household Formation in Japan : Analysis of the National Survey on Household Changes," in Sato Ryuzaburo(ed.) A Report on Recent Changes in Transition to Adulthood in Japan : Demography, Socioeconomic Implications and Policies, 国立社会保障・人口問題研究所「少子化の要因としての成人期移行の変化に関する人口学的研究」第2報告書,2010年3月
伊藤正一「台湾における少子化のマクロ分析」『人口問題研究』第65巻第4号,pp.29-47,2009年12月
小島 宏「東アジアにおける就業と家族形成意識・行動-JGSS,TSCS,WMFES,EASSの比較分析」『早稲田社会科学総合研究』第10巻第1号,pp.47-73,2009年7月
小島 宏「東アジアにおける同棲とその関連要因-学歴との関連を中心に」『人口問題研究』第66巻第 1号,2010年3月
Ito,Shoichi "The Social Safety Net in China, "in Ichimura, Shinichi, Tsuneaki Sato,and William James(eds.)Transition from Socialist to Market Economics, Chapter 7, Palgrave Macmillan, 2009.
菅 桂太「離家とパートナーシップ形成タイミングの日米比較」『人口問題研究』第65巻第3号,pp.40-57,2009年9月
・学会発表
鈴木 透「若者の就業と家族形成に何が起こっているのか? -親子関係の視点から」日本人口学会第61回大会シンポジウム,関西大学(2009.6.13)
Toru Suzuki,"Policy Measures to Cope with Low Fertility in Tokyo," Low Fertility Issues in Metropolitan Cities : The Current Facts & Policy Reactions, Seoul, Korea, September 3 & 4,2009
Toru Suzuki,"Population Policy in Eastern Asian Low Fertility Countries, "XXVI IUSSP International Population Conference, Marrakech, Morocco, October 2, 2009
鈴木 透「東アジアの超少子化-その人口学的接近」日本人口学会東日本地域部会,早稲田大学(2010.3.14)
Kojima, Hiroshi "Citizenship Implications of Pronatalistic Family Policies in Japan,"International Conference, "Contested Citizenship in East Asia," Seoul, May 28-29, 2009
小島 宏「宗教別人口推計方法の比較」日本人口学会第61回大会,関西大学千里山キャンパス(2009.6.13)
小島 宏「東アジアにおける就業と家族形成ミクロデータの比較分析」日本家族社会学会第19回大会,奈良女子大学(2009.9.13)
小島 宏「同棲の規定要因」第82回日本社会学会大会,立教大学池袋キャンパス(2009.10.11)
小島 宏「アジアの少子化と人口政策」福祉社会学会第26回研究例会,名古屋大学(2009.11.7)
小島 宏「東アジア・欧米諸国における同棲とその関連要因-少子化対策への含意」日本人口学会東日本地域部会,早稲田大学(2010.3.14)
菅 桂太「離家とパートナーシップ形成タイミング-日米比較」日本人口学会第1回東日本部会,札幌市立大学(2009.9.4)
菅 桂太「シンガポールにおける少子化要因の分析-少子化対策への含意」日本人口学会東日本地域部会,早稲田大学(2010.3.14)
(障害保健福祉総合研究事業)
17 障害者の自立支援と「合理的配慮」に関する研究-諸外国の実態と制度に学ぶ障害者自立支援法の可能性-(平成20 ~ 22 年度)
平成21年度総合研究報告書及はここからZIPでダウンロードできます。(1) 研究目的
本研究では,障害者権利条約の将来の批准を見据えて,日本における障害者政策においてどのような解 決すべき課題があるのかを,「合理的配慮」というキーワードの理解を深めながら,課題を拾い出すことを 目標にしている。3年計画の2年目である平成21年度は当事者が求める「合理的配慮」とは何かを念頭に研究を行った。(2) 研究計画・実施状況
障害者権利条約において「合理的配慮」が行われないことを障害者差別と定義したことで,各分野における合理的配慮の範囲や限界について検討する必要がでてきた。本研究では第19条自立した生活及び地域社会に受け入れられること第27条労働及び雇用第33条国内における実施及び監視について,3つの条文 の範囲について「合理的配慮」の政策における実行可能性を踏まえて研究の範囲としている。第19条関連では,アメリカ合衆国・カリフォルニア州の発達障害者のためのリージョナルセンターサービスについての検討,カナダ・マニトバ州における"In the company of friends" 制度について検討,スウェーデンにおける脱施設化の過程の検討,パーソナルアシスタントやダイレクトペイメントの経験が長いイギリスにおける障害者問題対策局(Office for Disability Issues)の考察,国内のパーソナルアシスタント利用者については,インタビュー調査を通じて地域差と介助するものと介助される者との意識を明らかにした。ま た,ダイレクトペイメントを国内に導入するために,どのような課題があるかについても整理した。
第27条関連では,外国については,保護雇用(シェルタードエンプロイメント)の国際的位置付けを障害者権利条約の策定過程において整理し,国内については,障害者雇用のさまざまな公的統計からその課題を検討する一方,社会的事業所の実例について北海道札幌市,大阪府箕面市の社会的事業所制度に関するヒヤリングを実施しその考察をまとめている。
第33条関連では,韓国政府保健福祉家族部における研究(2009年発行)「障害者差別改善モニタリングシステム構築のための政策研究」の日本語訳を作成し,条約批准後に新たに構築する監視委員会の在り方について諸外国の実態から検討を実施した。このほか,障害者自立支援法でも特に対応の遅れを指摘されている精神障害者について検討するため,アメリカにおける精神障害者の合理的配慮の実例について判例をもとに考察を行っている。なお,国内における自立支援法導入後の動向についても把握すべく,委託研究「地域 主導による障害者支援プロセスのケーススタディ」を実施した。調査では行政のみならず市民も広く参画して地域主導の障害者支援プロセスを実践している事例として,兵庫県西宮市を取り上げた。地域の実践のなかで,障害者権利条約の掲げる障害当事者の地域生活の実現のための政策的に重要なポイントが明らかにされた。
(3) 研究会等の開催状況
・研究会第1回研究分担者及び研究協力者による平成20年度分最終報告(Part3)
平成21年4月11日(土)
第2回研究会『障害者の権利条約の各国の批准状況と国内法への影響について( UNESCAP会議の報告を中心に)』
報告者:勝又幸子(研究代表者)
平成21年7月31日(金)
第3回研究会『「労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会」における議論-主な論点を中心に-』
講師:松井亮輔(法政大学現代福祉学部教授)
平成21年8月24日(月)
第4回研究会『オーストラリアにおける障害児教育-ニューサウスウェールズ州を中心に』
講師:安倍冴子(埼玉大学教育学部特別支援教育講座准教授)
平成21年8月31日(月)
第5回『特別支援教育と政治的戦略-英国の2人の女性をめぐって-』
講師:落合俊郎(広島大学大学院教育学研究科教授)
第6回研究会研究分担者及び研究協力者による中間報告(Part1)
平成21年12月26日(土)
第7回研究会研究分担者及び研究協力者による中間報告(Part2)
平成22年1月15日(金)
(4) 研究組織の構成
- 研究代表者
- 勝又幸子(情報調査分析部長)
- 研究分担者
- 岡部耕典(早稲田大学文学学術院准教授),土屋 葉(愛知大学文学部准教授),
- 遠山真世(立教大学コミュニティ福祉学部助教),
- 星加良司(東京大学大学院教育学研究科専任講師)
- 遠山真世(立教大学コミュニティ福祉学部助教),
- 研究協力者
- 白瀨由美香(社会保障応用分析研究部研究員),磯野 博(静岡福祉医療専門学校教員),
- 大村美保(東洋大学大学院院生),木口恵美子(東洋大学社会学部助教),
- 佐々木愛佳(自立生活センター日野コーディネーター),
- 中原 耕(同志社大学大学院社会学研究科院生),山村りつ(同研究科院生),
- 西山 裕(北海道大学公共政策大学院教授)
- 大村美保(東洋大学大学院院生),木口恵美子(東洋大学社会学部助教),
(5) 研究成果の公表
・刊行物平成21年度総括研究報告書「障害者の自立支援と「合理的配慮」に関する研究-諸外国の実態と制度に学ぶ障害者自立支援法の可能性-」(2010年3月)
岡部耕典『知的障害者が「自分の家」で暮らすための支援-アメリカ・カリフォルニア州のサポーテッドリビング・サービス』ノーマライゼーション12月号,第20巻12号,pp.44-47(2009年12月)
中原耕『居住に関する権利と施設入所-国連の障害者政策を通して』『同志社大学大学院社会福祉学論集』第24号,pp.24-41(2010年3月)
・学会発表
日本社会福祉学会第57回全国大会
日程:平成21年10月10~ 11日
場所:東京都町田市法政大学
勝又幸子『障害者権利条約第33条「国内における実施及び監視」について-日本と諸外国におけるアプローチ比較-』
岡部耕典『知的障害者の「生活の自律」とそのために必要な支援-アメリカ・カリフォルニア州における調査を踏まえて』
障害学会第6回大会
日程:平成21年9月26~ 27日
場所:京都府立命館大学
磯野 博『障害者雇用における保護雇用のあり方に関する一考察-障害者の所得保障のあり方を視野に入れて-』
星加良司『Equality of Opportunity and Japanese Type of Quota System in Employment Todai Forum 2009 in UK(Manchester Metropolitan University)"Disability and Economy : Creating a SocietyforAll"』
(統計情報総合研究事業)
19 パネル調査(縦断調査)に関する統合的高度統計分析システムの開発研究(平成20 ~ 21 年度)
(1) 研究目的
厚生労働省は国民生活について国が講ずるべき施策検討の基礎資料を得るために,国民の生活やライフコー ス上の各種事象の規定要因の特定,施策の効果測定等を主眼として,21世紀縦断調査を実施している。縦 断調査は行政ニーズの把握や施策効果の測定に有効な調査形態であるが,その活用には横断調査と異なる独 自のデータ管理と分析手法が必要である。しかし上記の調査は日本の政府統計上初のパネル調査であり,管 理・分析法に関する知識,経験の蓄積は十分とはいえない。本研究では,この縦断調査について基礎分析か ら高度統計分析にいたる科学的な分析によって行政ニーズの把握や施策効果の測定を行うためのデータ管理 から統計分析手法の適用までを統合化するシステムを開発するとともに,多様な分析法の相互の関係や位置 づけが明確となるよう,3調査における調査テーマならびにその分析手法の体系化を行うことを目的とする。 また,標本脱落等の縦断調査データ特有の問題点やそれらの対処法についても検討する。以上によって,信 頼性の高い調査分析結果を効率的に提供するためのインフラ構築を目指す。(2) 研究計画
研究は平成20,21年度の2ヶ年で行うものとし,平成20年度はすでに構築されたパネル情報ベースのコ ンテンツを充実するための国内外のパネル調査に関する概要や分析手法の情報収集を行い,同様にすでに構 築されたデータ管理,分析システムの実装と実用化における課題とその解決のための方策の検討を行なった。 また,調査テーマとその分析手法の体系化に取り組み,さらに脱落等データ特性に関する研究の追加等を行 なった。平成21年度は情報ベースの拡張,分析システムについて検討された方策についての開発と確立, ならびに分析手法の高度化,体系化された調査テーマに沿った事例研究によるデータ特性ならびに分析手法 の検討などを行った。これら2ヶ年の研究を通して開発されたシステムは実用性を強化し,本格的な分析の 実効ある支援が可能なものとする。本事業の成果として,年々蓄積されて行く縦断調査データに対し,縦断 調査特有のデータ管理から高度統計分析までを統合化するシステムを開発することにより,速やかで質の高 い結果公表に資することと,方法論,分析結果の双方において国際的に価値の高い貢献が得られることが期 待される。(3) 研究実施状況
本事業では,①データ管理・統計分析システムの開発,②パネル調査に関する情報ベースの開発,③分析 手法の確立・体系化,④データ特性の分析・把握,⑤事例研究とその体系化,という五つの領域に分けて, それぞれ並行して研究を進めており,①~③にあたるシステム開発ならびに手法確立・体系化については, これまで開発を進めてきたデータ管理・分析統合支援システム( PDA21)ならびにパネル調査情報ベース システム,さらに分析手法の検討・体系化の結果を踏襲し,完成に向けて作業を継続し,これらに並行する 形で④⑤の領域においては次に挙げる個別のテーマを設定して研究を進めた。すなわち,④としては,出生 児調査,成年者調査における脱落の状況と要因の把握,ならびに分析結果への影響の評価,出生児調査の回 答者・保育担当者の不一致の問題,対象児の特徴の横断調査との比較,希望子ども数無回答の把握・分析, 脱落を考慮した因果分析の試み,マイクロシミュレーション分析システム作成作業などが行われた。一方, ⑤としては,出生児調査に関するものとして,成長パターンの測定,肥満危険因子と社会的因子・生活環境 因子,第2子出生タイミング,婚外出生児,若年出産と高齢出産,社会経済階層と疾病・育児不安・負担感, 父親の不在の影響,子ども観と育児方針,子育て費用と習い事に関する分析,成年者調査に関するものとし て,配偶者選択選好,結婚意欲に関する分析,中高年者調査に対するものとして,健康状態変化とその要因 に関する分析が,それぞれ行われた。今後は一般の利用に向けた体系化,実用化のための作業を行うことが 予定されている。(4) 研究組織の構成
- 研究代表者
- 金子隆一(人口動向研究部長)
- 研究分担者
- 釜野さおり(人口動向研究部第2室長),北村行伸(一橋大学経済研究所教授)
- 研究協力者
- 阿部 彩(国際関係部第2室長),石井 太(同部第3室長),
- 岩澤美帆(人口動向研究部第3室長),守泉理恵(同部主任研究官),
- 三田房美(企画部主任研究官),鎌田健司(客員研究員),
- 阿藤 誠(早稲田大学人間科学学術院特任教授),津谷典子(慶應義塾大学経済学部教授),
- 中田 正(日興ファイナンシャルインテリジェンス副理事長),
- 西野淑美(首都大学東京都市教養学部助教),
- 福田節也(マックスプランク人口研究所研究員),
- 相馬直子(横浜国立大学大学院国際社会科学研究科准教授),
- 元森絵里子(明治学院大学社会学部専任講師),
- 井出博生(東京大学医学部付属病院助教),
- 藤原武男(国立保健医療科学院生涯保健部行動科学室長)
- 岩澤美帆(人口動向研究部第3室長),守泉理恵(同部主任研究官),
(5) 研究成果の公表
本年度の研究成果は,『平成21年度総括研究報告書-パネル調査(縦断調査)に関する統合的高度統計分析システムの開発研究』ならびに『平成20-21年度総合研究報告書-パネル調査(縦断調査)に関する統合的高度統計分析システムの開発研究』として取りまとめた。