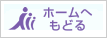欧米における既存研究を参考としながら「社会的包摂-排除」の概念を明らかにし,日本の実状に合った社会的排除の指標を作成する。また,作成された指標を基に,質問紙を設計し,大規模調査を行い,社会的排除と所得・世帯属性・個人属性・ライフヒストリーなどとの関連を分析する。
既存の大規模統計調査を用いて,社会から排除されていると思われる人々(貧困者,失業者,不安定就労者,障害者など)の状況を定量的に分析する。分析では経済状況を中心に分析するとともに,上記①で作成された社会的排除指標に沿った分析も行う。同時に,公的年金や公的医療保険,生活保護,児童扶養手当等の社会保障制度がこれらの人々に与えている効果(経済的効果だけでなくこれらの人々の主観的満足度等を含む)を計測する。
近年蓄積が進んでいる,排除されていると考えられる者(失業者・ホームレス等)を対象にした,生活史の定性調査結果を理論・実証の両面から再検討する。
(2) 研究計画
平成16・17 年度は,平成14 年『社会生活調査』を用いて社会的排除指標およびそれに関連する相対的剥奪指標を構築し,社会的排除のリスクが高いグループの分析,所得との関連等の分析を行った。さらに,欧米における既存の貧困・社会的排除に関する社会調査のサーベイとその概念の整理,『社会生活調査』の問題点を明らかにした上で,調査票を設計し,K 市を対象とする大規模調査を行った。平成18 年度は調査の詳細な分析を行い,その結果をワークショップの開催などによって公表し,学識研究者,実務担当者などとの意見交換を行う。(3) 研究組織の構成
- 主任研究者
- 阿部 彩(国際関係部第2 室長)
- 分担研究者
- 西村幸満(社会保障応用分析研究部第2 室長),菊地英明(社会保障基礎理論研究部研究員),
- 大石亜希子(千葉大学法経学部助教授),
- 後藤玲子(立命館大学大学院先端総合学術研究科教授)
- 大石亜希子(千葉大学法経学部助教授),
- 研究協力者
- 稲田七海(客員研究員)
(4) 研究結果の公表予定
本研究の成果の一部は,平成18 年度に行うワークショップにて報告される。また,『季刊社会保障研究』の特集として,とりまとめられる予定である。
15 税制と社会保障に関する研究(平成17 ~ 18 年度)
(1) 研究目的
平成19 年度を目処に税制の抜本的改革が予定されている中,平成17 年度税制改正の答申にあるように,経済社会の構造変化を踏まえて税・社会保障負担のあり方を検討する必要性がある。したがって,本研究は,消費税等の税と社会保険料の転嫁・帰着,国民負担率と経済活動の関係,税と保険料の役割分担,家族政策における手当と税制の関係等に関する実証分析と制度分析を行い,これらの成果を合わせて税制と社会保障の望ましい在り方について研究することを目的とする。(2) 研究計画・実施状況
1 年目の平成17 年度は,各種統計データ・文献収集,転嫁と帰着に関する文献研究,各方面(社会保障制度,経済,財政(国家財政及び地方財政)等)の専門家からヒアリングを行うとともに,これらの成果に制度論的分析を加えた論点に基づき,計量分析を用いて制度改正を行った場合の影響分析等を行った。とくに社会保障財源として消費税を利用することについて議論が進んでいるなかで,税の転嫁と帰着に関する時系列分析の応用と,企業に対するアンケート調査を活用して,計量分析を進めた。 また,制度分析においては,消費に課税する付加価値税の税率がより高いEU 諸国の動向やOECD による財政動向分析も活用して,国際的な社会保障と税制との動きをフォローした分析を行った。2 年目の平成18 年度は,1 年目の結果を踏まえ,企業アンケート調査のフォローアップと所得・消費・資産等の課税ベースの選択と保険料との関係及びその帰着(分配面への影響等)を見るための実証分析,並びに制度論的分析を進める。そして,これらの成果を反映させたモデル分析等による推計を活用しつつ,税制と社会保障の主要な論点について今後のグランドデザインの構築を行う。
具体的な研究課題としては,これまでも議論が行われてきた点であるが,社会保険料と消費税の選択が大きな争点になりつつある状況を考えれば,消費税等の税及び社会保険料の比較転嫁・帰着の問題を主要な論点として取り上げる。計量分析については,マクロ経済モデルを用いた転嫁と帰着に関する分析を行う。企業調査については,1 年目において製造業と流通業の大企業を対象とした調査を実施したが,調査対象を比較するために2 年目には中小企業を対象とした調査を実施する。また,国民負担率と経済活動の関係,税と保険料の役割分担,家族政策における手当と税制の関係,適切な課税ベースとは何か等についても研究を行う。
制度分析については,社会保障法学関係者に加えて,税法や会計分野の専門家からもヒアリングを行い,多角的な分析を試みる。
なお,研究に漏れがないかどうか等について,以下の主要な論点を中心に,宮島洋教授(早稲田大学)や小西砂千夫教授(関西学院大学)などの所外の有識者からアドバイスを受けながら,研究を行う。
(3) 研究組織の構成
- 主任研究者
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部長)
- 分担研究者
- 島崎謙治(政策研究調整官), 本田達郎(企画部長),米山正敏(同部第1 室長),
- 山本克也(社会保障基礎理論研究部第4 室長),
- 尾澤 恵(社会保障応用分析研究部研究員),酒井 正(企画部研究員),
- 漆原克文(川崎医療福祉大学医療福祉学部教授),
- 加藤久和(明治大学政治経済学部教授),佐藤雅代(北海道大学公共政策大学院特任助教授),
- 宮里尚三(日本大学経済学部専任講師),
- 小島克久(日本社会事業大学社会事業研究所派遣研究員)
- 山本克也(社会保障基礎理論研究部第4 室長),
- 研究協力者
- 宮島 洋(早稲田大学法科大学院教授),小西砂千夫(関西学院大学経済学部教授),
- 山重慎二(一橋大学大学院経済学研究科助教授),
- 横山由紀子(兵庫県立大学経営学部専任講師),? 豊(青山学院大学法学部助教授)
- 山重慎二(一橋大学大学院経済学研究科助教授),
16 国際比較パネル調査による少子社会の要因と政策的対応に関する総合的研究(平成17 ~ 19 年度)
(1) 研究目的
本研究は,平成14 年度から16 年度まで3 年間実施してきた「「世代とジェンダー」の視点からみた少子高齢社会に関する国際比較研究」プロジェクトを踏まえた上で,新たにパネル調査の実施や政策効果に関する研究を行う総合的研究を企図したものである。日本を含む国際比較可能なマクロ・ミクロ両データの分析に基づいて,結婚・同棲などを含む男女のパートナー関係,子育て関係などの先進国間の共通性と日本的特徴を把握し,これによって,日本における未婚化・少子化の要因分析と政策提言に資することを目的とする。(2) 研究方法・活動計画
本研究は,個人を単位とした調査の実施・分析(ミクロ・データ)と各国の法制度改革時期や行政統計データを含むマクロ・データ・ベースの構築という,大きな2 つの柱からなる。前者のミクロ・データについてはドイツのマックスプランク人口研究所が中心となり質問検討委員会が構成され,比較可能な共通のフレームで実査を行う。後者は,フランス国立人口研究所が中心となってデータベース委員会が構成され,マクロ・データに関する基本方針が決定される。これら2 つの委員会の方針に従って,各参加国は調査実施とマクロ・データの提供を行う。さらに,ミクロ班で設定されたテーマのもと,ミクロ・データ,マクロ・データを用いて多層的な国際比較研究を行う。18 年度は,具体的に以下の活動を行う(第2 年度目)。- 国連ヨーロッパ経済委員会人口部が主催するGGP 国際共同会議に出席し,日本で実施予定の第2 回「ジェンダーと世代パネル調査」の概要を報告する(於スロベニア)。また,GGP 参加各国の意見を持ちより,日本側の見解を明らかにし,最終的な調査票の確定へ向けて作業を進める。
- 第2 回「ジェンダーと世代パネル調査」の本調査を実施する。
- GGP のホーム・ページ用に,日本での調査の進行状況や第1 回調査の結果について情報を提供する。
- GGP マクロ・データ・ベース委員会が提示した共通フレームに基づき,マクロ・データ・ベースのためのデータ入力作業を行う。
- 前年度に引き続き,「GGP ニューズ・レター」を刊行し,本プロジェクトの進捗状況の公表と被調査者へのフォローアップを継続する。
- 日本の第1 回GGP データとイタリア,ドイツなど,すでにGGP 第1 回調査を終えた国々のデータを利用して国際比較分析を行う。
(3) 研究組織の構成
- 主任研究者
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 分担研究者
- 福田亘孝(人口構造研究部第1 室長),
- 阿藤 誠(早稲田大学人間科学学術院特任教授),津谷典子(慶應義塾大学経済学部教授)
- 研究協力者
- 菅 桂太(客員研究員),
- 赤地麻由子(元人口構造研究部研究員),
- 岩間暁子(和光大学人間関係学部助教授),
- 田渕六郎(名古屋大学大学院環境学研究科助教授),
- 吉田千鶴(関東学院大学経済学部講師),星 敦士(甲南大学文学部講師)
- 赤地麻由子(元人口構造研究部研究員),
17 少子化関連施策の効果と出生率の見通しに関する研究(平成17 ~ 19 年度)
(1) 研究目的
政府は,2004 年に「少子化対策大綱」を閣議決定し,従来の「子育て支援」政策から「出生率上昇」政策へとより積極的に少子化問題への取り組みを始めた。こうした少子化対策については,その政策の効果を評価し,より一層効果的な施策展開の必要性が求められている。本研究は,少子化関連施策の効果を人口学,社会学,経済学などの学問的見地から評価研究を行い,今後の少子化対策について家族労働政策の視点から効果的な施策提言をすることを目的として実施する。具体的には,
- マクロ計量経済モデルにならびに社会経済学的分析手法による少子化対策要因の出生率におよぼす影響評価研究
マクロ計量経済モデルによる少子化対策要因ならびに家族・労働政策要因のシミュレーション研究により,保育キャパシティ(保育需要に対する施策拡大),出産育児の機会費用(女性就業の制約改善による育児コストの低減)等の施策要因が合計特殊出生率の動向にどのような効果を及ぼすかを測定評価する。
- 地方自治体の少子化対策に関する効果研究
自治体において取り組まれる少子化対策(少子化対策の行動計画)が,各自治体における他の施策や自治体の置かれている様々な環境条件との組み合わせで,具体的に自治体単位の出生率がどのように変化しているのかを分析し,自治体における少子化対策の効果を評価し,そのあり方を施策提言する。
- 少子化の見通しならびに少子化対策に関する専門家調査
近年,人口学・経済学・社会学等様々な研究領域において議論が展開されつつある少子化の見通しや少子化対策に対する考え方を把握し,それら専門家の少子化対策に対する評価ならびに少子化の見通しに関する意見をデルファイ(反復)調査により分析し,現在実施あるいは取り組まれようとしている少子化対策改善のための基礎資料を得る。また今後実施される将来人口推計の議論展開に寄与するための基礎資料として活用する。
本研究では,人口学・社会学,経済学などのあらゆる分野の研究成果を活用しながら,上述の3 つの研究の柱から研究を進め,より効果的な少子化対策のあり方を評価するとともに将来の出生率改善への見通しを検討するとともに,国と地方における少子化対策にかかわる厚生労働政策の推進に貢献することを目的として行う。(2) 研究計画
- マクロ計量経済モデルならびに社会経済学的分析手法による少子化対策要因の出生率におよぼす影響評価研究
- 平成17 年度
ア. 少子化対策要因評価のためのマクロ計量経済モデルの開発
イ. 少子化要因を把握するための社会経済要因分析
ウ. 少子化対策にかかわる基礎資料の情報収集ならびに分析- 平成18 年度
ア. 少子化対策要因評価のためのマクロ計量経済モデルによる分析
イ. 少子化要因を把握するための社会経済要因分析- 平成19 年度
ア. 少子化対策要因評価のためのマクロ計量経済モデルによる分析
イ. 政策要因の変化にともなう効果の分析
ウ. 少子化の社会経済要因に対する施策の検証 - 平成17 年度
- マクロ計量経済モデルならびに社会経済学的分析手法による少子化対策要因の出生率におよぼす影響評価研究
- 地方自治体の少子化対策に関する効果研究
ア. 次世代育成支援推進法にもとづく自治体行動計画を策定した地域のうち,既に自治体が独自に調査を実施している地域から,調査データの提供を受け,調査分析の実施
イ. 研究対象地域のヒアリング調査を通じた効果分析
ウ. 地域マクロデータの分析
エ. 出生率上昇地域と低下地域の差異に関する研究
オ. 少子化地域政策の効果の評価 - 少子化の見通しならびに少子化対策に関する専門家調査
- 平成17・18 年度
ア. 専門家調査の設計
イ. 第1 回調査の実施と分析
ウ. 第2 回調査の実施
エ. 第1 回調査と第2 回調査の分析 - 平成19 年度
ア. 調査データに基づく,少子化対策の有効性に関する分析
イ. 寿命動向等の人口学的調査項目の分析
ウ. 将来出生率等の確率分布の研究
- 平成17・18 年度
(3) 研究組織の構成
- 主任研究者
- 高橋重郷(副所長)
- 分担研究者
- 佐々井 司(人口動向研究部第1 室長),守泉理恵(同部研究員),
- 中嶋和夫(岡山県立大学保健福祉学部教授),安藏伸治(明治大学政治経済学部教授)
- 研究協力者
- 別府志海(情報調査分析部研究員),
- 大石亜希子(千葉大学法経学部助教授),大淵 寛(中央大学経済学部教授),
- 和田光平(中央大学経済学部教授),加藤久和(明治大学政治経済学部教授),
- 仙田幸子(千葉経済大学経済学部助教授),永瀬伸子(お茶の水女子大学生活科学部助教授),
- 渡邉吉利(エイジング総合研究センター主任研究員),君島菜菜(大正大学講師),
- 新谷由里子(武蔵野大学非常勤講師),福田節也(明治大学政治経済学部助手),
- 増田幹人(東海大学非常勤講師),鎌田健司(明治大学政治経済学部助手)
- 大石亜希子(千葉大学法経学部助教授),大淵 寛(中央大学経済学部教授),
18 将来人口推計の手法と仮定に関する総合的研究(平成17 ~ 19 年度)
(1) 研究目的
少子高齢化が進み人口減少が始まろうとする現在,社会経済施策立案に不可欠な将来推計人口の重要性はかつてない高まりを見せている。しかしながら,同時に前例のない少子化,長寿化は人口動態の見通しをきわめて困難なものとしている。本研究では,こうした中で社会的な要請に応え得る科学的な将来推計の在り方を再検討し,手法および人口の実態の把握と見通しの策定(仮定設定)の両面から推計システムを再構築することを目的とする。第1 に,人口推計手法の枠組みとして従来から最も広く用いられている1)コーホート要因法の再検討を行い,新たな手法としての2)確率推計手法,3)計量経済学的手法,4)シミュレーション技法等の有効性を検討する。第2 に人口動態率(出生率,死亡率および移動率)の将来推計に関する先端的な手法について国際的な議論を踏まえ,推計手法および将来の動向に関する理論について,従来の方法・理論との比較,有効性と限界の検証等を行う。第3 に人口状況の実態の測定と分析,出生,死亡,国際人口移動の見通し策定に関する科学的方法論について検討し,わが国ならびに諸外国の人口状況と動向の国際的,横断的把握,データ集積およびデータベース化を行い,上記において開発されたモデル,手法を適用することにより,人口動態率の今後の見通しに関する把握と提言を行う。なお,本事業は,公的将来推計人口策定における精度向上と説明責任の遂行に資することを一つの目的とするが,その前提となる科学的理論・手法に対する学術的,技術的検討が主眼であることから,公的推計の策定作業とは異なり,特定の組織の枠を越えた国内外の研究協力体制をつくることで広範な分野の学術的知見の集積を行うこととしている。
(2) 研究計画
第1 年次においては,1)将来人口推計に関する理論,枠組み,手法等,および2)人口動態事象(出生,死亡,人口移動)に関する理論,モデル,分析手法等について先端的な研究を中心に,文献,ソフトウェア等の収集,開発を行った。第2 年次以降においては,上記1),2)において得られた知見および体系を元に,人口推計の理論,モデル,手法等のそれぞれの技術的特徴,有効性,公的推計システムへの適用可能性,その際の課題等について,試験的運用を含めた検討,分析を行う。(3) 研究組織の構成
- 主任研究者
- 金子隆一(人口動向研究部長)
- 分担研究者
- 石井 太(企画部第4 室長),
- 岩澤美帆(人口動向研究部主任研究官)
- 研究協力者
- 石川 晃(情報調査分析部第2 室長),佐々井 司(人口動向研究部第1 室長),
- 三田房美(企画部主任研究官),守泉理恵(人口動向研究部研究員),
- 国友直人(東京大学経済学部教授),稲葉 寿(東京大学理学部助教授),
- 堀内四郎(ロックフェラー大学準教授),大崎敬子(国連アジア太平洋経済社会委員会委員),
- エヴァ・フラシャック(ワルシャワ経済大学教授),
- スリパッド・タルジャパルカ(スタンフォード大学教授)
- 三田房美(企画部主任研究官),守泉理恵(人口動向研究部研究員),
19 男女労働者の働き方が東アジアの低出生力に与えた影響に関する国際比較研究(平成18 ~ 20 年度)
(1) 研究目的
2000 年代に入って東アジアの高度経済国・地域は急激な出生率低下を経験し,2004 年の合計出生率は日本が1.29,韓国が1.16,台湾が1.18 となった。このうち韓国・台湾の出生率は,ヨーロッパでも匹敵する国が稀なほど極端に低い水準である。このような低出生率の重要な決定因として,男女労働者の働き方の影響を分析する。たとえば欧米に比べ長い労働時間は,男性の家事・育児参加を阻害し,伝統的性役割意識を保存する方向に作用しているものと思われる。日本の長期不況や韓国の経済危機は,多くの若年労働者の経済的自立を挫折させ,また家計の将来に対する不安感を増幅し,結婚・出産意欲を減退させたと推測される。出産・育児休暇,家族看護休暇,フレックスタイム制度等のファミリーフレンドリー施策の導入の遅れも,東アジアの出生率低下を加速させたと考えられる。良質な保育サービス供給の不足も,妻の就業と出産・育児の両立を阻害し,やはり少子化をもたらしたと思われる。本研究は,こうした働き方に関する諸要因が東アジアの出生率低下に与えた影響を分析する。(2) 研究計画
本研究では,働き方に関する諸要因が出生率に与える影響を,文献研究および専門家インタビュー,マクロ・データ分析,マイクロ・データ分析の各段階を踏んで分析を進める。そのような分析を通じて,労働時間や勤務形態のフレキシビリティー,家庭内分業の実態,若年労働者の経済的自立度将来の見通し,企業のファミリーフレンドリー施策の導入努力,地域の保育サービス供給の量といった諸側面が,どのように結婚率・出生率に影響するかを定量的に調べることを目的とする。それぞれの側面における改善がどの程度の出生促進効果を持つかの見極めを通じて,政策の優先順位等に関わる政策提言が得られる。現在まであまりはかばかしい成果が得られていない日本の出生促進策を考える上でも,日本より急激に出生率が低下している韓国・台湾との比較研究は不可欠である。初年度は韓国・台湾における近年の出生率低下と,その社会経済的要因に関する既存研究を収集し,日本や欧米先進国から得られた知見と比較・検討する。また出生促進策の導入に関わる政府・自治体の動きや,導入をめぐる議論・言説等を,アカデミックな研究に限定せず新聞・雑誌等からも幅広く集める。これらを用い,経済の状況や政治的・文化的風土をも考慮した解釈と将来予測を試みる。
(3) 研究組織の構成
- 主任研究者
- 鈴木 透(国際関係部第3 室長)
- 分担研究者
- 小島 宏(国際関係部長),
- 伊藤正一(関西学院大学経済学部教授)
20 社会保障の制度横断的な機能評価に関するシミュレーション分析(平成18 ~ 20 年度)
今日,社会保障が果たすべき機能・果たしている機能を再検討することは極めて重要な課題となっている。この場合,社会保障の機能の整理とともに,関係団体の意見の収集は重要である。関係団体は社会保障制度の利害関係者であり,彼らの意向は社会保障制度を拡充する一方で,関係者間の利害対立は制度の持続性および安定性を損なうことになる。この関係団体の意見をシミュレーションモデルに取り入れることにより,制度の持続性・安定性を加味した社会保障制度の機能の分析の実現が期待されている。本研究においては,1)制度横断的に社会保障の機能を分析し,家族形態や就労形態の変化に対応した社会保障の機能を考察し,2)社会保障の機能評価に関するシミュレーション分析を通して,政策の選択肢が社会保障の機能に与える影響を評価する。現金給付と現物給付のバランスや年金・医療等制度相互の給付の調整を考えるうえに必要なデータを得ることが期待される。シミュレーション分析には,統計的な変数の作成のほかにカリブレーション分析と呼ばれる方法を採用する。これは,社会保障制度の利害関係者(保険者,被保険者はもちろん,企業経営者,労働組合などが含まれる)にヒアリング・アンケートを行い,そこから得られる情報を数値化してシミュレーション分析を行う方法である。
カリブレーションの結果は,3 年目に開催予定の社会保障制度の利害関係者を集めたシンポジウムにおいて議論のたたき台としても利用される。もちろん,シンポジウムの成果も盛り込んだ形で最終報告書は形作られる。
(1) 研究目的
社会保障制度をとりまく環境は過去40 年間で大きく変化した。今日では,少子高齢化や雇用構造の変化が進む中で社会保障制度の持続可能性を高めることが緊急の課題となっている。社会保障制度の再構築に必要なのは現行制度の単なるスリム化ではなく,合理化である。現行制度に含まれる誤ったインセンティブも是正されなければならない。このため,社会保障が果たすべき機能・果たしている機能を再検討することは極めて重要な課題となっている。本研究においては,1)制度横断的に社会保障の機能を分析し,家族形態や就労形態の変化に対応した社会保障の機能を考察し,2)社会保障の機能評価に関するシミュレーション分析を通して,政策の選択肢が社会保障の機能に与える影響を評価する。現金給付と現物給付のバランスや年金・医療等制度相互の給付の調整を考えるうえに必要なデータを得ることが期待される。
シミュレーション分析には,統計的な変数の作成のほかにカリブレーション分析と呼ばれる方法を採用する。これは,社会保障制度の利害関係者(保険者,被保険者はもちろん,企業経営者,労働組合などが含まれる)にヒアリング・アンケートを行い,そこから得られる情報を数値化してシミュレーション分析を行う方法である。この分析により,利害関係者の選好が社会保障制度にどのように波及するのかをシミュレーションモデル上で見ることができる。また,関係団体の意見をシミュレーションモデルに取り入れることにより,制度の持続性・安定性を加味した社会保障制度の機能の分析の実現が期待される。
(2) 研究計画
本研究においては,1)ライフイベントに即した社会保障機能の評価シミュレーションモデルの作成と2)カリブレーション分析の為の数値指数の収集を同時に進める手法をとる。1 年目は研究テーマとして a)年金のシミュレーション分析,b)介護保険のホテル・コストと年金給付の関係,を取り上げる。先進諸国の年金給付算定方法からみた年金政策シミュレーションを実施して,所得再分配機能やIncome Smoothing 機能など,年金給付の果たしている各種機能を分析する。現物給付では介護給付を取り上げ,介護保険のホテル・コストと年金給付の関係を分析する。いずれも,現行制度を効率化した場合に抑制される費用を算定し,これを若年層への社会保障サービスに還元した場合の効果も考察される。すなわち,シミュレーション分析を行うに当たっては,ライフイベント毎に必要度の高い社会保障の機能が異なること,および,制度が持続的・安定的に推移することを制約条件として加える。そして,この制度の持続条件・安定条件を算出するために,関係団体に対するアンケート調査等を行う。2 年目は1 年目の研究テーマの分析を進めるとともに,医療・介護のシミュレーション分析を行う。これまで現物給付で対応してきた分野についても,現金給付を手厚くする代わりに現物給付を抑えるような方法をとった場合,厚生はどのように変化するのかといった分析を行う。例えば,社会的入院の是正や介護予防の効果測定もここに含まれる。加えて,いくつかの関係団体にはヒアリングを行い,より詳細な社会保障制度改正に関するシナリオを収集し,利害関係者の制約条件を付した形でシミュレーション分析を行うことができる。
3 年目は,いくつかの関係団体におこなったヒアリングも加味し,より詳細な社会保障制度改正に関するシナリオを作成し,利害関係者の制約条件を付した形でシミュレーション分析を行う。このシミュレーションの結果は,3 年目に開催予定の社会保障制度の利害関係者を集めたシンポジウムにおいて議論される予定である。なお,研究成果は1 年目から随時ディスカッションペーパーとして発表する。
(3) 今年度の研究課題と進め方
今年度はミクロな分析を進める。8 つの家計,すなわち夫婦(専業主婦,子あり),夫婦(専業主婦,子なし),夫婦(給与所得,子あり),夫婦(給与所得,子なし),男性(単身),男性(子有り),女性(単身),女性(子有り)を中心に,どのタイミングでどのような(広義の)社会保障ニーズが発生するかを考える。12 月までは,育児・保育,税制,企業福祉等の専門家へのヒアリング作業を行う。同時に,ベースモデルの開発にも着手する。これまでのモデル分析では,“平均” 的な家計を取り上げることが多かったが,今回は“分散” に注目した分析モデルを作成する。(4) 研究組織の構成
- 主任研究者
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 分担研究者
- 山本克也(社会保障基礎理論研究部第4 室長),酒井 正(企画部研究員),
- 佐藤 格(社会保障基礎理論研究部研究員)
- 研究協力者
- 本田達郎(企画部長),菊池 潤(客員研究員)
(長寿科学総合研究事業)
21 介護予防の効果評価とその実効性を高めるための地域包括ケアシステムの在り方に関する実証研究(平成18 ~ 19 年度)
(1) 研究目的
本研究は,①全国データに基づくケアマネジメントの現状分析(介護保険制度改正前との比較を含む),②パネル・データ(生活機能/介護/医療/健診に関する包括的データ)に基づく介護予防の総合的効果評価,③効果的な介護予防サービスの在り方の検証,④介護予防の実効性を高めるための地域包括支援センターの在り方の検証を通じて,今後の地域包括ケアシステムの在り方に関する提言を行うことを目的とする。(2) 研究計画
本研究は,3 年後の介護予防の見直しに向けた提言を目指しているため,研究期間を2 年としているが,この期間において以下の4 つのサブテーマに関する研究を行う。- 全国データに基づくケアマネジメントの現状分析
平成18 年度は,全国の認定・給付に関するデータを目的外使用申請により再集計し,認定者特性及びサービス給付に関するデータベースを構築し,制度改正以前におけるケアマネジメントとサービス効果の実態を整理する。平成19 年度は,さらに制度改正後のデータを再集計し,制度改正前後での比較検証を行う。
- パネル・データに基づく介護予防の総合的効果評価
介護予防の総合的効果評価を行うため,平成18 年度は,ア)生活機能,イ)介護(認定/給付/介護費),ウ)老人医療(給付/医療費),エ)健診,オ)主観的健康観,カ)日常生活自立度,キ)運動機能/栄養状態/口腔機能,ク)意欲等に関する包括的パネル・データを,モデル地区(島根県松江市)にて構築する。その上で,平成19 年度に,介護予防の生活機能等に対する効果評価や老人医療費・介護費に及ぼす影響を評価する。また,高齢者特性の経時変化とサービスの関係性から,介護予防が有効な対象者像の明確化を図る。さらに,高齢者の生活機能及び健診データの分析をもとに,介護予防と生活習慣病予防の在り方を検討する。
- 効果的な介護予防サービスの在り方の検証
平成18 年度は,まず,介護予防対象者の運動機能/栄養状態/口腔機能の実態を把握する。その上で,各種サービス(バランストレーニング,簡易体操,ブラッシング,嚥下体操,食形態の見直し等)を,分担研究者・研究協力者の協力を得て一定期間提供し,生活機能,QOL,運動機能/栄養状態/口腔機能,主観的健康観等に対する効果評価を行う。これらを通じて,高齢者の特性に応じた効果的な介護予防サービスの在り方を検討する。
- 介護予防の実効性を高めるための地域包括支援センターの在り方の検証
平成18 年度は,諸外国(カナダ)の地域包括ケアシステムの実態を調査する。また,同センターの重要な役割である,病院⇔地域間の円滑な入退院支援の在り方を,ケーススタディを中心に検証する。また,マネジメント担当者と医療専門職等との連携の在り方に関する検討も行う。
(3) 研究組織の構成
- 主任研究者
- 川越雅弘(社会保障応用分析研究部第4 室長)
- 分担研究者
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部長),府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長),
- 泉田信行(社会保障応用分析研究部第1 室長),
- 信友浩一(九州大学医学研究院基礎医学部門医療システム学分野教授),
- 備酒伸彦(神戸学院大学総合リハビリテーション学部助教授),
- 山本大誠(神戸学院大学総合リハビリテーション学部助手)
- 泉田信行(社会保障応用分析研究部第1 室長),
- 研究協力者
- 鍋島史一(福岡県メディカルセンター保健・医療・福祉研究機構主任研究員),
- 黒田留美子(潤和リハビリテーション診療研究所主任研究員)
(障害保健福祉総合研究事業)
22 障害者の所得保障と自立支援施策に関する調査研究(平成17 ~ 19 年度)
平成18年度総括研究報告書PDF版全文はここから圧縮ファイル(ZIP)でダウンロードしていただけます。
(1) 研究の目的 本調査の目的は,社会福祉基礎構造改革の理念である,障害者がその障害の種類や程度,また年齢や世帯状況,地域の違いにかかわらず,個人が尊厳をもって地域社会で安心した生活がおくれるようになるために必要な施策へとつなぐ基礎データを得ることである。そのために,独自の調査を実施して,既存の調査では得ることの出来ない障害者の生活実態を明らかにするとともに,それを基礎データとして,障害者の自立支援にはなにが重要であるかを,総合的学際的に研究する。生活者としての障害者を明らかにするという意味は,障害者の定義を手帳保持者などの狭い範囲に限定することなく広く捉えることと,障害者の暮らしの実態に着目して,障害者を個人だけでなく世帯の一員として捉えること,そして,経済的な自立と身体的な自立を,通院やサービス利用の実態と生活時間から観察しようとするものである。このような障害者をミクロで観察する社会調査はいままで希少で,それも自治体などの地域的区分の中を無作為に調査する試みは初めてと言って過言でない。(2) 研究計画
17 年度に引き続き,調査地点を変えて障害者生活実態調査を行い,障害者の生活実態を収入・消費面と生活時間面から明らかにし,健常者との共通点と相違点を分析する。地域格差の大きい居宅支援サービスの理由と実態を解明するため,異なるサービス実態の地域を選択し,障害の種類や世帯状況の違いも考慮した調査設計を行う。調査は障害者の生活実態を正確に把握するために,インタビュー調査を中心に設計する。
なお,本調査で得られたオリジナルデータを中核として,経済学・社会学等多分野の研究者を招いて,障害者福祉研究に学際的基盤の構築をめざす。特に財政的視点を踏まえて,持続可能な社会保障財政につながる障害者福祉政策の方向性を探る経済学的アプローチも試みる。また,知的障害の定義や障害程度区分,障害者の給付内容の国際比較や年金・税制等他制度との関係についても,さまざまな専門家による学際的研究を行う。
(3) 研究組織の構成
- 主任研究者
- 勝又幸子(企画部第3 室長)
- 分担研究者
- 本田達郎(企画部長),
- 福島 智(東京大学先端科学技術研究センター助教授),
- 遠山真世(立教大学コミュニティ福祉学部助手),
- 圓山里子(特定非営利活動法人自立生活センター新潟調査研究員),
- 土屋 葉(愛知大学文学部人文社会学科専任講師)
- 福島 智(東京大学先端科学技術研究センター助教授),
- 研究協力者
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部長),
- 三澤 了(DPI 日本会議議長),磯野 博(静岡福祉医療専門学校教員)
(統計情報高度利用総合研究事業)
23 パネル調査(縦断調査)に関する総合的分析システムの開発研究(平成18 ~ 19 年度)(1) 研究目的
本研究は,厚生労働省が各種の施策策定に資する科学的基礎資料を得るために実施しているパネル調査(21 世紀出生児縦断調査,成年者縦断調査,中高年者縦断調査(以下,21 世紀縦断調査))に対し,この調査が対象とする国民生活上の諸事象に関する要因や発生メカニズムの特定,施策効果の測定,ならびに行政ニーズの把握等に結びつく総合的な分析システムを構築し,年々蓄積されるデータの速やかで有効な結果公表に資するとともに,手法開発ならびに分析研究による学術的貢献を目指すものである。本来,パネル調査は,施策効果測定,行政ニーズ把握等に有効な調査形態であるが,横断調査とは異なる独自のデータ管理方法と分析法を要する。21 世紀縦断調査は,政府統計における初めてのパネル調査であり,これまで当該の行政目的に適したデータ管理,分析システムが必ずしも確立されているわけではない。これに対し申請者は平成16 ~ 17 年度の本事業において,当該調査(出生児調査,成年者調査)のデータ特性分析,管理システム構築を中心とした研究開発を行い,縦断調査分析の基礎を確立した。本研究では,その成果を踏まえつつ,年々蓄積されつつある当該調査時系列データについて,定例の公表事項に加え,縦断調査データの特性を活かしたより高次で総合的な分析結果の提供を可能とするような分析システムの構築を目指す。本研究の成果として,縦断調査の利点を活かした,より質の高い結果の公表に資するとともに,調査の中心的課題に対しては,データの蓄積と共に知見が改善するよう分析を定型化・システム化することによって,結果の速やかな公表と実施主体の実務負担の軽減等が期待される。また,縦断・横断両調査の連携など新しいアプローチの開発により,学術的観点からも,方法論,分析結果の双方において国際的に価値の高い貢献が期待される。(2) 研究計画
本研究は平成18,19 年度の2 ヶ年で実施するものとし,初年度は手法の調査研究および21 世紀縦断調査における検証,分析システムの検討と開発,第2 年度はシステムの検証と確立ならびにシステムを用いたデータ分析と信頼性の検討を行う予定である。(3) 研究組織の構成
- 主任研究官
- 金子隆一(人口動向研究部長)
- 分担研究者
- 釜野さおり(人口動向研究部第2 室長),
- 北村行伸(一橋大学経済研究所教授)
- 研究協力者
- 石井 太(企画部第4 室長),三田房美(同部主任研究官),
- 岩澤美帆(人口動向研究部主任研究官),守泉理恵(同部研究員),
- 阿藤 誠(早稲田大学人間科学学術院特任教授),
- 津谷典子(慶應義塾大学経済学部教授),
- 中田 正(日興ファイナンシャルインテリジェンス年金研究所副理事長),
- 越路幹男(厚生労働省統計情報部社会統計課縦断調査室長補佐),
- 後藤敬一郎(同室長補佐),山下りつ子(同専門官),
- 福田節也(明治大学大学院政治経済学研究科助手),
- 西野淑美(日本女子大学人間社会学部社会福祉学科助手),
- 鎌田健司(明治大学大学院政治経済学研究科),
- 相馬直子(東京大学大学院総合文化研究科),
- 元森絵里子(東京大学大学院総合文化研究科)
- 岩澤美帆(人口動向研究部主任研究官),守泉理恵(同部研究員),