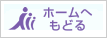
(1)研究目的
本研究は,社会保障と私的保障とのかかわりに着目し,公私の役割分担を明確にした社会保障パッケージのあり方を以下の4つの視点から考察することを目的としている。具体的な研究テーマは以下の通り。(1)企業年金と公的年金のすみ分けに関する研究,(2)企業による福祉と社会保障の関係に関する研究,(3)公的年金が労働供給に及ぼす影響と所得保障のあり方に関する研究,(4)非正規労働者への社会保険適用に関する分析。
(2)研究計画・実施状況
第1に,海外の研究動向を把握するために平成15年6月に分担研究者を米国のEBRI他に派遣してヒアリング調査等を実施した。第2に,公的年金に関連したテーマについては,平成15年9月に研究者と行政関係者からなる「公的年金ワークショップ」を国立社会保障・人口問題研究所で開催し,研究成果を発表するとともに内容について議論を行ったほか,平成16年度には諸外国の年金改革の動向や日本におけるキャッシュ・バランス型年金の実状について分析した。第3に,企業負担の実態把握方法について,平成15年6月~16年3月にかけて日本経団連,生命保険文化センター,(株)帝国データバンク,厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課などを対象にヒアリングを実施した後,平成16年度にはアンケート調査を実施した。第4に,非正規労働者の中でも近年増加が著しい請負労働者の実態把握も行った。第5に,未納・未加入問題についても,予備的な実証分析を行った。
3年目にあたる平成17年度は,16年度の企業アンケート調査から得られたデータに企業財務データ等を組み合わせて,業種・業績や労務構成によって福利厚生制度の実状がどのように異なるのか,代行返上が企業業績のどのようなタイミングで起こっているのか,などについて実証分析を行うとともに,他のテーマについても調査結果をワークショップで報告し,研究成果を報告書にとりまとめる。
(3)研究会の構成員
(4)研究成果の公表
本事業による平成16年度までの研究成果の一部は『季刊社会保障研究』第39巻第3号,第40巻第3号の特集として発表した。最終年度に当たる平成17年度は,16年度の調査等から得られたデータをさらに分析した上で,総合研究報告書をとりまとめるとともに,今後,ワーキングペーパーやThe Japanese Journal of Social Security Policy等の形態で国内外に積極的に普及・啓発を図る予定である。
(1)研究目的
医療・介護等の社会保障制度の改革は焦眉の課題であるが,これまでの議論は,経済の低成長と医療費等の増大のギャップを背景に費用のファイナンスの仕組みとしての医療保険制度の改革などに焦点をあてるものが中心であり,医療等の供給体制のあり方に関する検討は立ち遅れている。また,供給体制に関する研究の多くは概して個別論点に関わるものであり,わが国の医療等の供給体制に関わる構造的問題を総合的・実証的に分析し,あるべき医療等の供給体制のビジョンを明らかにした上で,具体的な政策提言を行っているものは乏しい。本研究は,医療政策の目標(医療の質・アクセス・効率性の向上)に照らし,高齢社会における医療等の提供体制のあるべき姿を明示した上で,その実現に向けた具体的な政策手段を明らかにすることを目的とする政策指向型の研究である。
なお,国民の医療等に対する不満や不安の多くは,高齢化等に伴い費用負担が今後更に増大するのではないか,また,費用負担の増加に見合う質の高い医療等のサービスを将来受けられるのかが分からないことに起因している。したがって,国民の医療等に対する満足度を高め,将来不安を払拭することが必要である。また,医療等の供給体制の総合化・効率化等を通じ,サービスの生産性・効率性を高めコストベネフィットを最大化することは,ファイナンスの面でも重要であり,本研究は結果的に医療費の効率化にも資することとなる。
(2)研究計画
2年目である平成17年度は,1年目で行った分析の精緻化を図ることに加え,重要テーマのうち1年目で取り組めなかった「欠落の補充」を行う。例えば,グランドデザイン達成の誘導策として,①地域医療計画的手法,②診療報酬による経済的評価,③情報開示と患者選択の具体的方策,の手法の比較検討および相互補完関係についての検討を行う。また,諸外国の医療改革の評価・政策の普遍性及び日本への適用可能性について検討するほか,1年目の成果として得られたグランドデザインの類型化の精緻化を図るために数量的な分析・評価を中心にさらに検討を進め,望ましい姿と現状との乖離の状況について実証的に分析する。
具体的には,受療行動調査・医療施設調査・患者調査等の統計の目的外使用申請を行い,文献のサーベイやヒアリング等で得られた都市部および農村部における知見を数量的な面から詳細に分析する他,アンケート調査を実施し,健康に対する意識と,医療費の関係について分析を行う。また,日本と比較的類似した医療システムを採っているドイツと日本と対極的なシステムを採っているアメリカにおける実地調査を予定している。
(3)研究会の構成員
(4)研究成果の公表
本研究の成果は,平成17年度報告書としてとりまとめて厚生労働省の関係部局に提出するとともに,関係団体や研究者に配布する。なお,各研究者はそれぞれの所属する学会および学術雑誌への投稿等を行うなど,積極的な成果の普及に努めるものとする。
(1)研究目的
本研究は,先進諸国等における国際人口移動と移動者の社会的統合の実態・政策,それに伴って必要となる社会保障政策との連携に関する分析を行い,各国の実態・政策の比較検討を行うことにより,人口減少に直面するわが国における国際人口移動政策と社会保障政策の連携の可能性を検討することを目的とする。
(2)研究計画
本研究は,平成16年度から3年間にわたり,①先進諸国等における国際人口移動と移動者の社会的統合・社会保障制度利用(医療・労働保険,年金等)についての実態・政策に関する資料収集と分析,②先進諸国等における国際人口移動政策と社会保障政策の連携に関する資料収集と分析,③以上を踏まえた,わが国における国際人口移動と移動者の社会的統合・社会保障制度利用についての実態・政策,国際人口移動政策と社会保障政策との連携に関する比較分析と政策的含意導出の三者を目的として実施する。
第2年度の平成17年度は一部先進諸国等と国内における資料収集を継続するとともに,日系ブラジル人の実地調査を実施する予定である。また,マクロデータと既存ミクロデータの詳細な分析も行うことになっている。さらに,初年度末に立ち上げた「外国人労働者の社会保障制度加入に関する研究会」で年金法・改正労働者派遣法・入国管理法・外国人登録法等と関連する外国人労働者の処遇の在り方について議論を進め,研究会参加者の専門研究論文と研究会報告をとりまとめるとともに,国際比較研究を実施する予定である。
(3)研究会の構成員
(1)研究目的
我が国における「社会的排除と包摂(ソーシャル・インクルージョン)」概念を確立し,社会保障制度の企画立案に係る政策評価指標として活用する可能性を探るものであり,その中で,①諸外国の経験を資料・文献・データから複眼的に捉え,その整理を行いつつ,②我が国の社会保障制度が発揮してきた効果を「社会的包摂」の観点から検証し,今後のより効果的な施策の立案に資するための提言を行う。
(2)研究計画
本研究では,以下の3つのサブテーマについて3年計画で研究を行う:①日本における社会的排除指標の作成,②社会保障制度による,社会的包摂効果の計測,③被排除者をめぐる既存の定性調査結果の再検討。平成16年度は,『社会生活調査』を用いて社会的排除指標を暫定的に定義,その動向と所得の関連等の分析を行った。また,既存の貧困・社会的排除に関する社会調査のサーベイとその問題点の整理等を行うとともに,被排除者と思われる人々についての研究に取り組んでいる研究者から報告を行い,最新の研究動向の摂取に努めた。平成17年度は,以上の研究の蓄積を踏まえて,第一に,社会的排除-包摂概念を操作化し,我が国に最もふさわしいと思われる指標を設定する。第二に,その概念ないしは指標が妥当であるか否かを検証するために,フォーカス・グループ・インタビューなどを実施する。第三に,以上の手続きを踏まえて,質問紙を設計し,我が国の社会保障制度が社会的包摂に及ぼす効果について調査を行う。
(3)研究会の構成員
(4)研究結果の公表
各年度の研究成果は,年度末に外部の有識者,行政関係者などを招いたワークショップを開催し発表する予定である。また,口頭発表以外にも『季刊社会保障研究』(国立社会保障・人口問題研究所)や学会誌などにて広くその結果の普及に努める。
(1)研究目的
本研究では,「社会保障審議会意見書」(平成15年6月)の趣旨に沿って,我が国の所得・資産格差の現状と再分配政策の効果について実証分析を行い,その成果を踏まえつつ理論的考察とシミュレーション分析を行うことにより,①家計ベースでみた社会保障の給付と負担の在り方に関する政策の選択肢を示し,それぞれについて所得・資産格差の是正や世代別への影響および経済成長への影響等を視点に比較考量し,②経済環境の変化に対応して考慮すべき低所得者層の把握と低所得者層への新たな対応を含むセーフティネットとしての社会保障の給付と負担の在り方について考察する。そして,③比較考量の基準を得るため,再分配に関連する社会保障政策の動向に関して国際比較を行う。
経済環境の変化は所得・資産格差の変化をもたらすとともに,所得再分配政策の効果にも影響を及ぼす。したがって,社会保障制度を①社会経済との調和,②公平性の確保,③施策・制度の総合化を視点に発展させていくためには,国民一人あたりあるいは家計ベースを対象とした所得再分配効果の実態把握を行う必要があるのみならず,世帯類型別,コーホート別等からの比較,検討を行う必要がある。さらに,医療や介護の分野では経済力などに応じた応分の負担を求める方向で制度改正等が行われているが,OECD諸国の動向とOECDの新しい分析手法を参照しながら,所得階層別の年金給付と医療・介護の負担との関係に配慮しつつ,医療・介護サービスの利用状況を分析することで,所得格差のある社会における保健医療制度の在り方についても新たな知見を提示することができる。こうした点においても本研究を実施する意義は大きい。
(2)研究計画
①所得・資産格差の実態把握と再分配効果の計測,及び②家計ベースでみた社会保障負担の在り方の分析,及び低所得者層の実態把握を行うために,2年計画で「所得再分配調査」「国民生活基礎調査」等の使用申請を順次行うとともに,分析手法や既存研究を知るための有識者に対するヒアリングを行う。17年度は,すでに使用許諾を得た「所得再分配調査」の基本的な再集計等を引き続き行うとともに,「国民生活基礎調査」の使用申請とその再集計等を行う。以上のクロスセクション・データの分析を補完して,所得変動を考慮した場合の再分配効果を分析するために,アンケート調査を利用した2時点からなるパネル・データについては,平成17年は1年目のサンプルを含めサンプル数を増やした調査を行い分析する。国際比較研究については,外国研究者招聘事業によりOECDの所得格差に関する国際比較プロジェクトの研究者を招聘し共同研究を行う。また,所得格差は資産格差や健康状態とも関連することに留意して,ルクセンブルグ所得研究(LIS),OECD等のデータを活用しながら,OECDにおける所得格差等の社会経済要因と医療・介護の実態に関する比較研究プロジェクトと情報交換等を行う。さらにカナダ日本社会保障政策研究円卓会議を活用した比較研究を行う。
(3)研究会の構成員
(4)研究成果の公表
本研究の成果は,平成17年度報告書としてとりまとめて厚生労働省の関係部局に提出するとともに,関係団体や研究者に配布する。なお,各研究者はそれぞれの所属する学会および学術雑誌への投稿等を行うなど,積極的な成果の普及に努めるものとする。
(1)研究の目的
少子高齢化や右肩上がり経済の終焉など税制と社会保障のいずれのあり方にも大きく影響を及ぼすような社会経済の変化の中で,税制改革の方向性は社会保障制度のあり方に大きな影響を与える要素である。税制については,平成19年を目途に抜本的な改革が予定されているが,「経済社会の構造変化等を踏まえ,どのような形で国民一人一人が社会共通の費用を分担していくべきかを考えなければならない。その際,個人のライフスタイル(生き方,働き方)の多様化等が進む中,所得・消費・資産等多様な課税ベースに適切な税負担を求めていくことが課題となる。」(平成16年6月税制調査会基礎問題小委員会)とされている。一方,社会保障制度については,その財源を保険料から目的税化した消費税にすべきとの議論や年金の基礎的部分は租税財源によるべきとの議論など,税制に関係する議論が出ている。さらに,国際競争力や雇用維持との関連で企業が求める負担賦課の水準や財政赤字を含めた潜在的国民負担率にも配慮する必要性がある。したがって,「平成17年度の税制改正に関する答申」は,「経済社会の構造変化を踏まえて税・社会保障負担のあり方を改革する中で,受益と負担のバランスを図る観点から,給付面の抜本的見直しとあわせ,現在世代の負担水準の引上げを図るべき」こと,「その際,社会保障における税負担と社会保障負担の意義・役割や,そのどちらにより重く依存すべきかの検討が重要な政策課題」となることを指摘している。
本研究の目的は,これらの指摘に示される政策課題に対応して,持続可能な社会保障制度を構築するためには,どのような税制のあり方が望ましいかについて方向性を見出すための研究を行う。この研究によって,平成19年に予定されている抜本的な税制改正に当たり,企業活動等の経済活動の観点からだけではなく,持続可能な社会保障制度の構築の視点からみた望ましい税制のあり方を政策提言するための基礎的なエビデンスを提供できることになる。
(2)研究計画
1年目には,各種統計データ・文献収集,転嫁と帰着に関する調査及び各方面(社会保障制度,経済,財政(国家財政及び地方財政)等)の専門家からヒアリングを行うとともに,これらの成果に制度論的分析を加えた論点に基づき,計量分析を用いて制度改正を行った場合の影響分析等を行う。
2年目には,1年目の結果を踏まえ,調査のフォローアップと制度論的分析を進めるとともに,その成果を反映させたモデル分析とシミュレーション分析による推計を活用しつつ,税制と社会保障の主要な論点について今後のグランドデザインの構築を行う。
具体的な研究課題としては,社会保険料と消費税の選択が重要な争点になりつつある状況を考慮して,消費税等の税及び社会保険料の比較,及び転嫁・帰着の問題を主要な論点として取り上げる。研究方法としては,転嫁・帰着の実証分析については,公表された統計データを活用した時系列分析や疑似パネル・データによる分析を行うとともに,企業に対する調査を実施して,社会保障の財源選択とその水準に対する企業行動の変化に関するミクロ的なデータの収集と分析を行う。一方,国民負担率と経済活動の関係についてはマクロ経済分析の観点から考察する。また,税と保険料の役割分担,家族政策における手当と税制の関係,適切な課税ベースとは何か等については,制度分析・社会保障法学的な研究と計量分析を併せて行うとともに,諸外国の動向についても資料収集と考察を行い,多角的な観点から分析を行う。
(3)研究会の構成員
(1)研究目的
日本では少子化の急速な進行にともない,年金や医療といった社会保障制度の根幹が揺るぎつつあり,少子化の背景を明らかにし,実効性のある少子化対策を行うことが重要な政策課題となっている。少子化は程度の差こそあれ先進諸国で共通して見られる現象であり,各国とも少子化対策を実施しており,他の先進国との比較は日本の少子化対策を考える上で有益である。また,日本をはじめとする先進諸国における少子化は家族の変化(世代関係・ジェンダー関係)と密接に関連しており,社会経済に加え家族のあり方の変化という視点からも,少子化問題を考える必要がある。現在,先進諸国の少子化の要因と政策的対応を国際比較するために,本主任研究者が中心となって「結婚と家族に関する国際比較研究会」を組織し,国連ヨーロッパ経済委員会(UNECE)人口部が企画・実施している国際研究プロジェクト「世代とジェンダー・プロジェクト(GGP)」に参加している。そして,本プロジェクトは,国連人口部が企画したこの国際共同プロジェクトの中核部分であるパネル調査(「世代とジェンダーに関するパネル調査(GGS)」)を日本でも実施し,そこから得られる少子化のミクロ的側面に関するパネル・データと雇用・労働政策や家族・子育て支援政策といった少子化のマクロ的側面に関するコンテキスト・データを連結させて因果関係を分析する新手法によって,未婚化や晩婚化といったパートナー形成(ジェンダー関係)と少子化(次世代育成・世代関係)の日本的特徴を明らかにし,これと諸政策との関連を他の先進国との比較を通じて検討する。これにより,先進国との比較という広い視野から,日本における未婚化・少子化分析と少子化対策についての政策提言を行うことを目標とする。(2)研究計画
本研究は,個人を単位とした調査の実施・分析(ミクロデータ)と各国の法制度改革時期や行政統計データを含むマクロデータベースの構築という,大きな2つの柱からなる。前者のミクロデータについてはドイツのマックスプランク人口研究所が中心となり質問検討委員会が構成され,比較可能な共通のフレームで実査を行う。後者は,フランス国立人口研究所が中心となってデータベース委員会が構成され,マクロデータに関する基本方針が決定される。これら2つの委員会の方針に従って,各参加国は調査実施とマクロデータの提供を行う。さらに,ミクロ班で設定されたテーマのもと,ミクロデータ,マクロデータを用いて多層的な国際比較研究を行う。
10月に国連ヨーロッパ経済委員会人口部によって主催されるGGP国際会議(トルコ・イスタンブール)に出席し,日本で実施した一回目の「ジェンダーと世代パネル調査」の結果概要を報告する。さらに,この会議では,日本側から第二回目の「ジェンダーと世代パネル調査」の質問項目,調査デザインに対する見解,要求も提示する。
第一回「ジェンダーと世代パネル調査(2004年3~4月実施)」のデータを分析し,非回答項目などを吟味し,二回目のパネル調査にむけての調査項目,調査デザイン,調査実施プロセスについての検討,改良を行う。
第一回「ジェンダーと世代パネル調査」の調査回答者に対してヒアリングを行う。これに基づき,研究会を開催し,第一回目の調査の問題点を検討し,第二回目のパネル調査実施に向けて,調査票,調査手順についての改善をおこなう。
研究会での議論をふまえて,第二回「ジェンダーと世代パネル調査」のプレ調査の調査票を作成し,プレ調査を実施する。プレ調査実施後は,データ・クリーニング,単純集計,ヒアリングを行って,来年度の本調査に実施に向けて,調査を包括的に検討する。
「GGPニューズ・レター」を発行し,第一回「ジェンダーと世代パネル調査」の調査協力者に結果概要をフィード・バックすると共に,第二回調査への協力を依頼する。「GGPニューズ・レター」は年1~2回を目標に平成18年度以降も継続して発行する。
スロベニア(予定)で行われるGGP国際会議に出席し,日本で実施予定の第二回「ジェンダーと世代パネル調査」の概要を報告する。また,GGP参加各国の意見を持ち寄り,日本側の見解,要求も明らかにし,最終的な調査票の確定へ向けて,作業をすすめる。
第二回「ジェンダーと世代パネル調査」の本調査を,2007年3月~4月に実施する。調査実施後は,調査票を回収し,データ・クリーニングを行う。
GGPマクロ・データ・ベース委員会が提示した共通フレームに基づき,マクロ・データ・ベースのためのデータ入力作業を行う。本年度はナショナル・レベルのマクロ・データを中心に作業を進める。
前年度に引き続き,「GGPニューズ・レター」を年1~2回のペースで発行し,本プロジェクトの進捗状況を公表する。
日本のGGPデータを用いた集計,分析を行い報告書をまとめる。ここでは,第二回の調査データだけでなく,第一回の調査データも利用したパネル・データによる分析を行う。これと,同時にマクロ・データ・ベースを使ったコンテキスト分析も行う。
GGPマクロ・データ・ベース委員会が提示した共通フレームに基づき,マクロ・データ・ベースのためのデータ入力作業を継続して行う。本年度は都道府県レベルのマクロ・データを中心に作業を進める。
ロシア(予定)で行われる予定のGGP国際会議に出席し,日本で実施した二回目の「ジェンダーと世代パネル調査」の結果概要を報告する。さらに,この会議では,GGPコンソーシアムが取りまとめる,「世代とジェンダーに関する国際比較報告書」の内容について,日本側の意見を提示し,最終的な報告書の確定に向けて作業を進める。
(3)研究者の組織
(1)研究目的
本研究事業は,少子化関連施策の効果を人口学,社会学,経済学などの学問的見地から評価研究を行い,今後の少子化対策について家族労働政策の視点から効果的な施策提言をすることを目的として実施する。具体的には,
マクロ計量経済モデルによる少子化対策要因ならびに家族・労働政策要因のシミュレーション研究により,保育キャパシティ(保育需要に対する施策拡大),出産育児の機会費用(女性就業の制約改善による育児コストの低減)等の施策要因が合計特殊出生率の動向にどのような効果を及ぼすかを測定評価する。
自治体において取り組まれる少子化対策(少子化対策の行動計画)が,各自治体における他の施策や自治体の置かれている様々環境条件との組み合わせで,具体的に自治体単位の出生率がどのように変化しているのかを分析し,自治体における少子化対策の効果を評価し,そのあり方を施策提言する。
近年,人口学・経済学・社会学等様々な研究領域において議論が展開されつつある少子化の見通しや少子化対策に対する考え方を把握し,それら専門家の少子化対策に対する評価ならびに少子化の見通し関する意見をデルファイ(反復)調査により分析し,現在実施あるいは取り組まれようとしている少子化対策改善のための基礎資料を得る。また今後実施される将来人口推計の議論展開に寄与するための基礎資料として活用する。
(2)研究計画
本研究は平成17年度より3カ年にわたり研究を以下のように実施する。
平成14~16年度に実施された厚生労働科学研究「少子化の新局面と家族労働政策の対応に関する研究」において実施された出生率の計量経済モデルの研究を引き継ぎ発展させ,政策評価モデルとして再構築する。研究初年度においては,マクロ計量経済モデルによる少子化対策要因ならびに家族・労働政策要因のシミュレーションモデルを開発し,とくに保育キャパシティ(保育需要に対する施策拡大),出産育児の機会費用(女性就業の制約改善による育児コストの低減)等の施策要因が合計特殊出生率の動向にどのような効果を及ぼすかを測定評価する。研究2年度目においては,女性就業の施策展開(両立支援策)と出産育児の機会費用の関係についてモデルを拡張し,より詳細な評価を行う。研究3年度目においては,税制・年金制度等の施策変化が出生率動向に及ぼす影響を評価する。
過去10年間の出生率上昇地域と低下地域について,出生率のトレンドの差異を生み出している要因を明らかにし,少子化対策の果たした影響効果を実証的に分析し,少子化の地域行動計画施策に対する提言を行う。初年度においては,自治体情報ならびに地域出生率に関する統計分析を行い,調査地を選定しヒアリング調査を行う。研究2年度目において,自治体の協力の下少子化対策におけるメニューの利用状況,ならびに住民の意識調査を実施し,対策とニーズの整合性の程度と出生率指標との関係を分析する。研究3年度目には,自治体関係当局と共同で,当該調査自治体の少子化対策の総合評価を行う。
研究初年度は,人口学・経済学・社会学領域の研究者に対する調査項目を検討し,第1回調査を実施する。調査の集計分析を行い,研究者が考える少子化の見通しや少子化対策のあり方を,現在の施策項目と比較分析し,問題点を把握する。研究2年度目は,第1回調査結果を調査対象専門家に開示し,第2回調査を実施し,分析する。これら2回の調査分析を行い,現在の少子化対策に対する専門家の評価を検討し,施策提言としてまとめる。研究3年度目は,調査の詳細分析を進めると同時に,今後予定される社会保障審議会人口部会等を通じ研究成果を広く普及し,新将来人口推計ならびに少子化対策の基礎資料として厚生労働政策に貢献する。
(3)研究組織
上記研究は主任研究者ならびに各分担研究者によって小委員会を構成し,研究協力者の参加のもと小委員会ごとに研究を実施する。そして,それらの小委員会における研究の成果は,主任研究者のもと研究全体を統括し,総合報告書としてとりまとめる。小委員会は上記目的に即し,①マクロ計量経済モデルによる少子化対策要因の出生率におよぼす影響評価研究,②地方自治体の少子化対策に関する効果研究,③少子化の見通しならびに少子化対策に関する専門家調査,に分けて研究を進める。
(1)研究目的
世界のフォアランナーとして少子高齢化が進み,恒常的人口減少が始まろうとする現在のわが国において,社会経済の制度設計,施策立案に不可欠な将来推計人口の重要性はかつてない高まりを見せている。しかしながら,同時に前例のない少子化,長寿化は人口動態の見通しをきわめて困難なものとしている。本研究では,こうした中で社会的な要請に応え得る科学的な将来推計の在り方を再検討し,手法および人口の実態の把握と見通しの策定(仮定設定)の両面から推計システムを再構築することを目的とする。本事業は,公的将来推計人口策定における精度向上と説明責任の遂行に資することを一つの目的とするが,その前提となる科学的理論・手法に対する学術的,技術的検討が主眼であることから,公的推計の策定作業とは異なり,特定の組織の枠を越えた国内外の研究協力体制をつくることで関連諸分野の学術的知見の集積を行うこととする。
(2)研究計画
本研究においては,第一に,人口推計手法の枠組みとして従来から最も広く用いられている1)コーホート要因法の再検討を行い,新たな手法としての2)確率推計手法,3)計量経済学的手法,4)シミュレーション技法等の有効性を検討する。第二に人口動態率(出生率,死亡率および移動率)の将来推計に関する先端的な手法について国際的な議論を踏まえ,推計手法および将来の動向に関する理論について,従来の方法・理論との比較,有効性と限界の検証等を行う。第三に人口状況の実態の測定と分析,出生,死亡,国際人口移動の見通し策定に関する科学的方法論について検討し,わが国ならびに諸外国の人口状況と動向の国際的,横断的把握,データ集積およびデータベース化を行い,上記において開発されたモデル,手法を適用することにより,人口動態率の今後の見通しに関する把握と提言を行う。以上の研究は並行して行われ,主として第1年次においては各研究分野における,文献,ソフトウェア等の収集,検討,ならびに基礎的な理論,モデル,手法等の技術的特徴,有効性,公的推計システムへの適用可能性,課題等についての検討を行い,第2年次においては,それらのわが国への応用,実データの分析,システム開発を行い,さらに第3年次においてはそれらソフトウェアの整備,シミュレーション分析,システムの評価等を行う。
(3)研究会の構成員
(1)研究の目的
社会福祉基礎構造改革の理念は,個人が人としての尊厳をもって,家庭や地域の中で,障害の有無や年齢にかかわらず,その人らしい安心のある生活がおくれるよう自立を支援することにある。障害者福祉サービスについても,平成15年4月から措置費に代わる支援費制度が施行された。これを機にホームヘルプサービスやデイサービスなど,居宅生活支援サービスの利用が促進され,多くの障害者が自立を志向するようになった。平成16年10月社会保障審議会障害者部会で「今後の障害者福祉施策について(改革のグランドデザイン案)」が示され,平成17年2月「障害者自立支援法案」が国会に提出され審議された。本研究はこのような大きな改革の過渡期にある障害者福祉の在り方を,総合的に検討すべきという時代的要請を敏感に受け止め,障害者の自立支援に軸足を置きながら整合性を備えた検討に資するために科学的資料たる基礎調査研究の実施を提案するものである。
本調査の目的は,社会福祉基礎構造改革の理念である,障害者がその障害の種類や程度,また年齢や世帯状況,地域の違いにかかわらず,個人が人として尊厳をもって地域社会で安心した生活がおくれるようになるために必要な支援はなにか,その支援を続けるためにはどのような制度が必要なのかを検討するための基礎データを得ることである。そして,得られたデータを活用し,経済学や社会学等の多分野の研究者と障害者福祉に関する学際的研究の基盤を構築したい。
(2)研究計画
障害者生活実態調査において障害者の生活実態を収入・消費面と生活時間面から明らかにし,健常者との共通点と相違点を分析する。地域格差の大きい居宅支援サービスの理由と実態を解明するため,異なるサービス実態の地域を選択し,障害の種類や世帯状況の違いも考慮した調査設計を行う。
調査は障害者の生活実態を正確に把握するために,インタビュー調査を中心に設計する。また,調査の実施じたいが,障害者の自立支援となるよう,さまざまな障害者NPO組織との連携を前提に,2004年にすでに障害者計画策定が義務化された都道府県政令指定都市の障害者福祉行政関係部署との連携をめざす。
なお,本調査で得られたオリジナルデータを中核として,経済学・社会学等多分野の研究者を招いて,障害者福祉研究に学際的基盤の構築をめざす。特に財政的視点を踏まえて,持続可能な社会保障財政につながる障害者福祉政策の方向性を探る経済学的アプローチも試みる。また,知的障害の定義や障害程度区分,障害者の給付内容の国際比較や年金・税制等他制度との関係についても,さまざまな専門家による学際的研究をおこなう。
3年計画の前半2年間は調査の実施を中心に研究を進める。障害者生活実態調査は,初年度をプレ調査と位置づけながらも,予算制約を踏まえて,2年間で収集するデータを有効に活用できるように,調査票の設計段階はユーザーとしての自治体及び当事者団体及び研究者の意見を十分に聴取し,慎重な調査票設計を行う。
本調査では,家計調査(参照例;総務省統計局全国消費実態調査)と時間簿調査(参照例;NHK放送文化研究所「国民生活時間調査」)両方の必要情報の入手を想定して,障害者の生活実態が健常者の生活実態と異なる部分を明らかにしたい。すなわち障害者の生活実態をミクロデータで明らかにすることが目的である。既存一般世帯調査との比較を前提とした,調査票の設計を行い,承認統計調査の個票データを目的外使用申請等によって入手し,障害者の実態を明らかにする。調査地区を自治体単位(県又は政令指定都市)で選定し,福祉施策の充足度の違いによる比較を行う。障害種別(身体・知的・精神・その他)特徴を明らかにする。世帯類型別(健常者との同別居等の違い)特徴を明らかにする。ただし予算制約があるので,統計分析に耐えうるサンプルを入手出来ない場合は,地域や対象を限定せざるをえない場合がある。調査票の設計や集計は研究者が中心となり当時者団体の協力を得て行い,調査の実施はNPO等が研究者と協同して実施する。また,地方自治体を調査単位に選定することで,地方自治体の政策担当者への協力を求め,地域障害者の自立支援策への提案へと発展させることも念頭に置いている。
また,知的障害の定義や障害程度区分等の諸外国の状況について基礎的情報の収集を行う。
(3)研究会の構成員