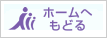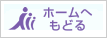一般会計プロジェクト
1 社会保障調査・研究事業
・平成13 年度社会保障給付費推計
( 1 )研究目的
本研究所では,毎年我が国の社会保障給付費を推計公表している。社会保障給付費とは,ILO(国際労働機関)が定めた基準に基づき,社会保障や社会福祉等の社会保障制度を通じて,1年間に国民に給付される金銭またはサービスの合計額である。社会保障給付費は,国全体の社会保障の規模をあらわす数値として,社会保障制度の評価や見直しの際の基本資料となるほか,社会保障の国際比較の基礎データとして活用されている。
「平成13年度社会保障給付費」は平成15年12月2日(訂正版24日)に公表した。以下記述は訂正版の数値を基礎とする。
( 2 )推計結果の概要
① 平成13年度社会保障給付費の概要
- 平成13年度の社会保障給付費は81兆4,007億円となり,集計以来はじめて80兆円を超えた。対前年度増加額は3兆2,735億円,伸び率は4.2%で前年度並だった。
- 社会保障費の対国民所得比は22.00%となり,集計開始以来最高を記録した。これは社会保障給付費が増加している一方で,国民所得の対前年度伸び率が△2.7% と下落したことによる。
- 国民1人当たりの社会保障給付費は63万9,500円で,対前年度伸び率は3.9%と前年度並となっている。
Mli<社会保障給付費を「医療」,「年金」,「福祉その他」に分類して部門別にみると,「医療」が26兆6,415億円で総額に占める割合は32.7%,「年金」が42兆5,714億円で総額に占める割合は52.3%,「福祉その他」が12兆1,878億円で15.0%である(公表資料表1参照)。
- 「医療」の対前年度伸び率は2.4%である。平成12年度は,介護保険施行で高齢者医療費が福祉その他へ組み替えられた結果,対前年度伸び率が△1.5%とマイナスであったが,平成13年度では費用組み替えの影響が無くなり増加に転じている。
- 「年金」の対前年度伸び率は3.3%である。平成12年度の3.2%に比べると少し大きくなっているが,平成12年度同様に物価スライドがなかったことが反映して,昭和40年度(独立の部門として集計を開始)以来2番目に低い伸び率にとどまっている。
- 生活保護,児童手当,失業給付,社会福祉費等からなる「福祉その他」の対前年度伸び率は11.6%である。平成12年度の25.0%には及ばないが,再掲している「介護対策」が27.0%の伸びとなっていること等を受けて,かなり大きな伸び率となっている。
- 機能別(公表資料表2参照)にみると最も大きいのは老齢年金や老人福祉サービス給付費などからなる「高齢」であり38兆9,509億円,総額に占める割合は47.9%である。2番目に大きいのは医療保険や老人保健などの医療給付などからなる「保健医療」であり26兆2,085億円,総額に占める割合は32.2%で,これら上位2機能分類で,総額の80.0%を占めている。
- 額としては小さく全体の伸びへの影響は小さいものの,対前年度伸び率では「家族」が12.0%と最も高い。「家族」には,子供その他の被扶養者がいる家族(世帯)を支援するために提供される給付が計上されている。
② 平成13年度社会保障財源の概要
- 平成13年度の社会保障収入総額は90兆3,902億円で,対前年度伸び率が0.3%である。
注)収入総額とは,社会保障給付費の財源に加えて,積立金への繰入・管理費及び給付外の施設整
備費の財源も含む。
- 大項目では「社会保険料」が56兆1,257億円で,収入総額の62.1%を占める。次に「税」が26兆6,922億円で,収入総額の29.5%を占める。
- 収入総額の伸びを見ると,「社会保険料」及び「税」については増加しているが,「資産収入」の減少が大きい。
以上の「平成13年度社会保障給付費」については,本研究所のホームページ(https://www.ipss.go.jp/index.html)で公表資料と同じものが掲載され,PDFファイルでも提供されている。「平成13年度社会保障給付費」英語版“The Cost of Social Security in Japan FY2001”も英語ホームページ(https://www.ipss.go.jp/English/cost01/main.htm)より同様に入手できる。また,『季刊社会保障研究』(第39巻第4号)において,「平成13年度社会保障費―解説と分析―」を担当者(勝又幸子・阿萬哲也・佐藤雅代)で執筆した。
③ OECD(経済協力開発機構)『社会支出統計(SOCX)』日本データの推計
平成13年度社会保障給付費のデータを基に,2001年度までのデータをOECD基準に当てはめて再計算した結果をOECDに提出した。
( 3 )担当者
- 担当部長
- 中嶋 潤(総合企画部長)
- 所内担当
- 勝又幸子(総合企画部第3室長),阿萬哲也(同部第1室長),佐藤雅代(同部研究員)
- 所外委員
- 西岡 隆(厚生労働省政策統括官付政策評価官室補佐),仙浪昌和(同室調査総務係)
・社会保障給付費の国際比較研究
動向「社会保障費用の国際統計の動向―ILO, OECD, EUROSTATを中心として―」『海外社会保障研究』(第146号)に問い合わせの多い国際比較データについての解説を掲載した。国際比較データではデータの入手が比較的困難なEUROSTATのデータについて,2003年9月8日より,『ユーロスタット2003「社会保護支出統計」部分翻訳版』,として研究所ホームページに掲載し利用者に配慮した。
・平成15年版社会保障統計年報の編纂と刊行
社会保障研究資料第3号として「社会保障統計年報 平成15年版」を編纂し刊行した。平成13年1月の省庁再編によりそれまで同資料を編纂・刊行していた社会保障制度審議会事務局が廃止となったため国立社会保障・人口問題研究所が編集を引き継いだ。本資料は平成15年3月に同平成12・13年版が本研究所によって刊行されたが,社会保障調査・研究事業の成果として位置づけられ研究資料番号を付与したのは平成14年版からであり,今後継続的に本資料の編纂と刊行を行い,社会保障研究の基礎資料として役立てる。
2 新将来人口推計事業に関する調査研究(平成13〜15年度)
国立社会保障・人口問題研究所は,国が行う社会保障制度の中・長期計画ならびに各種施策立案の基礎資料として,1全国人口に関する将来人口推計,2都道府県別将来人口推計,ならびに3世帯に関する将来世帯
数推計(全国・都道府県)を定期的に実施し,公表してきている。
・全国人口推計
全国推計の結果は,すでに平成14年1月に公表を行い終了したが,平成15年度においては,引き続き推計後の人口指標のモニタリングを行い,推計結果の評価検討を継続して行った。
(1)研究概要
推計に関連する人口指標を作成し,推計仮定値ならびに推計結果を人口学的手法により評価した。
(2)担当者
- 担当部長
- 高橋重郷(人口動向研究部長)
- 所内担当
- 金子隆一(総合企画部第4室長),三田房美(同部主任研究官),
- 石川 晃(情報調査分析部第2室長),加藤久和(社会保障基礎理論研究部第1室長),
- 池ノ上正子(人口動向研究部主任研究官),小松隆一(同部主任研究官),岩澤美帆(同部研究員)
- 守泉理恵(客員研究員)
・地域人口推計(都道府県別人口推計,日本の市区町村別将来人口推計)
近年,地域福祉計画の策定や行政需要を見通すための基礎資料として,小地域人口の将来予測への要望が高まっていることから,「日本の将来推計人口(平成14年1月推計)」,「都道府県別将来推計人口(平成14年3月推計)」に続いて,今回新たに「日本の市区町村別将来推計人口」を平成15年12月に公表した。推計方法ならびに推計結果の概要は以下の通りである(詳しくは,ホームページhttps://www.ipss.go.jp参照)。
(1)推計方法の概要
5歳以上の年齢階級の推計においては,コーホート要因法を用いた。コーホート要因法は,ある年次の男女・年齢別人口を基準として,ここに人口動態率や移動率などの仮定値を当てはめて将来人口を計算する方法であり,5歳以上人口推計においては生残率と純移動率の仮定値が必要である。一方0〜4歳人口については出生率に関する仮定値が必要であるが,市区町村別の出生率は年による変動が大きいことから,婦人子ども比の仮定値によって推計した。以上の推計においては仮定値として,(1)基準人口,(2)将来の生残率,(3)将来の純移動率,(4)将来の婦人子ども比,(5)将来の0〜4歳性比,が必要となる。なお推計期間は「都道府県別将来推計人口(平成14年3月推計)」と整合する形で,平成12(2000)年〜平成42(2030)年まで5年ごとの30年間とし,平成13(2001)年末現在の市区町村の領域(3,245自治体)を推計単位とした。
(2)推計結果の概要
①総人口の推移
- 全国推計(中位推計)・都道府県別推計と歩調を合わせて,多くの自治体で人口規模が縮小する。人口規模別の自治体数をみると,人口規模3万人以上の自治体は,平成12(2000)年から平成42(2030)年にかけて735から678に減少するのに対し,人口規模5千人未満の自治体が722から1,122と1.6倍増となり,全自治体の1/3以上を占めるようになる。
- 平成12(2000)年から平成42(2030)年にかけて,人口が2割以上減少する自治体は1,817(全自治体の56.0%)と半数を超え,このうち人口が5割以上減少(半数未満)となる自治体も158(全自治体の4.9%)存在する。特に小規模自治体での人口減少が顕著となっている。
- しかしながら,人口減少の度合いは地域によって格差が認められる。平成42(2030)年の総人口指数(平成12年=100とした場合)を地域ブロック別にみると,北海道・東北・中国の3ブロックにおいては,総人口指数100未満の自治体の割合が95.3%と,ほとんどの自治体で人口が減少する一方,南関東・北関東・近畿の3ブロックでは総人口指数が100以上となる自治体の割合も22.8%と相対的に高く,大都市とその郊外において人口が増加する自治体が目立っている。
②年齢別人口の推移
- 全国推計(中位推計)によれば,全国の年少人口(0〜14歳)は今後も減少を続けるが,市区町村別においても平成12(2000)年から平成42(2030)年にかけて年少人口割合が低下する自治体は3,221(全自治体の99.3%)である。この間に,年少人口割合が10%未満の自治体は102から1,017へと増加する一方,年少人口割合が16%以上の自治体は691から21へと減少する。
- 全国推計(中位推計)によれば,全国の生産年齢人口(15〜64歳)も今後一貫して減少するが,市区町村別においても平成12(2000)年から平成42(2030)年にかけて生産年齢人口割合が低下する自治体は3,210(全自治体の98.9%)にのぼる。この間に,生産年齢人口割合が50%未満の自治体は117から1,039へと増加する一方,生産年齢人口割合が60%以上の自治体は1,956から330へと減少する。
- 全国推計(中位推計)によれば,全国の老年人口(65歳以上)はほぼ一貫して増加し続けるが,市区町村別においても老年人口割合が増加するのは3,232自治体(全自治体の99.6%)となっている。この間に,老年人口割合が40%以上の自治体は77から987へと増加する一方,老年人口割合が20%未満の自治体は967から7へと激減する。
- 以上のように各自治体は高齢化が進行することとなるが,地域ブロック別にみると,その状況には若干差異がみられる。全体として,平成42(2030)年時点での「老年人口割合」と平成12(2000)年から平成42(2030)年にかけての「老年人口増加率」との間に負の相関が認められることは注目に値する。地域ブロック別では,老年人口割合が高く老年人口増加率が低いのは北海道・中国・四国の自治体に多いが,老年人口割合が低く老年人口増加率が高いのは南関東や近畿などの大都市圏に属する自治体に多くみられる。
(3)担当者
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 大場 保(人口構造研究部第1室長),小池司朗(同部研究員),山内昌和(同部研究員)
・世帯推計(全国世帯推計)
全国世帯推計は,将来の全国の一般世帯数を世帯主の男女・5歳階級別,家族類型別に推計したもので,結果は平成15年10月に公表した。推計方法と結果の概要は,以下の通りである。
(1)推計方法の概要
推計期間は,2000(平成12)年10月1日から2025(平成37)年10月1日までの25年間である。一般世帯の家族類型は,「単独世帯」,「夫婦のみの世帯」,「夫婦と子から成る世帯」,「ひとり親と子から成る世帯」,「その他の一般世帯」の5類型である。本推計の男女別・5歳階級別人口は,先に公表された全国人口の将来推計の中位推計と合致する。
①推計の方法
推計方法は世帯推移率法によった。これは男女別,5歳階級別,推計期間別に,配偶関係・世帯内地位間の推移確率行列を用意し,それに期首の配偶関係・世帯内地位別人口ベクトルを適用して期末ベクトルを求めるものである。ただし推移確率の推定は配偶関係に関する確率と配偶関係別世帯内地位に関するそれの2段階に分かれ,さらに後者の推移確率が標本調査から得られるのは一般世帯人口についてのみで施設世帯人口については別途推計する必要があるため,推計作業は多くの段階を含む複雑なものとなった。
②配偶関係別世帯内地位の定義
国勢調査の世帯主に対し,推計モデルの対象となる世帯の準拠成員をマーカと呼ぶ。世帯の家族類型とマーカの性・配偶関係の組合せを限定し,男子12種類,女子11種類の配偶関係と世帯内地位の組合せを定義した。
③将来の配偶関係間推移確率の設定
全国人口推計(2002年1月推計)の中位推計で設定された死亡率および女子初婚率を用いて,前回の配偶関係間推移確率行列を調整した。
④推移確率行列の作成
第4回世帯動態調査(1999年)のデータから,個々の配偶関係間推移を条件とする世帯内地位間推移確率を得た。これを配偶関係間推移確率行列に適用し,男女・5歳階級別の配偶関係・世帯内地位間の推移確率行列を作成した。これを1995年国勢調査から得た配偶関係・世帯内地位ベクトルに乗じて結果を2000年国勢調査と比較し,推移確率を調整した。
⑤未婚者の離家の将来推計
婚姻状態間推移ごとの条件付世帯内地位間推移確率は1995〜2000年試行推計で求めたものを適用したが,期首40歳未満の未婚→未婚推移における非マーカ→単独世帯マーカの推移確率だけは将来も低下を続けると仮定した。将来値の設定は,コーホート毎の比例ハザードモデルによった。
⑥施設世帯人員割合の将来推計
男女別,5歳階級別,配偶関係別,施設世帯人口割合を国勢調査から得,1995〜2000年の変化率を補外して将来の施設世帯人口割合を推計した。
⑦基準人口
推計の出発点となる基準人口は,2000年国勢調査の男女別,5歳階級別,配偶関係別,世帯内地位別人口に基づき,モデルの仮定に合わせた若干の調整を経て得た。
⑧配偶関係・世帯内地位別将来推計人口
推計された男女別,5歳階級別の配偶関係・世帯内地位分布を全国推計人口に乗じ,男女別,5歳階級別,配偶関係別,世帯内地位(施設世帯を含む)別人口を得た。最後に,基準人口作成時の世帯主・非世帯主からマーカ・非マーカへの変換を逆に適用し,男女別,5歳階級別,配偶関係別,家族類型別世帯主数,非世帯主数および施設世帯人員数を得た。
(2)推計結果の概要
①人口と世帯数の趨勢
全国人口の将来推計(中位推計)によると,日本の総人口は2006年に1億2,774万人に達した後減少に転じるとされるのに対し,一般世帯総数は2000年の4,678万世帯から2015年の5,048万世帯まで増加を続け,以後減少に転じると予想される。2025年の一般世帯総数は,4,964万世帯となる。
②平均世帯人員の変化
一般世帯の平均世帯人員は,2000年の2.67人から2025年の2.37人まで減少を続けると予想される。
③家族類型別一般世帯数および割合の変化
今後増加するのは「単独世帯」「夫婦のみの世帯」「ひとり親と子から成る世帯」であり,減少するのは「夫婦と子から成る世帯」「その他の一般世帯」である。
「単独世帯」は2000年の1,291万世帯から2025年には1,716万世帯まで増加し,一般世帯総数に占める割合も2000年の27.6%から2025年の34.6%まで上昇する。「夫婦のみの世帯」は2000年の884万世帯から2025年には1,029万世帯まで増加し,割合も2000年の18.9%から2025年の20.7%まで上昇する。ただしこの類型のピークは2015年で,それ以後は減少に転じる。「ひとり親と子から成る世帯」は2000年の358万世帯から2025年には479万世帯まで増加し,割合も2000年の7.6%から2025年の9.7%まで上昇する。
「夫婦と子から成る世帯」は2000年の1,492万世帯から2025年には1,200万世帯まで減少し,割合も2000年の31.9%から2025年の24.2%まで低下する。「その他の一般世帯」は2000年の654万世帯から2025年には540万世帯まで減少し,割合も2000年の14.0%から2025年の10.9%まで低下する。
(3)担当者
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 鈴木 透(国際関係部第3室長),小山泰代(人口構造研究部第3室長)
3 第3回全国家庭動向調査(実施)
(1)調査の目的
近年,人口の少子化や高齢化が急速に進むわが国の家族は,単独世帯や夫婦世帯の増加,女性の社会進出による共働き家庭の増加など,その姿とともに機能も大きく変化している。この家庭機能の変化は,家庭内における子育て,老親扶養・介護などのあり方に大きな影響を及ぼすだけでなく,社会全般に多大な影響を与える。家族変動の影響を大きく受ける子育てや高齢者の扶養・介護などの社会サービス政策の重要性が高まっているなかで,わが国の家族の構造や機能の変化,それに伴う子育てや高齢者の扶養・介護の実態,およびその変化と要因などを正確に把握することが重要な課題となっている。
国立社会保障・人口問題研究所では,家庭機能の実態や動向を明らかにするため,平成5(1993)年,平成10年(1998)年の2度にわたって「全国家庭動向調査」を実施してきた。とくに,前回調査以降の家庭の状況を明らかにするため,平成15年に「第3回全国家庭動向調査」を実施した。本調査の結果は,広く各種の行政施策立案の基礎資料として活用される予定である。調査の概要は以下のとおりである。
①調査対象
平成15年国民生活基礎調査地区内より無作為に抽出した300調査区のすべての世帯を調査対象とする。
②調査期日
平成15年7月1日
③調査事項
- 世帯員の人口学的・社会経済的属性
- 夫婦の人口学的・社会経済的属性
- 両親,子どもに関する事項
- 出産・育児,扶養・介護に関する事項
- 日常生活でのサポート資源に関する事項
- 夫の家事・育児に関する事項
- 夫婦関係に関する事項
- 子どもや家族に関する考え方(意識)に関する事項
- 資産の継承に関する事項
④調査方法
調査票の配布・回収は調査員が行い,調査票の記入は調査対象者の自計方式による。調査系統は,国立社会保障・人口問題研究所が厚生労働省大臣官房統計情報部,都道府県,保健所を設置する市・特別区および保健所の協力を得て実施。
⑤調査票の回収状況および調査結果の公表
調査は平成15年7月1日に実施され,調査票配布枚数14,322に対して,回収票数は12,681票(88.5%),うち有効票数11,018(76.9%)であった。回収された調査票は,研究所における点検作業の後,データ入力作業が終了した。現在データのクリーニング作業を行っている。
(2)担当者
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 小山泰代(人口構造研究部第3室長),赤地麻由子(同部研究員),星 敦士(客員研究員)
- 所外委員
- 白波瀬佐和子(筑波大学助教授)
4 第12回出生動向基本調査(分析)
(1)研究概要
国立社会保障・人口問題研究所は2002(平成14)年6月,第12回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)を実施した。この調査は他の公的統計では把握することのできない結婚ならびに夫婦の出生力に関する実態と背景を調査し,少子化対策等の関連諸施策ならびに将来人口推計に必要な基礎資料を得ることを目的としている。
本調査は,夫婦を対象とする夫婦調査に加えて,独身者を対象とする独身者調査を同時実施している。平成14年度は調査の実施とデータチェックを行い,平成15年度に基本集計を終えた後,基本的な分析を行い,結果の概要を公表する段階である。その後,調査報告書を刊行する。なお,夫婦調査は,既に平成15年5月,独身者調査は平成15年7月に結果の概要を公表した。
(2)夫婦調査の結果概要
①調査実施の概要
夫婦調査は,全国の妻の年齢50歳未満の夫婦を対象とした標本調査であり(回答者は妻),平成14年6月1日現在の事実について調べたものである。調査対象地域は,平成14年「国民生活基礎調査」(厚生労働省大臣官房統計情報部実施)の調査地区1,048カ所(平成12年国勢調査区から層化無作為抽出)の中から,系統抽出法によって選ばれた600地区である。したがって,そこに居住する全ての50歳未満の有配偶女子が本調査の客体である。
調査方法は配票自計,密封回収方式によった。その結果,調査票配布数(調査客体数)9,021票に対して,回収数は8,382票であり,回収率は92.9%であった。ただし,回収票のうち記入状況の悪い466票は無効票として集計対象から除外した。したがって,有効票数は7,916票であり,有効回収率は87.8%である。なお,概要報告では夫妻が初婚どうしの夫婦6,949組について集計を行った。
②結果の概要
- 晩婚化はさらに進行し,出会い年齢が女性側でやや遅くなる傾向がみたれた。最近5年間の結婚(初婚どうし)では,結婚した男性の半数強(55.3%),女性の2/3(68.0%)は25歳までに結婚相手と知り合っている。
- 夫妻が初めて出会った時から結婚するまでの交際期間は長くなっており,10年前(第10回調査)に比べ約2割(21.2%),15年前(第9回調査)に比べると約4割(40.7%)も長くなっている。これにも見合い結婚の減少が関与しているが,恋愛結婚だけを見ても長くなっている。また,15年前(第9回調査)では,出会ってから1年以内に結婚した夫婦が1/3(34.3%)を占めていたが,最近5年の結婚ではその割合は半分以下(15.4%)に減少している。
- 男性に比べて女性の晩婚化が著しいので,夫妻の年齢差が小さくなっている。この年齢差の縮小にも,見合い結婚の減少が寄与しているものの,恋愛結婚だけについて見ても縮小は顕著であること
がみられた。
- 夫妻が知り合ったきっかけは,「職場や仕事の関係で」が最も多く,約1/3を占める。ついで「友人・兄弟姉妹を通じて」が約3割,「学校で」が約1割と,概して日常的な場での出会いが多い。近年「友人・兄弟姉妹を通じて」の割合がやや増え,徐々に「職場や仕事で」の割合に近づいている。また,見合い結婚はさらに減少して,今回は前回の約1割をさらに下回り,約7%となった。
- 結婚持続期間15〜19年の夫婦の平均出生子ども数(完結出生児数)は,戦後大きく低下した後,第6回調査(1972年)において2.2人となり,以後30年間ほぼこの水準で安定している。今回の調査においても完結出生児数は2.2人と,同様の水準を維持しており,この世代の夫婦(1980年代半ばに結婚)の出生力は安定していたことがわかった。
- 夫婦の最終的な子ども数は2人または3人が8割以上を占め,結婚持続期間15〜19年の夫婦の出生子ども数は,第7回調査以降ほとんど変化がなく,2人ないし3人に集中した構成となっている。すなわち,約8割の夫婦が2人か3人の子どもを持っている。また,子どものいない夫婦は約3%,1人っ子が1割弱,4人以上は4〜5%となっている。今回も子どもを生み終えた世代の夫婦では,こうした構成にほとんど変化はなかった。
- 出生途上の夫婦の子ども数は,結婚後5〜9年,10〜14年の夫婦で,平均子ども数の低下が続いている。10回調査(1992年)から低下していた結婚持続期間0〜4年の夫婦の平均出生子ども数は,今回調査ではやや上昇した。他方,結婚持続期間5〜9年,10〜14年の夫婦では,前回調査で見られた平均出生子ども数の低下が継続した。
- 結婚後5〜9年,10〜14年の夫婦で,1人っ子を持つ割合が増える傾向がみられ,10回調査(1992年)以降,10〜14年では第11回調査(1997年)から,子ども数2人以上の夫婦が減り,1人っ子が増えている。結婚持続期間5〜9年では同時期に子どものいない夫婦もやや増えた。
- 妻の出生世代による比較から,1990年代以降,夫婦出生力に低下が見られた。1990年前後(第9〜10回調査の間)に20歳代後半から30歳代前半で最初に低下が見られ,その低下は30歳代後半へ広がりながら90年代半ば(第10〜11回調査)へと継続したことがわかる。さらに,2000年前後(第11〜12回調査)でも30歳以上で低下した。また,生まれ年別にみると,1960年代生まれの世代が20歳代の終わりに達した頃から夫婦の出生力が低下していることが明らかとなった。
(3)独身者調査の結果概要
①調査実施の概要
独身者調査は,全国の年齢18歳以上50歳未満の独身者を対象とした標本調査であり,平成14年6月1日現在の事実について調べたものである。調査対象地域は,平成14年「国民生活基礎調査」(厚生労働省大臣官房統計情報部実施)の調査地区1,048カ所(平成12年国勢調査区から層化無作為抽出)の中から,系統抽出法によって選ばれた600地区である。したがって,そこに居住する18歳以上50歳未満の全ての独身者が本調査の客体である。
調査方法は配票自計,密封回収方式による。その結果,調査票配布数(調査客体数)12,866票に対して,回収数は10,888票であり,回収率は84.6%であった。ただし,回収票のうち記入状況の悪い1,202票は無効票として集計対象から除外した。したがって,有効票数は9,686票であり,有効回収率は75.3%である。なお,概要報告ではそのうち18歳以上35歳未満の未婚男女を中心に集計分析を行った。
②調査結果の概要
- これまでの調査で減少傾向にあった「いずれ結婚するつもり」,「ある程度の年齢までには結婚するつもり」の未婚男女の割合は5年前とほぼ同程度で,彼らの生涯の結婚に対する意識の変化は一段落している。しかし,当面の結婚に対しては主要な年齢層で「まだ結婚するつもりはない」とする未婚者が継続して増えている。
- 結婚に利点を感じない未婚男性が増えている。社会的信用や生活上の利便など,結婚の実利面を挙げる人が減っているためで,逆に男女とも「子どもや家族をもてる」など内面的な利点を挙げる人は増えている。
- 未婚者が独身にとどまっている理由は,25歳未満の若い層では「仕事(学業)にうちこみたいから」が増え,25歳以上の層では「適当な相手にめぐり合わないから」が継続的に減少するなど,概して「結婚できない」から「結婚しない」へ重心が移っている。
- 未婚者が希望する結婚年齢は高まっており,ここでも結婚を先送りする意識が続いていることがわかる。
- 男女とも自分と近い年齢の結婚相手を希望する傾向が強まっている。これは夫婦で実際に見られる年齢差の縮小と符合しており,これが当事者たちの希望に沿った傾向であることがわかる。
- 異性の交際相手を持たない未婚者の割合は男性5割強,女性4割と,1987年調査(第9回調査)以降ほとんど変化がない。しかし,恋人以上の親密な交際相手(恋人および婚約者)を持つ割合は,女性では25歳以上の年齢層で継続的に増加しており,相手がいないか親密な相手を持つかの二極化の傾向が見られる。
- 同棲していると回答した未婚者は男女とも2%台と未だ少数派ではあるものの増加傾向を示しており,とりわけ20代後半の同棲経験者は今回調査では1割に達した。
- 未婚男女の性経験率は男性では頭打ち傾向にあるのに対して,女性では全年齢とも継続して増加しており,過去に見られた男女の差は消失しつつある。
- 専業主婦を理想のライフコースと考える未婚女性が急速に減っており,前回調査(1997年)以降は,仕事と家庭を両立するコースが逆転してこれを上回っている。ただし,最も多いのは出産・子育て後の再就職コースである。また,実際になりそうなコース(予定のライフコース)でも「専業主婦」は減っており,今回,両立コースが逆転して上回った。なお,男性が女性に望むコースでも今回「専業主婦」と「両立」が逆転して後者が上回った。
- 女性のライフコースについての未婚者の理想と現実(予定)は「専業主婦」を除いて一致率が上がる傾向が見られる。
- 結婚相手を決める条件として,女性では相手の「仕事に対する理解と協力」「家事・育児に対する能力や姿勢」を重視する度合いが高まっている。また多くの子どもを持ちたい女性ほどそれらを重視する傾向が強い。
- 未婚者が30代,50代に一緒に暮らしたい相手は,それぞれ「配偶者と子ども」,「配偶者のみ」が最も多く,「三世代同居」を望む割合はどちらも1割に満たない。30代では「恋人」と暮らすことを望む人が1割程度(男性10%,女性8%)いる。
- 未婚者が持ちたいと望む子ども数は近年一貫して減少しており,今回夫婦の予定子ども数を大きく下回った。しかし,結婚意思のない男女でも女性の35%,男性の29%は子どもを持つことを望んでいる。
- 希望する子どもの男女構成では,女児を望む傾向が男女ともに強まっている。とくに女性で女児を望む傾向が強い。
- 20代以降の男性,30代以降の女性で親と同居する未婚者が大幅に増えている。フリーター(パート,アルバイト,無職)が増加していることと,このグループでの親との同居率の上昇が寄与していると見られる。
- 家庭内の役割にとどまらない女性の生き方(性別役割分業への反対,自己目標の保持,育児専念規範への反対)に対し引き続き支持が増大している反面,今回の結果では,独身として生きること(生涯独身,離婚,同棲)に対する評価にゆらぎが見られる。
(4)担当者
- 担当部長
- 高橋重郷(人口動向研究部長)
- 所内担当
- 金子隆一(総合企画部第4室長),大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2室長),
- 釜野さおり(人口動向研究部第2室長),佐々井 司(同部第3室長),池ノ上正子(同部主任研究官),
- 三田房美(総合企画部主任研究官),岩澤美帆(人口動向研究部研究員),守泉理恵(客員研究員)
5 第5回人口移動調査(事後事例調査)
(1)研究実施状況
平成15年度の人口移動調査では,データクリーニングを継続し,同時に合成変数,集計表の作成・分析と結果のとりまとめの準備を行った。結果の概要公表後,速やかに報告書の刊行を行う予定である。
(2)担当者
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 千年よしみ(国際関係部第1室長),清水昌人(人口構造研究部第2室長),小池司朗(同部研究員)
- 所外委員
- 江崎雄治(専修大学専任講師),小林信彦(第一生命経済研究所)
6 第5回世帯動態調査(企画)
(1)調査の概要
単独世帯や夫婦世帯の増加など,人口構造の高齢化の進展とともにわが国の世帯構造は大きく変化している。世帯は国民の生活単位であることから,世帯構造の変化が与える影響は,国民一人一人の生活はもちろんのこと,社会全体に対しても極めて大きい。子育てや高齢者の扶養・介護といった社会サービス政策の重要性が高まるなか,その基礎となる世帯構造の実態とその変化を解明することは不可欠の課題である。また,各種の行政施策の立案や将来の行政需要を見通す上で,近年の世帯構造の変化を適切に把握することは極めて重要である。
本調査は,全国規模のサンプル調査で本格的に世帯構造の変化を把握したわが国唯一の調査であり,他の公式統計では捉えることのできない世帯の形成・拡大・縮小・解体の実態などを明らかにするものである。その結果は,各種の行政施策立案などのほか,国立社会保障・人口問題研究所が実施する世帯数の将来推計のための基礎資料として活用されている。平成16年度は「第5回世帯動態調査」の実施年にあたり,平成15年度はその予算要求,調査準備等を行った。
(2)担当者
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 鈴木 透(国際関係部第3室長),清水昌人(人口構造研究部第2室長),小山泰代(同部第3室長),
- 山内昌和(同部研究員)
7 社会保障改革分析モデル事業(平成13〜15年度)
(1)研究目的
少子高齢化の進展や経済環境の変化とともに,社会保障制度が有するセーフティ・ネットの役割やこれが経済活動に及ぼす効果に対する関心が高まっている。本事業は,社会保障制度の財政動向,所得再分配効果,社会保障改革が経済に及ぼす影響,あるいは世代間の公平性の試算など,今後,社会保障制度の運営とともに注目される諸課題を定量的に明らかにすることを目的としている。
以上の目的を遂行するため,マクロ計量経済モデルや世代重複モデルなどを開発するとともに,政策的な効果が明らかになるようなシミュレーションを実施する。
(2)研究計画
本事業は3年計画に沿って運営された。初年度には分析ツールの拡充を図り,2年目に新人口推計に沿ったシミュレーションを行い,最終年度には社会保障改革を視野に入れたさまざまな効果分析を行った。
平成15年度は,計画の最終年度にあたり,過去2年間で開発・改良を行ってきた各モデルによる,将来展望及び政策シミュレーションを実施した。とりわけ,公的年金制度改革の方向性をモデルに組み入れたシミュレーションを行い,本事業の目的である,社会保障制度改革と社会経済の諸側面との関係の検証や社会保障制度改革がもたらすマクロ経済,国民負担,世代内・世代間分配への影響を明らかにした。これに加えて,マイクロ・シミュレーション・モデルを利用した,第三号被保険者問題などの分析を行った。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 所内担当
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部長),加藤久和(社会保障基礎理論研究部第1室長),
- 山本克也(同部主任研究官),宮里尚三(社会保障応用分析研究部研究員)
- 所外委員
- 大林 守(専修大学商学部教授),小口登良(専修大学商学部教授),
- 藤川清史(甲南大学経済学部教授),山田節夫(上智大学経済学部教授),
- 上村敏之(東洋大学経済学部助教授),人見和美(電力中央研究所主任研究員)
- 研究協力者
- 稲田義久(甲南大学経済学部教授),日高政浩(大阪学院大学経済学部助教授),
- 佐藤 格(慶應義塾大学大学院経済学研究科),
- 中田大悟(横浜国立大学エコテクノロジー・システム・ラボラトリー講師),(財)国民経済研究協会
(4)研究会の開催状況
第1回 2003年7月16日
- 社会保障改革分析モデル事業の最終年度の取り組みについて
- 最近の年金改革論議について(発表者:山本克也)
- 簡易版世代会計について(発表者:金子能宏)
- マクロ経済・財政シミュレーションの試算結果(発表者:加藤久和)
第2回 2003年12月8日 報告書論文の中間報告会
第3回 2004年3月12日 報告書論文の最終発表会(ワークショップ)
―最終報告書論文―
- 社会保障財政の将来展望(発表者:加藤久和)
- 厚生年金における保険料固定方式の効果分析(発表者:金子能宏,中田大悟)
- 世代間公平からみた公的年金改革の厚生分析(発表者:上村敏之,佐藤 格)
- 年金給付算定方法の再検討(発表者:山本克也)
- マクロ計量モデルを用いた年金制度改革の需要面への影響分析(発表者:山田節夫,国民経済研究協会)
(5)研究結果の公表
報告書を作成するとともに,日本経済学会,日本財政学会等で報告を行った。
8 自殺による社会・経済へのマクロ的な影響調査(平成13〜15年度)
(1)研究目的
自殺率が増加する中で,中高年男性の自殺率が特に高まっていることが指摘されている。中高年男性は,企業の担い手としてまた世帯主としてわが国の経済活動と人口の再生産にとって重要な貢献をしてきたにもかかわらず,その自殺率が増加していることは,これらの活動に少なからぬ損失を生じさせている可能性がある。これまで,経済活動や人口再生産の担い手である勤労者(とくに中高年の男女労働者)が自殺した場合の逸失利益を明確にして自殺の社会・経済への影響を明確にすることは,殆どなされてこなかった。しかし,自殺防止対策を効果的に実施するためには,自殺防止対策の費用と便益の関係を明らかにする必要がある。また,このような分析を行うには,中高年労働者の自殺率の上昇が景気後退に伴う失業率の上昇に関係しているマクロ的な側面と,個々の労働者に対して職場における能力主義の浸透(賃金体系や人事考課の変化)が職場のストレス要因となっているというミクロ的な側面それぞれに留意する必要がある。したがって,本研究の目的は,このような問題意識のもとに,厚生・労働政策との関連に留意しながら,労働者の職場におけるストレスがその治療成果や自殺に及ぼす影響を世帯構造や個人属性に配慮しながら分析する調査研究を実施するとともに,自殺のマクロ経済的な損失,及び雇用政策による職場環境の向上と医療政策による治療成果の向上が自殺を減少させることによる社会・経済への影響を分析することである。
(2)研究実施状況
自殺による死亡率は,経済環境の変化もあって近年増加しており,医療政策や精神保健政策に加えて,経済問題との関連にも関連した分析が求められている。リストラなどに伴う従業員のストレスにも配慮しながら自殺予防が可能になるためには,企業の理解を高める必要があり,そのためには,自殺の経済的損失や国民経済に及ぼす影響を測ることが重要な課題である。本研究は,このような問題意識のもとに,次のような研究を行う。
- 労働需給,就業状態,消費・貯蓄動向等の経済環境の変化と,職場環境の変化等によるストレス,景気循環に伴う世論の変化など社会心理的環境の変化とが自殺率に及ぼす影響に関する分析
- 家族のライフサイクルに注目した自殺の逸失利益の推計
- 自殺による労働力の変化が国民経済に及ぼす影響の推計
- 自殺予防における医療政策,精神保健福祉政策,地域やNGO取り組みの連携がもたらす効果と,国民経済に及ぼす影響に関する分析
- 自殺の社会経済的要因に関する実証分析
- 自殺予防対策に関する国際比較研究
平成14年度は,1について公表統計に基づく実証分析を行い,3で用いるマクロ経済モデルにおける自殺関連変数の特定化を行った。2については,一世代の家族を対象とする場合の推計を行った。3については,自殺率が中高年男性に多いことに留意して,労働力を中高年労働者とそれよりも若い労働者に分けた生産関数をもつ供給型マクロ経済モデルを推定し,これを利用して自殺によって失われるGDPの大きさを推計した。4については,分析に用いるデータ・ベースの整備を平成13年度に引き続き行った。6については,スウェーデン,アメリカ,オーストラリアを対象に比較研究を行った。
平成15年度は,4に関連して,3で用いるマクロ経済モデルを推定するデータ・ベースをSNA97に基づくものへの更新を行うとともに,都道府県別と年齢階級別それぞれの時系列からなるプールされたクロスセクションデータを用いて5に関する実証分析を行った。6については,WHO(世界保健機関),カナダ,ドイツの自殺予防対策の動向調査をし,わが国への示唆を得るための考察を行った。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 所内担当
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部長),山下志穂(客員研究員)
- 所外委員
- 池上直己(慶應義塾大学教授),反町吉秀(京都府立医科大学助教授),
- 音山若穂(郡山女子大学専任講師)
(4)研究成果の公表
研究成果は,厚生労働省社会援護局障害保健福祉部の第5回「自殺防止対策有識者懇談会」(平成14年8月)において報告し,同懇談会報告書「自殺予防に向けての提言」資料編(平成14年12月)に採録され一般に公開された。また,自殺予防策の海外動向をわが国の現状と比較し今後の課題を検討するために,国立社会保障・人口問題研究所において一般公開の社会保障セミナー「海外の自殺防止対策の動向と日本への」を開催した(平成15年3月)。この成果を含む自殺予防の国際比較研究は,『海外社会保障研究』145号の動向として公表した。さらに,自殺の社会経済的要因に関する実証分析は,厚生労働省社会援護局障害保健福祉部の平成15年度「自殺防止関連研究者懇談会」において報告し,『季刊社会保障研究』第40巻第1号・特集「社会経済の変化と自殺予防」の論文として公表した。これらの成果を,一般に提供するため,研究資料『自殺による社会経済へのマクロ的な影響調査』I(平成13・14年度)及びII(平成15年度)としてとりまとめた。
9 出生力に関連する諸政策が出生調節行動を介して出生力に及ぼす影響に関する研究(平成14〜16年度)
(1)研究目的
わが国をはじめ多くの先進諸国では置き換え水準を下回る低出生力が持続し,著しい少子高齢化・人口減少問題に直面している。わが国の低出生力の要因については従来,様々な経済学的・社会学的アプローチによって社会・経済条件との関連が研究されてきたが,これまで体系的な研究があまりなされていない2つの大きな研究課題があると考えられる。
一つは出生力の近接要因(結婚年齢,避妊,人工妊娠中絶,妊孕力など生物学的行動的要因)の観点に立ったアプローチであり,ミクロ(個々のカップル)レベルでいえば,出生意図と出生調節行動に関する研究である。低出生力の社会では夫婦の大部分がなんらかの出生調節行動をおこなっており,出生意図/出生調節行動とその結果としての出生力との関係を明らかにすることは出生力の決定要因を測る上できわめて重要である。換言すれば,出生力の要因研究には子どもの需要側に着目する研究と子どもの供給側に着目する研究があるが,本研究は主に後者の視点に立つ研究である。つまり供給過多(望まない妊娠/出産)あるいは供給過少(夫婦にとっての希望子ども数の未達成)がどのようなメカニズムでおこるのか,という点の解明に力点を置く。
いま一つは政府が採ってきたあるいは今後採りうる政策と出生調節行動との関連である。もとより民主主義国において強権的な出生促進政策はありえず,国民の福祉向上のために様々な政策が実行あるいは模索されているが,それらの諸政策の中には個人の出生調節行動の変化を介して出生力に影響を及ぼす可能性のある政策が含まれる。出生力の供給側に影響を与えうる政策として,たとえば,直接的な出産・育児支援政策(母子保健医療対策,育児休業,保育支援など),リプロダクティブ・ヘルス/ライツ政策(避妊法の認可,人工妊娠中絶に関する規制の変更,女性健康対策,思春期保健対策など),がある。また出産・子育てをめぐる全般的な女性の意識と行動に影響を与えうるものとして,ジェンダー政策(男女雇用機会均等,男女共同参画など),IEC(情報・教育・コミュニケーション)活動などが挙げられる。
なお本研究でいう「政策」は広義の概念であり,「自由放任=自然状態あるいは市場に委ねる」に対して何らかの「介入」が実行または企図されることを意味する。政府の直接・間接的活動のみならず,性教育/健康教育/人権教育,マスメディアなどを通した情報や観念の伝播・形成を含んでいる。その意味からすれば,「情報・政策」と括るべきものである。
本研究は,このような出生力に関連する諸政策および情報が個々の男女の出生調節行動を介して出生力に及ぼす影響を詳細に明らかにしようとするものであり,広い意味の生態学的観点に立った出生力研究ともいえる。その成果は,この分野の学問的発展ならびに少子化に対する政策対応および評価に関する科学的方法の発展に寄与することが期待される。
(2)研究計画
- 先行研究について文献レビューを行い,研究会における議論を経て,分析枠組みを固める。
- 所内外の研究者が交流する場として,「リプロダクション情報・政策研究会」を年6回程度開催する。産婦人科医など現場の専門家から実際の状況を聞き,最新情報の収集に努める。また女性史研究家などに参加を求め,ジェンダー・セクシュアリティ・リプロダクションをめぐる近現代史における日本の文化的状況の変容にも注目する。
- 人口動態統計などマクロ統計を用いて,マクロ出生力分析(要因分析,シミュレーションなど)をおこなう。
- 出生動向基本調査などを用いて,ミクロ出生力分析(要因分析,シミュレーションなど)をおこなう。
- 以上を総括して,包括的なモデルを構築し,その妥当性について検討する。
○リプロダクション情報・政策研究会
○セミナー「少子化の要因と政策効果に関する研究の動向と課題」(2004年3月24日国立社会保障・人口問題研究所にて開催)
- 基調報告1「日本の少子化と政策目標:出生力の置換水準回復は可能か」大淵 寛(中央大学)
- 基調報告2「少子化の要因と政策効果に関する研究の動向と課題」佐藤龍三郎・白石紀子(国立社会保障・人口問題研究所)
- 討論:多数の専門家の参加があり,人口政策,経済政策,ジェンダー,地域社会,倫理など多様な観点から活発な意見交換がおこなわれた。
(4)研究会の構成員
- 担当部長
- 佐藤龍三郎(情報調査分析部長)
- 所内担当
- 石川 晃(情報調査分析部第2室長),白石紀子(同部第3室長)
- 所外委員
- 荻野美穂(大阪大学大学院文学研究科助教授),早乙女智子(ふれあい横浜ホスピタル産婦人科医師)
(5)研究結果の公表
①研究資料の作成
先行研究のレビュー(文献検索)をほぼ終え,2種類の文献リスト(『関連文献分類項目別索引』ならびに『少子化に関する文献目録』)を作成した。
前者は本研究の特徴である広い意味の医学的観点に立ったものであり,「医学中央雑誌」などの文献データベースにより文献を検索し,以下の4大項目に分類したものである。
- 生殖の医学生物学的側面(妊孕力,不妊,多胎,出生性比,父母の年齢など)
- 性行動と出生調節(性行動,避妊,人工妊娠中絶,出産意図・規範,理想/予定子ども数,性別選好など)
- 結婚・離婚(パートナーシップ形成・解消)の人口学(結婚,結婚年齢,離婚など)
- 性と生殖をめぐる政策と倫理(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ,日本の「少子化対策」とこれをめぐる議論,生命倫理の視点,ジェンダー・フェミニズムの視点,教育・マスメディアの影響など)
「少子化に関する文献目録」は本研究所図書室が2001〜03年にかけて収集し所蔵する図書・資料を①少子化に関する現状と見通し,②少子化の背景と要因,③少子化の経済的影響,④少子化の影響に対する対応,⑤少子化の要因への対応,⑥出生(人口)理論・分析方法の6項目に分類したものである。
②関連した研究発表
- 佐藤龍三郎・早乙女智子・白石紀子「近年の日本の妊孕力に関する文献的検討」日本人口学会(岐阜)2003年6月7日
- 佐藤龍三郎「少子化とリプロダクティブ・ヘルス/ライツ」人口学研究会(中央大学後楽園キャンパス)2004年3月13日
10 戦後日本の社会保障制度改革に関する政治社会学的研究(平成14〜16年度)
(1)研究目的
社会保障について,2000年には年金改革,社会福祉基礎構造改革がなされ,介護保険の実施もはじまったが,これらについて更なる改革を求める意見も強く,医療保険改革も喫緊の課題として残されている。現行の社会保障制度はこれまでのさまざまな改革の積み重ねで出来上がったものであり,それぞれの次元での政策判断がどのような議論の積み重ねとどのような時代背景の下でなされてきたかを整理分析することは,今後の社会保障制度改革について政策決定を行う上で不可欠である。本研究は,高度経済成長が低成長に移行し,社会保障改革も単純な制度の拡充から財政制約への対応に重点が移行した1980年代以降を中心に,制度改革に関する文書資料を収集し改革の流れを追うとともに社会経済との関連を分析し,今後の社会保障制度改革の政策決定のための基礎資料を得ようとするものである。
(2)研究計画
初年度は,社会保障制度の諸改革に関する各種先行研究,並びに政府各省庁の資料,関係審議会の答申・勧告・建議等の文書資料の収集を行う。次年度は,前年度の資料の整理・検討並びに研究者及び政策担当者からの補完的なヒアリングを実施する。最終年度は,前2年度で収集,整理・検討した文献・資料等を基に,社会保障制度改革について分析・検討し,報告書を作成する。あわせて,収集・整理した資料のうち重要なものを社会保障資料集として取りまとめる。資料集の作成については,膨大な量であることを勘案しCD-ROMに画像ファイルとして収集・整理を行い,キーワード検索など汎用的なソフトの整備を行い公開を行う。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長,〜12月)/
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部長,平成16年1月〜)
- 所内担当
- 西村幸満(社会保障応用分析研究部第2室長),菊地英明(社会保障基礎理論研究部研究員),
- 宮崎理枝(客員研究員)
- 所外委員
- 土田武史(早稲田大学教授),田多英範(流通経済大学教授),北場 勉(日本社会事業大学教授),
- 清水英彦(早稲田大学教授),横山和彦(新潟医療福祉大学教授),菅沼 隆(立教大学助教授)
(4)研究実施状況
当初の計画通り,1980年以降の社会保障制度の諸改革に関する文書資料の収集整理を継続的に行った。文書資料の整理に当たって,個別の先行研究,政府各省庁,関係審議会ごとに整理されているものを,年金改正関連(85年,89年,94年),国民健康保険改正関連(88年),医療改正関連(91年),老人保健法改正関連(91年),共済年金・農業者年金関連,企業年金改正関連(94年)などの分類を作成し,再分類を行った。そして,再分類された文書資料はその政策決定までのプロセスにそって整理され画像処理をおこない保存を行っている。CD-ROMによる資料公開を目指し,画像処理については資料の原本とOCRソフトによる文字認識作業をおこなった部分との二層構造で作成し,PDFファイル化した。この手続きにより画像内における文書テキストの検索が可能になり,また利用の汎用性が高まった。