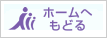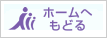厚生科学研究費補助金研究
(政策科学推進研究事業)
11 地理情報システム(GIS)を用いた地域人口動態の規定要因に関する研究(平成12~14年度)
(1)研究目的
本研究の目的は地理情報システム(Geographic Information Systems: GIS)を用いて,わが国における人口動態とその変動の規定要因を解明することにある。具体的にはミクロスケールの人口分布データと土地条件データ(国土数値情報など)の組み合わせにより,人口密度や人口増加率と,傾斜,高度,土地利用,交通網分布等の土地条件との関連性を明らかにする。これにより,人口分布やその変動を規定する要因について新たな知見が得られ(たとえば中山間地域において最も過疎が著しいのはどの高度帯に位置し,平均傾斜はどの程度で,他の集落との位置関係がいかなる場合であるか,など),これらは特にミクロスケールの将来人口予測を行う際の有益な情報として活用可能となる。
(2)研究計画
平成14年度においては分析対象範囲をさらに拡大し,首都圏と他の大都市圏,大都市圏と地方圏といった比較を行い,前年度までに得られた知見の一般性を検証する。その際,メッシュ統計の特性を生かし,たとえば地方圏内においては県内の都市部と郡部,郡部内での中心集落と周辺過疎地域といったスケールの異なる比較分析を行う。これにより少子化の進展,波及など人口動態変化のメカニズム,あるいは地形条件などの自然環境と人口動態との関連性について,これまで県単位,市町村単位でのデータしか扱えなかったために不明瞭だった点について,多くの知見が新たに得られるものと考えられる。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 大場 保(人口構造研究部第1室長),小池司朗(同部研究員)
- 所外委員
- 小口 高(東京大学空間情報科学研究センター助教授),江崎雄治(専修大学専任講師),
- 青木賢人(金沢大学助教授),伊藤史子(東京大学空間情報科学研究センター研究員),
- 堀 和明(日本学術振興会科学技術特別研究員)
12 個票データを利用した医療・介護サービスの需給に関する研究(平成13~15年度)
(1)研究目的
医療費の適正な支出を管理することは医療保険制度の健全な運営にとって必要欠くべからざる項目であり,現状の医療費支出の状況を的確に把握する必要がある。医療費の実態を把握する方法のひとつとして大量のレセプトデータ等を用いて包括的に患者の受診行動や医療費受給構造を把握する方法が考えられる。このタイプの研究では各医療機関の診療内容の詳細についての情報はほとんど得られない。しかし,個別の医療機関の行っている診療行為についての情報を得た上で,その医療機関の医療費が医療機関全体の中でどの程度の水準にあるかを知ることは重要な政策課題である。
本研究の目的は医療機関が選択する診療行為によって医療費がどの程度異なるか,その選択に市場環境や他の要因がどのように影響を与えているかを知ることによりどのような政策的選択肢が存在するかが明らかにすることである。また,その背景にある地域における医療・介護サービス提供者の資本装備・労働投入などの状況とサービスのアウトカム指標との関係や,それが医療費・介護給付費に与える影響も実証的に明らかにしようとするものであり,こうした受給両面からの医療費の増嵩要因分析はこれまで例のないものである。
以上のように果は,厚生労働行政の政策にこれまで以上の選択肢を提供するものであり,きわめて重要性・緊急性の高い研究である。
(2)研究計画
医療・介護にかかる需要・供給両サイドの個票データを用いた分析を行う。ほぼ毎月1回研究会を開催し,委員が個別の分析について報告する。主たる研究課題は下記のとおりである。
- 地域域医療供給体制の格差の制度的補完の分析
- 診療内容の差異が医療費の格差に与える効果の分析
- 診療内容の地域的変動と医療供給体制の間の関係の分析
- 医療・介護提供者の地域的偏在とその費用に与える効果の実証的分析
- 地域の社会経済的背景と医療費・介護費の間の関係についての分析
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長)
- 所内担当
- 植村尚史(副所長),金子能宏(社会保障応用分析研究部第1室長),小島克久(同部第3室長),
- 泉田信行(同部研究員),宮里尚三(同部研究員),山本克也(社会保障基礎理論研究部研究員),
- 佐藤雅代(総合企画部研究員)
- 所外委員
- 尾形裕也(九州大学大学院医学研究院教授),山田篤裕(慶應義塾大学専任講師),
- 江口隆裕(筑波大学教授),原田啓一郎(駒沢大学専任講師)
(4)研究結果の公表
厚生科学研究費補助金政策科学推進研究事業報告書として公表し,学会等での報告,学術雑誌への投稿を行う。
13 こどものいる世帯に対する所得保障,税制,保育サービス等の効果に関する総合的研究(平成13~14年度)
(1)研究目的
政府は平成11年度,12年度と2年連続して児童手当を拡充した。児童手当をはじめとする,こどものいる世帯に対する所得移転および保育サービスなどでは,社会保障分野において高齢者対策と並ぶ重要課題である。これは少子化問題をかかえる先進諸国の多くと共通する問題意識であり,NBER,Brookings Institute, UNICEF等各研究機関においてもこどもの社会保障をテーマとする研究プロジェクトが立ち上がっている。
しかし,我が国においては,こどものいる世帯の経済的状況,所得再分配など,こどもの厚生(Welfare)に関する基礎研究が乏しいのが現状である。また,「少子化対策」として掲げられた児童手当にしても,保育サービスとの比較など,その政策効果について十分に議論されていない。1994年「こどもの権利条約」批准した日本国は,こども全体の福祉の向上と人権の擁護を実現する義務がある。そのために効果的な政策を行う必要がある。具体的にこどものいる世帯に対する社会保障を政策立案する際に,これら基礎研究は重要な資料であり,その早急な実施が望まれる。
これらをふまえ,本研究では,「所得再分配調査」「国民生活基礎調査」などマイクロ・データを用いた実証研究及び,こどもに関する社会保障費のマクロ分析など,「こどもの社会保障」に関する基礎研究を行う。
(2)研究計画
上記平成13年度の実績を基に分析を進め,その結果を積極的に国内および国外に発信することを計画している。方法としては,海外の研究者の招聘および国際比較を目的とするワークショップの開催報告書の英訳と海外研究所への発送,国内の研究者に対する本研究の成果の発表・意見交換を目的とするワークショップなどである。
平成14年度は,政策科学研究推進事業で2名の外国人研究者を招聘する。以下の日程で研究者対象のワークショップを開催する。
- 11月18日(月)
- 「低出生時代の政策アプローチを考える―こどものいる世帯に関する実証研究を基盤として―」
- 11月20日(水)~21日(木)
- 「少子化と家族・労働政策に関する国際ワークショップ」
- 11月27日(水)
- 「低出生時代の政策アプローチを考える―こどものいる世帯に関する実証研究を基盤として―」
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長)
- 所内担当
- 勝又幸子(総合企画部第3室長),千年よしみ(国際関係部第1室長),阿部 彩(同部第2室長),
- 大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2室長),金子能宏(社会保障応用分析研究部第1室長),
- 上枝朱美(客員研究員),周 燕飛(客員研究員)
(4)研究結果の公表
ディスカッションペーパー(英文)の作成:本プロジェクト独自のディスカッションペーパーを作成し,広く人々の知るところとなるように配布する。
14 社会経済変化に対応する公的年金制度のあり方に関する実証研究(平成13~14年度)
(1)研究目的
社会保障有識者会議の報告書において「社会保障制度の暗黙の前提になっていた男性労働者中心の家計は崩れつつあり,新しいタイプの社会的リスクが登場している」と指摘されているように,家族形態の変化や就労形態の変化は,伝統的な世帯像を前提とした公的年金の負担と給付の両面についてさまざまな議論を生んでいる。さらに人生80年時代を迎え,高齢期の所得保障を就労と社会保障のミックスにおいてどう達成するかが問われている。これらの変化に公的年金制度としてどのように対応し,制度を維持・発展させていくかは重要な問題である。
この問題意識に沿って本研究では,上記のような社会経済環境の変化が公的年金制度にもたらしている影響の実情把握を行うとともに,その要因を分析し,今後の政策対応のための基盤となることを目的とする。実務担当者を交えた研究会を組織し,行政の実態に即した研究を行う。これにより本研究会の研究成果が様々な行政施策の有効な基礎資料となることを目指す。
(2)研究計画
本研究は2年計画で以下の4つのテーマを研究する。どのテーマについても,1年目は先行研究のサーベイを行うとともに,1年目後半より利用可能な個票データを用いた実証研究を開始する。
- 就労形態の変化に対応した社会保険制度設計のための実情把握と分析
- 女性のライフスタイルの変化に対応した社会保険制度のあり方に関する研究
- 公的年金が労働供給に及ぼす影響と所得保障のあり方に関する研究
- 未納・未加入と無年金との関係に関する研究
平成14年度の研究計画
- 「就労形態の変化に対応した社会保険制度設計のための実情把握と分析」
平成14年度は統計データを利用して就労形態の多様化と公的年金制度との関係についても実証分析を
行う。
- 「女性のライフスタイルの変化に対応した社会保険制度のあり方に関する研究」
平成14年度は「ライフスタイルと年金に関するアンケート調査」(平成13年度実施)から得られたデータを
もとに女性の年金に関する分析を深め,調査結果の報告会を開催する。
- 「公的年金が労働供給に及ぼす影響と所得保障のあり方に関する研究」
平成14年度は13年度の実証分析を踏まえ,諸外国の研究成果と比較・検討を行う。
- 「未納・未加入と無年金との関係に関する研究」
平成14年度はデータ整備と実証分析を行う予定である。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 所内担当
- 阿部 彩(国際関係部第2室長),白波瀬佐和子(社会保障応用分析研究部第2室長),
- 大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2室長),山本克也(同部研究員)
15 実質社会保障支出に関する研究-国際比較の視点から-(平成13~14年度)
(1)研究目的
OECDでは,「実質社会支出」(Net Social Expenditures)の研究を進めており,その重要性は平成12年に報告書をまとめた「社会保障構造の在り方について考える有識者会議」においても指摘された。社会保障費の国際比較では,給付のみならず税制や民間への権限の委譲等など,総合的な「移転」をみる必要がある。
本研究においては,現在各国際機関がとりまとめている諸外国の社会保障給付費の違いを検証する。そして「実質社会支出」の議論を日本の制度に照らし併せて検討し,そこから日本の社会保障制度の特徴を明らかにする。
1980年代より,先進諸国において社会保障費の増加が重い社会的負担として認識されるようになった。1992年OECD厚生大臣会議で,各国の社会保障費の実態を把握するための国際統計の必要性が指摘され,OECDは調査を経て1999年社会支出統計として刊行を開始した。一方,ILO(国際労働機関)では,1949年以来「社会保障給付費」として集計してき費用の見直しをおこない,1994年の数値より「機能別分類」を採用した新しい社会保障費統計を1999年より公表しはじめた。ILOとOECDの新基準の採用は,1996年に欧州連合統計局(EUROSTAT)が社会保護支出統計のマニュアルとして刊行した,費用の国際比較基準に強い影響を受けている。
国際機関の費用統計の改訂は,先進国とりわけ欧州における,制度や給付の「民営化」および租税支出などの新たな政策を,費用統計においてどのように評価していくかという問題意識のあらわれである。実質社会保障支出の研究では,諸外国の社会保障改革における政策の効果を費用統計の側面からとらえ,日本との比較を行う。
(2)研究計画
最終年度(平成14年度)は公開講座の成果をふまえて,日本における実質社会保障支出の試算を1999年度について再度行う。国際比較の視点にたち日本の社会保障費用の評価を多角的に行う。韓国における社会的私的給付費の調査を研究協力者に依頼し,先進5カ国の社会支出の政策分野別の比較については,平成13年度海外研究機関委託研究の成果をふまえて,再度現地調査をおこない成果をまとめる。なお,最終年度の報告では初年度の公開講座を含め,和文英文の2カ国語で報告をまとめる。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 須田康幸(総合企画部長,~8月)/中嶋 潤(総合企画部長,8月~)
- 所内担当
- 勝又幸子(総合企画部第3室長),宮里尚三(社会保障応用分析研究部研究員),
- 上枝朱美(客員研究員)
- 所外委員
- 清家 篤(慶應義塾大学教授),宮島 洋(東京大学教授),山田篤裕(慶應義塾大学専任講師),
- 金 明中(慶應義塾大学大学院博士課程)
16 公的扶助システムのあり方に関する実証的・理論的研究(平成13~14年度)
(1)研究目的
本研究は,公的扶助システムの機能と実態,社会保障システム全体における位置づけと役割に関して,理論的,実証的に分析することを目的とする。研究の第一の柱は,日本の生活保護受給者や低所得者の実態を実証的に分析し,今日的な意味における「貧困」の実態と公的扶助プログラムの効果を明らかにすることにある。第二の柱は,他の社会保障制度(年金・医療・失業保険・介護保険・福祉サービス)や公共政策(教育・雇用・住宅)との補完性・連関性を明らかにすることである。研究の第三の柱は,諸外国で着手されている公的扶助制度改革,ならびに,関連する経済学・哲学的議論を広く参照する一方で,我が国の実態に即した観点から,公的扶助システムのあり方について考察することである。
(2)研究計画
前年度の研究活動によって,公的扶助の研究にあたっては,次の2点が重要であることが確認された。第一に,公的扶助を孤立した制度として捉えるのではなく,他の社会保障制度や公共政策と相互連関性をもつシステムとして捉えること。第二に,公的扶助の受給を帰結として捉えるのではなく,プロセスにおいて捉えること。換言すれば,公的扶助受給者自身のライフ・ステージの中での公的扶助の意味(効能)に着目することである。
今後は,①日本の生活保護制度に焦点を当てながら,医療保険・介護保険と医療扶助,あるいは,公的年金保険と生活保護との間の補完性・整合性を理論的に解明すること,②公的扶助受給者の受給前後の生活・行動様式ならびに生活困窮者の生活・行動様式に関して実証的に研究すること,③諸外国の福祉国家システム像に関する理論研究と内外における現地調査をもとに公的扶助制度の役割と位置付けに関する見取り図を描くこと,④貧困概念の再定義を行い,<基本的福祉>を捉えるための新しい指標を仮説的に構築すること,⑤これらの理論研究をもとに,貧困や福祉に関する国民意識を捉えるための予備的調査を行うことが主要な柱として設定される。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長)
- 所内担当
- 後藤玲子(総合企画部第2室長),勝又幸子(総合企画部第3室長),阿部 彩(国際関係部第2室長)
- 所外委員
- 橘木俊詔(京都大学教授),八田達夫(東京大学教授),埋橋孝文(日本女子大学教授),
- 菊池馨実(早稲田大学教授)
17 福祉国家の規範とシステムに関する総合的研究(平成14~16年度)
(1)研究目的
本研究は,現代の主要な規範理論と厚生経済学の新パラダイムをもとに,各国の社会保障改革のプロセスで提出された代替的な政策案について,各々の規範的な特性及び機能的な特性を比較分析すること,さらにそのような分析をもとに,価値の多元性を特質とする現代社会の人々が理性的・公共的に受容しうるような福祉国家の規範とシステムを構想することを目的とする。価値の多元性を特質とする現代社会は,諸個人を政策の意思決定主体として扱う仕組みを民主主義システムとして用意している。だが,そのことは人々の私的利益に基づく選好をそのまま尊重することを意味するものではない。諸個人が主体的に,政策評価に相応しい公共的・不偏的な判断を形成することが民主主義の前提として要請される。そして,諸個人がそのような判断を形成するためには,私的な利益や個人的な価値判断を相対化し,多様な状況にある様々な人々に広く及ぼされる影響を広く考慮し,道理ある複数の価値判断の両立可能性を探るような機会(公共的討議の場)と確かな情報が必要不可欠である。本研究は,そのような機会と情報の提供をめざすものである。
(2)研究計画
社会哲学と規範経済学の各々の分野で発展的・独創的な研究を進めている内外の研究者とともに,「福祉国家の基礎となる規範(体系)とシステム(体系)を構想する」ことを目的として共同研究を進める。具体的には月1回の研究報告会を開催する。研究会の課題は次の3つに設定される。
第一は,政策評価という実践的な観点に基づいて,次のような理論的問題を共同討議すること。①現代の主要な規範理論の解読を通じて抽出された福祉国家の分析視座の有効性を確認し,より広い視野から再構成すること。②新しいシステム像を構想する目的で構成された厚生経済学の新パラダイムの有効性を確認し,理論の精緻化を図ること。
第二は,各国の社会保障改革で提出された複数の代替的な政策案の特性を次の4つの作業を通じて分析すること,すなわち,
- 各政策案の規範的な特性を明示化すること(哲学的分析によって)
- 各政策案の機能的な特性を明示化すること(規範経済学的分析によって)
- 政策を推進する上で制約条件となる現代社会の諸特徴を解明すること
- 各政策案が現代社会の制約条件のもとでもたらす効果・影響を予測すること
第三は,このような分析をもとに,価値の多元性を特質とする現代社会の人々が理性的・公共的に受容しうるような福祉国家の規範とシステムを構想すること。
平成14年度の具体的な研究計画は以下の通りである。【前半】先述した2つの先行するプロジェクトに継続的に参加した研究協力者(経済哲学,社会哲学,法哲学,社会学,憲法学,社会保障法,数理経済学)を母体として,月1回の研究報告会を開催し,課題1の①と②を行う。また,同時に,課題2の基礎資料となる各国の社会保障改革の動向を整理し,分析素材となる主要な政策案や背景的論議を抽出する。議論の結果は適宜,邦文と英文双方の論文にまとめる作業を進める。【後半】課題2の①と②に着手する。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 須田康幸(総合企画部長,~8月)/中嶋 潤(総合企画部長,8月~)
- 所内担当
- 後藤玲子(総合企画部第2室長)
- 所外委員
- 鈴村興太郎(一橋大学経済研究所),塩野谷祐一(一橋大学名誉教授),盛山和夫(東京大学教授),
- 今田高俊(東京工業大学教授),山脇直司(東京大学教授)
18 韓国,台湾,シンガポール等における少子化と少子化対策に関する研究(平成14~16年度)
(1)研究目的
本研究ではわが国との比較を交えながら,アジアNIESにおける少子化と少子化対策の動向と内外の格差について比較分析をするとともに,少子化対策の効果を分析し,わが国の政府・地方自治体における少子化対策の策定・実施・評価に資することを目的とする。そのため,利用可能なデータの分析と並行して,アジアNIESと日本国内(少子・多子の地域・階層)において収集したデータによって内外の地域間・階層間格差を分析し,少子化の要因と少子化対策の潜在的効果を明らかにするとともに,わが国にとっての対策の選択肢を提示しようとするものである。
(2)研究計画
本研究は平成14年度から3年間にわたり実施する予定である。①初年度は国内における文献研究と専門家からのヒアリングを行うとともに,利用可能な内外のデータの予備的分析を行った上で,国内と一部の国・地域で実地調査を実施する。②第2年度は,文献研究とヒアリングを継続するとともに,利用可能な内外のデータの比較地域分析を行うのと並行して国内と一部の国・地域で実地調査を実施する。③第3年度は国内と一部の国・地域で実地調査を実施するとともに,比較分析に各種の政策変数を導入することにより政策志向的な分析を行い,政策効果を中心に分析結果をとりまとめる。
なお,本年11月には恩賜財団母子愛育会を通じた推進事業により下記の2名を招聘し講演会等を開催する予定である。
Kyung-Sup CHANG(Professor, Seoul National University, Korea)
Mui-Teng YAP(Senior Research Fellow, Institute of Policy Studies, Singapore)
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 小島 宏(国際関係部長)
- 所内担当
- 西岡八郎(人口構造研究部長),鈴木 透(国際関係部第3室長),
- 佐々井 司(人口動向研究部第3室長),清水昌人(人口構造研究部研究員)
- 外部委員
- 伊藤正一(関西学院大学教授)
19 家族構造や就労形態等の変化に対応した社会保障のあり方に関する総合的研究(平成14~16年度)
(1)研究目的
近年,家族構造や就労形態等の変化によって社会保障のもつ重要な機能の一つである所得分配が適正に機能していないおそれがあるとされている。このため今後の社会保障のあり方を考えるに当たっては,家族構造や就労形態等の変化と社会保障の所得分配機能との関係等を研究することが必要である。本研究の目的は,家族構造や就労形態の変化が社会保障を通じて所得分配に及ぼしている影響を把握し,社会経済的格差が生じる要因を分析することを通じて効果的な社会保障のあり方を展望することにある。具体的には,①家族構造・就労形態等の変化が所得分配に及ぼす影響,②ライフコース別にみた社会保障の所得分配に及ぼす影響,③人々の不平等感と①,②から把握される不平等度との関係について分析をする。
(2)研究計画
本研究は3年計画で3つの課題を研究する。どの課題についても研究会を組織し,1年目は先行研究のサーベイを行うとともに,分析に用いる統計調査データの整備および目的外使用申請作業を行い,後半から分析作業に着手する。2年目は実証分析を進める。3年目は分析結果の頑健性を検討するとともに,ワークショップ等を開催し,研究成果の普及に努める。
- 家族構造・就労形態等の変化が所得分配に及ぼす影響の研究
三世代同居率の低下や共働きの増加などの変化が社会保障制度を通じて世代内・世代間の所得分配にどのような影響を及ぼしているかを把握し,諸外国との比較を交えて格差を是正するための政策のあり方を明らかにする。
- ライフコース別にみた社会保障の所得分配に及ぼす影響
ライフコース別に生涯所得と生涯の社会保障給付・負担の実情をみることにより,一時点での再分配効果でなく,生涯にわたる所得の再分配効果を把握する。
- 所得分配と人々の不平等感との関係に関する社会学的分析
人々の不平等感が1,2で把握された不平等度とどのように結びついているかを社会学的観点から分析する。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 所内担当
- 白波瀬佐和子(社会保障応用分析研究部第2室長),阿部 彩(国際関係部第2室長),
- 大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2室長),宮里尚三(社会保障応用分析研究部研究員)
- 所外委員
- 寺崎康博(東京理科大学教授),田近栄治(一橋大学教授),小塩隆士(東京学芸大学助教授),
- 松浦克己(横浜市立大学教授),石田 浩(東京大学教授),苅谷剛彦(東京大学教授),
- 玄田有史(東京大学助教授),佐藤俊樹(東京大学助教授)
20 高齢者の生活保障システムに関する国際比較研究(平成14~16年度)
(1)研究目的
人口高齢化,経済の低成長等を背景に先進各国において社会保障の改革が進展している。それらの中には共通の政策もあれば各国独自の対応も見られる。これらを今後のわが国の社会保障改革の参考にするには,各国の既存制度や背景となる社会経済の状況を十分踏まえる必要がある。そのためには,当該国の研究機関との共同研究を実施することが最も有益な情報を得られる方法であると考えられる。特に日本の介護保険は画期的な制度であるにも拘わらず,政策的な影響を分析するためのデータ・ベースが必ずしも十分には整備されて来なかった。従って,本研究では,Brandeis大学で確立された介護研究のためのパネル・データの手法を導入して,国際比較可能な日本のデータ・ベースを開発して,共同研究を実施することを目的とする。また,介護保険は社会的弱者に対して必ずしも十分な手だてがなされておらず,保険者である市町村では保険料減免の動きも出ている状況下で所得水準に配慮した研究が重要である。このような観点から,本研究では,高齢者の所得として重要な役割を果たす年金制度の国際比較研究,並びに年金制度等の公的所得移転と家族の生活保障機能の代替・補完関係に関する実証分析を行うこともその目的とする。
(2)研究計画
本研究は3年計画で以下の3つのテーマを研究する。
- 高齢者の介護に対するサービス,費用負担と所得保障の関係に関するパネル・データの構築とこれを用いた実証分析
Brandeis大学のSchneider Institute for Health Policyと共同で,日米で比較可能な形式で,高齢者の所得とインフォーマルケア,介護サービスの利用と費用負担に関するパネル・データの構築を行う。
- 高齢者の所得保障としての年金に関する5カ国共同研究
日本の年金改革の議論にとって欠かすことのできない論点について,先進5か国(アメリカ,イギリス,ドイツ,フランス,スウェーデン)でどのような議論がなされ,どのようなエビデンスが提示されているかについて,共通の論点を取り上げて国際比較を行う。
- 高齢者の生活保障における所得移転と家族の生活保障機能に関する共同研究
年金制度等の公的な所得移転と私的トランスファーによる家族の生活保障機能との関係を実証分析する。わが国の年金制度の発展は発展途上国に示唆を与えるという観点から,この研究の一環として,中国社会科学院「居民収入調査プロジェクト」(所得再分配調査に相当する調査)と連携することにより,このマイクロ・データを用いた実証分析の可能性についても検討する。
平成14年度の研究計画
本研究は3年計画なので,一年目となる平成14年度においては,主としてパネル・データの開発,分析手法に関する文献調査,年金制度等の改革動向に関する調査等,基礎的な研究を行う。そして,複数の時点のデータが合わさって完成するパネル・データの解析及び中国社会科学院「居民収入調査プロジェクト」の解析は,2年目以降に実施する。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 所内担当
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部第3室長)
- 所外委員
- 池上直己(慶應義塾大学教授),清家 篤(慶應義塾大学教授),
- チャールズ・ユージ・ホリオカ(大阪大学教授)
21 介護に関する調査・実証研究-世帯・地域との関係を探る-(平成14~16年度)
(1)研究目的
介護サービスの量的・質的な充実は必要不可欠である。他方,介護サービスの供給体制の充足は利用者の行動を変化させ,長期的に日本の家族・世帯構造を変化させ,それがさらにまた供給構造の変化を促す可能性がある。
今後における介護保険制度のあり方,介護サービスのあり方等を検討するに当たっては,介護保険制度の導入が介護サービスの普及等を通じて世帯や地域にどのような影響を与えてきたか,また,個人の介護サービス利用行動がどのような要因によって決定されてきたか等について,介護保険制度の導入前後を比較して実証的に分析することが必要である。
そこで,本研究計画では以下の点について検討する。1家族介護の実態把握,2施設入(院)所・家族介護の選択に与える,世帯構造等の要因分析,3遠距離介護の実態把握,4介護サービス利用と就業選択の分析,5介護サービス事業者とボランティア組織の役割分担の実態把握,からなる。
これらは厚生労働行政に直結する内容である。このように,本研究は介護保険導入後の介護の実態把握をもとに,これからの介護保障のあり方を考えるための有効な基礎資料を作成し,厚生労働行政に対する貢献を通じて国民の福祉の向上に資するものとすることを目的とする。
(2)研究計画
平成14年度
- 既存研究・民間調査の整理による介護保険制度の利用状況,及び介護における介護サービス事業者と民間非営利組織の役割分担に関する整理
- 既存指定・承認統計等の再集計を実施するための申請作業の実施及びそれらの統計を用いた介護サービス利用状況の実証的検討及び理論的問題に関する分析の実施
- 次年度実施予定の高齢者の介護サービス利用状況の実態調査の実施準備作業
平成15年度
- 前年度に引き続いて,既存指定・承認統計等の再集計による介護サービス利用状況の実証的検討及び理論的問題に関する分析の実施
- 高齢者の介護サービス利用状況の実態調査の実施
平成16年度
- 前年度までの実証的研究,理論的分析の整理と実態調査の実施に基づいた報告書の作成
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 須田康幸(総合企画部長,~8月)/中嶋 潤(総合企画部長,8月~)
- 所内担当
- 白波瀬佐和子(社会保障応用分析研究部第2室長),泉田信行(同部研究員)
(4)研究成果の公表
厚生科学研究費補助金政策科学推進研究事業報告書として公表予定。
22 「世代とジェンダー」の視点から見た少子高齢社会に関する国際比較研究(平成14~16年度)
(1)研究目的
わが国では,最新の将来人口推計でも明らかなように少子化と高齢化が急激に進行し,社会保障制度全体の根幹を揺るがせているが,この問題は多かれ少なかれ先進諸国に共通する。先進諸国の少子化の進行は,広義の家族・家族観の変化と密接に関わり,少子化と長寿化がひき起こす高齢化はその家族・家族観の変化をひき起こすものと考えられる。本プロジェクトは,少子高齢化の進展と家族・家族観の変化の相互関係を「世代とジェンダー」という視点から国際比較分析をするために,国連ヨーロッパ経済委員会(UNECE)人口部が企画中の国際比較調査研究プロジェクト「世代とジェンダー・プロジェクト(GGP)」に参加する。そのうえで,主として,このプロジェクトにおける国際比較調査「世代とジェンダー調査(GGS)」の実施集計分析を通じて,結婚・同棲を含むパートナー関係(特にジェンダー関係の視点),子育て問題(ジェンダー関係と世代間関係の両方の視点),高齢者扶養問題(特に世代間関係の視点)の先進国間の共通性と日本的特徴を把握する。これによって先進国との比較という広い視野を踏まえたうえで,日本における未婚化・少子化の原因分析と政策提言,ならびに高齢者の自立と私的・公的扶養のあり方に関する政策提言に資することを目指す。
(2)研究計画
初年度(平成14年度)
- UNECE人口部ならびにGGPコンソーシアムが主催する企画連絡会議等に参加し,日本からの独自提案も含めたGGP共通フレームづくり,共通質問票づくりに努める。
- テーマ別研究班毎に,それぞれのテーマについての研究状況(日本を含む国際比較研究)のレビュー,ならびに日本の既存データを用いた予備的分析等を行う。
第2年度(平成15年度)
- 親委員会を中心として,国内におけるGGS「世代とジェンダー調査」のプリテスト,標本抽出,調査実施,調査データのデータベース化を行う。
- マクロ国際比較研究班は,共通フレームに基づく日本についてデータ収集を行い,GGPコンソーシアムと国際比較分析のための検討を行う。
- 他のテーマ別研究班は前年と同様の研究を継続する。
第3年度(平成16年度)
- テーマ別研究班毎に,日本のGGSデータを用いた分析を行い,報告書をとりまとめる(その一部はGGPの国別報告書ともなる)。さらに他のGGP参加国のGGSデータを含めた比較分析を行い,報告書をとりまとめる。
第4年度(平成17年度)以降
GGPコンソーシアムでは,GGS調査実施から3年後に,パネル調査(同一調査対象者に追跡調査)を行うことを企画している。したがって,本研究は平成14~16年度の第1フェーズに続いて,平成17~19年度の第2フェーズ(平成18年度にパネル調査実施)を実施することを企図している。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 白波瀬佐和子(社会保障応用研究部第2室長),福田亘孝(人口動向研究部第1室長),
- 赤地麻由子(人口構造研究部研究員),星 敦士(客員研究員)
- 所外委員
- 津谷典子(慶應義塾大学教授),田渕六郎(名古屋大学専任講師),岩間暁子(和光大学専任講師),
- 吉田千鶴(関東学院大学専任講師)
23 少子化の新局面と家族・労働政策の対応に関する研究(平成14~16年度)
(1)研究目的
本研究は,平成11年度から13年度に実施された厚生科学研究「少子化に関する家族・労働政策の影響と少子化の見通しに関する研究(主任研究者高橋重郷)」の研究成果を継承し,さらに平成14年1月に公表された「日本の将来人口推計」に鑑み,近年の少子化の動向要因を探るとともに,今後の結婚や出生動向を社会学や経済学などの学問的な見地から解析し,また少子化への対応について家族労働政策の視点から効果的な施策メニューを提言することを目的としている。
(2)研究計画
本研究では,人口学や社会学,労働経済学,計量経済学などのあらゆる分野の研究成果を活用し,将来の少子化傾向の見通しを立てるとともに,今後行われる人口推計の手法の改善に寄与するとともに,アンケート調査などの活用によって人々の価値観や家族意識の変化などに着目した研究を進め,平成14年の新全国推計で示された夫婦出生力低下の新たな局面に対応するための研究を実施し,少子化にかかわる厚生労働政策の推進に貢献することを目的として行う。具体的には以下の観点から研究を進める。
- 女子の労働供給をはじめとする労働市場の環境や結婚の動向をミクロ・データから検証し,その構造的要因や今後の動向を調査分析し,将来の人口動態に関する見通しの基礎資料を作成する。
- 国民の少子化や高齢化に関する意識を把握し,有効な少子化対策のメニューを構築するためのアンケート調査を行うとともに,地域における少子化対策の具体策を検討し,提言を行う。
- 人口学的な手法による将来人口推計モデルの改善を図るとともに,社会経済要因を考慮した総合的な計量モデルを作成し,経済成長や社会意識の変化,家族労働政策などの政策効果に伴う出生率の見通しなどを試算する。
- 少子化に関する内外の諸文献を整理し,家族労働政策と少子化対策に関する文献データを蓄積し,厚生労働政策に関する実務者の利用に供する。
- 人口推計に関する形式人口学による手法を改善・発展するための基礎研究を行い,シナリオに基づく将来人口推計を行いわが国の少子化の新局面へのさらなる対応を図る。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 高橋重郷(人口動向研究部長):研究の総括と出生の社会経済モデル分析
- 所外委員
- 大淵 寛(中央大学教授):結婚・出生に関するアンケート調査
- 樋口美雄(慶應義塾大学教授):女子労働力と出生力の分析
上記研究者のもと今後班編成を行い,各班単位に研究が進められる。
24 社会保障負担のあり方に関する研究(平成14~15年度)
(1)研究目的
少子高齢化が進展する中で,公平で安定的な社会保障制度を構築するため,中長期的な観点から,制度横断的な検討を行うことが求められている。制度横断的な検討を行うに当たって,給付面からのアプローチは困難であることから,負担面から検討を行う必要がある。社会保障負担については,現在,職種間,世代間,被扶養者の有無などで負担の不公平感があるとともに,保険料負担が増大していく中,所得のみの賦課には負担過重感が生じている。そこで,本研究では,公平で安定的な社会保障制度を構築するため,社会保障負担のあり方について制度横断的な検討を行うものである。特に,今後増大していく社会保障費用をどのように国民が公平に負担していくのが望ましいかという観点から,年金,医療,介護などあるべき社会保険の構造,所得・消費・資産のバランスのとれた総合的な負担能力に応じた負担賦課のあり方,各種人的控除を変更した場合の社会保障への影響,諸外国の社会保障における負担賦課の方法について,マクロ分析とミクロ分析を組合せて実施することを目的とする。
(2)研究計画
社会保障負担については,現在,職種間,世代間,被扶養者の有無などで負担の不公平感があるとともに,保険料負担が増大していく中,所得のみの賦課に負担過重感が生じている。そこで,本研究では,特に今後増大していく社会保障費用をどのように国民が公平に負担していくのが望ましいかという観点から,社会保障負担のあり方について次のような研究を行う。
- 公平な社会保障費用の負担という観点から,社会保険のプロトタイプから見たあるべき社会保険の構造について,被用者保険と地域保険の分立の解消を前提とし,年金,医療,介護,生活保護なども含めた2 つのモデルによりシミュレーションを行う。
- 経済財政諮問会議などにおける税制の議論を踏まえ,高齢者や子を持つ親などの負担能力を考慮して設けられている各種人的控除(配偶者控除,扶養控除など)や公的年金等控除を変更した場合の社会保障への影響,およびパート労働者に対して厚生年金適用を拡大した場合の影響について,マクロ・ミクロ両面から試算を行う。
- 諸外国の社会保障における負担賦課の方法について調査研究を行う。
なお,以上のほか,所得・消費・資産のバランスのとれた総合的な負担能力に応じた負担賦課のあり方について,世代重複モデル(OLGモデル)を用いた分析もあわせて行う。
平成14年度の研究計画
本研究は2年計画なので,平成14年度は,モデルの構築や粗い試算を行うとともに,諸外国の負担賦課の方法について幅広く調査を行うことする。2年度目は,モデルの検証を行った上で1.と2.の分析の総合化を図るとともに,諸外国の負担賦課の方法については,所得以外にも賦課している手法について詳細な調査を行うこととする。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長)
- 所内担当
- 勝又幸子(総合企画部第3室長),大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2室長),
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部第1室長),山本克也(社会保障基礎理論研究部研究員),
- 宮里尚三(社会保障応用分析研究部研究員)
- 所外委員
- 江口隆裕(筑波大学教授)
25 医療負担のあり方が医療需要と健康・福祉の水準に及ぼす影響に関する研究(平成14~15年度)
(1)研究目的
高齢社会対策大綱が示したように,負担能力に応じて医療負担を求めると同時に,低所得者に配慮する医療負担の望ましいあり方を検討するためには,所得格差の要因と医療需要に関連する所得格差の結果を,引退による所得低下や失業率の増加に伴う労働市場の変化に留意する必要がある。高齢者の引退過程に注目すると,再雇用,嘱託,パートタイム労働など,若年層と同様に就業形態の多様化が見られる。したがって,低所得になりやすい共通性を有している高齢者と若年者に対する医療負担が医療需要に及ぼす影響を実証分析することは,低所得者に配慮した医療負担のあり方を検討する上で,基礎的な知見として有益である。
同時に,健康・福祉水準は医療需要に対応する医療サービス供給により変化するので,所得格差に配慮した望ましい負担のあり方を検討するためには,こうした健康・福祉水準に及ぼす影響も分析対象に含めることが望ましい。この点については,カナダやアメリカで行われている所得水準などの経済的要因と健康・福祉水準との関係に関する新しい実証分析やOECDの医療パーフォーマンス計測プロジェクトから学ぶことが必要である。
従って,本研究では,引退や労働需給の変化によって低所得になる場合の多い高齢者と若年者に対して,医療負担と受診行動との関係についてアンケート調査とその解析を行い,上記の課題に応える新たな知見を明らかにすることにより,社会保障政策に多様な選択肢を提供することを目的とする。同時に,こうした選択肢が国民の健康・福祉の向上に寄与するように,所得格差に配慮した医療負担と医療サービスのあり方に関する実証分析を統計データを用いて行い,望ましい医療パーフォーマンスをもたらす選択肢の提示に努めることとする。
(2)研究計画
本研究は2年計画で以下の4つのテーマを研究する。どのテーマについても,1年目は先行研究のサーベイを行うとともに,1年目後半より利用可能な個票データ及びアンケート調査を用いた実証研究を開始する。
- 医療関連支出に関する分析
- 所得格差など医療負担の負担能力の格差と健康の不平等度に関する分析
- 医療施設利用状況からみた医療需要と健康・福祉水準の格差に関する分析
- 引退や労働需給の変化により所得低下に直面しやすい高齢者と若年者に対する医療負担と医療需要に関する調査
平成14年度の研究計画
- 「医療関連支出に関する分析」
所得に占める医療支出比率と自己負担の累進性・逆進性(カクワニ指数)について,所得階層別,世帯属性別に「所得再分配調査」または「国民生活基礎調査」を用いて分析を行う。
- 「所得格差など医療負担の負担能力の格差と健康の不平等度に関する分析」
「国民生活基礎調査」と「人口動態統計」等を地域ブロック別に再集計して比較する分析を行う。
- 「医療施設利用状況からみた医療需要と健康・福祉水準の格差に関する分析」
「医療施設静態調査」を経時的に再集計して,地域(都道府県,二次医療圏,市区町村)間の所得不平等と受診状況との関連から地域間健康不平等度について検証する
- 「引退や労働需給の変化により所得低下に直面しやすい高齢者と若年者に対する医療負担と医療需要に関する調査」
アンケート調査票の企画を行い,本調査のためのプレ調査を実施する。
(3)研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長)
- 所内担当
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部第1室長),小島克久(同部第3室長)
- 所外委員
- 大日康史(大阪大学社会経済研究所助教授),山田篤裕(慶應義塾大学専任講師)