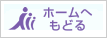17 社会保障の改革動向に関する国際共同研究(平成11 ~13 年度)
(1 )研究目的
人口高齢化,経済の低成長等を背景に先進各国において社会保障の改革が進展している。それらの中には共通の政策もあれば,各国独自の対応も見られる。これらを今後のわが国の改革の参考にする際には,それぞれの国の既存制度や背景となる社会経済の状況を十分踏まえる必要がある。そのためには,当該国の研究機関との共同研究を実施することが最も有益な情報を得られる方法であると考えられる。今般,ドイツのベルテルスマン財団より,国際的な社会保障改革の動向に関する情報ネットワークへの参加を要請され,国立社会保障・人口問題研究所が同ネットワークに参加することになった。これを契機に,本研究は同ネットワーク及び二国間の関係を通じ,各国の研究機関との情報,意見交換を行うとともに,特定の社会保障に関するテーマについての共同研究を実施することを目的とする。
(2 )研究実施状況
- 共同研究1 :「社会保障改革の動向に関する国際情報ネットワーク開発」(平成11 ~13 年度)
-
平成13 年度は,平成11 年度に立ち上げたネットワークから得られた15 カ国の改革を集積し,年金,医療,福祉の各分野における国際的な改革動向の比較分析を行った。
- 共同研究2 :「病院医療サービスの高度化とその経済効率性に関する実証分析」(平成11 ~13 年度)
-
NCVC とスタンフォード大学病院との間の比較可能なデータ・ベースを用いて,急性心筋梗塞に 対するステント適応の効果について,日本の臨床的変遷,アウトカム,在院日数などを視点に比較 研究を行った。
- 共同研究3 :「所得分配に関する国際比較研究」(平成11 ~13 年度)
-
「国民生活基礎調査」「所得再分配調査」を用いて,日本の所得分配,低所得者層の現状と動向 を国際比較を交えた分析を行った。平成13 年度は,LIS などを使った所得分配の国際比較研究 を拡充するとともに,社会保障・税制が所得分配に及ぼす影響の把握,世帯構造の変化が所得 分配に及ぼす影響(未婚成人や高齢者の同居など)の分析を行い,その成果をウェブ・ジャーナ ル“Journal of Population and Social Security”に掲載すべくまとめる作業を行った。
- 共同研究4 :「公的年金のfoundation に関する比較研究」(平成11 ~13 年度)
-
イギリス・アメリカ・ドイツの年金研究の専門家と研究交流を行い,日本の公的年金制度の客観的 な特徴づけを多角的に行った。
- 共同研究5 :「医療制度が医療の質に及ぼす影響の共同研究」(平成11 ~12 年度)実施済
- 共同研究6 :「家族の生活保障機能が社会保障の発展に及ぼす影響に関する研究」(平成12 ~13 年度)
-
マイクロ・データを用いて,今日の社会保障の機能と私的トランスファーによる家族の生活保障機 能との関係の実証分析を行うべく,準備作業を行った。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 所内担当
- 阿部 彩(国際関係部第2 室長),大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2 室長),
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部第1 室長)
- 所外委員
- 池上直己(慶應義塾大学教授)
(4 )研究成果の公表
平成13 年度研究報告書として公表した。また,共同研究3 についてはウェブ・ジャーナル“Journal of Population and Social Security” Vol. 1, No1 (2002 年8 月発行)の特集として掲載する。18 少子化に関する家族・労働政策の影響と少子化の見通しに関する研究 (平成11 ~13 年度)
(1 )研究目的
本研究プロジェクトは,近年に続く長期的な出生率低下を背景として,「少子化」の要因を実証的な研究から解明し,政策的な含意を引き出すことを第一の目的とし,さらに,「少子化」の今後の見通しに関して知見を見いだすことを第二の目的として実施するもので,平成11 年度から始まった標題研究の最終年次の研究プロジェクトである。本研究プロジェクトは,主任研究者:高橋重郷(人口動向研究部長)のほか,分担研究者:大淵 寛(中央大学教授),樋口美雄(慶應義塾大学教授),西岡八郎(人口構造研究部長),佐藤龍三郎(情報調査分析部長)のもとで実施した。
(2 )研究実施状況
- 結婚・出生行動の社会経済モデルに基づく出生率の見通しに関する研究
結婚・出生行動の社会経済モデル研究では,結婚や出生行動を経済社会要因から説明するためのモデル開発を行った。
結婚と出生行動に影響を及ぼす社会経済的変数の関係を「連立方程式体系」として表現し,経済社会モデルによる結婚・出生の将来予測を試みた。さらに,結婚・出生行動にかかわる様々な要因に関して,いくつかのシナリオ,1 )高成長ケースと2 )低成長ケースを加え,検討した。
社会経済モデルから予測された今後の合計特殊出生率の推移は,国立社会保障・人口問題研究所の平成14 年1 月推計の仮定値と比較し,おおむね将来動向については整合性がみられた。ただし,経済成長率の動きによっては,出生率の動きにいくつかの相違点も明らかとなった。すなわち,経済成長率が今後上昇した場合,晩婚化傾向が一層進み,出生率は相当低い水準となることが示唆され,女性就業と出生率のトレードオフの関係が,高い経済成長により強く表れることになる。一方,低成長下では,出生率の上昇がみられた。 - 女性の就業と結婚・出生力に関する研究
女子就業と結婚ならびに出生力の関係の研究については,1 )保育サービスの拡大を目指すのであれば,今後は幼稚園も保育士を雇用し,0 ~2 歳児の保育にあたることの有効性があること。2 )女性の就業・育児の両立に対し,高齢者の果たす役割が非常に大きいこと。3 )夫のサービス残業が妻の就業を抑制するという関係が見られた。4 )所得格差が拡大していくと,年収の低い世帯にとって,育児の負担はますます重くなる。年収の低い世帯に対しては,現在より手厚い児童手当を支給することが必要である。5 )育児資源の利用可能性が職種により異なることが明らかになった。6 )職種別に育児サポートの利用促進のサポートや育児サポートの効果測定の必要が明らかになった。
女性の出産と就業継続の両立支援策については,7 )出産と女性の継続就業に負の相関の関係があることが分かった。また,8 )勤め先で育児休業制度が規定された場合,出産確率を高めることができ,女性の継続就業をも促進していることが分かった。女性の就業行動と出生行動の間にあるトレードオフ問題を解決するためには,企業と社会における労働時間の短縮やファミリーフレンドリーな雇用管理政策の更なる充実が必要だと思われる。 - 少子化の見通しに関する専門家調査研究
過去に例をみない出生率低下のもと,今後の出生率の見通しが極めて困難な状況にある。そのような認識から,少子化問題に詳しい専門家を対象として,少子化の見通しや望ましい施策を探り,人口の将来予測や少子化に関わる施策の方向付けの参考資料とすることを目的として実施した。
専門分野の種別にみた,今後25 年間の変化(社会経済状況,性・生殖に関する状況,家族規範に関する状況,家族形成に関する状況)の見通しは,専門分野によって将来の結婚・出生予測が異なることが明らかにされた。
合計(特殊)出生率の見通しに関して,「専門家予測シナリオ」として将来人口推計を行い,社人研による平成14 年1 月推計と比較を行った。その結果,1 )社人研の推計結果とほぼ同じ数値を得た。専門家調査の予測のほうが若干低めの出生率のため,総人口も2050 年の時点で若干少なくなっている。また,2 )平均初婚年齢と生涯未婚率については,専門家の予測は平均初婚年齢について社人研仮定値よりも晩婚化するとの予測であった。3 )平均寿命については,社人研予測よりも伸びが低いと予測されているという結論を得た。 - 厚生労働政策と結婚・出生変動に関する文献情報の動向に関する研究
日本の少子化に関し政策的観点から,概ね1990 年以降の結婚・出生変動に関する文献情報を収集し,体系的に整理した。この間,法令の施行・改正,政府内における計画・方針等の策定,審議会答申,提言等の動きがあった。論文,著書,報告書等に関しては,1990 年~2002 年3 月の間に刊行されたものについて文献リストを作成し,過去1 年間の重要文献を抜粋し文献解題をおこなった。近年における少子化研究の特徴として,主題の多様化とともに,少子化対策との関連についての関心の高まりが挙げられる。政策評価に資する情報データベースの整備と既存研究の総合的レビュー手法の発展が今後の課題といえよう。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 高橋重郷(人口動向研究部長)
- 所内担当
- 西岡八郎(人口構造研究部長),佐藤龍三郎(情報調査分析部長),小島 宏(国際関係部長),
- 金子隆一(総合企画部第4 室長),白石紀子(情報調査分析部第3 室長),坂東里江子(同部研究員),
- 大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2 室長),加藤久和(同部第4 室長),
- 小山泰代(人口構造研究部第3 室長),赤地麻由子(同部研究員),岩澤美帆(人口動向研究部研究員),
- 守泉理恵(客員研究員)
- 金子隆一(総合企画部第4 室長),白石紀子(情報調査分析部第3 室長),坂東里江子(同部研究員),
- 所外委員
- 大淵 寛(中央大学経済学部教授),樋口美雄(慶應義塾大学商学部教授),
- 駿河輝和(大阪府立大学教授),兼清弘之(明治大学教授),安蔵伸治(明治大学教授),
- 吉田良正(朝日大学教授),和田光平(中央大学助教授),坂井博通(埼玉県立大学助教授),
- 北村行伸(一橋大学助教授),永瀬伸子(お茶の水女子大学助教授),阿部正浩(獨協大学助教授),
- 岸 智子(大妻女子大学助教授),仙田幸子(獨協大学専任講師),新谷由里子(武蔵野女子大学講師)
- 駿河輝和(大阪府立大学教授),兼清弘之(明治大学教授),安蔵伸治(明治大学教授),
(4 )研究成果の公表
平成11 年度,12 年度,ならびに13 年度の研究成果と平成11 ~13 年度総合研究報告は,厚生科学研究報告書として公表した。19 地域の医療供給と患者の受診行動に関する実証的研究(平成12 ~13 年度)
(1 )研究目的
本研究の目的は,縦覧可能なレセプトデータおよびその他の官庁統計(医療施設調査や地理的データ)を用いて国民健康保険の被保険者の包括的な受診状況を把握し,それが被保検者の属性,地域要因にどのように依存しているかを統計的に明らかにすることである。より具体的には①年間を通じた国保被保険者の医療受給パターンの解明,②医療機関ごとのレセプトの再集計により,医療機関別・被保険者の年齢別の医療費や入院期間などを推計する,③二次医療圏毎に再集計することにより,医療圏の地理的条件等を踏まえた被保険者の外来受診,入院パターンの把握等があげられる。上記の①ではこれまで行われてきたレセプト一件当たり医療費を分析する方法と1エピソードあたりの医療費を分析する方法を比較することにより,これまでのレセプト単位の分析が適切であるか否かを検討することができる。また,②では受診医療機関単位にレセプトを再集計することにより,個別医療機関の診療パターン(いわゆる病診選択の問題)をエピソード単位で分析できることになる。また③は二次医療圏の再編成,あるいは保険者が医療圏内のどの医療機関をモニターするのが政策的に効率的かといった指数の開発を目指している。特に③の指数は,国保保険者の再編成,あるいは保険者機能論といった政策的な含意も持ちうるものとする予定である。
(2 )研究実施状況
ほぼ毎月1 回研究会を開催し,次の研究課題に関し国民健康保険業務データを用いた分析について委員が報告した。- エピソードデータを用いた医師誘発需要の実証分析国民健康保険データを用いた患者の病院選択
- 診療機関属性でコントロールした重複受診確率の推定
- 医療供給体制の医療需要に与える影響の考察
- 地理的データを用いた医療圏と病院選択の統計的分析
- 越境受診の実態について
- 患者の受診行動の実態に関する包括的分析
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長)
- 所内担当
- 泉田信行(社会保障応用分析研究部研究員),山本克也(社会保障保障基礎理論研究部研究員),
- 佐藤雅代(客員研究員)
- 所外委員
- 鴇田忠彦(一橋大学経済学部教授),大日康史(大阪大学社会経済研究所助教授),
- 尾形裕也(九州大学大学院医学研究院教授),近藤康之(富山大学専任講師),
- 山田 武(千葉商科大学助教授),太鼓地武(国民健康保険中央会審議役),
- 石井 聡((財)医療経済研究機構研究員),山田聖子((財)医療科学研究所研究員),
- 岸田研作(京都大学大学院経済学研究科)
- 尾形裕也(九州大学大学院医学研究院教授),近藤康之(富山大学専任講師),
(4 )研究会の開催状況
月に一度程度研究会を開催した。(5 )研究成果の公表
厚生科学研究費補助金政策科学推進研究事業報告書として公表した他,『季刊社会保障研究』第38 巻第1 号において特集として論文を発表した。20 社会保障制度が育児コストを通じて出生行動と消費・貯蓄行動に及ぼす影響に関する研究(平成12 ~13 年度)
(1 )研究目的
本研究の主たる目的は,多様な社会保障政策のうち少子化に対応することのできる政策手段を明らかにし,その政策手段がどれだけ出生力の回復などの効果を発揮しうるかを数量的に把握するために,社会保障政策が育児コストを通じて出生行動と消費・貯蓄行動に及ぼす影響を実証分析することである。少子・高齢化が進行する一方,経済成長率が低い水準を推移し,将来の国民生活が豊かになれるかどうかについては不確実性が増しつつある。成長率の低下には,生産年齢人口の減少や国民経済における総消費の伸び悩みが影響しており,これらは少子化と関係している側面もある。ただし,少子化に対応する社会保障政策は出生行動を制度的に促す政策を意味しない。あくまで,出生行動は男女の自己選択に基づくものであり,強制的な政策介入は避けなければならない。したがって,出生行動に影響する育児コストという経済要因に効果を持ちうる社会保障政策を実証分析によって見出すことは,男女の自己選択を尊重しながら少子化に対する社会保障政策の実現につながることが期待される。この研究では,こうした面にも配慮して,海外の子育て支援策や育児と就業の両立支援の状況など,育児コストに拘わる諸政策の実態について国際比較を行うことを,研究のもう一つの目的とする。(2 )研究実施状況
「国民生活基礎調査」の使用申請の承認を経て,育児コストに関連する再集計を行い,調査報告書の付属統計表としてとりまとめた。また,女性の結婚,出産,育児に伴う離転職と子育て支援策との関係について「女性の就労と育児に関する調査」を実施した。研究会等による実証分析の結果,保育所政策の充実により育児コストが低下するために,女性の就業率が上昇する可能性が見られる反面,就業期間や就業形態が多様化しているため,勤続年数に基づく退職一時金額は,女性では平均50 万円程度であることがわかった。したがって,育児コストを低下させる子育て支援策と,女性の引退後の所得保障に影響する貯蓄手段を補完する女性の年金制度の充実や企業年金の普及を図る施策との連携が必要であるという結果が示唆された。また,国際比較の観点から,加日社会保障政策研究円卓会議・大阪会議(平成13 年6 月23 ~24 日)において,育児コストに関わる諸問題及び消費・貯蓄行動と引退後の所得保障に関わる問題に関する論文報告を行い,カナダ側の研究とこれらを合わせた研究成果を『海外社会保障研究』において公表した。(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長)
- 所内担当
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部第1 室長),小島克久(総合企画部主任研究官)
- 所外委員
- 永瀬伸子(お茶の水女子大学大学院助教授),有田冨美子(東洋英和女学院大学教授),
- 小川 浩(関東学園大学助教授),高山憲之(一橋大学経済研究所教授),
- 森田陽子(名古屋市立大学専任講師)
- 小川 浩(関東学園大学助教授),高山憲之(一橋大学経済研究所教授),
(4 )研究成果の公表
- 高山憲之・小川 浩・吉田 浩・有田富美子・金子能宏・小島克久「結婚・育児の経済コストと出生力―少子化の経済学的要因に関する一考察―」『人口問題研究』第56 巻第4 号
- Nobuko Nagase (永瀬伸子)“Balancing Work and Family in Japan: Inertia and a Need for Change”,「加日社会保障政策研究円卓会議・大阪会議(平成13 年6 月23 ~24 日)」報告論文
- 永瀬伸子「子育て支援の日加比較」『海外社会保障研究』No.139
- 金子能宏「子育て時期の女性の生活状況と年金に関する情報」『年金フォーラム』No.13
- 高山憲之「カナダの年金制度」『海外社会保障研究』No.139
- 金子能宏・小島克久「地域格差と所得格差を考慮した社会保障研究の展開」『海外社会保障研究』No.139
21 日本の所得格差の現状と評価に関する研究(平成12 ~13 年度)
(1 )研究目的
本研究の目的は,日本の所得格差について,ミクロデータを用いて1980 年代からの趨勢や現状を把握しながら,その評価・検討を行うことにある。具体的には,「所得再分配調査」や「国民生活基礎調査」を用いて実証分析を行うとともに,OECD 等の国際データを活用しながら,我が国の所得格差の推移と現状,社会保障による再分配効果の推移を明らかにする。さらに,欧米諸国との比較や所得格差を論ずる際の理論的視点についても言及する。大規模な全国データに基づいた厳密な実証研究を行うことで,日本の所得格差の現状について多角的な観点から分析するとともに,世帯や世帯を構成する世帯員の経済状態や就業雇用状況の動向についても分析する。(2 )研究実施状況
初年度(平成12 年度)においては,所得格差に関する国内外の既存研究の整理・検討や文献収集を行うとともに,「所得再分配調査」及び「国民生活基礎調査」のデータクリーニングとデータ分析を行なった。次年度(13年度)においては,「国民生活基礎調査」所得票や「所得再分配調査」を用いて各自の分担テーマについてさらなる分析を進め,報告書に取りまとめた。分析テーマの担当は次に示すとおりである。- 松浦克己・白波瀬佐和子:女性の就業と分配,社会保障政策の関係―出産・育児を中心として
- 玄田有史:保育,就業選択と所得格差―子育て世帯の所得構造に関する試論―
- 山田篤裕:OECD 加盟9 カ国における引退期所得の実態と改革の方向性
- 白波瀬佐和子:国際比較からみた日本の世帯構造別所得格差
- 小島克久:地域ブロック別所得格差
(3 )研究成果の公表
各分担テーマに沿って分析を行い,報告書として取りまとめた。今後,学術雑誌への掲載を試みることとしている。(4 )研究会の構成員
- 担当部長
- 椋野美智子(総合企画部長,~7 月),須田康幸(総合企画部長,7 月~)
- 所内担当
- 白波瀬佐和子(社会保障応用分析研究部第2 室長),小島克久(同部第3 室長)
- 山田篤裕(同部研究員)
- 所外委員
- 松浦克己(横浜市立大学教授),玄田有史(東京大学助教授)
22 地理情報システム(GIS )を用いた地域人口動態の規定要因に関する研究(平成12 ~14 年度)
(1 )研究目的
本研究の目的は地理情報システム(Geographic Information Systems: GIS )を用いて,わが国における人口動態とその変動の規定要因を解明することにある。具体的な研究課題としては以下の3 点を設定した。 ①緯度経度系による人口データをメートル単位によるものに変換するための手法の開発を行う。②上記によって変換された1km ×1km の修正メッシュデータを用いて,土地高度,傾斜などの自然的土地条件と人口分布との関連性について検討する。③都市圏程度の地域的範囲において,特に少子化,高齢化などの現象に注目しながら,人口動態の地域差とそれをもたらす諸要因について考察する。平成13 年度においては,研究初年度において得られた研究成果及び残された課題をふまえ,上述のテーマに関する分析作業を継続した。(2 )研究実施状況
本研究の平成13 年度における研究成果は以下のようにまとめられる。研究初年度において緯度経度系のメッシュデータを1km ×1km のものに補正する手法がおおむね確立されたが,内水面に近接する地域において,内水面の含まれるメッシュを人口希薄メッシュと見なしてしまうことにより,非現実的な補正結果が得られてしまうという問題点が残された。そこで平成13 年度においてはこの点に関し,より現実的な補正結果が得られるよう,手法の改良を行った。次にこの修正データを用い土地高度,傾斜と人口分布との関連性について検討した。研究初年度においては関東甲信地域を分析対象としていたが,これを全国に拡大し分析を行ったところ,標高が低く傾斜が小さいほど人口密度が高い傾向があるが,県によってはその傾向からの明瞭な乖離が見られ,特に巨大都市を持つ県やその県に隣接する県では他とは異なる傾向が存在する,最低標高・最低傾斜の階級では人口密度が下がる場合があり,水災害や地盤条件を反映する,過去25 年間では高標高・急傾斜の地域の人口は一定もしくは減少し,低標高・緩傾斜の地域では増加する傾向が一般的であるが,近年の人口増加の頭打ちにともない変化の傾向が変わりつつある,などの知見を得た。また人口動態と地理的諸条件との関連性については,研究初年度においては東京大都市圏,大阪大都市圏を対象として各メッシュの子ども・婦人比を求め各年次の分布状況を比較し,少子化の進行が都心地域から郊外に向かって波及していった様子が確認されたが,平成13 年度においては分析対象を47 都道府県の各県庁所在都市が形成する都市圏に拡大し,都市圏相互間に見られる波及プロセスの異同について分析を行った。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 大場 保(人口構造研究部第1 室長),江崎雄治(同部研究員)
- 所外委員
- 小口 高(東京大学助教授),青木賢人(日本学術振興会特別研究員),
- 堀 和明(東京大学空間情報科学研究センター研究員)
(4 )研究成果の公表
研究会の開催状況は,平成13 年度前半においてはおおむね隔月で,後半においては1 ヶ月に1 回研究会を開催した。研究成果は,「人口分析におけるGIS の可能性」東京大学空間情報科学センターDiscussion Paper Series, No. 48, 1-15 など個別論文の公表とともに,報告書を刊行予定である。23 個票データを利用した医療・介護サービスの需給に関する研究(平成13 ~15 年度)
(1 )研究目的
医療費の適正な支出を管理することは医療保険制度の健全な運営にとって必要欠くべからざる項目であり,現状の医療費支出の状況を的確に把握する必要がある。医療費の実態を把握する方法のひとつとして大量のレセプトデータ等を用いて包括的に患者の受診行動や医療費受給構造を把握する方法が考えられる。このタイプの研究では各医療機関の診療内容の詳細についての情報はほとんど得られない。しかし,個別の医療機関の行っている診療行為についての情報を得た上で,その医療機関の医療費が医療機関全体の中でどの程度の水準にあるかを知ることは重要な政策課題である。本研究の目的は医療機関が選択する診療行為によって医療費がどの程度異なるか,その選択に市場環境や他の要因がどのように影響を与えているかを知ることによりどのような政策的選択肢が存在するかが明らかにすることである。また,その背景にある地域における医療・介護サービス提供者の資本装備・労働投入などの状況とサービスのアウトカム指標との関係や,それが医療費・介護給付費に与える影響も実証的に明らかにしようとするものであり,こうした受給両面からの医療費の増嵩要因分析はこれまで例のないものである。
以上のように本研究の成果は,厚生労働行政の政策にこれまで以上の選択肢を提供するものであり,きわめ て重要性・緊急性の高い研究である。
(2 )研究実施状況
医療・介護にかかる需要・供給両サイドの個票データを用いた分析を行った。ほぼ毎月1 回研究会を開催し,委員が個別の分析について報告を行った。主たる研究課題は下記のとおりである。- 地域医療供給体制の格差の制度的補完の分析
- 診療内容の差異が医療費の格差に与える効果の分析
- 診療内容の地域的変動と医療供給体制の間の関係の分析
- 医療・介護提供者の地域的偏在とその費用に与える効果の実証的分析
- 地域の社会経済的背景と医療費・介護費の間の関係についての分析
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長)
- 所内担当
- 植村尚史(副所長),金子能宏(社会保障応用分析研究部第1 室長),小島克久(同部第3 室長),
- 山田篤裕(同部研究員),泉田信行(同部研究員),宮里尚三(総合企画部研究員),
- 山本克也(社会保障基礎理論研究部研究員),佐藤雅代(客員研究員)
- 山田篤裕(同部研究員),泉田信行(同部研究員),宮里尚三(総合企画部研究員),
- 所外委員
- 尾形裕也(九州大学大学院医学研究院教授)
(4 )研究会の開催状況
統計データを用いた分析については必要に応じて研究会を開催し,相互の進捗状況を確認した。12 月から2月にかけては外国人研究者3 名を招へいし,それぞれ5 日間連続で研究会を開催した。(5 )研究成果の公表
厚生科学研究費補助金政策科学推進研究事業報告書として公表。24 こどものいる世帯に対する所得保障,税制,保育サービス等の効果に関する総合的研究(平成13 ~14 年度)
(1 )研究目的
政府は平成11 年度,12 年度と2 年連続して児童手当を拡充した。児童手当をはじめとする,こどものいる世帯に対する所得移転および保育サービスなどでは,社会保障分野において高齢者対策と並ぶ重要課題である。これは少子化問題をかかえる先進諸国の多くと共通する問題意識であり,NBER ,Brookings Institution, UNICEF 等各研究機関においてもこどもの社会保障をテーマとする研究プロジェクトが立ち上がっている。しかし,我が国においては,こどものいる世帯の経済的状況,所得再分配など,こどもの厚生(Welfare )に関する基礎研究が乏しいのが現状である。また,「少子化対策」として掲げられた児童手当にしても,保育サービスとの比較など,その政策効果について十分に議論されていない。1994 年「こどもの権利条約」批准した日本国は,こども全体の福祉の向上と人権の擁護を実現する義務がある。そのために効果的な政策を行う必要がある。具体的にこどものいる世帯に対する社会保障を政策立案する際に,これら基礎研究は重要な資料であり,その早急な実施が望まれる。
これらをふまえ,本研究では,「所得再分配調査」「国民生活基礎調査」などマイクロ・データを用いた実証研究及び,こどもに関する社会保障費のマクロ分析など,「こどもの社会保障」に関する基礎研究を行う。
(2 )研究実施状況
平成13 年度は,まず,保育事業の需要の分析として,4 歳未満の児童を持つ母親からなるフォーカス・グループ・ディスカッション(FGD )を計5 回全研究者が協力して実施した。FGD から,保育園に求めるものが,世帯の所得・属性によって大きく左右されること(質vs.価格),保育園に預ける意志と動機などにも大きな違いがみられることなどが分かった。また,平成13 年度後期には,既存のデータを整理・入力し,世帯における保育費のWillingness to Pay の分析を行った。さらに,保育士市場の需要・供給分析を行った。最新保育政策についてもヒヤリングとサーベイを実施した。社会保障給付費の観点から,OECD Social Expenditure Database における「家族」機能給付の各国比較を試みこどもに関係する社会保障支出の各国の特徴を考察している。「国民生活基礎調査」,「所得再分配調査」等を用いて保育手段の選択と世帯属性(所得など)の関係の分析を行った。また,米国のCurrent Population Survey1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 年のデータを用い,ネイティブと移民両グループのこどものいる世帯における貧困率,公的扶助の受給程度を計算し比較を試みた。「国民生活基礎調査」「所得再分配調査」などのマイクロ・データを用いてこどものいる世帯の低所得率,不平等度などを計算し,国際比較を行った。また,アメリカにおける児童政策(TANF, EITC, Child Tax Credit など)を分析し,日本への応用度を検討した。(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長)
- 所内担当
- 勝又幸子(総合企画部第3 室長),千年よしみ(国際関係部第1 室長),阿部 彩(同部第2 室長),
- 大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2 室長),上枝朱美(客員研究員),周 燕飛(客員研究員)
(4 )研究成果の公表
平成13 年3 月末に当該年度の報告書を作成し公表した。分担研究者はそれぞれの報告内容について各所属学会で発表を行っている。25 社会経済変化に対応する公的年金制度のあり方に関する実証研究(平成13 ~14 年度)
(1 )研究目的
社会保障有識者会議の報告書において「社会保障制度の暗黙の前提になっていた男性労働者中心の家計は崩れつつあり,新しいタイプの社会的リスクが登場している」と指摘されているように,家族形態の変化や就労形態の変化は,伝統的な世帯像を前提とした公的年金の負担と給付の両面についてさまざまな議論を生んでいる。さらに人生80 年時代を迎え,高齢期の所得保障を就労と社会保障のミックスにおいてどう達成するかが問われている。これらの変化に公的年金制度としてどのように対応し,制度を維持・発展させていくかは重要な問題である。この問題意識に沿って本研究では,上記のような社会経済環境の変化が公的年金制度にもたらしている影響の実情把握を行うとともに,その要因を分析し,今後の政策対応のための基盤となることを目的とする。
(2 )研究実施状況
初年度である平成13 年度は,公的年金に関する先行研究サーベイを行い,既存研究をサーベイし,今後の研究課題を明らかにするために研究会を組織し,座談会形式で論評を行った。その成果は国立社会保障・人口問題研究所の機関誌『季刊社会保障研究』の特集号として14 年3 月末に刊行された。また以下に述べる4 つの研究課題について分析を進めた。- 「公的年金が労働供給に及ぼす影響と所得保障のあり方に関する研究」
高齢期の就業・引退行動について既存のマイクロデータから可能な限りパネル的データを復元し,支給開始 年齢の引き上げや給付切り下げが高齢者の引退率や年金財政に及ぼす影響をマイクロシミュレーションした。 - 「就労形態の変化に対応した社会保険制度設計のための実情把握と分析」
所得階層間の再分配効果が測定可能な年金数理モデルを作成し,これにマクロデータである人口デー タ,学歴別(所得階層の代理変数)就業率や賃金等を用いて所得の再分配効果を測定した。 - 「未納・未加入と無年金との関係に関する研究」
後述する『ライフスタイルと年金に関するアンケート調査』の結果を用いて,女性がライフサイクルを通じて どのように公的年金と関わっているかを特に公的年金未加入・加入に着目して初期的な分析を行った。 - 「女性のライフスタイルの変化に対応した社会保険制度のあり方に関する研究」
女性のライフスタイルの変化に対応した社会保険制度のあり方を探るため,『ライフスタイルと年金に関す るアンケート調査』を平成13 年12 月に実施した。同調査では個々人の過去の経歴や年金加入状況を調査し ており,就労形態や配偶関係によって女性の将来年金額にどのような違いが生じているかを把握できる。 詳細な分析は,平成14 年度に行う。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 所内担当
- 阿部 彩(国際関係部第2 室長),白波瀬佐和子(社会保障応用分析研究部第2 室長),
- 大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2 室長),山本克也(同部研究員)
(4 )研究成果の公表
本年度の研究成果のうち,既存研究サーベイは『季刊社会保障研究』(第37 巻第4 号)の特集として平成14 年3 月末に刊行され,関係各方面に配布した。「公的年金が労働供給に及ぼす影響と所得保障のあり方に関する研究」については,本年度の研究成果を平成14 年5 月末に予定されているNBER (全米経済研究所)の国際ワークショップで報告し,同様のアプローチで研究を進めている各国との国際比較および意見交換を行う予定である。「ライフスタイルと年金に関するアンケート調査」については,平成14 年度にさらに分析を深め,調査分析結果の報告会を行政関係者を交えて開催する。26 実質社会保障支出に関する研究-国際比較の視点から-(平成13 ~14 年度)
(1 )研究目的
OECD では,「実質社会支出」(Net Social Expenditures )の研究を進めており,その重要性は平成12 年に報告書をまとめた「社会保障構造の在り方について考える有識者会議」においても指摘された。社会保障費の国際比較では,給付のみならず税制や民間への権限の委譲等など,総合的な「移転」をみる必要がある。本研究においては,現在各国際機関がとりまとめている諸外国の社会保障給付費の違いを検証する。そして「実質社会支出」の議論を日本の制度に照らし併せて検討し,そこから日本の社会保障制度の特徴を明らかにする。
1980 年代より,先進諸国において社会保障費の増加が重い社会的負担として認識されるようになった。1992 年OECD 厚生大臣会議で,各国の社会保障費の実態を把握するための国際統計の必要性が指摘され,OECD は調査を経て1999 年社会支出統計として刊行を開始した。一方,ILO (国際労働機関)では,1949 年以来「社会保障給付費」として集計してきた費用の見直しをおこない,1994 年の数値より「機能別分類」を採用した新しい社会保障費統計を1999 年より公表しはじめた。ILO とOECD の新基準の採用は,1996 年に欧州連合統計局(EURO-STAT )が社会保護支出統計のマニュアルとして刊行した,費用の国際比較基準に強い影響を受けている。
国際機関の費用統計の改訂は,先進国とりわけ欧州における,制度や給付の「民営化」および租税支出などの新たな政策を,費用統計においてどのように評価していくかという問題意識のあらわれである。実質社会保障支出の研究では,諸外国の社会保障改革における政策の効果を費用統計の側面からとらえ,日本との比較を行う。
(2 )研究実施状況
初年度(平成13 年度)はOECD 「Net Social Expenditure 第2 編」の翻訳を行い純社会支出の概念の理解を深めた。マイクロシュミレーションモデルの活用について,スウェーデンとカナダについて分担研究者が調査した結果を報告書にまとめた。なお,周辺部分の社会支出については住宅について研究協力者のサーベイを報告書にまとめた。平成14 年3 月にはOECD の担当研究者を招聘し,主任研究者分担研究者を交えて公開講座を開催し,純社会支出の考え方と日本の社会支出の規模について検討した。(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 椋野美智子(総合企画部長,~7 月)/須田康幸(総合企画部長,7 月~)
- 所内担当
- 勝又幸子(総合企画部第3 室長),宮里尚三(同部研究員),
- 山田篤裕(社会保障応用分析研究部研究員),上枝朱美(客員研究員)
- 所外委員
- 清家 篤(慶應義塾大学教授),宮島 洋(東京大学教授),
- 船津 潤(横浜国立大学大学院博士課程)
(4 )研究成果の公表
平成13 年度の研究については中間報告としてとりまとめ,関係機関へ配付した。27 公的扶助システムのあり方に関する実証的・理論的研究(平成13 年~14 年度)
(1 )研究目的
近年,日本においては「自助」を強調した社会保険制度の見直しが本格的に進められている。その中で,社会保障システム全体における公的扶助システムの位置づけと役割,社会保険制度や公共政策との連携のあり方等に関して再検討する必要性はきわめて高い。本研究は,公的扶助システムの機能と被扶助者や低所得者の生活や行動実態,社会保障システム全体における位置づけと役割に関して,理論的,実証的に分析することを目的とする。(2 )研究実施状況
平成13 年度は,1 月までに計5 回研究会を開催し,岩田正美(社会学),小沢修司(社会福祉学),柴田謙治(社会学),前田雅子(社会福祉法),西村淳(厚生労働省),阿部彩(国際関係部)など多彩な研究者・実務者からのヒアリングを行った。これら研究会には,厚生労働省の行政官も出席し,研究と実務の両サイドからの活発な議論が行われた。またこれと併行して,研究課題の4 つのサブ・テーマに関する予備的な調査・研究が行われた。主要な研究成果は以下の通りである。①公的扶助と他の社会保障制度や公共政策との連関を捉える基本的な構図の作成。②ホームレス支援団体の視察とホームレスの人々の生活の実態に関する参与観察。③OECD の調査報告など公的扶助制度の国際比較に関する先行研究の検討。④アメリカやイギリスの公的扶助改革の動向とその効果・影響に関する文献サーベイ。⑤ 社会保障制度が貧困脱却の可能性に及ぼす影響に関する国際比較。⑥貧困の定義に関するタウンゼントの相対的剥奪理論とアマルティア・センの潜在能力理論の比較検討など。3月にこれらに関する研究報告会が開催された。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長)
- 所内担当
- 後藤玲子(総合企画部第2 室長),勝又幸子(同部第3 室長),阿部 彩(国際関係部第2 室長)
- 所外委員
- 橘木俊詔(京都大学教授),八田達夫(東京大学教授),埋橋孝文(日本女子大学教授),
- 菊池馨実(早稲田大学教授)
(4 )研究成果の公表
平成13 年度「総括研究報告書」を出した。収録されている研究報告は次の通りである。- 「福祉国家の分析視座:公的扶助システムの比較制度分析に向けて」(後藤玲子),
- 「福祉国家論序説」(橘木俊詔),
- 「公的扶助を取り巻く環境と政策的舵取り」(埋橋孝文),
- 「最低生活保障のあり方と公的扶助の役割:サービス保障と所得保障の両面から」(菊池馨実),
- 「アメリカ各州の福祉制度とその就労促進効果」(八田達夫・池田真介),
- 「GIS を用いたホームレス地域分布の分析」(鈴木 亘),
- 「アメリカのEITC の歴史と動向」(阿部 彩),
- 「“Universalism andTargeting: An International Comparison using the LIS database”」(阿部 彩)