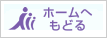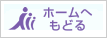一般会計プロジェクト
1 社会保障調査・研究事業
・平成11 年度社会保障給付費の推計
(1 )推計の方法
本研究所では,毎年我が国の社会保障給付費を推計公表している。社会保障給付費とは,ILO (国際労働機関)が定めた基準に基づき,社会保障や社会福祉等の社会保障制度を通じて,1 年間に国民に給付される金銭またはサービスの合計額である。社会保障給付費は,国全体の社会保障の規模をあらわす数値として,社会保障制度の評価や見直しの際の基本資料となるほか,社会保障の国際比較の基礎データとして活用されている。「平成11 年度社会保障給付費」は平成13 年12 月12 日に公表した。平成11 年度社会保障給付費の公表は前年と同様の内容で行われた。
(2 )推計結果の概要
1 平成11 年度社会保障給費の概要
- 平成11 年度の社会保障給付費の総額は75 兆417 億円であり,部門別では,「医療」が26 兆3,953 億円(35.2 %),「年金」が39 兆9,112 億円(53.2 %),「福祉その他」が8 兆7,352 億円(11.6 %)である。
- 平成11 年度社会保障給付費の対前年度伸び率は4.0 %であり,対国民所得比は19.60 %である。
- 国民1 人当たり社会保障給付費は59 万2,300 円であり,1 世帯当たりでは165 万3,300 円である。
- 年金保険給付費,老人保健(医療分)給付費,老人福祉サービス給付費および高年齢雇用継続給付費を合わせた高齢者関係給付費は,平成11 年度には50 兆3,559 億円となり,社会保障給付費に対する割合は67.1 %である。
平成11 年度より追加された「機能別社会保障給付費」とは,ILO が第19 次社会保障費用調査として新たに提案し1994 年の統計より採用した基準に基づいて集計された給付費である。
(注)費用の範囲と定義については公表資料参照。第18 次の定義については平成9 年度公表資料を参照。
- 9 つの機能別分類において,最も大きいのは「高齢給付」であり,33 兆6,447 億円,総額に占める割合は44.8 %である。
- 2 番目に大きいのは「保健医療給付」であり,26 兆787 億円,総額に占める割合は34.8 %である。これら上位2 機能分類「高齢給付」「保健医療給付」で,総額の79.6 %を占める。
- 上位2 機能以外では大きい順に,「遺族給付」5 兆7,326 億円で7.6 %,「失業給付」2 兆8,037 億円で3.7 %,「家族給付」2 兆360 億円で2.7 %,「障害給付」1 兆8,465 億円で2.5 %,「生活保護その他」1 兆6,741 億円で2.2 %,「労働災害給付」1 兆449 億円で1.4 %,「住宅給付」1,776 億円で0.2 %となっている。
- 対前年度伸び率では「住宅給付」の12.3 %がとくに大きくなっている。
2 平成11 年度社会保障費財源の概要
社会保障費の負担など「社会保障財源」の収入面の推計結果については2 つの分類方法で財源の計数を提供した。公表資料統計表:第10 表および第11 表である。前者は第18 次までの調査票に,後者は第19次の調査票に基づいて集計された。集計方法の違いは第19 次で事業主拠出を民間と公的に分け,被保険者拠出を被用者と自営業および年金受給者に分けたこと,収入項目としては「積立金からの受入」が財源項目として別掲されたことである。財源に項目としては「積立金からの受入」が追加されたが日本では数字をいれていない。積立金からの受入はIII .他の収入の「その他」に含まれている。
- 収入総額96 兆9,265 億円である。(注)収入総額とは,社会保障給付費の財源に加えて,管理費および給付以外の支出の財源も含む。
- 大項目では「社会保険料」が54 兆5,285 億円で,収入総額の56.3 %を占める。次に「税」が24 兆6,610 億円で,収入総額の25.4 %を占める。
- 社会保険料収入が対前年比較で4,452 億円減少したのは,本推計を始めて以来のことである。
- 「他の収入」は資産収入の伸び(59.18 %)によって飛び抜けて大きくなった。これは平成11 年度において,厚生年金基金等の基金運用益が,国内の株式相場の好転により大きくなったことによる。
(注)11 年度の時価ベース運用利回りが13.09 %を記録した。
以上の「平成11 年度社会保障給付費」については,本研究所のホームページ(https://www.ipss.go.jp/index.html )で公表資料と同じものが掲載され,PDF ファイルでも提供されている。「平成11 年度社会保障給付費」英語版“The Cost of Social Security in Japan FY1999”も英語ホームページ(https://www.ipss.go.jp/ss-cost/cost99/main.html )より同様に入手できる。また,『季刊社会保障研究』(第37 巻第4 号)において,「平成11 年度社会保障費―解説と分析―」を担当者(勝又幸子・宮里尚三)で執筆した。
また,月刊「厚生」2 月号誌上において,「平成11 年度社会保障給付費について」を担当者(須田康幸・勝又幸子・宮里尚三・小島克久)連名で執筆した。
3 OECD (経済協力開発機構)『社会支出統計(SOCX )』日本データの推計
平成11 年度社会保障給付費のデータを基に,1999 年度までのデータをOECD 基準に当てはめて再計算した結果を厚生労働省政策統括官付政策評価官室及び同国際課を通じてOECD に提出する。なお,OECD は2002 年1 月に1980 年度から1998 年度を範囲として,加盟諸国の社会支出をまとめCD-ROM (OECDSocial Expenditure Database 1980‐1998, 2001 3rd Edition OECD ISBN92-64-09850-x )として出版した。
(3 )担当者
- 担当部長
- 椋野美智子(総合企画部長,~7 月)/須田康幸(総合企画部長,7 月~)
- 所内担当
- 勝又幸子(総合企画部第3 室長),宮里尚三(同部研究員)
- 所外委員
- 石井 太(厚生労働省政策統括官付政策評価官室補佐),小倉寿子(同室調査総務係)
・社会保障給付費の国際比較研究
ILO 第19 次調査データはウェブ上だけで公開されている。2001 年度は全体のデータの更新が行われなかったため,動向「社会保障費用の国際比較」として『海外社会保障研究』(第138 号)に,ウェブ掲載されている各国のデータ表を翻訳して公表した。
2 新将来人口推計事業に関する調査研究(平成13 ~15 年度)
国立社会保障・人口問題研究所は,国が行う社会保障制度の中・長期計画ならびに各種施策立案の基礎資料として,①全国人口に関する将来人口推計,②都道府県別将来人口推計,ならびに③世帯に関する将来世帯数推計(全国・都道府県)を定期的に実施し,公表してきている。
・全国人口推計
全国人口推計は,平成12 (2000 )年国勢調査の基本集計結果ならびに同年人口動態統計の出生数・死亡数等の確定数の公表を受け,本年1 月「日本の将来推計人口(平成14 年1 月推計)」を公表した。
(1 )推計の方法
本推計は,基本的に前回推計の方法と同様①コーホート要因法による。②推計期間は2000 年10 月1 日国勢調査人口を基準人口として100 年間,2100 年までとし,2051 年以降は参考値とする。③出生率の仮定は高位,中位,低位の三種類とする。④出生性比は,過去の実績に基づいて推定した。また,出生率予測モデル,生存率予測モデル,国際人口移動などは「将来推計人口結果のモニタリングと推計システムの評価・改善に関する調査研究」で得られた研究結果をもとにモデルの開発を行い,本推計に用いた。
(2 )推計結果の概要
- 総人口の推移:総人口の減少
人口推計のスタート時点である平成12 (2000 )年の日本の総人口は同年の国勢調査によれば1 億2,693 万人であった。中位推計の結果に基づけば,この総人口は今後も緩やかに増加し,平成18 (2006 )年に1 億2,774 万人でピークに達した後,以後長期の人口減少過程に入る。平成25 (2013 )年にはほぼ現在の人口規模に戻り,平成62 (2050 )年にはおよそ1 億60 万人になるものと予測される。
高位推計によれば,総人口は,中位推計よりやや遅れて,平成21 (2009 )年に1 億2,815 万人でピークに達する。そして,それ以降は減少に転じ平成62 (2050 )年には1 億825 万人に達するものと見込まれる。一方,低位推計では平成16 (2004 )年に1 億2,748 万人でピークに達し,以後減少して平成62 (2050 )年には9,203 万人に達する。
このように日本の人口はまもなく人口減少時代に突入し,右肩上がりの人口増加の趨勢は終焉する。日本の出生率が1970 年代半ばから人口を一定の規模で保持する水準(人口置換水準,合計特殊出生率で2.08 前後の水準)を大きく割り込んでいるため,このような過去四半世紀続いた低出生率水準と今後の見通しは今世紀初頭から始まる人口減少をほぼ避けることの出来ない現象としている。
- 年少人口の推移:少子化社会の進展
出生数は昭和48 年(1973 )年の209 万人から平成12 (2000 )年の119 万人まで減少してきた。その結果,年少(0 ~14 歳)人口も1980 年代初めの2,700 万人規模から平成12 (2000 )年国勢調査の1,851 万人まで減少してきた。
中位推計の結果によると年少人口は,2003 年に1,700 万人台に減少する。その後も低い出生率のもとで減少が続き,平成28 (2016 )年には1,600 万人を割り込み,緩やかな長期減少過程に入る。そして推計の最終年次である2050 年には1,084 万人の規模となるものと予測される。
総人口に占める年少人口の割合は,総人口が同時に減少するため,絶対数ほどは大きく変化せず緩やかな減少となる。中位推計によると,平成12 (2000 )年の14.6 %から減少を続け,平成17 (2005 )年には14 %台を割り込み,平成33 (2021 )年に12.0 %に達する。その後も年少人口割合は減少を続け,平成48(2036 )年に11.0 %を経て,平成62 (2050 )年に10.8 %になるものと見込まれる。
- 生産年齢人口の推移:働き盛り人口の高齢化
生産年齢人口(15 ~64 歳とする)は戦後一貫して増加を続け,平成7 (1995 )年の国勢調査では8,717 万人に達したが,その後減少局面に入り,平成12 (2000 )年国勢調査によると8,638 万人を記録した。
中位推計の結果によれば,生産年齢人口は平成7 (1995 )年をピークに以後一転して減少過程に入り,平成42 (2030 )年には7,000 万人を割り込み,平成62 (2050 )年には5,389 万人に達する。今後も低出生率が持続するものと見込まれる現状のもとで,生産年齢人口の減少傾向は避けられない情勢になっている。そして,このような生産年齢人口の変化は,若い労働力の減少,労働力の高齢化,総労働力の減少をもたらす可能性が大きい。
- 老年人口の推移:超高齢化社会の到来
推計結果によれば年少人口の減少に続いて,今後生産年齢人口の減少が始まる一方で,老年(65 歳以上)人口はおよそ現在の2,200 万人から平成25 (2013 )年に3,000 万人を突破し,平成30 (2018 )年の3,417 万人へと急速な増加を続ける。すなわち,団塊の世代(昭和22 ~24 年出生世代)が65 歳以上の年齢層に入りきるまで急速な老年人口の増加を生じることになる。その後,戦後の出生規模の縮小世代が老年人口に参入するため,増加の勢いは弱まり,緩やかな増加期となるが,第二次ベビーブーム世代が老年人口となる平成55 (2043 )年に老年人口はピークに達し,その後緩やかな減少に転じ,平成62 (2050 )年に3,586 万人となる。なお,高位と低位推計では,将来の生残率や国際移動の仮定が同じであるため,中位推計と同じ結果である。
老年人口の割合は平成12 (2000 )年現在の17.4 %から平成26 (2014 )年には25 %台に達し,日本人口の4人に1 人が65 歳以上人口となる。その後,平成29 (2017 )年に27.0 %になる。老年人口は,平成30 (2018 )年以降平成46 (2034 )年頃まで,おおよそ3,400 万人台で推移するが,老年人口割合は低出生率の影響を受けて平成30 (2018 )年以降も上昇を続け,平成45 (2033 )年には30 %台に達する。そして,その後も持続的に上昇が続き,平成62 (2050 )年には,35.7 %の水準に達する。すなわち2.8 人に1 人が65 歳以上人口となるものと予測された。
(3 )担当者
- 担当部長
- 高橋重郷(人口動向研究部長)
- 所内担当
- 金子隆一(総合企画部第4 室長),石川 晃(情報調査分析部第2 室長),
- 加藤久和(社会保障基礎理論研究部第4 室長),三田房美(総合企画部主任研究官),
- 池ノ上正子(人口動向研究部主任研究官),岩澤美帆(同部研究員),小松隆一(同部研究員),
- 守泉理恵(客員研究員)
- 所外委員
- 辻 明子(早稲田大学大学院助手)
・都道府県別人口推計
平成12 年の国勢調査結果をふまえた「日本の将来推計人口(平成14 年1 月推計)」が公表された。この新全国人口推計に基づいて新たに都道府県別人口の将来推計を行い,平成14 年3 月に公表した。推計方法ならびに推計結果の概要は以下の通りである(詳しくは,ホームページhttps://www.ipss.go.jp 参照)。
(1 )推計の方法
推計の方法は前回同様,コーホート要因法を用いた。この方法は,ある年の男女・年齢別人口を基準として,ここに出生率や移動率などの仮定値をあてはめて将来人口を計算する方法である。具体的には,コーホート要因法による推計においては,①基準人口,②将来の出生率,③将来の生残率,④将来の純移動率,⑤将来の出生性比が必要となる。なお推計期間は平成12 (2000 )年~平成42 (2030 )年まで5 年ごとの30 年間とした。
(2 )推計結果の概要
1 総人口の推移
- 2000 年の国勢調査の結果によれば,1995 年から2000 年にかけて既に23 道県で人口が減少している。今回の推計によれば,人口が減少する都道府県は今後も増加を続け,2005 年から2010 年にかけては36 道府県,2015 年から2020 年にかけては滋賀県,沖縄県を除く45 都道府県で人口が減少するようになる。以後2030 年までほとんどの都道府県で人口の減少が続く。
- 2030 年の人口を,2000 年人口を100 とした場合の人口指数でみると,指数が100 を超える,すなわち2000 年より人口が増加する都道府県は東京都,神奈川県,滋賀県,沖縄県の4 都県のみであり,他の43 道府県ではいずれも2030 年の人口が2000 年人口を下回る。また指数が90 以下,すなわち人口が1割以上減少する都道府県は30 道府県に達する。
- 地域ブロック別にみると,2000 年時点で全国人口に占める割合が最も大きかったのは南関東ブロック(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県)で,26.3 %であった。全国人口に占める南関東ブロックのシェアは今後も緩やかに上昇を続け,2030 年には28.5 %に達する。一方でその他の地域ブロックの占める割合は横ばいないしは減少となる。
2 年齢別人口の推移
- 年少人口(0 ~14 歳)が各都道府県の総人口に占める割合をみると,2000 年から2030 年までの期間を通じて,すべての都道府県で低下する。2030 年時点で,年少人口の割合が最も大きいのは沖縄県(15.8 %),最も小さいのは東京都(9.8 %)である。
- 生産年齢人口(15 ~64 歳)が各都道府県の総人口に占める割合は,各都道府県とも当初は減少傾向にあるが,年少人口あるいは老年人口の減少に影響されるため,2020 年から2030 年にかけては,一部の都府県で生産年齢人口割合の上昇がみられる。2030 年時点で,生産年齢人口の割合が最も大きいのは東京都(64.1 %),最も小さいのは秋田県(53.3 %)である。
- 今回の都道府県推計によれば,老年人口(65 歳以上)は2020 年まで全都道府県で増加する。しかし老年人口の増加率はおおむね縮小傾向にあり,2020 年以降は老年人口の減少県が現れる。2020 年から2025 年にかけては19 府県で老年人口が減少し,2025 年から2030 年にかけては老年人口の減少県は32 道府県に増加する。2030 年の段階で老年人口数が多いのは,東京都,神奈川県,大阪府,埼玉県,愛知県など大都市圏に属する都府県である。また増加率でみると,2000 年から2030 年にかけて老年人口が100 %以上の増加(2 倍以上)になるのは埼玉県と千葉県であり,そのほか神奈川県,愛知県,滋賀県,沖縄県についても75 %以上の増加となる。
- 老年人口が総人口に占める割合は,各都道府県とも今後一貫して増加する。2000 年時点では老年人口割合が30 %を超える都道府県は1 つもないが,2015 年には4 県で30 %を超える。そして2030 年には35 道県で老年人口割合が30 %を超える。2030 年に最も老年人口割合が大きいのは秋田県(36.2 %)であり,最も小さいのは滋賀県(25.1 %)である。
(3 )担当者
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 大場 保(人口構造研究部第1 室長),江崎雄治(同部第2 室研究員),小林信彦(客員研究員)
・世帯推計
(1 )研究概要
本研究プロジェクトでは,全国および都道府県別世帯数の前回推計の評価作業を行い,新たに推計手法と仮定設定の見直し作業を行った。平成14 年以降,全国人口推計,都道府県別人口推計の結果を受けて本格的作業に入る。
(2 )担当者
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 鈴木 透(国際関係部第3 室長),小山泰代(人口構造研究部第3 室長),
- 赤地麻由子(同部研究員)
3 第5 回人口移動調査(実施)
(1 )調査目的
わが国では,2006 年前後の総人口のピークに向かって,人口増加が縮小しつつあり,人口移動が地域人口の変動を左右する傾向を強めている。こうした傾向を踏まえながら,近年の人口移動の要因を明らかにするとともに,将来の人口移動の傾向を見通すことを目的として,平成8 年度の第4 回調査に引き続き,平成13 年度に第5 回の人口移動の調査を行った。
この調査では,過去5 年間で人口移動の傾向がどのように変化したかを探るのは当然であるが,さらに以下の点を重点的な課題としている。
①東京圏への純流入がプラスになった要因を探るとともに,この傾向が今後も持続する可能性があるか否かを判断する資料を得る,②高齢者の移動および高齢者との同居等をめぐる家族の移動を明らかにする,③少子化と子供の進学・就職・結婚等による移動との関連性を明らかにする,④人口分布変動に影響を与える移動を取り出し,その要因を明らかにする,⑤近い将来にどの地域に居住するかという見通しを明らかにすることによって,地域人口の将来推計に必要な資料を得る。
(2 )担当者
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 千年よしみ(国際関係部第1 室長),江崎雄治(人口構造研究部研究員),
- 清水昌人(同部研究員),小林信彦(客員研究員)
(3 )調査対象
本調査は,全国の世帯主および世帯員を対象にしたサンプル調査である。平成13 年国民生活基礎調査で設定された調査地区内から無作為に抽出した300 調査区内全世帯の世帯主および世帯員を調査の客体とした。
(4 )調査期日
平成13 (2001 )年7 月1 日
(5 )調査事項
①世帯の属性②世帯主および世帯員の人口学的属性③世帯主および世帯員の居住歴に関する事項④世帯主および世帯員の将来(5 年後)の居住地域(見通し)に関する事項
(6 )調査方法
国立社会保障・人口問題研究所が厚生労働省大臣官房統計情報部,都道府県,保健所を設置する市・特別区および保健所の協力を得て実施した。調査票の配布・回収は調査員が行い,調査票への記入は世帯主の自計方式によった。
(7 )調査結果の公表
調査は7 月に実施され,その後は調査票の内容の点検を行っている。結果は,この作業が終わり次第,公表する。
4 社会保障生活調査-世帯内単身者に関する実態調査-(分析)
(1 )調査の方法
本調査は,少子化の主たる原因としての晩婚化と関連して,親と共に生活する成人した未婚者である世帯内単身者の実態を捉えることを主たる目的とする。本調査は世帯票と個人票から構成され,前者は世帯内単身者が属する世帯の経済的状況を把握し,後者は世帯内単身者自身の経済的社会的状況を把握する。
全国の世帯主を対象とし,平成12 年国民生活基礎調査で設定された調査地区内より無作為抽出した300 調査地区すべての世帯(約15,000 世帯)のうち,18 歳以上の未婚親族と同居する世帯およびその18 歳以上の未婚世帯員を調査の客体とする。本調査は,平成12 年6 月1 日に実施され,国立社会保障・人口問題研究所が厚生労働省大臣官房統計情報部,都道府県,保健所を設置する市・特別区および保健所の協力を得た。調査票の配布・回収は調査員が行い,調査票への記入は世帯主およびその世帯に同居する18 歳以上の未婚者の自計方式によった。
(2 )調査結果の概要
調査票配布数は世帯票で3,552 票,個人票で4,604 票であった。そのうち世帯票の回収率は3,203 票,個人票は4,334 票であり,白票や極めて記入状況の悪い票を削除した有効回答率は世帯票で88.8 %,個人票で92.5 %であった。分析においては,世帯票,個人票ともに有効であり,かつ学生の未婚者を除く世帯(2,667 ケース,以降該当世帯とする)と個人(3,422 ケース,以降該当個人とする)を対象とした。
分析の結果,該当世帯の持ち家率は8 割と一般に比べると高かったが,経済状況は本調査と同時に実施された「平成12 年国民生活基礎調査」の結果と比べて豊かな層のみに偏っているわけではなかった。それどころか,世帯人員数を除して世帯員一人あたり所得は,どの世帯主年齢層をとっても該当世帯の方が低い値であった。該当個人についてみてみると,そのほとんどは20 歳代,30 歳代前半に集中しており,晩婚化の傾向にあるいま,親との同居が今後どの程度継続するかどうかは,未定の段階にあるものが多い。学歴分布をみてみると約3 分の1 が短大・大卒以上であるが,平均からみて大きく高学歴層に偏っていなかった。該当個人の7 割以上はフルタイムの仕事に就いて,いくらかの貯蓄を有していた。さらに,該当個人全体の約7 割は家計にいくらかの繰り入れをしていた。親と同居することが該当個人にとって一方的な利益になるというよりも,成人した未婚子と同居することが家計に貢献している側面も認められた。
(3 )担当者
- 担当部長
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 所内担当
- 椋野美智子(総合企画部長,~7 月)/須田康幸(総合企画部長,7 月~),
- 松本勝明(社会保障応用分析研究部長),大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2 室長),
- 白波瀬佐和子(社会保障応用分析研究部第2 室長)
- 所外委員
- 清野仁子(第一生命経済研究所研究員)
5 第4 回世帯動態調査(分析)
(1 )調査の目的と方法
急速に進む人口の高齢化や,晩婚化・未婚化の進行,離婚率の上昇など,近年,個人や世帯をとりまく環境の変化が著しい。高齢の単身世帯,夫婦世帯の急増,ひとり親と子の世帯の増加,未婚のまま親と同居を続ける若・中年層の増加など,生活の基本単位である世帯は大きく変動している。世帯動態調査は,世帯がどのように形成,拡大,あるいは解体・縮小したかという世帯変動の実態と変化要因を明らかにすることを目的として5 年周期で実施されている。今回調査が4 回目となる。調査結果は,福祉をはじめとする厚生労働行政の基礎資料として,また,国民が将来どのような世帯で暮らすかを推計するための基礎データとして活用されている。
調査は厚生省大臣官房統計情報部,都道府県,保健所を設置する市・特別区および保健所の協力を得て,平成11 (1999 )年7 月1 日に実施された。平成11 年国民生活基礎調査で設定された調査地区内より無作為に抽出した300 調査区内のすべての世帯の世帯主を調査の客体とした。調査票配布世帯数14,359 に対して回収世帯数は 13,385 であり,回収率は93.2 %,有効回収率は86 %(前回は89 %)であった。
(2 )調査結果の概要
- 親族との居住関係:子との同居率は前回調査(1994 年)より減少したが,高齢者が娘と同居する割合は上昇している。一方,親との同居については,高齢者が老親と同居する割合が上昇している。また,夫の親との同居割合はやや減少傾向にある。
- 世帯の継続と発生:世帯員の転入のあった世帯よりも転出のあった世帯の方が多く,世帯員の転出入にも世帯の縮小傾向がみてとれる。転出入の理由では,死亡・出生といった人口学的要因が依然として優勢であるが,社会経済的要因によるものも少なくない。近年の世帯変動には,長引く不況などの社会情勢の影響も現れている。
- 世帯形成の現状と動向:男女とも若いコーホートの離家未経験率が上昇している。20 歳未満の離家理由の中心は就職から進学へ移行したが,進学離家の割合の伸びは頭打ちである。ライフコースから世帯形成をみると,30 代以降では,男女とも多数が離家,結婚,子の出生を経験するが,男子では30 代後半などを中心に,離家せずに結婚,子の出生を経験する世帯形成パターンもみられる。
- 世帯の解体と縮小:エンプティ・ネスト(空の巣)状態への移行は50 歳代後半から60 歳代前半で活発である。一度離家した子と同居する者の割合は年齢とともに増大する。要介護高齢者では,子と再同居している割合はより高い。子との再同居に親の健康状態の変化が影響していることが示唆される。
(3 )担当者
- 担当部長
- 西岡八郎(人口構造研究部長)
- 所内担当
- 鈴木 透(国際関係部第3 室長),小山泰代(人口構造研究部第3 室長),清水昌人(同部研究員)
- 所外委員
- 山本千鶴子(前人口構造研究部第3 室長)
(4 )調査結果の公表
2001 年10 月に「第4 回世帯動態調査結果の概要」として公表した。公表資料は本研究所ホームページ(https://www.ipss.go.jp )でも提供しているほか『人口問題研究』(第57 巻第3 号)にも掲載されている。なお,報告書についても刊行済みである。
6 第12 回出生動向基本調査(企画)
(1 )調査目的
国立社会保障・人口問題研究所は,昭和15 年に日本における最初の大規模な「出産力調査」を実施し,戦後は昭和27 年に第2 次調査を行い,その後平成9 年まで5 年ごとに11 回の調査を行ってきた。その結果,人口動態統計では把握できない戦後の夫婦出生児数の急激な減少と最近の低出生率に関する各種の実態を明らかにし各方面から高く評価されている。また,昭和55 年の国勢調査から結婚年数と出生児数の調査項目が削除されたため,この調査は,日本における夫婦出生児数の動向を把握し得る唯一の全国調査となった。
「出産力調査」のデータは,政府の経済計画・地域計画・福祉計画の策定に不可欠の将来人口推計(国立社会保障・人口問題研究所が定期的に実施・発表)の基礎資料として欠かせないものであった。また,近年の日本における出生率低下の趨勢は顕著であり,かりに,こうした急激な出生率低下が長期にわたり継続すると,人口高齢化の進展・若年労働力の減少といった生産・消費などの社会経済の基礎的構造に与える影響は計り知れないものがある。したがって,出生の動向をより正確に把握し,確固たる将来の指針をたてることは主として若い世代の結婚年齢の動向,再生産年齢期間の人口における未婚率の増加といった近年の結婚パターンの変化,および結婚した夫婦における出生意欲,出生抑制行動,夫婦出生児数がどのように変化するかに大きく依存すると判断している。第12 回出生動向基本調査は,結婚行動と出産行動の人口学的・生物医学的・社会経済的要因の解明を通じて,日本の将来人口の的確な予測,ならびに少子化対策の基礎資料として資するものである。
(2 )担当者
- 担当部長
- 高橋重郷(人口動向研究部長)
- 所内担当
- 金子隆一(総合企画部第4 室長),三田房美(同部主任研究官),
- 大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2 室長),福田亘孝(人口動向研究部第1 室長),
- 釜野さおり(同部第2 室長),佐々井 司(同部第3 室長),池ノ上正子(同部主任研究官),
- 岩澤美帆(同部研究員),守泉理恵(客員研究員)
(3 )調査の対象及び客体
この調査は全国のすべての国勢調査区から,無作為に抽出された調査区内に居住する妻の年齢50 歳未満の夫婦ならびに18 歳以上50 歳未満の独身男女を対象とする。標本抽出は,平成14 年度の国民生活基礎調査の標本を親標本とし,そのなかから無作為に600 調査区を選定し,その地区内の該当する夫婦(約10 ,000 組)と独身の男女(約13,000 人)を対象とする。
(4 )調査の方法
厚生労働省統計情報部が平成14 年度に実施する国民生活基礎調査に併行して,配票自計・密封回収方式により行う。
(5 )調査期日
平成14 年6 月1 日現在の事実を調査する。
(6 )調査事項
「夫婦票」
- 夫婦の結婚に関する事項
夫婦の出生年月,結婚年月,初再婚の別,結婚形態,結婚時の親との同居の有無
- 夫婦の社会経済的属性
夫婦の職業,夫婦の学歴,住居の規模,所有形態,夫婦の所得,妻の就業に関する意識,妻の結婚後の就業行動,夫婦の属する世帯の類型,保育・教育状況
- 夫婦の妊娠・出産歴に関する事項
出産児の男女別,出産年月,生死の別,現在の妊娠能力
- 夫婦の出産に対する意識に関する事項
追加予定子ども数,理想子ども数,理想の男女児組み合わせ,希望の出産間隔
- 出産調節に関する事項
避妊に関する意識,避妊・出生抑制の状況
「独身者票」
- 両親の社会経済的属性に関する事項
両親の職業,両親の学歴,両親の居住地
- 社会経済的属性に関する事項
年齢,学歴,職業,居住地
- 結婚に関する事項
結婚志向の有無,希望結婚年齢,希望結婚形態,結婚後の両親との同居志向,男女交際の有無,結婚相手の条件,両親の結婚に対する意識
- 子どもに関する事項
希望子ども数
- 出産調節に関する事項
避妊に関する知識,避妊知識の情報源
7 少子化・長寿化が21 世紀人口に及ぼす影響に関する研究(平成11 ~13 年度)
(1 )研究目的
日本の将来推計人口に基づけば,21 世紀半ばのわが国の人口高齢化水準はより一層高まるものと予測されている。このような人口趨勢にあって,結婚行動の変化(晩婚化・非婚化)や子ども数の減少によって引き起こされる少子化ならびに寿命の伸長(長寿化)は,わが国の人口高齢化を一層深刻なものにするが,少子化や長寿化は,それに止まらず,さらに21 世紀に暮らす人々のライフサイクルやライフコースを大きく変容させることになる。たとえば,生涯独身の人々の増加は,これまで施策の前提とされてきた標準的な世帯の減少を招き,多様なライフスタイルをもつ家族の出現につながる。したがって,施策展開においても少子化や長寿化のもたらす影響がどのようなものであるかを明らかにし,それに基づいた政策対応が求められる。
本研究においては,このような少子化と長寿化が21 世紀の人口に及ぼす影響について,数量的に明らかにし,高齢化社会の施策対象となる高齢者の様々な状態を人口学的に把握しようとするものであり,21 世紀の高齢化に関わる行政ニーズを把握するための極めて重要な研究課題である。
(2 )研究実施状況
本研究は,平成11 年度から3 年間にわたり実施してきている。平成13 年度は研究最終年次目にあたる。①21世紀人口のライフコースならびにライフサイクルをモデル,②21 世紀人口の家族関係の変化過程に関するモデル,ならびに,③高齢者の健康・疾病の状態と変化に関するモデル研究を進め,三つのそれぞれのテーマごとに,21 世紀の高齢者像を明らかにした。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 高橋重郷(人口動向研究部長)
- 所内担当
- 金子隆一(総合企画部第4 室長),石川 晃(情報調査分析部第2 室長),
- 三田房美(総合企画部主任研究官),池ノ上正子(人口動向研究部主任研究官),
- 岩澤美帆(同部研究員),小松隆一(同部研究員)
- 所外委員
- 渡邉吉利(国際医療福祉大学教授),永瀬伸子(お茶の水女子大学助教授),
- 和田光平(中央大学助教授),岩間暁子(和光大学講師),河野稠果(麗澤大学教授),
- 堀内四郎(ロックフェラー大学准教授),梯 正之(広島大学教授),斎藤安彦(日本大学助教授),
- 稲葉 寿(東京大学助教授)
(4 )研究成果の公表
本研究の成果の一部は,機関誌『人口問題研究』の特集号として掲載するとともに,全体の報告書をまとめ,刊行する予定である。
8 社会保障改革の理念と構造-福祉国家の比較制度分析(平成11 ~13 年度)
(1 )研究目的
本研究は,先進諸国の社会保障改革の動向・歴史的経緯に関する調査研究と経済学・哲学・社会学・政治学などの学際的な理論研究を関連させつつ,諸政策を評価するための規範的観点を明らかにすること,また,それらをもとに各国の社会保障改革を通底する基本的な理念と規範の構造を探究することを目的とする。
(2 )研究実施状況
自由至上主義,共同体主義,功利主義,リベラルな平等主義,正義理論,潜在能力理論,ジェンダー理論,進化経済学,社会的選択理論,ゲーム的認識理論などの専門家とともに,①公共性の構造・形成過程・正当性に関する研究を進めた。②現代の多元的な民主主義社会に相応しい社会保障システムと意思決定システムの理論を探究した。③社会保障政策の効果・影響を比較評価するための指標と人々の選好構造に関する理論的枠組みを再検討した。
具体的には,研究報告会における共同討議をペース・メーカーとしながら,各人の個人研究活動(学会報告・学術論文の執筆)において共通テーマを探究する作業を進めた。研究報告会は基本的にオープンとし,広く報告者を募るとともに,報告経験者たちの継続的な参加によって議論の深化を図った。3 年間のまとめとしては,①関連する領域の研究者との集中討議を目的とする3 日間のコンファレンス,及び,②行政関係者や他分野の研究者との交流を図るセミナーを開催した。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 椋野美智子(総合企画部長,~7 月)/須田康幸(総合企画部長,7 月~)
- 所内担当
- 後藤玲子(総合企画部第2 室長),阿部 彩(国際関係部第2 室長),上枝朱美(客員研究員)
- 所外委員
- 鈴村興太郎(一橋大学経済研究所教授),今田高俊(東京工業大学教授),
- 盛山和夫(東京大学教授),嶋津 格(千葉大学教授),山脇直司(東京大学大学院教授),
- 長谷川 晃(北海道大学教授),森村 進(一橋大学教授),藤村正之(武蔵大学教授),
- 小林正弥(千葉大学教授),渡辺幹雄(山口大学教授)
(4 )研究会の開催状況
- 2001 年2 月23 日
- 「社会保障の法理念」
報告者:菊池馨実(大阪大学教授)
- 「福祉国家変容が描きだす構図―資源配分論と社会関係論への展開」
報告者:藤村正之(武蔵大学教授)
- 2001 年3 月23 日
- 「生存権と社会的連帯について」
報告者:倉田 聡(北海道大学教授)
- 「経済の進化と論理」
報告者:山脇直司(東京大学大学院教授)
- 2001 年6 月1 日
- 「自由の平等」
報告者:立岩真也(信州大学医療技術短期大学部助教授)
- 2001 年7 月24 日
- 「社会保障の倫理学」
報告者:塩野谷祐一(国際医療福祉総合研究所副所長)
- 「Current State of Handbook of Social Choice and Welfare 」
報告者:鈴村興太郎(一橋大学経済研究所教授)
- 2001 年10 月11 日
- 「ポルノグラフィーについて」
報告者:紙谷雅子(学習院大学教授)
- 「公共善と重複的合意」
報告者:後藤玲子(総合企画部第2 室長)
- 2001 年12 月14 日
- 「認識論理とゲーム論」
報告者:金子 守(筑波大学教授)
- 2002 年2 月22 日
- 「憲法と自由の再検討」
報告者:樋口陽一(早稲田大学教授)
「福祉国家と規範理論」コンファレンス
- 日程:2002 年3 月8 日(金)15:00 ~20:00 ,3 月9 日(土)9:30 ~19:10 ,3 月10 日(日)9:30 ~16:00
- 場所:山口大学
- 塩野谷祐一「社会保障改革の経済と倫理」
- 宮本太郎「クリーヴィッジ変容と福祉政策」
- 橘木俊詔「安心の経済学」
- 渡辺幹雄「Property-Owing-Democracy と福祉国家」
- 嶋津 格「ハイエクと福祉国家」
- 森村 進「リバタリアンから見た福祉国家像」
- 鈴村興太郎「センの潜在能力理論と社会保障」
- 今田高俊「リスク社会と再帰的近代:ウルリッヒ・ベックの問題提起」
- 盛山和夫「福祉国家の規範とシステム」
- 後藤玲子「福祉国家の分析視座」
「社会保障と規範理論」公開セミナー
- 日時:2002 年3 月26 日(火)13:30 ~18:00
- 場所:国立社会保障・人口問題研究所第4 ・5 会議室
- 司会:鈴村興太郎
- はじめに:塩野谷祐一・鈴村興太郎
- 発題:後藤玲子「福祉国家の分析視座」
- 発展協議1 :堤 修三「行政と規範研究」の観点から
- セッション討論(新田秀樹,西村 淳):「社会保障政策の諸課題と規範理論の役割」
- 発展協議2 :三重野 卓「福祉と必要の分析手法」の観点から
- セッション討論(菊池馨実,宮本太郎):「比較福祉国家論の課題と方法」
- おわりに:植村尚史・鈴村興太郎
(5 )研究成果の公表
研究成果は,『海外社会保障研究』での特集を経て,単行本として刊行される予定である(塩野谷祐一・鈴村興太郎・後藤玲子編集『福祉の公共哲学』(仮題))。
9 転換期における福祉国家の国際比較研究(平成11 ~13 年度)
(1 )研究目的
1960 年代を中心とした福祉国家の「黄金期」から1980 年代に入って経済が停滞しはじめ,スタグフレーションや失業率の上昇が長期化して,福祉国家としてのあり方にも見直しが迫られている。本研究の主たる目的は,福祉国家の発展・停滞・再構築といった時系列的な変化について,国際マクロデータを用いて分析し,時系列パターンを考慮にいれた福祉国家の類型について検討することにある。わが国は福祉国家としてどの位置にあるかが,本研究のもととなる問題提起である。
(2 )研究実施状況
初年度は130 あまりの国を単位とした国際マクロデータを作成し,2 年度は先進西欧諸国に限定した時系列マクロデータを作成した。担当分野は次に示すとおりである。
- 富永健一:
- 福祉国家の国際比較研究―社会学的アプローチ
- ・総論および理論的枠組みの提示
- 三重野卓:
- 社会保障給付費の構造分析
- ・社会保障給付費の構造決定要因と変動パターンについて
- 武川正吾:
- 社会保障財源の国際比較分析
- ・ OECD19 カ国を中心とした時系列分析
- 平岡公一:
- 社会保障給付費の趨勢分析
- ・社会保障の支出面に焦点をあてた時系列分析
- 織田輝哉:
- 福祉国家発展の時系列データ分析
- ・ pooled-time-series 手法を用いた分析の試み
- 下平好博:
- グローバル化の中の福祉国家
- ・雇用政策からみた福祉国家の類型論についての検討
- 白波瀬佐和子:
- ジェンダーと福祉国家
- ・ジェンダーの視点からみた福祉国家論再考
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 松本勝明(社会保障応用分析研部長)
- 所内担当
- 白波瀬佐和子(社会保障応用分析研究部第2 室長),小林信彦(人口構造研究部客員研究員)
- 所外委員
- 富永健一(武蔵工業大学教授),織田輝哉(慶應義塾大学助教授),下平好博(明星大学助教授),
- 武川正吾(東京大学助教授),平岡公一(お茶の水大学教授),三重野 卓(山梨大学教授)
(4 )研究成果の公表
研究報告書を刊行したのち,学術雑誌への掲載に向けて検討会を実施する。
10 国際移動者の社会的統合に関する研究(平成11 ~13 年度)
(1 )研究目的
わが国では1980 年代半ば以降,外国人労働者,日系人,国際結婚配偶者の流入が急増し,その一部が日本社会に定着するにつれ,社会保障制度等を通じた国際移動者とその家族の社会的統合が政策的課題となりつつある。他方,企業等による海外赴任者とその家族を中心とする日本人の国外への移動も1980 年代半ば以降に急増し,より多くの日本人(家族)が現地の地域社会への統合や日本社会への再統合の問題に直面するようになった。しかし,わが国における国際人口移動に関する研究は移動そのものに焦点を合わせたものが多く,国際移動者の社会的統合とそれに関する政策に焦点を合わせたものは少数である。そこで,本研究では国際移動者,特に日本人移動者の社会的(再)統合とそれに関する政策について資料収集,ヒアリング,実地調査等に基づく理論的,実証的,政策的研究を行うものである。
(2 )研究実施状況
本研究では平成11 年度から3 年間にわたり,①主要な国際移動者受け入れ国における社会的統合の実態と対策に関する資料収集とそれに基づく比較分析,②主要な在留邦人受け入れ国における日本人(家族)の社会的統合の実態と対策に関する資料収集とそれに基づく比較分析,③国内における国際移動者とその家族の社会的統合・再統合の実態と対策に関する調査とそれに基づく比較分析,の三者を行った。研究方法としては1と2 については文献研究と専門家からのヒアリングを行い,3 については,所外委員の一部が外部機関の協力を得てアンケート調査を行うとともに,企業関係者等からのヒアリングを行った。
初年度は国内における文献研究と専門家からのヒアリングを行うとともに実地調査の予備調査(フォーカス・グループ討論)を行い,第2 年度は文献研究,ヒアリング,フォーカス・グループ討論を継続するとともに東京学芸大学付属附属高等学校のご協力による元帰国生に関するアンケート調査の実施を支援した。第3 年度は元帰国生調査結果の分析を行うとともに,(社)日本在外企業協会のご協力による海外派遣帰任者に関するアンケート調査の実施を支援し,分析を行って,両調査の分析結果をとりまとめた。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 小島 宏(国際関係部長)
- 所内担当
- 千年よしみ(国際関係部第1 室長),阿部 彩(同部第2 室長),
- 東 幸邦(社会保障基礎理論研究部第1 室長),釜野さおり(人口動向研究部第2 室長),
- 清水昌人(人口構造研究部研究員)
- 所外委員
- 白木三秀(早稲田大学教授),加賀美雅弘(東京学芸大学助教授),
- 近藤 敦(九州産業大学助教授),永井裕久(筑波大学大学院助教授),
- 平野(小原)裕子(九州大学医療技術短期大学部助教授),松本邦彦(山形大学助教授),
- 石井由香(立命館アジア太平洋大学助教授),正木智幸(東京学芸大学附属高等学校教諭)
(4 )研究会の開催状況
本年度は研究会における専門家からのヒアリング,文献研究,調査結果の分析を行った。研究会の実施状況は以下の通りである。
- 第1 回平成13 年7 月23 日
- 「帰国生のアイデンティティ」
報告者:南 保輔(成城大学文芸学部)
- 第2 回平成13 年12 月13 日
- 「『帰国生調査』の報告」
報告者:阿部 彩(国際関係部第2 室長),千年よしみ(国際関係部第1 室長)
- 第3 回平成14 年3 月7 日
- 「Metropolis International について」
報告者:Howard Duncan (Metropolis International ・カナダ政府市民権・移民局)
(5 )研究成果の公表
元帰国生に関する調査の資料・分析結果の一部は『「国際移動者の社会的統合に関する研究」―帰国生の長期的適応ストラテジーに関する研究―資料集』(所内研究報告第2 号)として取りまとめられ,最終報告書は『国際移動者の社会的統合に関する研究』(人口問題研究資料第305 号)として刊行された。
11 人口・経済・社会保障システムのダイナミック・モデルに関する基礎研究(平成11 ~13 年度)
(1 )研究目的
本事業の目的は,人口-経済社会システムと社会保障との動的な関係をモデル化し,システム分析を適用してその動態の理解を深めることによって,少子高齢社会へと一大転換を迎えつつある21 世紀わが国における社会保障あるいは行政諸施策の理念的基盤形成に資することにある。少子高齢化を含めおよそ人口変動は個人のライフコース変化により引き起こされるが,逆に人口変動は経済社会の変容を通して人々のライフコースを変える。社会保障の役割はこの循環のうち好ましくない流れの是正であって,人口-経済社会-ライフコースの自律的変動過程に対し,内側から政策的理念を実現するものとして組み込まれている必要がある。しかしながら,これまでの社会保障は人口,経済,社会の変化に対応して,いわば受動的な立場から働いてきた。成長型経済社会における循環の基調は,大勢を占める個人あるいは社会にとって好ましいものであるから,そこでの社会保障の役割はいわば落ち穂拾い型,問題対処型で十分機能してきたと考えられるが,近年経済社会基調が大きく転換し,循環の方向性そのものに構造的な阻害を孕むようになるに当たって,従来の社会保障のパラダイムは変革を迫られている。たとえば少産化ならびに少子化といった社会現象は,そもそも,教育の普及や経済社会の進展に呼応した諸個人の合理的・主体的な選択がもたらした当然の成り行きであると考えられる。だが,それは意図されざる帰結としての人口減少・高齢社会を招来し,その進行プロセスにおいて,労働力需給の不適合,社会保障の世代間アンバランスなどの問題を引き起こすことになった。そしていま,経済のマイナス成長,社会の活力低下といった負の循環基調が始まろうとしている。このような状況下ではもはや問題対処型の社会保障は有効とは言えない。負の循環それ自体を変革し,諸個人の福祉(quality of life )を真に向上しうるようなシステムへと社会保障制度を再構築する必要があるだろう。しかしながら,現代の民主主義社会は,諸個人の私的目的やライフコースが多様化しているのみならず,システムの望ましさを評価し設計する際の基準や価値判断もまたきわめて多様化している。
このような多元性を特徴とする社会において,諸個人の自律的・主体的な価値や目的を尊重しながら,人口-経済社会-ライフコースの自律的変動過程に介入するためには,はたしてどのような視座をもつべきだろうか。このような問題意識のもとに,本事業は,自律的変動過程と社会保障の役割に関するシステム的な理解を形成することを目的とし,これまで人口研究ならびに社会保障研究の各分野において展開されてきた主要なシステム・モデルを接合し,よりダイナミックなモデルを開発すること,これによって人口-経済社会,社会保障システムの変動過程を記述,予測,制御することを目指すものである。
(2 )研究実施状況
本研究プロジェクトは,平成11 ~13 年の3 年間に渡って,概ね以下の三段階に分けて研究が進められた。すなわち,①文献・資料に基づく人口研究分野,社会保障研究分野双方におけるシステム・モデル関連事項の調査および統合化への検討,とくに既存マクロ,ミクロデータの集積・加工・データベース化とこれを用いた実証的解析。②社人研において開発されている人口推計モデル,社会保障推計モデルを中心とした統合的モデルの開発,とくに近年発展を見ているオブジェクト指向型モデルの構築,③以上により開発されたモデルによる主としてマイクロシミュレーション分析によるシステム分析とシステム予測。④一定の政策的理念の実現を可能とする民主主義的意思決定システムを捉えるための理論枠組みの構築。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 椋野美智子(総合企画部長,~7 月)/須田康幸(総合企画部長,7 月~)
- 所内担当
- 金子隆一(総合企画部第4 室長),後藤玲子(同部第2 室長),
- 加藤久和(社会保障基礎理論研究部第4 室長),三田房美(総合企画部主任研究官)
- 所外委員
- 塩野谷祐一(一橋大学名誉教授)
(4 )研究会の開催状況
- 第1 回平成12 年6 月27 日
- 「意思決定を含むシステムモデル開発の試み―未婚者の結婚に関する意思決定モデル―」
報告者:金子隆一(総合企画部第4 室長),三田房美(同部主任研究官)
- 第2 回平成12 年9 月26 日
- 「リベラルな平等理論の尊重と多元的民主主義の構想―新しい規範理論の構築に向けて―」
報告者:後藤玲子(総合企画部第2 室長)
- 「個人の意志決定を中心にした人口・経済・社会保障のモデル」
報告者:金子隆一(総合企画部第4 室長),三田房美(同部主任研究官)
- 「Chaotic Simulation of the “Very Simple” Population Growth Model 」
報告者:加藤久和(社会保障基礎理論研究部第4 室長)
- 第3 回平成12 年12 月12 日
- 「個人的選好再考」
報告者:後藤玲子(総合企画部第2 室長)
- 「人口・経済・社会保障システムのモデル化―女子の再生産年齢期間の時間配分モデル―」
報告者:金子隆一(総合企画部第4 室長),三田房美(同部主任研究官)
- 第4 回平成13 年3 月8 日
- 「マクロ経済,財政および社会保障の長期展望―供給型計量経済モデルによる分析―」
報告者:加藤久和(社会保障基礎理論研究部第4 室長)
- 第5 回平成13 年5 月16 日
- 「Democracy and Economic System―Two concepts of Freedom to Participate―」
報告者:後藤玲子(総合企画部第2 室長)
- 「再生産期間の時間配分モデルによる出生と経済のダイナミクス分析の試み」
報告者:金子隆一(総合企画部第4 室長),三田房美(同部主任研究官)
- 「経済・社会保障と人口変動のリンク―経済学的視点からの考察―(1 )」
報告者:加藤久和(社会保障基礎理論研究部第4 室長)
- 第6 回平成13 年7 月16 日
- 「経済と理論―福祉国家の哲学―」
報告者:塩野谷祐一(一橋大学名誉教授)
- 「正義の二原理の公理化―規範理論の分析手法としての社会的選択アプローチ―」
報告者:後藤玲子(総合企画部第2 室長)
- 「人口・経済・社会保障に対するシステム論的アプローチの可能性」
報告者:金子隆一(総合企画部第4 室長),三田房美(同部主任研究官)
- 「経済・社会保障と人口変動のリンク―経済学的視点からの考察―(2 )」
報告者:加藤久和(社会保障基礎理論研究部第4 室長)
- 第7 回平成13 年9 月10 日
- 「人口社会システムへのワールドモデルの応用」
講師:原 俊彦(北海道東海大学国際文化学部教授)
(5 )研究成果の公表
研究成果は「人口,経済,社会保障システムのダイナミックモデルに関する基礎研究」報告書として取りまとめられた。
12 自殺による社会・経済へのマクロ的な影響調査(平成13 ~15 年度)
(1 )研究目的
自殺率が増加する中で,中高年男性の自殺率が特に高まっていることが指摘されている。中高年男性は,企業の担い手としてまた世帯主としてわが国の経済活動と人口の再生産にとって重要な貢献をしてきたにもかかわらず,その自殺率が増加していることは,これらの活動に少なからぬ損失を生じさせている可能性がある。これまで,経済活動や人口再生産の担い手である勤労者(とくに中高年の男女労働者)が自殺した場合の逸失利益を明確にして自殺の社会・経済への影響を明確にすることは,殆どなされてこなかった。
しかし,自殺防止対策を効果的に実施するためには,自殺防止対策の費用と便益の関係を明らかにする必要がある。また,このような分析を行うには,中高年労働者の自殺率の上昇が景気後退に伴う失業率の上昇に関係しているマクロ的な側面と,個々の労働者に対して職場における能力主義の浸透(賃金体系や人事考課の変化)が職場のストレス要因となっているというミクロ的な側面それぞれに留意する必要がある。したがって,本研究の目的は,このような問題意識のもとに,厚生・労働政策との関連に留意しながら,労働者の職場におけるストレスがその治療成果や自殺に及ぼす影響を世帯構造や個人属性に配慮しながら分析する調査研究を実施するとともに,自殺のマクロ経済的な損失,及び雇用政策による職場環境の向上と医療政策による治療成果の向上が自殺を減少させることによる社会・経済への影響を分析することである。
(2 )研究実施状況
自殺による死亡率は,経済環境の変化もあって近年増加しており,医療政策や精神保健政策に加えて,経済問題との関連にも関連した分析が求められている。リストラや配置転換などに伴う従業員のストレスにも配慮しながら自殺予防が可能になるためには,企業の理解を高める必要があり,そのためには,自殺の経済的損失や国民経済に及ぼす影響を測ることが重要な課題である。本研究は,このような問題意識のもとに,次のような研究を行う。
- 労働需給,就業状態,消費・貯蓄動向等の経済環境の変化と,職場環境の変化等によるストレス,景気循環に伴う世論の変化など社会心理的環境の変化とが自殺率に及ぼす影響に関する分析
- 家族のライフサイクルに注目した自殺の逸失利益の推計
- 自殺による労働力の変化が国民経済に及ぼす影響の推計
- 自殺対策と医療政策,精神保健政策の連携が医療費の変化を通じて,国民経済に及ぼす影響に関する分析
これらの研究の内,平成13 年度は,1 については,公的統計に基づく実証分析を行い,3 で用いるマクロ経済モデルにおける自殺関連変数の特定化を行った。2 については,一世代の家族を対象とする場合の推計を行った。3 については,現行のSNA 統計に基づくマクロ経済モデルを用いて,自殺による労働力の変化が国民経済に及ぼす影響を推計した。4 については,自殺防止対策と関連する医療費の変化を推計するためのデータ・ベースの設計・開発を行った。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 所内担当
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部第1 室長)
- 所外委員
- 池上直己(慶應義塾大学教授),池田俊也(慶應義塾大学専任講師),
- 反町吉秀(京都府立医科大学専任講師),宮崎俊一(国立循環器病センターCCU 部長),
- 野口晴子(東洋英和女学院大学専任講師),音山若穂(郡山女子大学専任講師),
- 橋本英樹(帝京大学専任講師)
- 研究協力者
- 山下志穂(学習院大学大学院博士課程)
(4 )研究成果の公表
研究成果は,平成13 年度厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「自殺防止対策研究者懇談会」に報告して,同部の「自殺防止対策有識者懇談会」の検討に資する基礎的資料としてとりまとめた。
今後の研究成果は,平成14 年度「自殺防止対策研究者懇談会」及び「自殺防止対策有識者懇談会」において報告するとともに,国立社会保障・人口問題研究所の機関誌『季刊社会保障研究』,『人口問題研究』,および社会保障・人口問題研究シリーズ等によって一般に公表する。
13 社会保障改革分析モデル事業(平成13 ~15 年度)
(1 )研究目的
少子高齢化の進展や経済環境の変化とともに,社会保障制度が有するセーフティ・ネットの役割やこれが経済活動に及ぼす効果に対する関心が高まっている。本事業は,社会保障制度の財政動向,所得再分配効果,社会保障改革が経済に及ぼす影響,あるいは世代間の公平性の試算など,今後,社会保障制度の運営とともに注目される諸課題を定量的に明らかにすることを目的としている。
以上の目的を遂行するため,マクロ計量経済モデルや世代重複モデルなどを開発するとともに,政策的な効
果が明らかになるようなシミュレーションを実施する。
(2 )研究実施状況
本事業は3 年計画に沿って運営されている。初年度には分析ツールの拡充を図り,2 年目に新人口推計に沿ったシミュレーションを行い,最終年度には社会保障改革を視野に入れたさまざまな効果分析を行うこととしている。
本年度は3 年計画の初年度ということもあり,基礎的なデータベースの作成やモデルの開発・メンテナンスを
行うとともに,作成したモデル等を用いたいくつかのシミュレーションを行った。
(3 )研究会の構成員
- 担当部長
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長)
- 所内担当
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部第1 室長),加藤久和(社会保障基礎理論研究部第4 室長),
- 山本克也(社会保障基礎理論研究部研究員),宮里尚三(総合企画部研究員)
- 所外委員
- 大林 守(専修大学教授),藤川清史(甲南大学教授),山田節夫(専修大学教授),
- 人見和美(電力中央研究所主任研究員)
- その他協力者
- 佐藤 格(慶應義塾大学大学院経済学研究科),(財)国民経済研究協会
(4 )研究会の開催状況
- 第1 回2001 年9 月12 日
- 「社会保障に関するOLG モデル・ワークショップ」
講師:岡本 章(岡山大学助教授),上村敏之(東洋大学専任講師)
- 第2 回2001 年11 月28 日
- 「社会保障改革分析モデルの設計の方向性について」
報告者:大林 守(専修大学教授),藤川清史(甲南大学教授),山田節夫(専修大学教授),人見和美(電力中央研究所主任研究員)
- 第3 回2002 年3 月29 日
- 「新SNA と社会保障改革分析モデル」
講師:小田克起(内閣府国民経済計算部長)
(5 )研究成果の公表
報告書を作成するとともに,学会等で報告を行った。