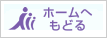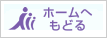1 社会保障情報・調査研究事業
・平成10 年度社会保障給付費の推計
(1 )推計の目的と方法
本研究所では,毎年我が国の社会保障給付費を推計公表している。社会保障給付費とは,ILO (国際労働機関)が定めた基準に基づき,社会保障や社会福祉等の社会保障制度を通じて,1 年間に国民に給付される金銭またはサービスの合計額である。社会保障給付費は,国全体の社会保障の規模をあらわす数値として,社会保障制度の評価や見直しの際の基本資料となるほか,社会保障の国際比較の基礎データとして活用されている。
「平成10 年度社会保障給付費」は平成12 年12 月25 日に公表した。平成10 年度社会保障給付費の公表はILO 第19 次調査という新しい枠組みを採用したという点で前年までと違った意味をもっている。
まず,国際比較の参考資料として,前年まで長いこと更新されなかった各国のデータは,限られた国ではあるが1996 年まで更新された。しかし,それらはすでに第19 次調査の定義で推計された結果であり,1993 年までの統計と連続性が確保されていない。そこで平成10 年度社会保障給付費の公表資料では「付録」としてあえて,第19 次調査として入手可能な国についてのみ情報を提供した。
一方従来どおり,社会保障給付費を「医療」「年金」「福祉その他」の3 部門に分類して,構成比,対国民所得比等の年次推移比較を行うほか,昭和60 年度以降,高齢者関係給付費の推計も継続している。
(2 )推計結果
平成10 年度社会保障給付費の概要は次のとおりである。
- 平成10 年度の社会保障給付費の総額は72 兆1,411 億円であり,部門別では,「医療」が25 兆4,077 億円(35.2 %),「年金」が38 兆4,105 億円(53.2 %),「福祉その他」が8 兆3,228 億円(11.5 %)である。
- 平成10 年度社会保障給付費の対前年度伸び率は3.9 %であり,対国民所得比は18.88 %である。
- 国民1 人当たり社会保障給付費は57 万300 円であり,1 世帯当たりでは160 万4,100 円である。
- 年金保険給付費,老人保健(医療分)給付費,老人福祉サービス給付費および高年齢雇用継続給付費を合わせた高齢者関係給付費は,平成10 年度には47 兆8,041 億円となり,社会保障給付費に対する割合は66.3 %である。
本年度(平成10 年度)より追加された「機能別社会保障給付費」とは,ILO が第19 次社会保障費用調査として新たに提案し1994 年の統計より採用した基準に基づいて集計された給付費である。(注)費用の範囲と定義については公表資料参照。第18 次の定義については平成9 年度公表資料を参照。
- 9 つの機能別分類において,最も大きいのは「高齢給付」であり,32 兆2,287 億円,総額に占める割合は44.7 %である。
- 2 番目に大きいのは「保健医療給付」であり,25 兆1,640 億円,総額に占める割合は34.9 %である。これら上位2 機能分類「高齢給付」「保健医療給付」で,総額の79.6 %を占める。
- 上位2 機能以外では大きい順に,「遺族給付」5 兆5,611 億円で7.7 %,「失業給付」2 兆6,742 億円で3.7 %,「家族給付」1 兆9,310 億円で2.7 %,「障害給付」1 兆8,025 億円で2.5 %,「生活保護その他」1 兆5,576 億円で2.2 %,「労働災害給付」1 兆639 億円で1.5 %,「住宅給付」1,581 億円で0.2 %となっている。
- 対前年度伸び率では「失業給付」の16.9 %がとくに大きくなっている。また,所得保障制度が中心である「高齢給付」が6.3 %と,伸び率が大きかったのに比較して,「保健医療給付」の伸び率は0.3 %と低かった。
(3 )平成10 年度の社会保障費財源の推計
社会保障費の負担など「社会保障財源」の収入面の推計結果については2 つの分類方法で財源の計数を提供した。公表資料統計表:第10 表および第11 表である。前者は第18 次までの調査票に,後者は第19 次の調査票に基づいて集計された。集計方法の違いは第19 次で事業主拠出を民間と公的に分け,被保険者拠出を被用者と自営業および年金受給者に分けたこと,収入項目としては「積立金からの受入」が財源項目として別掲されたことである。財源に項目としては「積立金からの受入」が追加されたが日本では数字を入れていない。積立金からの受入は「III 他の収入」の「その他」に含まれている。
- 収入総額89 兆2,188 億円である。(注)収入総額とは,社会保障給付費の財源に加えて,管理費および給付以外の支出の財源も含む。
- 大項目では「社会保険料」が54 兆9,737 億円で,収入総額の61.6 %を占める。次に「税」が21 兆9,882 億円で,収入総額の24.6 %を占める。
- 収入総額が対前年比較で8,489 億円減少したのは,本推計を始めて以来のことである。収入の減少は「資産収入」の減少(対前年比較で1 兆4,171 億円減少)が影響した。
- 1995 年度(平成6 年度)以降の項目別社会保障財源の動向は,収入総額の伸びが小さくなる傾向にある。平成9 年度から10 年度にかけては資産収入の減少に加え,社会保険料の伸びも0.3 %と例年になく低い伸びにとどまった。(事業主拠出0.22 %,被保険者拠出0.37 %,国庫負担0.33 %,他の公費負担3.83 %,資産収入△13.65 %,その他収入5.61 %)
以上の「平成10 年度社会保障給付費」については,本研究所のホームページ(https://www.ipss.go.jp/)で公表資料と同じものが掲載され,PDF ファイルでも提供されている。「平成10 年度社会保障給付費」英語版“The Cost of Social Security in Japan FY1998”も英語ホームページ(https://www.ipss.go.jp/English/cost98/main.htm )より同様に入手できる。また,『季刊社会保障研究』第36 巻第4 号において,「平成10 年度社会保障費―解説と分析―」を担当者(勝又・小島・宮里)で執筆した。
(4 )OECD (経済協力開発機構)『社会支出統計(SOCX )』日本データの推計
平成10 年度社会保障給付費のデータを基に,1998 年度までのデータをOECD 基準に当てはめて再計算した結果を厚生省大臣官房政策課および国際課を通じてOECD に提出した。なお,OECD は2001 年1 月に1980 年度から1997 年度を範囲として,加盟諸国の社会支出をまとめCD-ROM (OECD Social Expenditure Database 1980‐1997, 2000, 2nd Edition, OECD, ISBN92-64-08290-5 )として出版し、その中に提出した日本データが使われている。
(5 )担当者
- 所外委員
- 石井 太(厚生省大臣官房政策課課長補佐),丸山恵美(同課調査係)
- 所内担当者
- 増田雅暢(総合企画部長),勝又幸子(同部第3 室長),小島克久(同部主任研究官),
- 浅野仁子(社会保障応用分析研究部客員研究員),宮里尚三(同部研究員)
・社会保障給付費の国際比較研究
ILO 第19 次調査の各国データの公表が始まったことをうけて,浅野仁子が「社会保障費の国際比較―基礎統計の解説と分析―」(『海外社会保障研究』No.134 掲載)をまとめた。
2 将来推計人口結果のモニタリングと推計システムの評価・改善に関する調査研究
(平成10 ~12 年度)
(1 )研究目的
国立社会保障・人口問題研究所は,国が行う社会保障制度の中・長期計画ならびに各種施策立案の基礎資料として,①全国人口に関する将来人口推計,②都道府県別将来人口推計,ならびに③世帯に関する将来人口・世帯数推計を定期的に実施し,公表してきている。最新の全国将来推計人口は,平成7 年国勢調査結果に基づき,人口問題審議会への中間報告を経て平成9 年1 月に公表し,続いて平成9 年度上期に都道府県別将来人口推計,ならびに世帯に関する将来人口・世帯数推計をそれぞれ公表した。平成9 年1 月に公表した将来推計人口は,例えば平成11 (1999 )年に予定される年金財政再計算の前提となる基礎数値であり,この基礎数値の信頼性と精度が将来の財政計画の正確性を支えるものとなる。したがって,上記各種推計について継続的にモニタリングを行い,推計システムの評価・改善を行うことは極めて重要な意味をもっている。本研究では,各種将来推計のための基礎データの収集と手法の改善により,システムの改善を図ることを目的としている。
(2 )研究の概要
本研究は,上記の「全国人口に関する将来人口推計」,「都道府県別将来人口推計」,ならびに「世帯に関する将来人口・世帯数推計」の推計手法と結果について,推定結果のモニタリングを行うとともに,推計システムの評価見直しを行い,評価結果に基づいて推計システムの精度の改善を図ろうとするものである。なお,本年度は2000 年国勢調査が実施され,その結果に基づく新推計のためのモデル開発を行った。
平成12 年度に実施した研究は,以下のとおりである。
- 全国将来人口推計手法の調査研究
- 都道府県別将来人口推計手法の調査研究
- 将来人口・世帯数推計手法の調査研究
- 諸外国における人口予測手法に関する調査研究
(3 )研究会の構成員
- 全国推計班
- 高橋重郷(人口動向研究部長),金子隆一(総合企画部第4 室長),
- 三田房美(同部主任研究官),石川 晃(情報調査分析部第2 室長),
- 加藤久和(社会保障基礎理論研究部第4 室長),池ノ上正子(人口動向研究部主任研究官)
- 岩澤美帆(同部研究員),小松隆一(同部研究員)
- 都道府県推計・世帯推計班
- 西岡八郎(人口構造研究部長),鈴木透(国際関係部第3 室長),
- 大場 保(人口構造研究部第1 室長),小山泰代(同部第3 室長),江崎雄治(同部研究員)
(4 )研究成果の公表
各班の研究成果報告会および研究会を開催した。下記にその報告会および研究会をあげておく。
- 第1 回平成12 年12 月1 日
- 「Brass のOn the scale of mortality について」
- 小松隆一
- 第2 回平成12 年12 月8 日
- 「人間の寿命はどこまでのびるのか―スウェーデンにおける超高齢化人口の長期趨勢と要因分析の示唆するもの」
- 堀内四郎
- 第3 回平成12 年12 月15 日
- 「安蔵伸治『結婚に関する将来推計:性比尺度と一致性モデル』の要約」
- 辻 明子
- 第4 回平成13 年1 月12 日
- 「結婚行動と初婚率関数の推定について」
- 岩澤美帆
- 第5 回平成12 年1 月19 日
- 「Himes らのA relational model of Mortality at older ages in low mortality countries について」
- 小松隆一
- 第6 回平成12 年1 月26 日
- 「年齢別初婚率の推定」
- 石川 晃
- 第7 回平成12 年2 月2 日
- 「出生率への近成要因の影響:年齢依存の両性シミュレーションモデルの構築と適用」
- 荻原 潤
- 第8 回平成12 年2 月9 日
- 「人口推計のアルゴリズム―横浜市将来推計人口で用いた手法および結果から」
- 辻 明子
- 第9 回平成12 年2 月16 日
- 「ランダム・シナリオ法を用いたコーホート要因法による人口推計の結果概要」
- 南條善治・吉永一彦
- 第10 回平成12 年2 月23 日
- 「ボンガーツ=フィーニー・モデルの日本への対応」
- 別府志海
3 第1 回社会保障生活調査-世帯内単身者に関する実態調査-(調査の実施)
(1 )調査の目的
本調査は,少子化の最も重要な要因の一つと見られる,成人未婚者が親と共に生活する世帯内単身者の実態を把握することを目的とする。本調査は世帯票と個人票から構成され,前者は世帯内単身者を受け入れる世帯の経済的状況を把握するためで,後者は世帯内単身者自身の経済社会的状況を調査するためのものである。この調査の結果は,少子化対策ひいては社会保障政策を考察する上での貴重な基礎資料として役立てられる。
(2 )所内担当者
-
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長),増田雅暢(総合企画部長),尾形裕也(社会保障応用分析研究部長),
- 大石亜希子(社会保障基礎理論研究部第2 室長),増淵勝彦(社会保障応用分析研究部第1 室長),
- 白波瀬佐和子(社会保障応用分析研究部第2 室長),浅野仁子(社会保障応用分析研究部客員研究員)
(3 )調査の対象および客体
全国の世帯主を対象とし,平成12 年国民生活基礎調査で設定された調査地区内より無作為抽出した300 調査地区すべての世帯(約15,000 世帯)のうち,18 歳以上の未婚親族と同居する世帯およびその18 歳以上の未婚世帯員を調査の客体とする。
(4 )調査の方法
本調査は,国立社会保障・人口問題研究所が厚生省大臣官房統計情報部,都道府県,保健所を設置する市・特別区および保健所の協力を得て実施する。調査票の配布・回収は調査員が行い,調査票への記入は世帯主およびその世帯に同居する18 歳以上の未婚者の自計方式による。
(5 )調査期日
平成12 (2000 )年6 月1 日
(6 )調査事項
- 世帯票:世帯の収入,住宅状況
- 個人票:本人の経済社会的属性(学歴,仕事,収入)とライフスタイル
本人と世帯との関係(家計への繰り入れ,家事時間)
(7 )調査実施状況
調査配布数は,世帯レベルで3,552 票,個人レベルで4,604 票で,回収率はそれぞれ90.2 パーセント(3,203 票),94.1 パーセント(4,334 票)であった。有効回答率は,世帯票で88.8 パーセント(3,155 票),個人票で92.5 パーセント(4,258 票)であった。
12 年度は,世帯情報を取得するために国民生活基礎調査世帯票とのデータリンケージを行い,データクリーニングを行ってデータ分析のための整備を行った。
4 第4 回世帯動態調査
(1 )調査の目的と方法
人口の高齢化が進行するとともに老人を含む世帯,とりわけ高齢の単身世帯,夫婦世帯が急速に増加するなど,国民の生活単位である世帯は急速に大きな変動をみせており,厚生行政を進める上で世帯の実態を正確に把握することは重要な課題となっている。世帯動態調査は,各世帯がどのように形成され,変化したかという世帯変動の実態と要因を明らかにすることを目的として5 年ごとに実施されており,今回が4 回目となる。調査結果は,福祉をはじめとする諸施策の基礎資料として,また,国民が将来どのような世帯で暮らすかを推計するための基礎データとして活用されている。
本調査は平成11 (1999 )年7 月1 日に実施された。調査対象は全国の世帯主及び世帯員であり,国立社会保障・人口問題研究所が厚生省大臣官房統計情報部,都道府県,保健所を設置する市・特別区および保健所の協力を得て平成11 年国民生活基礎調査で設定された調査地区内より無作為に抽出した300 調査区内のすべての世帯(約15,000 世帯)の世帯主を調査の客体とした。調査票の配布・回収は調査員が行い,調査票への記入は世帯主の自計方式による。調査項目は①世帯の属性に関する事項,②ライフコースと世帯内地位の変化,③親の基本属性と居住関係,④子の基本属性と居住関係である。調査票配布対象世帯数16,267 に対して回収世帯数は13,385 であり,回収率は82 %,有効回収率は76 %であった。
本年度はデータクリーニングを完了し,集計表の作成・分析と結果のとりまとめを行った。また,各自が世帯の現状,親族ネットワーク,世帯の継続と発生,世帯の形成と拡大,世帯の縮小と解体等のテーマに沿ってより詳細な分析を行っている。
(2 )所内担当者
-
- 西岡八郎(人口構造研究部長),鈴木 透(国際関係部第3 室長),山本千鶴子(人口構造研究部第3 室長),
- 小山泰代(同部研究員),清水昌人(同部研究員)
5 第2 回全国家庭動向調査
(1 )調査の目的
全国家庭動向調査は,他の公式統計では捉えることのできない出産・子育て,老親扶養などの家庭機能の変化要因や動向を正確に把握することを目的として,平成5 年度に第1 回目の調査を行い,今回2 回目の調査を平成10 年度に実施した。調査結果については,すでに平成11 年度に調査結果を公表した(「第2 回全国家庭動向調査」の結果概要は,国立社会保障・人口問題研究所のホームページhttps://www.ipss.go.jp/から入手可能)。平成12 年度は報告書を作成し,その成果は関係学会や『人口問題研究』等で順次公表されている。また,『厚生白書』(平成12 年版,平成13 年版にも掲載予定),『男女共同参画白書』(平成12 年版)等にも広く活用されている。
(2 )担当者
- 所内担当者
- 西岡八郎(人口構造研究部長),白波瀬佐和子(社会保障応用分析部第2 室長),
- 山本千鶴子(人口構造研究部第3 室長),小山泰代(人口構造研究部研究員)
- 所外担当者
- 星 敦史(東京都立大学大学院)
6 第5 回人口移動調査(調査の企画)
(1 )調査の目的と方法
わが国では,2007 年前後の総人口のピークに向かって,人口増加が縮小しつつあり,人口移動が地域人口の変動を左右する傾向を強めている。こうした傾向を踏まえながら,近年の人口移動の要因を明らかにするとともに,将来の人口移動傾向を見通すことを目的として,平成8 年度の第4 回調査に引き続き,平成13 年度に第5 回の人口移動調査を行う。
この調査では,この5 年間で人口移動傾向がどのように変化したかを探ることは当然であるが,さらに以下の点に重きを置く。
第1 に,東京圏への純流入がプラスになった要因を探るとともに,この傾向が今後も持続する可能性があるか否かを判断する資料を得ること。
第2 に,高齢者の移動および高齢者との同居等をめぐる家族の移動を明らかにすること。
第3 に,少子化と子供の進学・就職・結婚等による移動との関連性を明らかにすること。
第4 に,人口分布変動に影響を与える移動を取り出し,その要因を明らかにすること。
第5 に,近い将来にどの地域に居住しているかという見通しを明らかにすることによって,地域人口の将来推計に必要な資料を得ること。
本調査の結果は,厚生労働行政をはじめとする各種行政の基礎資料として活用され,政策形成やその実現のために役立てられる。
(2 )所内担当者
-
- 西岡八郎(人口構造研究部長),千年よしみ(国際関係部第1 室長),江崎雄治(人口構造研究部研究員),
- 清水昌人(人口構造研究部研究員)
7 少子化・長寿化が21 世紀人口に及ぼす影響に関する研究(平成11 ~13 年度)
(1 )研究の目的
平成9 年に本研究所が公表した日本の将来推計人口に基づけば,21 世紀半ばのわが国の人口高齢化水準はより一層高まるものと予測されている。このような人口趨勢にあって,結婚行動の変化(晩婚化・非婚化)や子ども数の減少によって引き起こされる少子化,ならびに寿命の伸長(長寿化)は,わが国の人口高齢化を一層深刻なものにするが,少子化や長寿化は,それに止まらず,さらに21 世紀に暮らす人々のライフサイクルやライフコースを大きく変容させることになる。たとえば,生涯独身の人々の増加は,これまで施策の前提とされてきた標準的な世帯の減少を招き,多様なライフスタイルをもつ家族の出現につながる。したがって,施策展開においても少子化や長寿化のもたらす影響がどのようなものであるかを明らかにし,それに基づいた政策対応が求められる。
本研究においては,このような少子化と長寿化が21 世紀の人口に及ぼす影響について,数量的に明らかにし,高齢化社会の施策対象となる高齢者の様々な状態を人口学的に把握しようとするものであり,21 世紀の高齢化に関わる行政ニーズを把握するための極めて重要な研究課題である。
(2 )研究方法
本研究は,次の三つの柱を立て,研究を進める。すなわち,①21 世紀のライフコースならびにライフサイクルに関する調査研究,②21 世紀人口の家族関係の変化過程に関する調査研究,そして,③21 世紀人口の健康・疾病の状態と変化に関する研究である。なお,この研究で想定する21 世紀人口とは2025 年前後の人口を想定する。
(3 )研究の年次計画
本研究は,平成11 年度から3 年間にわたり実施してきている。平成12 年度は研究2 年次目にあたり、①21 世紀人口のライフコースならびにライフサイクルのモデル,②21 世紀人口の家族関係の変化過程に関するモデル,ならびに,③高齢者の健康・疾病の状態と変化に関するモデル研究を進め,三つのそれぞれのテーマごとに,21世紀の高齢者像を明らかにする。
(4 )研究会の構成員
- 所外委員
- 河野稠果(麗澤大学教授),渡邉吉利(国際医療福祉大学教授),梯 正之(広島大学教授),
- 岩上真珠(明星大学教授),永瀬伸子(お茶の水女子大学助教授),
- 堀内四郎(ロックフェラー大学准教授),斎藤安彦(日本大学助教授),
- 稲葉 寿(東京大学助教授),吉永一彦(福岡大学助教授)
- 所内担当者
- 高橋重郷(人口動向研究部長),金子隆一(総合企画部第4 室長),
- 三田房美(同部主任研究官),福田宣孝(人口動向研究部第1 室長),
- 釜野さおり(同部第2 室長),岩澤美帆(同部研究員),
- 新谷由里子(客員研究員),石川 晃(情報調査分析部第2 室長),
- 池ノ上正子(人口動向研究部主任研究官),小松隆一(同部研究員)
8 社会保障改革の理念と構造-福祉国家の比較制度分析(平成11 ~13 年度)
(1 )研究目的
本プロジェクトの目的は,先進諸国の社会保障改革の現実・歴史的事実の調査研究と経済学・哲学・社会学等の学際的かつ理論的な研究を関連させつつ,各国の社会保障改革の理念と構造―福祉国家の哲学的基礎を明らかにすることにある。主たる研究項目は以下のとおりである。
- 経済システムの変化と人々の選好構造の変化との間のフィードバック連関の解明:社会保障政策の及ぼす効果に関する実証研究の理論的枠組みを再検討する。
- 公共性の構造・形成過程・正当性に関する研究:互恵性,共同性,共生等に関する社会哲学理論をもとに現代民主主義社会に相応しい公共性の理論を探究する。
- 各国の社会保障改革の過程で表出した諸議論の背景にある道徳原理,道徳判断,ならびに基礎理論を明らかにすることによって,各国の社会保障改革の理念を解明する。
- 各国の主要な経済・哲学思想と社会保障制度の形成プロセスとの間の関連を学説史的に,また,社会経済史的に分析する。
(2 )研究会の構成員
- 所外委員
- 主査:塩野谷祐一(国際医療福祉総合研究所副所長),鈴村興太郎(一橋大学経済研究所教授),
- 山脇直司(東京大学大学院教授),嶋津 格(千葉大学教授),長谷川 晃(北海道大学教授),
- 森村 進(一橋大学教授),藤村正之(武蔵大学教授)
- 所内担当者
- 幹事:後藤玲子(総合企画部第2 室長),阿部 彩(国際関係部第2 室長),本田昭彦(客員研究員)
(3 )研究計画
3 年計画の2 は,内外の多分野の研究者とともに,自由主義,自由至上主義,共同体主義等福祉国家論に関連する規範理論を広く解読し,問題別に議論を深め,最終年度には研究書をまとめ刊行の運びとする。
(4 )開催状況
①定例研究会
- 第1 回平成12 年4 月20 日
- 「自由主義・共同体主義・共同性主義・新公共主義」
- 講師:小林正弥(千葉大学教授)
- 第2 回平成12 年6 月17 日
- 「階層システムの公共哲学に向けて」
- 講師:盛山和夫(東京大学教授)
- 第3 回平成12 年7 月21 日
- On Conceptions of Public Preference
- 報告者:後藤玲子
- 「現代の立憲主義と自由・平等:『外国人の人権』問題に寄せて」
- 講師:長谷部恭男(東京大学教授)
- 第4 回平成12 年10 月13 日
- 「世代継承と公共性」
- 講師:今田高俊(東京工業大学教授)
- 第5 回平成12 年11 月10 日
- 「自己形成と公共的人格:Well- being の概念をめぐって」
- 報告者:長谷川 晃(北海道大学教授)
- 第6 回平成12 年12 月8 日
- 「選好概念をめぐる雑感」
- 講師:若松良樹(成城大学教授)
- 第7 回平成12 年12 月25 日
- 「リバタリアニズムにおける国家と社会と市場」
- 報告者:森村 進(一橋大学教授)
- 「信任と契約」
- 教授:岩井克人(東京大学教授)
②Allan Gibbard 教授 連続特別講演会への参加
(Professor,University of Michigan,Department of Philosophy )
平成12 年5 月9 日国立社会保障・人口問題研究所第5 会議室
**The Concept of Rationality:**
9 転換期における福祉国家の国際比較研究(平成11 年度~13 年度)
(1 )研究目的
1960 年代を中心とした福祉国家の「黄金期」から1980 年代に入って経済が停滞し始め,スタグフレーションや失業率の上昇が長期化して,福祉国家としてのあり方にも見直しが迫られている。本研究の主たる目的は,福祉国家の発展・停滞・再構築といった時系列的な変化について,国際マクロデータを分析することで検討し,時系列パターンを基にした類型化を試みてわが国の位置づけを明らかにすることにある。
(2 )研究会の構成員
- 所外委員
- 富永健一(武蔵工業大学教授),織田輝哉(慶応義塾大学助教授),下平好博(明星大学助教授),
- 武川正吾(東京大学助教授),平岡公一(お茶の水女子大学教授),三重野 卓(山梨大学教授)
- 所内担当者
- 尾形裕也(社会保障応用分析部長),白波瀬佐和子(社会保障応用分析研究部第2 室長),
- 浅野仁子(社会保障応用分析研究部客員研究員)
(3 )研究計画
初年度は130 あまりの国を単位とした国際マクロデータの作成を行った。2 年度は,先進西欧諸国に限定したデータを作成し,分析に取りかかる。最終年度は,日本の位置付けについて福祉国家類型論の立場を中心に検討をし,報告書にまとめて,出版物として公表する。
(4 )開催状況
- 第1 回平成12 年4 月4 日
- 「国際比較マクロデータについて」
- 講師:佐藤博樹(東京大学社会科学研究所教授)
- 第2 回平成12 年5 月12 日
- 「ジェンダーと福祉国家―家庭内性別役割分業に関する国際比較―」
- 報告者:白波瀬佐和子(国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部第2 室長)
- 第3 回平成12 年6 月16 日
- 「医療制度改革の国際的動向とわが国の位置づけをめぐって」
- 報告者:尾形裕也(国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部長)
- 第4 回平成12 年9 月19 日
- 「『社会変動の中の福祉国家』の概要」
- 報告者:富永健一(武蔵工業大学教授)
- 第5 回平成12 年11 月29 日
- 「社会学者と経済学者からみた社会経済的不平等論」
- 講師:盛山和夫(東京大学教授),橘木俊詔(京都大学教授)
- 第6 回平成12 年12 月25 日
- 「福祉社会のシステム論的基礎―共生と最適化の視点から」
- 報告者:三重野 卓(山梨大学教授)
- 第7 回平成13 年2 月1 日
- 「福祉国家発展の時系列データ分析―国別時系列とpooled time series ―」
- 報告者:織田輝哉(慶応大学助教授)
- 第8 回平成13 年3 月16 日
- 「社会保障費の内訳に関する時系列変化」
- 報告者:平岡公一(お茶の水女子大学教授)
- 「社会保障費負担の国際比較分析」
- 報告者:武川正吾(東京大学助教授)
- 「ジェンダーからみた福祉国家のあり方」
- 報告者:白波瀬佐和子(国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部第2 室長)
10 社会保障の社会経済への効果分析モデル開発事業(平成10 ~12 年度)
(1 )研究目的
社会保障制度の財政動向や制度変更の影響等を整合的かつ多面的に把握するためには,社会保障のみならずマクロ経済や財政,労働市場などを総合的に勘案して分析する必要がある。そのためのマクロ経済モデルの開発を3 年計画で行ってきたが,最終年度である今年度は,平成11 年度に作成したプロトタイプ・モデルを基に,日本経済の動向と社会保障財政との関連を見る長期計量モデルと年金改革・医療改革とマクロ経済との関連を見る計量モデルを完成させる。また,こうしたマクロ経済モデル開発において,子育て支援策,年金改革,医療改革,介護保険などがもたらす経済効果の分析を的確に取り入れるために,年金・雇用,医療・介護各研究班における分析をとりまとめ,マクロ経済モデル開発と合わせた成果発表を行う。
これによって,厚生労働行政の中で社会保障政策と経済政策との連携が求められた場合に資する基礎的な資料を提供するとともに,社会保障政策が社会経済に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるための資料を提供することに努める。
(2 )研究会の構成員
(マクロ経済効果研究班)
- 所外委員
- 主査:浅子和美(一橋大学経済研究所教授),副査:吉野直行(慶応義塾大学教授)
- 井堀利宏(東京大学教授),浅野幸弘(横浜国立大学教授),大林 守(専修大学教授),
- 山田節夫(専修大学教授),脇田 成(東京都立大学助教授),阿部正浩(獨協大学専任講師),
- 中里 透(上智大学専任講師),亀田啓悟(新潟大学助教授),藤丸麻紀(和洋女子大学専任講師)
- 所内担当者
- 増田雅暢(総合企画部長),府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長),
- 尾形裕也(社会保障応用分析研究部長),増淵勝彦(社会保障応用分析研究部第1 室長),
- 金子能宏(社会保障応用分析研究部第3 室長),加藤久和(社会保障基礎理論研究部第4 室長),
- 泉田信行(社会保障応用分析研究部研究員)
- 幹事:山本克也(社会保障基礎理論研究部研究員)
(年金・雇用研究班)
- 所外委員
- 主査:清家 篤(慶応義塾大学教授),副査:大竹文雄(大阪大学社会経済研究所教授)
- 赤林英夫(慶応義塾大学助教授),滋野由紀子(大阪市立大学助教授),
- 玄田有史(学習院大学教授),小川 浩(関東学園大学助教授),
- 臼杵政治(ニッセイ基礎研究所上級研究員),菅 桂太(慶応義塾大学研究助手)
- 所内担当者
- 増田雅暢(総合企画部長),府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長),
- 尾形裕也(社会保障応用分析研究部長)
- 幹事:金子能宏(社会保障応用分析研究部第3 室長),今井博之(国際関係部研究員)
(医療・介護研究班)
- 所外委員
- 主査:田近栄治(一橋大学教授),副査:知野哲朗(立命館大学教授)
- 油井雄二(成城大学教授),塚原康博(明治大学短期大学助教授),
- 大日康史(大阪大学社会経済研究所助教授),小山光一(北海道大学教授),
- 池田俊也(慶応義塾大学専任講師),佐藤主光(一橋大学専任講師)
- 所内担当者
- 府川哲夫(社会保障基礎理論研究部長),尾形裕也(社会保障応用分析研究部長),
- 吉田有里(社会保障応用分析研究部客員研究員)
- 幹事:泉田信行(社会保障応用分析研究部研究員)
(3 )研究計画
- マクロ経済モデルによる分析項目
わが国が21 世紀前半にどのような経済社会を迎えるのか,という点を考察するとともに,現行の社会保障制度改革に留まらず,様々な改革を行った場合に,マクロ経済あるいは財政にどのような効果・影響をもたらすかをシミュレーションする。さらには,技術進歩率の上昇,外国人労働導入等外生的なショックがわが国経済および社会保障制度にどのような影響をもたらすかについて試算を行う予定である。これによって,日本経済の長期的な動向と社会保障政策の経済効果との関連を明らかにする。また,年金改革,老人保健制度改革などが経済に及ぼす影響を調べるために,こうした基本モデルをベースとして社会保障財政を詳細にして,代わりに操作性を高めるため他の部門をある程度簡略化した社会保障財政重視型マクロ経済モデルを作成する。
- マクロ経済モデル分析を補完する多角的な経済モデル開発の検討
マクロ経済モデル開発において,子育て支援策,年金改革,医療改革,介護保険などがもたらす経済効果の分析を的確に取り入れるために,年金・雇用,医療・介護各研究班における分析をとりまとめる。また,各研究班で用いた様々な分析手法のうち,マクロ経済モデルを補完する経済モデル分析について検討し,今後の研究に資するプロトタイプ・モデルの開発を行う。
なお,マクロ経済モデル開発とこれを補完するその他の経済モデルのプロトタイプ・モデル開発に際しては,ノウハウを有する外部有識者および当研究所研究者による研究会を随時開催し,プログラム開発など技術的な問題をクリアしながら研究を進めていく。
(4 )研究会等の開催状況
①研究会の開催
- 第1 回平成12 年7 月2 日
- 「介護保険制度施行に伴う医療従事者の再配置について」
- 報告者:泉田信行(国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部研究員)
- 第2 回平成12 年7 月7 日
- 「医療と介護のCGE モデルについて」
- 報告者:吉田有里(国立社会保障・人口問題研究所客員研究員)
- 第3 回平成12 年9 月4 日
- 「社会保障・税政と既婚女性の労働供給」
- 報告者:赤林英夫(慶応義塾大学助教授)
- 第4 回平成12 年10 月18 日
- 「所得変動の不確実性と年金・雇用政策の役割」
- 報告者:金子能宏(国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部第3 室長)
- 「国保と政管健保:保険者機能の計測」
- 報告者:油井雄二(成城大学教授)
- 第5 回平成13 年2 月28 日
- 「『高年齢者就業実態調査』(1988,92,96 年)にみる厚生年金給付が男性高齢者の労働供給行へ与えた影響の分析」
- 報告者:清家 篤(慶応義塾大学教授)
- 菅 桂太(慶応義塾大学大学院経済学研究科助手)
- 「『平成8 年度人口動態社会経済面調査』による出生力分析」
- 報告者:今井博之(国立社会保障・人口問題研究所国際関係部研究員)
- 第6 回平成13 年2 月27 日
- 「健康状態の自己評価に関する国際比較―適応の影響についての研究―」
- 報告者:大日康史(大阪大学社会経済研究所助教授)
- 「医療サービスの集中度について:医療施設調査を用いた分析」
- 報告者:泉田信行(国立社会保障・人口問題研究所研究員)
②研究成果発表会
平成13 年3 月29 日午後1:30 ~6:00 (東京国際フォーラム会議室G602 )
プログラム:
- 開会の辞
- 阿藤 誠(国立社会保障・人口問題研究所長)
- 趣旨説明
- 尾形裕也(国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部長)
- 基調講演
- 「経済学の観点からみた年金改革の動向について」
- David A.Wise (ハーバード大学教授)
- 研究成果発表
- マクロ・モデル研究班
- 「マクロ・モデル分析の概要と年金・医療財政の分析」
- 加藤久和(国立社会保障・人口問題研究所社会保障基礎理論研究部第4 室長)
- 山本克也(国立社会保障・人口問題研究所社会保障基礎理論研究部研究員)
- 医療・介護研究班
- 「医療と介護の関係と健康の評価―経済学的アプローチ」
- 泉田信行(国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部研究員)
- 年金・雇用研究班
- 「年金が引退過程に及ぼす影響と子育て支援策の効果」
- 金子能宏(国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部第3 室長)
③研究成果ワークショップ
平成13 年3 月30 日午前10:00 ~午後6:30 (東京国際フォーラム会議室G602 )
プログラム:
- 開会の辞
- 植村尚史(国立社会保障・人口問題研究所副所長)
- 研究成果発表
- (午前の部)座長:浅子和美(一橋大学経済研究所教授)
- 「マクロ経済と社会保障・財政の長期展望」
- 報告者:加藤久和(国立社会保障・人口問題研究所社会保障基礎理論研究部第4 室長)
- コメンテーター:大林守(専修大学教授)
- 「社会保障の変更がマクロ経済に与える影響」
- 報告者:佐倉 環(国民経済研究所研究員)
- コメンテーター:脇田 茂(東京都立大学助教授)
- 「社会保障が金融市場に及ぼす影響とマクロモデル開発の視点」
- 報告者:亀田啓悟(新潟大学助教授)
- コメンテーター:浅野幸弘(横浜国立大学教授)
- 研究成果発表(午後の部)座長:井堀利宏(東京大学教授)
- 「介護保険制度が経済厚生に及ぼす影響:CGE モデルの応用」
- 報告者:吉田有里(国立社会保障・人口問題研究所客員研究員)
- コメンテーター:塚原康博(明治大学短期大学助教授)
- 「平均収益率からみた医療・年金受給世代内の公平性」
- 報告者:山本克也(国立社会保障・人口問題研究所研究員)
- コメンテーター:小野正昭(みずほ年金研究所年金研究部長)
- 「厚生年金給付が男性高齢者の労働供給行動へ与えた影響の分析―基礎年金による所得移転の影響」
- 報告者:清家 篤・菅 桂太(慶応義塾大学教授・助手)
- コメンテーター:大竹文夫(大阪大学社会経済研究所助教授)
- 「一般均衡動学モデルによる社会保障の経済厚生分析」
- “A Dynamic Macroeconomic Analysis on Social Security for Achieving Intergenerational
and Horizontal Equities”
- 報告者:宮里尚三・金子能宏(国立社会保障・人口問題研究所)
- コメンテーター:David A.Wise (Prof.of Harvard University )
- 閉会の辞
- 尾形裕也(国立社会保障・人口問題研究所社会保障応用分析研究部長)
(5 )研究成果の公表
研究成果は,平成13 年3 月29 日に東京国際フォーラム会議室G602 において開催した国立社会保障・人口問題研究所「社会保障セミナー」「社会保障の社会経済への効果モデル開発事業」研究成果発表会により一般に公開した。この研究成果発表会では,ハーバード大学ケネディー行政学院教授のデビット・ワイス氏による基調講演「経済学の観点からみた年金改革の動向について」を同時に実施して,この事業が諸外国の社会保障改革の動向や社会保障研究の展開とどのような関連性を持つかを明らかにすることにも配慮した。
また,同事業による個別の研究成果を学識経験者と意見交換するために,平成13 年3 月30 日に「社会保障の社会経済への効果モデル開発事業」研究成果ワークショップを開催した。これに基づいて,この事業の報告書のとりまとめを行うとともに,各研究班の成果のうちマクロ経済モデルの開発とこれを補完する経済モデルの検討については『季刊社会保障研究』特集号「社会保障のマクロ計量分析」(2001 年9 月)を刊行する。
11 国際移動者の社会的統合に関する研究(平成11 ~13 年度)
(1 )研究目的
わが国では1980 年代半ば以降,外国人労働者,日系人,国際結婚配偶者の流入が急増し,その一部が日本社会に定着するにつれ,社会保障制度等を通じた国際移動者とその家族の社会的統合が政策的課題となりつつある。他方,企業等による海外赴任者とその家族を中心とする日本人の国外への移動も1980 年代半ば以降に急増し,より多くの日本人(家族)が現地の地域社会への統合や日本社会への再統合の問題に直面するようになった。しかし,わが国における国際人口移動に関する研究は移動そのものに焦点を合わせたものが多く,国際移動者の社会的統合とそれに関する政策に焦点を合わせたものは少数である。そこで,本研究では国際移動者の社会的統合とそれに関する政策について資料収集,ヒアリング,実地調査等に基づく理論的,実証的,政策的研究を行う。
(2 )研究概要
本研究では平成11 年度から3 年間にわたり,①主要な国際移動者受け入れ国における社会的統合の実態と対策に関する資料収集とそれに基づく比較分析,②主要な在留邦人受け入れ国における日本人(家族)の社会的統合の実態と対策に関する資料収集とそれに基づく比較分析,③国内における国際移動者とその家族の社会的統合・再統合の実態と対策に関する調査とそれに基づく比較分析,の三者を行うことを計画している。研究方法としては①と②については文献研究と専門家からのヒアリングを行い,③については,特定の地域で面接等による実地調査を行うとともに,地方自治体・企業・労働組合・NGO 等の関係者からのヒアリングを行う予定である。そして,初年度は国内における文献研究と専門家からのヒアリングを行うとともに実地調査の予備調査を行い,第2 年度は文献研究とヒアリングを継続するとともに実地調査の本調査を行い,第3 年度は実地調査本調査の分析を行うとともに,事後事例調査を行ってそれを補足しながら,分析結果をとりまとめる予定である。
(3 )研究会の構成員
- 所外委員
- 白木三秀(早稲田大学教授),加賀美雅弘(東京学芸大学助教授),近藤 敦(九州産業大学助教授),
- 永井裕久(筑波大学助教授),平野(小原)裕子(九州大学医療技術短期大学部助教授),
- 松本邦彦(山形大学助教授),石井由香(立命館アジア太平洋大学助教授),
- 正木智幸(東京学芸大学附属高等学校教諭)
- 所内担当者
- 小島 宏(国際関係部長),千年よしみ(国際関係部第1 室長),阿部 彩(国際関係部第2 室長),
- 東 幸邦(社会保障基礎理論研究部第1 室長),釜野さおり(人口動向研究部第2 室長),
- 清水昌人(人口構造研究部研究員)
(4 )研究会の開催状況
本年度は研究会における専門家からのヒアリング,文献研究,マクロ統計の分析を行った。研究会の実施状況は以下の通りである。
- 第1 回平成12 年7 月7 日
- 「帰国生研究の現状と課題」
- 報告者:佐藤群衛(東京学芸大学海外子女教育センター教授)
- 第2 回平成12 年11 月17 日
- 「フィンランドにおけるEU からの移民の統合について」
- 講師:Ismo Soderling (フィンランド家族連盟人口研究所長)
- 第3 回平成13 年3 月1 日
- 「ワシントンの日本人社会」
- 講師:木村惠子(異文化コミュニケーションアドバイザー)
また,平成11 年度に試験的に実施した「元帰国生」を対象とするフォーカス・グループ討論を5 回にわたって実施するとともに,その成果に基いて一部の外部委員が実施した「元帰国生」を対象とするアンケート調査を支援した。また,平成12 年度に実施予定の「海外派遣帰任者」の調査(ヒアリングとフォーカス・グループ討論)に向けての文献研究も行った。
12 人口・経済・社会保障システムのダイナミックモデルに関する基礎研究
(平成11 ~13 年度)
(1 )研究目的
本研究は,人口-経済社会システムと社会保障との動的な関係をモデル化し,システム分析を適用してその動態の理解を深めることによって,少子高齢社会へと一大転換を迎えつつある21 世紀わが国における社会保障あるいは行政諸施策の理念的基盤形成に資することを目的とする。
少子高齢化を含めおよそ人口変動は個人のライフコース変化により引き起こされるが,逆に人口変動は経済社会の変容を通して人々のライフコースを変える。社会保障の役割はこの人口-経済社会-ライフコースの自律的変動過程において生ずる好ましくない循環の是正である。近年における経済社会基調の転換に際して,社会保障のあり方もこれまでの落ち穂拾い型から,むしろ積極的に人口-経済の変動過程に介入し,政策的理念を実現する型へとパラダイムの変革を迫られている。すなわち,社会保障が人口-経済社会システムの一部として組み込まれた,いわば人口-経済社会-社会保障システムの到来が必至である。しかしながら,個人のライフコースの多様化,自立と個人主義化の自然な進展,ライフコース各段階でのQOL (quality of life )確保に抵触することなく人口-経済社会の変動過程に介入するためには,変動過程に対するシステム的理解が前提となる。
こうした状況を踏まえて,本研究ではこれまで人口研究および社会保障研究の各分野において展開されてきたシステムモデルの接合によってダイナミックモデルを開発し,これによって人口-経済社会-社会保障システムの変動過程を記述,予測することを目指す。社会保障研究と人口問題研究の手法的接合は,上述のような現代的背景において必須の事業であるとともに,当研究所設立の理念に沿うものである。
(2 )研究会の構成員
- 所外委員
- 塩野谷祐一(国際医療福祉総合研究所副所長)
- 所内担当者
- 増田雅暢(総合企画部長),後藤玲子(総合企画部第2 室長),金子隆一(総合企画部第4 室長),
- 加藤久和(社会保障基礎理論研究部第4 室長),三田房美(総合企画部主任研究官)
(3 )研究計画
- 初年度:
- 文献・資料に基づく人口研究分野,社会保障研究分野双方における関連事項の調査,セミナー形式による関連分野専門家を交えてのモデルの検討
- 2 年度:
- 国立社会保障・人口問題研究所において開発されている人口推計モデル,社会保障推計モデルを中心とした既存モデルを用いた統合モデルの検討
- 3 年度:
- 主としてシミュレーション分析による各種制度・施策の効果予測の試み,施策の指針形成への応用の検討
(4 )研究成果
本年度は計画の2 年度目に当たり,初年度における調査研究,データ収集,セミナー,シミュレーションデザインの検討などの成果を踏まえて,既存の人口モデル,経済-社会保障モデルの構造の再検討と統合化への検討を行った。その結果,モデルは経済モデルを骨格とし,わが国の現状を踏まえて結婚・出生行動とミクロ-マクロ経済との連関を表現するものとした。次にこれに従い,その主要なサブモデルとなる結婚,出生,マクロ経済のそれぞれについて実際にプロトタイプモデルの開発を行った。その過程として,システムダイナミックス,マルチエージェント型モデル,マルチレベル型モデルなど異なるデザインのプロトタイプモデルの比較検討を行い,個人の意志決定過程を含むマルチエージェント型モデルが有効であるとの結論を得た。