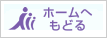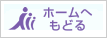(刊行物)
28 『季刊社会保障研究』(機関誌)
29 『海外社会保障研究』(機関誌)
30 『人口問題研究』(機関誌)
リンク http://www1ipss.go.jp/bunken/index-bj.htm
第2部 平成11 年度事業報告
31 RPSP (Review of Population and Social Policy ),No.9,2000
旧社会保障研究所の時代からRSP という略称で親しまれてきたReview of Social Policy は,1996 (平成8)年12月の国立社会保障・人口問題研究所発足後に編集開始したものとしては最初の号に当たる第7号から名称をReview of Population and Social Policy (RPSP )に改めた。かつては原則的に日本語で出版された論文を英訳して掲載していたが,7号からは英文論文(和文論文の著者による英訳,厚生政策セミナー発表論文を含む)も掲載することになった。第9号は九編の論文を掲載予定(秋に発刊予定)である。以下に暫定的な目次を示す。
- Articles
- “The Effect of Household Structure on the Employment Behavior of Elderly Male Workers” by Hiroshi OGAWA
- “The Welfare State, the Middle Class, and the Welfare Society” by Masayuki FUJIMURA
- “The Relationship between Women’s Increased Higher Education and the Declining Fertility Rate in Japan” by Sawako SHIRAHASE
- “Population Issues in the Netherlands” by Gijs BEETS and Nico Van NIMWEGEN
- “Household Projection for Japan, 1995‐2020: Methods and Results” by Hachiro NISHIOKA, Toru SUZUKI, Chizuko YAMAMOTO, Katsuhisa KOJIMA, and Yasuyo KOYAMA
-
Welfare Policy Seminar: Families in the New Century
- “Recent Trends in Fertility and Household Formation in the Industrialized World” by Ron LESTHAEGHE and Guy MOORS
- “Family Relationships in Australia: The Conservative-Liberal-Radical Debate” by Peter McDONALD
- “Gender, Employment, and Housework in Japan, South Korea, and the United States” by Noriko O.TSUYA, Larry L. BUMPASS, and Minja Kim CHOE
- “The Parent-Adult Child Relationships in Japan” by Hachiro NISHIOKA
32 研究資料
- 第297号(平成11年9月 刊)
- 「人口統計資料集1999 」(石川 晃・坂東里江子)
- 第298 号(平成12年3月 刊)
- 「日本の世帯数の将来推計(全国推計/都道府県別推計)―1995(平成7)年〜2020(平成32)年)―」
- (西岡八郎,鈴木 透,小山泰代,山本千鶴子,小島克久)
33 リプリントシリーズ/ワーキングペーパーシリーズ
- Working Paper Series (E )
- No.9 The Transformation of Partnerships of Japanese Women in the 1990s: Increased Reluctance towards Traditional Marriages and the Prevalence of Non-Cohabiting Couples (Miho Iwasawa )March 2000
34 先進諸国の社会保障シリーズ
『3 カナダ』(城戸喜子・塩野谷祐一編,(財)東京大学出版会,平成11 年4 月 刊)
- 第1部「社会保障の背景」
- 1章「社会保障制度の概要と特色」(城戸喜子)
- 2章「経済と人口・社会構造」(林 直嗣)
- 3章「財政の規模と構造―社会保障との関連を中心に」(城戸喜子)
- 4章「政治と現代福祉国家」(岩崎美紀子)
- 5章「社会保障の歴史」(岡本民夫)
- 第2部「所得保障」
- 6章「年金制度」(丸山 桂)
- 7章「労災補償制度」(桑原昌宏)
- 8章「雇用保険と労働市場政策」(國武輝久)
- 9章「児童給付」(都村敦子)
- 10章「社会扶助」(根本嘉昭)
- 第3部「医療保障と社会サービス」
- 11章「医療制度」(高橋淑郎)
- 12章「医療保険―財政連邦主義の終焉」(新川敏光)
- 13章「高齢者福祉サービス」(高橋流里子)
- 14章「障害者福祉サービス」(木村真理子)
- 15章「子ども家庭福祉」(高橋重広)
- 16章「住宅政策」(檜谷美恵子)
- 第4部「社会保障改革の動向」
- 17章「行財政改革」(岩崎美紀子)
- 18章「社会保障制度における民営化の動き―連邦,州,営利,非営利の役割分担」(栗沢尚志)
『4 ドイツ』(古瀬 徹・塩野谷祐一編,(財)東京大学出版会,平成11 年4 月刊)
- 第1部「ドイツ社会保障の特色」
- 1章「ドイツの社会保障と日本」(古瀬 徹)
- 2章「社会保障制度の歴史的発展」(足立正樹)
- 3章「社会的市場経済と社会保障」(足立正樹)
- 4章「ドイツの補完性原理と自治体行財政―ドイツ型福祉国家にとっての2 つの原動力」(山田 誠)
- 第2部「所得保障」
- 5章「労働保険と雇用政策」(西村健一郎)
- 6章「年金制度」(下和田 巧)
- 7章「家族手当」(田中耕太郎)
- 8章「社会扶助」(田中耕太郎)
- 第3部「医療保障と社会サービス」
- 9章「医療制度」(高智英太郎)
- 10章「医療保険」(土田武史)
- 11章「高齢者・障害者福祉サービス」(春見静子)
- 12章「児童福祉」(小宮山潔子)
- 13章「住宅政策・都市政策」(水原 渉)
- 第4部「社会保障改革の動向」
- 14章「経済・社会システムの構造改革」(松本勝明)
- 15章「医療保険改革」(松本勝明)
- 16章「介護保険の創設とその後の展開」(土田武史)
- 17章「最近の公的年金改革と企業年金の動向」(下和田 勉)
『5 スウェーデン』(丸尾直美・塩野谷祐一編,(財)東京大学出版会,平成11年4月 刊)
- 第1部「社会保障の背景」
- 1章「総論」(丸尾直美)
- 2章「経済と経済政策」(駒村康平)
- 3章「中央財政と地方財政」(飯野靖四)
- 4章「行政・政治」(岡沢憲芙)
- 5章「労使関係と労働組合」(下平好博)
- 6章「社会保障の歴史的発展」(永山泰彦)
- 第2部「所得保障」
- 7章「年金制度」(木村陽子)
- 8章「雇用関連の社会保険」(訓覇法子)
- 9章「その他の所得保障」(都村敦子)
- 第3部「医療保障と社会サービス」
- 10章「医療制度と医療保険」(西村万里子)
- 11章「高齢者福祉サービス」(三上芙美子)
- 12章「障害者福祉サービス」(加藤彰彦)
- 13章「児童福祉サービス」(古橋エツ子)
- 14章「住宅政策」(外山 義)
- 第4部「社会保障改革の動向」
- 15章「福祉改革の国際的動向とスウェーデン」(丸尾直美・的場康子)
- 16章「EU加盟後の社会保障」(益村真知子)
『6 フランス』(藤井良治・塩野谷祐一編,(財)東京大学出版会,平成11年4月 刊)
- 第1部「社会保障の背景」
- 1章「総論」(藤井良治)
- 2章「経済と社会保障」(長部重康)
- 3章「財政制度」(矢野秀利)
- 4章「政治・行政・地方自治」(木村琢磨)
- 5章「社会保障の歴史」(田端博邦)
- 第2部「所得保障」
- 6章「年金制度」(加藤智章)
- 7章「労災補償」(岩村正彦)
- 8章「家族給付」(上村政彦)
- 9章「失業保険と雇用政策」(岡 伸一)
- 第3部「医療保障と社会サービス」
- 10章「医療保険制度と医療供給体制」(江口隆裕)
- 11章「社会扶助」(林 信明)
- 12章「高齢者福祉サービス」(白波瀬佐和子)
- 13章「障害者政策」(大曽根 寛)
- 14章「児童福祉サービス」(神尾真知子)
- 15章「住宅政策」(原田純孝)
- 第4部「社会保障改革の動向」
- 16章「行政改革」(伊奈川秀和)
- 17章「フランス社会保障における改革」(藤井良治)
『7 アメリカ』(藤田伍一・塩野谷祐一編,(財)東京大学出版会,平成11年4月 刊)
- 第1部「社会保障の背景」
- 1章「総論」(藤田伍一)
- 2章「経済と社会保障財政」(馬場義久)
- 3章「連邦制・地方自治・立法過程」(砂田一郎)
- 4章「社会保障制度の歴史」(古川孝順)
- 第2部「所得保障」
- 5章「年金制度」(金子能宏)
- 6章「企業年金」(岡 伸一)
- 7章「労働保険と雇用政策」(奥西好夫)
- 8章「公的扶助」(後藤玲子)
- 第3部「医療保障と社会サービス」
- 9章「医療制度」(広井良典)
- 10章「メディケアとメディケイド」(西村周三)
- 11章「社会福祉サービス」
1 「老人福祉サービス」(和気純子)
2 「障害者サービス」(佐藤久夫・久保耕三)
3 「児童福祉サービス」(山本真美)
- 12章「企業福祉」(陶野哲雄)
- 第4部「社会保障改革の動向」
- 13章「医療改革の動向」(藤田伍一)
- 14章「社会保障改革の課題と展望」(Gary Burtless )
(セミナー等)
35 第4回厚生政策セミナー「21世紀の家族のかたち−国際比較の視点から−」
(平成12年3月14日 東京・国連大学国際会議場)
- 司 会:
- 阿藤 誠(国立社会保障・人口問題研究所副所長)
- 基調講演:
- ロン・レスタギ(ブリュッセル自由大学教授)
- ピーター・マクドナルド(オーストラリア国立大学教授)
- 津谷 典子(慶応義塾大学教授)
- 西岡 八郎(国立社会保障・人口問題研究所人口構造研究部長)
- コメント:
- 金 益基(韓国東国大学教授)
- 野々山久也(甲南大学教授)
- 袖井 孝子(お茶の水女子大学教授)
- 小島 宏(国立社会保障・人口問題研究所国際関係部長)
36 研究交流会
- 第1回 平成11年4月7日
- 「日本の年金制度からみたOECD 諸国の年金制度の将来」(J.F. Estienne )
- 第2回 4月21日
- 「平成11 (1999 )年度研究計画」(各委員会)
- 第3回 5月12日
- 「医療へのアクセスの経済分析」(泉田信行)
- 第4回 6月2日
- 「リプロダクティブ・ライツをめぐって」(佐藤龍三郎)
- 第5回 7月7日
- 「移動しない事の規定要因―エスニックネットワークとジェンダー(マレーシアのデータから)」(千年よしみ)
「所得分配の見方と統計上の問題点」(大石亜希子)
- 第6回 7月21日
- 「「ICPD +5 」―カイロ行動計画:5 年目の評価―」(阿藤 誠)
「健康余命と日本での適用事例」(小松隆一)
- 第7回 9月8日
- 「平成11 年版厚生白書について」(増田雅暢)
- 第8回 9月22日
- 「スウェーデンのカップル関係の質―子どもがいることの影響の分析―」(釜野さおり)
- 第9回 9月29日
- 「国際統計協会第52 回大会および大会前ワークショップ参加報告」(小島 宏)
「公正な資源配分システム・序―QOL プロジェクト助走報告―」(後藤玲子)
- 第10回 10月6日
- 「ルクセンブルク所得研究所セミナー参加 出張報告」(勝又幸子・白波瀬佐和子)
- 第11回 10月20日
- 「結婚・出産期における家族の多様化・個人化と出生力低下―1980 年代以降の家族の揺らぎと出生力」(新谷由里子)
- 第12回 11月10日
- 「ジェンダーと福祉国家論―労働市場における男女の地位を通して」(白波瀬佐和子)
- 第13回 11月24日
- 「平成9 年度社会保障給付費推計」(勝又幸子・浅野仁子)
- 第14回 12月8日
- 「中高年者の転職と企業年金の役割」(金子能宏)
- 第15回 平成12年1月26日
- 「地方圏出身者の還流移動―長野県および宮崎県出身男性の事例―」(江崎雄治)
- 第16回 2月9日
- 「Overlapping Generations Model with Endogenous Fertility 」(加藤久和)
- 第17回 2月23日
- 「中国における家族計画・母子保健・寄生虫予防インテグレーション・プロジェクト」
(佐藤龍三郎)
- 第18回 3月1日
- 「都道府県別世帯推計の方法と結果について」(西岡八郎・鈴木 透・山本千鶴子・小山泰代)
「第2 回全国家庭動向調査の結果概要」(西岡八郎・白波瀬佐和子・山本千鶴子・小山泰代)
- 第19回 3月29日
- 「福祉国家の危機と公共的理性」(塩野谷祐一)
37 政策研究会
- 第1回 平成11年4月15日
- 「社会福祉基礎構造改革について」松本勝明(厚生省社会・援護局福祉人材確保対策室長)
- 第2回 平成11年6月15日
- 「雇用保険制度の現実と課題」松井一實(労働省職業安定局雇用保険課長)
- 第3回 平成11年10月7日
- 「新SNA と社会保障の扱いについて」多田洋介・入江一成(経済企画庁経済研究所国民経済計算部企画調査課)
- 第4回 平成12年1月14日
- 「確定拠出型年金制度について」二川一男(厚生省年金局確定拠出型年金制度準備室長)
38 特別講演会
本年度は下記のとおり,5回の特別講演会が開催された。
- 第1回 平成11年5月13日
- 講 師:三瓶恵子(日本貿易振興会)
- 講義内容:「スウェーデンの人口問題の現状と政策対応:福祉社会における出生率の推移と高齢化への対応」
- 第2回 平成11年5月26日
- 講 師:Edward Jow-Ching Tu (Division of Social Science, Hong Kong University of Science & Technology, Hong Kong )
エドワード・テュー(香港科学技術大学社会科学部教授,東京都老人総合研究所客員研究員)
- 講義内容:“Long-Term Trends in Life Expectancy: Japan and Taiwan.”(平均寿命の長期的趨勢―日本と台湾の比較)
- 第3回 平成11年10月20日
- 講 師:Young J. Kim (Professor, Johns Hopkins University, USA )
ヤン・J ・キム(米国ジョンズ・ホプキンス大学人口学教授)
- 講義内容:“Changes in Timing and the Measurement of Fertility: Why the Bongaarts-Feeney Adjustment Does Not Work”(出生に関するタイミングと計測の変化:なぜボンガーツ・フィーニーモデルは機能しないのか)
- 第4回 平成12年3月15日
- 講 師:Dr. Peter F. McDonald (Professor, Dept. of Demography, Australian National University, Canberra, Australia )
ピーター・マクドナルド(オーストラリア国立大学人口プログラム長)
- 講義内容:“The Implications of Below Replacement Fertility for Labour Supply and International Migration, 2000‐2050”(少子化が示唆するもの―労働供給と国際移動に焦点をあてて:
2000 −2050 年)
- 第5回 平成12年3月24日
- 講 師:Dr. Jozef Mladek (Professor, Dept. of Humangeography and Demogeography, Comenius University, Slovak Republic )
ジョセフ・ムラデク(スロバキア共和国コメニウス大学人文・人口地理学教授)
- 講義内容:“Population Development in Slovakia and the Second Demographic Transition”(スロバキアにおける人口動向と第二の人口転換)